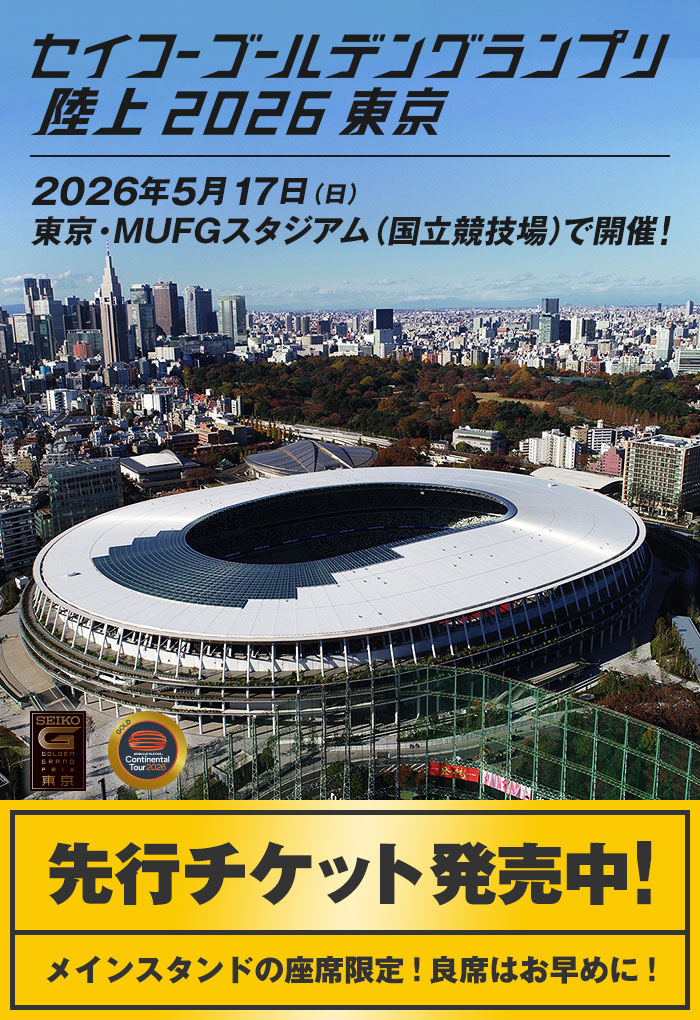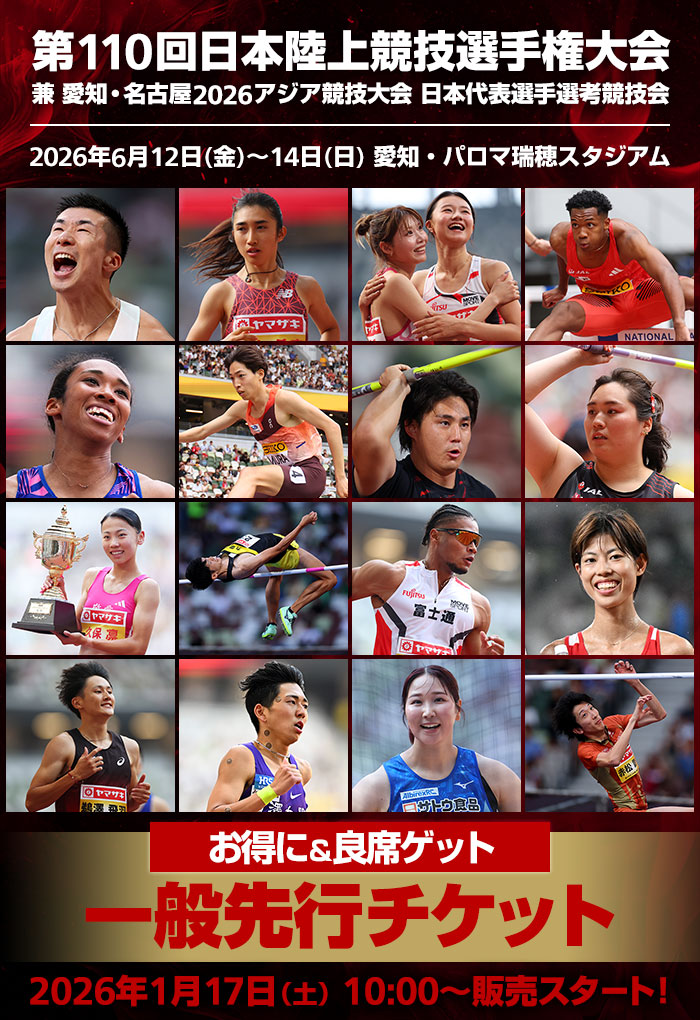大学生アスリートが、競技活動に取り組むなかで、競技力と人生の両面で自身の可能性を最大限に活かせる能力を獲得することを目指し、日本陸連が2020年度から実施している「ライフスキルトレーニングプログラム」。
5期生に向けた全体講義は、これまで3回にわたってオンラインで行われてきました。3月15・16日には、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターにおいて1泊2日の合宿形式で第4回全体講義を開催しました(本文中の所属・学年は、2024年度のもの)。
初日の3月15日は、3部構成で展開。まず、スポーツ心理学博士の布施努特別講師による講義からスタートしました。導入として、前回の全体講義の内容を振り返りながら、「勝ち続ける選手のサイクル」を回していくために、「CSバランス」「ダブルゴール」「仮説思考」をどのように使っていけばよいのかを改めて確認したうえで、「今日のメインポイント」(布施特別講師)として、実践知や主観的な経験を増やしていくことの大切さを解説。
受講者たちは、自らが経験を積むなかで培われる実践知や、遭遇した出来事を自分の視点で解釈・咀嚼する主観的な経験が増えると、その人独自の考え方や意識の方向性が形づくられたり、目標に適した役割性格が設定できるようになったり、仮説思考をより高度な形で回していけたりするようになることを理解し、さらに目標に向かっていく際には「腹落ち」するストーリーを持つのが有効であること、生じた課題に対して「どうすれば実現するか」と問いを立てるとよいことを学びました。

続いて、講義は、歴代ライフスキルトレーニング受講生をゲストに招いてのセッションに。1期生の伊藤陸選手(現スズキ、当時、近畿大学工業高等専門学校)、三浦励央奈さん(当時、早稲田大学)、金光由樹さん(当時、東海大学)、3期生の池田海選手(早稲田大学4年)、岩佐茉結子選手(東京学芸大学4年)の5名が、OBOGとして参加しました。5人は、受講して4年あるいは2年経った現在、ライフスキルトレーニングで学んだことが、自身にどんな変化をもたらしたか、また、実際にどんな活用ができているかを、1人ずつ報告。社会人として、競技者として、チームリーダーとして、それぞれに異なる立場の“生の声”を聞いた受講者たちは、ライフスキルトレーニングを実際にどう生かせるのかへの解像度をぐんと高めました。
1日目の最後のセッションと、2日目最初のセッションとして行われたのは、特別ゲストを囲んでの座談会です。第3回全体講義の福島千里さん(順天堂大学)に続いて、戸邉直人選手(男子走高跳日本記録保持者、JAL)と中村明彦さん(男子十種競技日本歴代2位、スズキ)が参加。1日目は中村さんが布施特別講師のサポートに回る形で戸邉選手が、2日目は福島さんがサポート役を務める形で中村さんが、それぞれ布施特別講師と対談したのちに、受講者たちからの質問に答えました。戸邉選手のセッションでは、「自分の陸上の“世界像”を構築」「主観と客観のバランス」「走高跳は2回失敗できる。失敗はヒントをもらえているということ」「“勝ちたい”思いと同時に“どこまで行けるか”の思いがある」といった言葉が出てきて、布施講師がこの日の講義で説明した実践知や主観的な経験を増やしていくなかで自身の競技観を確立した様子や、「CSバランス」「仮説思考」「内発的モチベーション」の概念を自然に使いこなしてきたことが明らかに。また、中村選手のセッションでは、「高い山を何個もつくって領地を広げるのが混成競技」(中村選手)という十種競技ならではの視点から、「常に俯瞰してみる自分がいる」「どの種目にも共通する要素がある。抽象度を上げて汎用性を高めることを意識」「最初の3種目で結果は見える。ダメだったときにどう戦うか。次に繋げるために最後までやりきる」「大枠から外れないトライ&エラー」「自分のコントロールできることに集中する」「終わりなき戦い」といった発言が。やはり「縦型比較思考」「仮説思考」「CSバランス」「ダブルゴール」「役割性格」内発的モチベーション」などを用いた取り組みがなされてきた様子が示されました。

その後、2日目の第2部として布施特別講師がレクチャー。ここでは「重要なときやピンチに陥ったなかでもトップアスリートが自身の力を発揮できるのはなぜか」として、結果を出しているアスリートたちは、チャレンジングな姿勢や自動的(速い)意思決定、チャンスを見つけに行こうとする「獲得型思考」で取り組んでいることが示されました。また、「本当に強い選手の特徴は、成功を掴むまで、失敗しても何度も立ち上がってチャレンジできること」と布施特別講師。そのチャレンジは、現在の自分を、目指すゴールや将来のなりたい自分と比較し(縦型比較)、そこから逆算して今の自分に必要なものを考え、仮説思考や役割性格、ダブルゴール、CSバランスなどを駆使して取り組んでいくことによって実現できると述べました。
最後に布施特別講師が紹介したのは、「オートテリック」という言葉でした。日本語では「自己目的的」と訳される心理学の用語で、評価や報酬など外から与えられた目的の達成や結果よりも、取り組んでいること自体に興味や関心を持ち、喜びや楽しさを見いだせる特性のことです。布施特別講師は、オートテリック獲得の条件として、1)挑戦のレベル、2)目標の明確さ、3)役割性格、4)自己決定能力、5)獲得型思考の5つを挙げ、これまでの講義で学んできた概念が、どこに関係していくのかを1つずつ説明。「トップ選手の才能も、こうやって可視化していくと、それぞれに工夫があることがわかる。考え方にはスキルがあり、それは変えることができる。まずは、皆さんが今、一所懸命に取り組んでいる陸上競技で、その考え方のスキルを高めていってほしい」と呼びかけ、講義を締めくくりました。
第5期では、受講生へのインタビューを通じて全体講義を振り返り、ライフスキルトレーニングで得た学びや自身の考え方の変化を聞いていく形をとってきました。最終回となる「全体講義振り返りインタビュー」は、京竹泰雅選手(関西大学3年、400mハードル)、原口颯太選手(順天堂大学2年、走高跳)、松岡萌絵選手(中央大学4年、400mハードル)の3名に登場いただきます。
対面での合宿研修で、一番心に残ったこと
――最後の全体講義で、初めて5期生がリアルで顔を合わせることが実現しました。また、講義もあれば、OBOGの皆さんから実体験を聞いたり、“レジェンドアスリート”の皆さんが自身の経験を話してくださったりと、本当に濃厚で、刺激的な2日間だったのではないかと思います。まず、第4回全体講義を振り返っての感想を、そのなかでも一番心に強く残ったことを伺っていきましょう。京竹選手、いかがでしたか?京竹:僕が一番心に残ったところは、「横型比較と縦型比較」の話です。今までの競技生活を振り返ると、ずっと横型比較。けっこう周りの選手だったり、環境だったりに影響されていた部分が多くて、自分のなかで一番意識しなければいけないところにフォーカスできていなかったなと、今回のディスカッションや講義を通じて感じました。やっぱり「将来のなりたい自分」との縦型比較で大事なところにフォーカスを当てて、周りに影響されずに競技を進めることが大事だと感じました。
――その「縦型・横型」で比較を考えることは、この全体講義を受けて初めて、「あ、自分は今まで横型比較だったんだな」と気づいた?
京竹:そうですね。今まで意識したことはなくて、自然に横型比較になっていたので、そこは講義を通して気づかされた点です。
――原口選手はいかがでしたか?
原口:自分は、全体講義のなかで出た「主観的・客観的」という話のところです。競技をしてきたなかで「自分を客観視して見ていく」という考え方すらなかったなか、講義のなかで出てきたんですね。そのうえで、先日、世界室内選手権(中国・南京)に出場したとき、「日本人が世界で戦うとなったら、やはり厳しい部分があるな」と思って、そのときに、「じゃあ、自分は、どうやって戦えるようにしていくのかというところの客観視が少しだけできるようになったかな」と感じたので、やはりこの部分が一番印象に残っています。
――今までは、自分を客観視することができていなかったのですか?
原口:そうですね。大学に入ってからは記録的にも、学生の試合では上位にいたこともあって、引いた視点で見るという考え方自体がありませんでした。今回の世界室内は記録的にも下のほうでの出場で、そのなかで自分がどう戦っていくかを客観的に、俯瞰して考える部分が多かったんです。
――全体講義で出てきた、「主観的な経験」を増やしていくうえで大切なところですね。中村明彦さんが話してくださった「俯瞰してみる」というところにも関係します。俯瞰して見られるようになることで「主観的な経験」が増えていくと気づいたわけですね。
原口:はい。実際に出場してみて初めてわかったというところが大きいです。
――世界室内の話は、のちほど改めて聞かせていただくとして、続いて松岡選手に伺いましょう。いかがでしたか?
松岡:私が2日間の合宿で一番心に残ったのは、直接、中村さんと福島さんと戸邉さんの話を聞けたことです。そうしたトップのアスリートの方は、もともとの能力が違うというか、別世界の方と思っていたのですが、実際に話を聞いていくなかで、「根本の考えは自分たちと一緒なんだな」と感じることができました。中村さんと福島さんが、「試合前はもちろん不安になるし、自信なんてない」と仰って、不安になるのは当たり前で、そのことを自分で知っていて、そのうえで「何ができるか」というのを考えたりイメージしたりして、試合に臨んでいると話してくださいました。自分を俯瞰してみたり、客観視したりすることを続けていけば、少しずつ中村さんや福島さんの考え方に近づくことができるのかなと思いました。それが大きな気づきでしたね。
――「不安を、不安のままにしない」という話でしたね。
松岡:はい。自分の価値観を変えられた瞬間だったと思います。

「考え方の技術」を自在に操っていたOBOGたち
――今回は、週末にもかかわらず、OGOBの方々が、「皆さんの役に立てるなら」と駆けつけてくださいました。春から社会に出る人、競技を引退して社会人として働いている人、社会人アスリートとして競技に取り組んでいる人と、それぞれの立場で、ご自身の経験や考えを率直に話してくれたことが印象的でした。皆さんは、先輩方の話を聞いて、どんなことを感じましたか?松岡:自分は、講義で教えてもらったことすべてを実用できているかというと、そうではないんですね。確かに振り返ってみたら、「あ、あのとき、仮説思考ができていたんだ」と思い当たるところもあったりはするのですが…。でも、OBOGの方は、講義で学んだことを自分のものにしているなと強く思いました。意識して使っているというよりは、日常的に仮説・実行・データ・再仮説というサイクルを回していくことができていて、それがすごいなあと…。
――確かに、自然に使いこなせている感じがしましたよね。
松岡:はい。自分もそうなれるようになりたいな、と素直に思いました。
原口:講義のときも話したのですが、自分は、ここに来るような選手というのは、けっこうリーダー性を持っている人が多いなと思っていたんですね。そのなかでOBOGの方々もやっぱりキャプテンを経験している人が多くて、これも客観視ができるからなのかもしれないけれど、「全体を見ることができる人なんだな」と思いました。陸上が個人競技ということもあり、自分はどうしても全体のことよりは、自分の結果が一番になってしまっているのですが、今回、キャプテンになるような人たちが、どういう考え方で周り巻き込んでいくのかとか、チームをまとめるためにライフスキルトレーニングで学んだことをどう使っているのかとかを、詳しく聞くことができました。それは、競技場面にかかわらず、今後、就職したときなどにも役立ちそうだな、と。松岡さんも話したように、OBOGの皆さんが「どの時、どの場面で、“これ”を使えばいい」というのがわかっていたことがすごいなと感じました。
――原口選手は、OBOGとのセッションで、「周りを巻き込んでいけるようになるために、リーダー的な立場を経験しておいたほうがいいのか?」といった相談のような質問もしていましたね。布施先生が、「リーダーシップというのは、周りを巻き込んでいける力のことだよ」と何度も話していましたが、「リーダーになりたい」というよりは、そうした「みんなを巻き込んで、コミュニケーションを取っていけるようになりたい」という思いがあるように感じたのですが、いかがですか?
原口:はい。そうですね。自分がやっている走高跳の仲間だけでも、それぞれに考え方が違っていて、なかなか難しいものがあるので、違う種目も含めてになると、もっと難しくなるだろうなと思いながら聞いてみました。
――すでに主将としてチームを引っ張っていく立場になっている京竹選手はいかがでしょう? リーダーシップの話も含めて、OBOGの方々の話から何を感じましたか?
京竹:自分は、ライフスキルトレーニングを受ける前は、キャプテンを務めるなかで不安を感じたり悩んだりすることが多かったのですが、今回、先輩方の話を聞いて、「あ、ここは、こうすればいいのかな」と思うことができました。また、リーダーシップについては、これまでの講義でも、主将を務める人たちがどんな役割性格に使っているのかを教えていただけて、「自分も使えそうだな」と思う事柄が多かったので、そこも非常に学びが多かったですね。もう一つは、ほとんどの人が「ライフスキルトレーニングで学んだ事柄には、社会人になってから活かせたことがいっぱいある」と話していたこと。自分も来年は社会人となるなかで、講義で学んだことや、新たに知った価値観を大切にして、社会人になったときに競技以外の場面で活かしていきたいなと思いました。

――5人の先輩方の話のなかで、「これが、すごく刺さった」というものはありましたか?
京竹:そうですね…。池田さんや金光さんが言っていた「チームで“こういうふうにしたい”と気になっていることがあったら、すぐに口にしてみるといい」ということでしょうか。そこは今まで自分が感じていても、「みんないろいろな考えがあるから、まだ言わなくていいかな」という考え方をしていたところでした。でも、「自分の思いをしっかりと伝えると、みんなが考えてくれるきっかけになる」ということだったので、自分もそうふうにチームを巻き込んで、自分の思いを話していきたいなと思いました。
――そうしたコミュニケーションが、関係の質を高め、それによって、思考の質、行動の質、結果の質を高めることに繋がっていく…。講義で学んだ「勝ち続ける組織・選手のサイクル」を回していくための大切なポイントですよね。
ライフスキルトレーニングで、どんな変化を感じている?
――今回で、全4回の全体講義が終了したわけですが、このライフスキルトレーニングを受けたことで、ご自身に変化を感じているところ、あるいは周りから「変わったね」といわれたところはありますか?原口:他人から言われるほどの変化はまだないと思うのですが…。自分は、陸上は小学校からやっていますが、考えて練習をするようになったのは大学に入ってからなんですね。もともと「考える力」があまり身についていないなかで、ライフスキルトレーニングを受けたので、まだ「そのとき、これを使えばいい」というのを理解しきるところには至っていないというのが正直なところです。どちらかというと、今は、以前の出来事を振り返ってみて、「あそこで、こう使えばよかった」とか、「あのとき、この役割性格をつかっていたんだな」と気づく部分のほうが大きいかなと思います。
――講義のなかで、布施先生が「まず、自分のことを知ることが大事」と話していたところですね。「自分のこんなところを発見した!」という感じ、ありますか?
原口:あります。「自分自身を知る」ということを今までしようとしていなかったので、自分が「そのとき、どういう考え方をしている」というところからまず見直していったという感じ。そこで学んだことを、どう使おうかという段階なのかなと思っています。

提供:アフロスポーツ
――松岡さんは、何か変化を感じていますか?
松岡:私は、もともと…というか、今も(笑)、どちらかというと考えることが苦手でした。でも、この講義を通して、やっぱり自分を知らないと上のステップには行けないと痛感したので、意識的にではあるのですが、練習や試合のなかで、その日の最高目標と最低目標を頭に入れて臨むようになりました。「自分の目標に対して、今、自分がどの位置にいるのか」というのを把握するようになってから、「練習の充実度が上がったな」と感じています。あとは、「大きな目標」「小さな目標」を決める「ダブルゴール」の考え方は、なんとなく頭の片隅にはあったのですが、実際に書きだしてみるようになったことで、今までよりも自分のことを理解できるようになった気がしています。もし、この先、競技でうまくいかないことがあっても、それをやっていたことが問題解決の鍵になるんじゃないかとも感じています。1回立ち止まって自分のことを考える、すごくいい機会になりました。
――京竹選手は、どうですか?
京竹:自分も、松岡さんや原口くんと似ているのですが、「しっかり考えるようになったこと」が変化かなと思います。受講する前と比べて、じっくり考えて練習に取り組んだり、生活を送ったりすることができるようになりました。今までは、けっこう感覚派のタイプで、練習していて調子がいいときも、「なぜ」を考えることができていなくて、再現性がなかったんですね。でも、講義を受けて「仮説思考」を理解してからは、調子がいいときも悪いときも、「なんでそうなるのか」「こうやってみたらどうだろう」と、自分を実験台に、いろいろなトライ&エラーを繰り返し、データを集めていくことができるようになりました。それによって、シンプルに練習の質も上がったし、再現性も高まったのかなと感じています。
――シーズンインが楽しみですね。今季初戦は、いつ?
京竹:そうですね。けっこういろいろと挑戦してみたり、試したりはしてきたので、それがシーズンでどう生かされるのか、めっちゃ楽しみです。試合は、3日後が初戦で、400mハードルに出場します。
――何か目標は立てているのですか?
京竹:最高目標と最低目標は立てていて、記録や結果を狙うというよりは、「しっかり実験したいな」という気持ちです。試合でなければわからないところをチェックして、次に生かしていこうという位置づけで臨もうとしています。
――そういう考え方自体も、ライフスキルトレーニングをやったことで整理ができている印象ですね。
京竹:そうですね。それはすごく感じています。
ライフスキルトレーニングを実戦で活かす
――原口選手に、世界室内の話を伺いましょう。合宿の全体講義を受けたすぐあとに出発して、その週末に試合。そして、今は帰国したばかり…というところですね。同じ走高跳の戸邉選手のほか、福島選手も中村選手も話していましたが、世界のトップ選手といきなり「バーン」とぶち当たってみることを現場で体験できたのでは?原口:まさに「壁にぶち当たった」というか…(笑)。それをどう壊していくかというなかで、「勝つ」はまず考えず、僕のなかでは「最低限、記録を残そう」という気持ちで臨みました。それは達成できた(13位:2m14)のですが、「出るからには…」という思いもあって、やっぱり悔しい気持ちが多かったですね。あとは「自分と世界の選手のギャップ」がとても大きくて、でも、そこで「打ちのめされているわけにはいかない。得られるものは得て帰ろう」と、トップ選手の跳躍を生で見て分析して、自分が取り入れられることがないかを考えました。それができたことはよかったと思います。
――その経験は、大きな財産ですね。この先、絶対に役立ってくると思います。松岡さんも先週、シーズン初戦を、400mハードルでなく、400mで迎えていますよね。自己新、おめでとうございます! 400mは高校2年生の時以来の記録更新では?
松岡:はい。5年ぶりに出すことができました。
――レースは、全体講義を受けた翌週でしたよね。何か役に立つことはありましたか?
松岡:実は試合の前の調整段階では、走りも感覚もあまり良くなかったんです。それで不安な気持ちで臨んでいたのですが、「調子が悪いからこそ、今できることをやろう」と思い、それこそ「CSバランス」で考えました。「今の自分がいるのはここだから、そこよりちょっと高い目標を出せるように頑張ろう」と思って、ウォーミングアップとかも少し工夫して変えてみたら自己ベスト。それも一つ、実践知として経験になったなと思いました。
――この時期に、そういう状態のなか、自己記録を0.3秒も更新できたのなら、400mハードルのほうも楽しみですね。400mハードルの初戦はいつですか?
松岡:5月の静岡国際を予定しています。4月には入社後の研修などもあるのですが、目標を見失わずに練習していきたいと思います。

提供:アフロスポーツ
競技においてもキャリアにおいても、自分の“最高”を引きだすために
――では、最後に、ライフスキルトレーニングで学んだことを、今後、どう活用していきたいかを聞かせてください。京竹:今回、自分の課題であった論理的に考えることや、仮説思考のサイクルを回して物事に取り組んでいくことを学ぶことができたので、それらを使って、自分の最大限のパフォーマンスを発揮できるようになりたいです。講義で教えていただいた仮説思考やCSバランス、役割性格などをしっかり活用して、今後の競技生活や、その後の生活に活かしていこうと思っています。
原口:自分は、春から3年生になるのですが、競技面では、大会に挑む気持ちなどの面を、CSバランスや役割性格などをもっと使って結果に繋げていくことを目指しています。また、上級学年になってチームをまとめる部分も必要になってくるので、自分の実践知とかをうまく伝えていくことができるようになったらいいなと思います。
松岡:学んだスキルを自分のものにして、自分をもう一度見つめ直し、それを競技や社会人になってからの生活に活かしていきたいと思っています。また、役割性格をつくったり、トライ&エラーしたりすることは、自分の可能性の幅を広げるはず。そういう経験を積み重ねて、自分の考え方をもっと変えていきたいですね。「自分にはこういう力があったんだ」という発見をたくさんしていきたいと思うので、もっと挑戦的に、この考え方を使っていければと思います。
――皆さんが、「すごい!」と感じたOBOGの方々も、受講していたころは、皆さんと同じようなことに迷ったり、戸惑ったりしていました。でも、学んだ「考え方の技術」を磨き続けていると、こんなに成長するんだと思うと、数年後の皆さんの姿がとても楽しみです。本日は、どうもありがとうございました。
(2025年3月26日収録)
文・構成:児玉育美(JAAFメディアチーム)
■【ライフスキルトレーニング特設サイト】

>>特設サイトはこちら
■第5期ライフスキルトレーニングプログラム 全体講義振り返りインタビュー&グループコーチングレポート
【トップアスリートの目標の使い方】ライフスキルトレーニング第1回全体講義振り返りインタビュー:瀧野未来/渕上翔太/宮尾真仁https://www.jaaf.or.jp/news/article/21322/
第1回全体講義「トップアスリートの『目標の使い方』」事後グループコーチングレポート
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21328/
【オリンピックメダリストに共通する5つの特徴】ライフスキルトレーニング第2回全体講義振り返りインタビュー:髙須楓翔/白土莉紅
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21399/
【ライフスキルトレーニング】第3回全体講義振り返りインタビュー:樋口隼人/山本釉未
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21410/
■受講生インタビュー
<Vol.1>福島聖:社会人として生かせているスキル、就職活動や競技面に繋がった経験を語るhttps://www.jaaf.or.jp/news/article/17053/
<Vol.2>中島佑気ジョセフ:活躍の糸口となった経験、更なる飛躍に向けた想いを語る
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17064/
<Vol.3>樫原沙紀:「なりたい自分」を見つめ直し、新たな一歩を踏み出す
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17070/
<Vol.4>梅野倖子:アジア選手権・世界選手権・アジア大会で日の丸を背負った1年を振り返り、自身に生じた変化を語る
https://www.jaaf.or.jp/news/article/19163/
■第2期ライフスキルトレーニングプログラム 実施レポート
第1回 ~なりたい自分に近づくためのゴール設定と目標の使い方~https://www.jaaf.or.jp/news/article/15699/
第2回 ~オリンピックメダリストに共通する特徴と成功するための行動~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15782/
第3回 ~フローを生み出す自己決定能力の5ステップ~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15833/
第4回 ~重要な時に力を発揮する「獲得型思考」~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15940/
第2期総括イベント ~身につけたライフスキルを社会で生かす~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15964/
■第3期ライフスキルトレーニングプログラム 実施レポート&受講生コメント
第1回 ~目標設定の大切さとトップアスリートの仕事における強み~https://www.jaaf.or.jp/news/article/17305/
第2回 ~オリンピックメダリストに共通する5つの特徴~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17538/
第3回 ~社会でも活かせるトップアスリートの能力~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17562/
第4回 ~重要な時に力を発揮する「獲得型思考」~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17642/
■第4期ライフスキルトレーニングプログラム 実施レポート&受講生コメント
第1回 ~目指す成果を達成している組織が実践できている原理原則とダブルゴールの重要性について~https://www.jaaf.or.jp/news/article/19305/
第2回 ~プログラム初の合宿研修!オリンピックメダリストに共通する5つの特徴について~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/19440/
第3回 ~プログラム初の合宿研修!フローを生み出す自己決定能力の5ステップについて~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/19441/
第4回 ~重要な時に力を発揮する「獲得型思考」~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/19648/