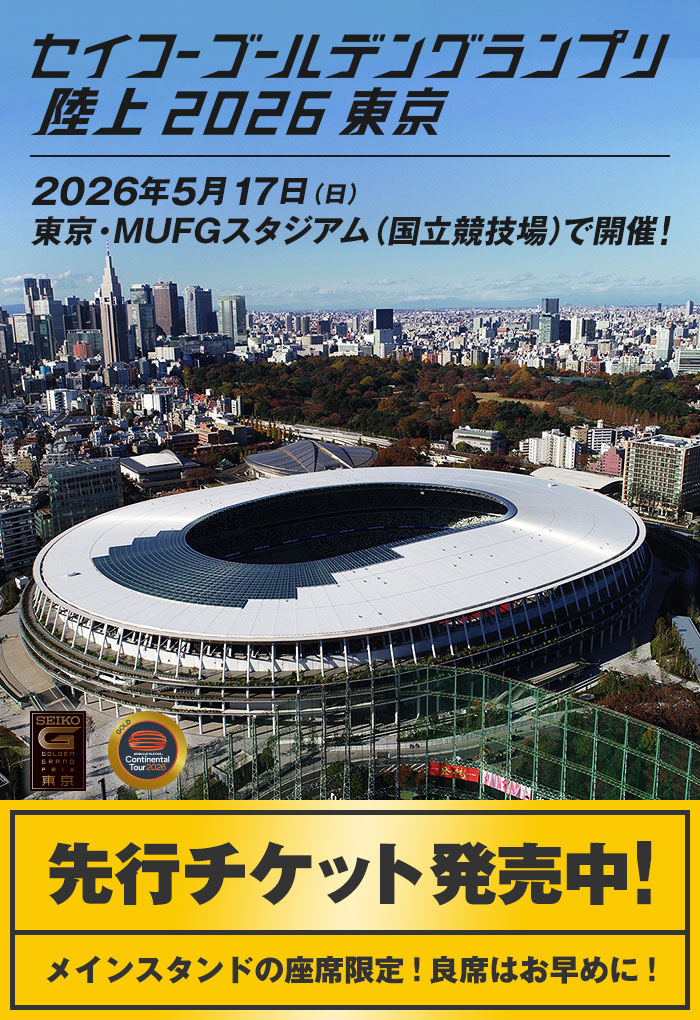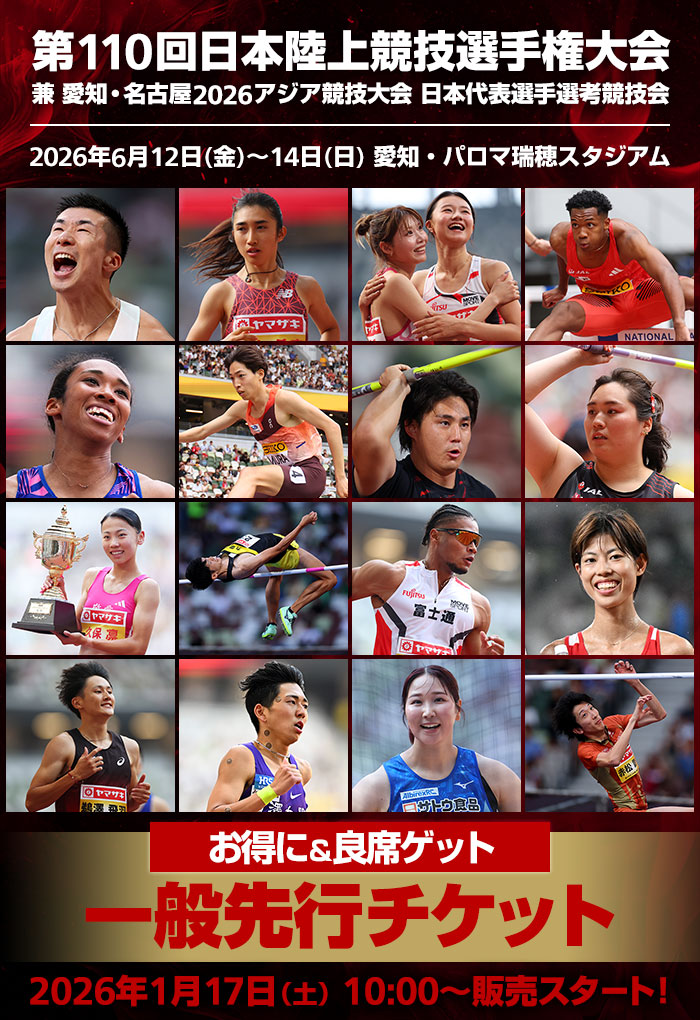9月13日(土)から21日(日)の9日間、国立競技場を舞台に20回目の世界選手権「東京2025世界陸上競技選手権大会(東京2025世界陸上)」が開催される。
日本での開催は、1991年(第3回)の東京(国立)、2007年(第11回)の大阪(長居)に続き3回目。国単位での開催回数では、最多である(2位は、フィンランドとドイツの2回)。
日本からは、全49種目のうちの38種目に80名(男子49名・女子31名)の代表選手がエントリーし、世界のライバル達と競い合う。
現地のスタンドあるいはテレビで観戦する方の「お供」に日本人選手が出場する全38種目と世界新記録や好勝負が期待される種目に関して、「記録と数字で楽しむ2025東京世界選手権」をお届けする。
なお、これまでにこの日本陸連HPで各種競技会の「記録と数字で楽しむ……」をお届けしてきたが、過去に紹介したことがある同じ内容のデータや文章もかなり含むが、可能な限りで最新のものに更新した。また、記事の中ではオリンピックについても「世界大会」ということで、そのデータも紹介している。
記録は原則として、世界選手権参加標準記録の有効期限であった25年8月24日現在のものによった。
現役選手の敬称は略させていただいた。
日本人選手の記録や数字に関する内容が中心で、優勝やメダルを争いそうな外国人選手についての展望的な内容には一部を除いてあまりふれていない。日本人の出場しない各種目の展望などは、陸上専門誌の観戦ガイドや今後ネットにアップされるであろう各種メディアの展望記事などをご覧頂きたい。
大会期間中は、日本陸連のX(https://x.com/jaaf_official)を中心に、記録や各種のデータを可能な範囲で随時発信する予定なので、そちらも「観戦のお供」にしていただければ幸いである。
▼「記録と数字で楽しむ東京2025世界陸上」記事一覧
こちらから>>
男子マラソン
・決勝 9月15日(月祝)08:00→07:30に変更吉田・近藤・小山が13年以来6大会ぶりの入賞に挑む
吉田祐也(GMOインターネットグループ/エントリー記録&自己記録2時間05分16秒=2024年・福岡国際)、近藤亮太(三菱重工/2時間05分39秒=2025年・大阪)、小山直城(Honda/2時間06分33秒=2024年・大阪)の3人が出場。いずれも世界選手権は初出場だが、小山は24年パリ五輪に続いての代表となった。大会3日目(9月15日)の朝8時00分にスタートする。国立競技場が発着点でコースは、24年パリ五輪の代表選考会となった「マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)」とかなり重なる部分が多い。
国立競技場のトラックを約2周して場外へ。外苑西通りを北上し富久町西で右折し靖国通りと外堀通りを右手にJRの線路を見ながら水道橋へ向かう。東京ドームを左に通り過ぎたところで右折し古本屋街で有名な神保町(約8km地点)へ。ここから1周約13kmの周回コースに入る。
神保町→須田町→秋葉原→須田町→日本橋→銀座4丁目で折り返し再び同じ経路で神保町へ戻る。そのあとは、南下して皇居の内濠沿いに東京駅中央口(丸の内側)の前を折り返し再び神保町へ。これが1周約13kmでそのコースを2周したあと往路と同じ経路で国立競技場に戻るという42.195kmだ。
序盤の3km付近から6km付近が約25mの下りでその後は高低差数mの細かなアップダウンはあるがほぼ平坦なコース。序盤とは反対に終盤の37km付近から40km付近まで続く約25mの上り坂がメダル争いや入賞争いの勝負を決する大きなポイントとなりそうだ。
◆世界選手権&五輪での日本人最高成績と最高記録◆
<世界選手権>最高成績 1位 2.14.57. 谷口浩美(旭化成)1991年
最高記録 2.08.35. 西山雄介(トヨタ自動車)2022年 13位
<五輪>
最高成績 1位 2.29.19.2 孫基禎(養成高普)1936年
最高記録 2.07.32. 赤﨑暁(九電工)2024年 6位
「世界選手権」での入賞者は下記の通り。
| 1991年 | 1位 | 2.14.57. | 谷口浩美(旭化成) |
|---|---|---|---|
| 〃 | 5位 | 2.15.52. | 篠原太(神戸製鋼) |
| 1993年 | 5位 | 2.17.54. | 打越忠夫(雪印) |
| 1999年 | 3位 | 2.14.07. | 佐藤信之(旭化成) |
| 〃 | 6位 | 2.15.45. | 藤田敦史(富士通) |
| 〃 | 7位 | 2.15.50. | 清水康次(NTT西日本) |
| 2001年 | 5位 | 2.14.07. | 油谷繁(中国電力) |
| 〃 | 8位 | 2.17.05. | 森下由輝(旭化成) |
| 2003年 | 5位 | 2.09.26. | 油谷繁(中国電力) |
| 2005年 | 3位 | 2.11.16. | 尾方剛(中国電力) |
| 〃 | 4位 | 2.11.53. | 高岡寿成(カネボウ) |
| 2007年 | 5位 | 2.17.42. | 尾方剛(中国電力) |
| 〃 | 6位 | 2.18.06. | 大崎悟史(NTT西日本) |
| 〃 | 7位 | 2.18.35. | 諏訪利成(日清食品) |
| 2009年 | 6位 | 2.12.05. | 佐藤敦之(中国電力) |
| 2011年 | 6位 | 2.11.52. | 堀端宏行(旭化成)=4位の選手がのちに失格で1つ繰り上がり |
| 2013年 | 5位 | 2.10.50. | 中本健太郎(安川電機) |
19大会のうち10大会で入賞を果たし、金1個と銅2個を獲得し、15名が計17回入賞している。
参考までに「五輪」での入賞者は以下の通り。
| 1928年 | 4位 | 2.35.29. | 山田兼松(坂出青年) |
|---|---|---|---|
| 〃 | 6位 | 2.36.20. | 津田晴一郎(慶大) |
| 1932年 | 5位 | 2.35.42. | 津田晴一郎(慶大OB) |
| 〃 | 6位 | 2.37.28. | 金恩培(養正高普) |
| 1936年 | 1位 | 2.29.19. | 2孫基禎(養正高普) |
| 〃 | 3位 | 2.31.42.0 | 南昇龍(明大) |
| 1956年 | 5位 | 2.29.19. | 川島義明(日大) |
| 1964年 | 3位 | 2.16.22.8 | 円谷幸吉(自衛隊) |
| 1968年 | 2位 | 2.23.31.0 | 君原健二(八幡製鉄) |
| 1972年 | 5位 | 2.16.27. | 君原健二(新日鉄) |
| 1984年 | 4位 | 2.10.55. | 宗猛(旭化成) |
| 1988年 | 4位 | 2.11.05. | 中山竹通(ダイエー) |
| 1992年 | 2位 | 2.13.45. | 森下広一(旭化成) |
| 〃 | 4位 | 2.14.02. | 中山竹通(ダイエー) |
| 〃 | 8位 | 2.14.42. | 谷口浩美(旭化成) |
| 2004年 | 5位 | 2.13.11. | 油谷繁(中国電力) |
| 〃 | 6位 | 2.13.24. | 諏訪利成(日清食品) |
| 2012年 | 6位 | 2.11.16. | 中本健太郎(安川電機) |
| 2021年 | 6位 | 2.10.41. | 大迫傑(Nike) |
| 2024年 | 6位 | 2.07.32. | 赤﨑暁(九電工) |
なお、五輪で8位までが入賞となったのは1984年ロサンゼルス大会からで、それまでは6位までが入賞だった。
◆世界選手権&五輪での国別歴代得点◆
各大会の1位に8点、2位7点~8位1点の点数で直近の大会までの国別得点を集計すると次のようになる。1983年に始まった世界選手権は、
【世界選手権での国別得点(2023年大会まで)】
| 順)点 | 国名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | 入賞数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)116 | ETH | 3 | 6 | 4 | 3 | ・ | 2 | 2 | 1 | = | 21 | エチオピア |
| 2)96 | KEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ・ | 2 | 4 | = | 20 | ケニア |
| 3)66 | JPN | 1 | ・ | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | = | 17 | 日本 |
| 4)58 | ITA | ・ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | = | 16 | イタリア |
| 5)51 | ESP | 3 | 2 | ・ | ・ | 1 | 2 | ・ | 3 | = | 11 | スペイン |
| 6)33 | UGA | 2 | ・ | 1 | ・ | 1 | 2 | ・ | 1 | = | 7 | ウガンダ |
| 7)27 | MAR | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | = | 5 | モロッコ |
| 8)26 | TAN | ・ | 1 | 1 | ・ | 2 | 1 | 1 | ・ | = | 6 | タンザニア |
| 9)22 | GBR | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | ・ | 1 | 1 | = | 6 | イギリス |
| 10)20 | AUS | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 4 | オーストラリア |
| 11)18 | ERI | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | = | 4 | エリトリア |
| 12)16 | BRA | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 5 | ブラジル |
| 13)14 | USA | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 2 | アメリカ |
| 14)14 | DJI | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 2 | ジブチ |
| 15)10 | POR | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 2 | ポルトガル |
| 16)9 | MEX | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | = | 2 | メキシコ |
| 17)9 | GER | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | = | 2 | ドイツ |
| 17)9 | BEL | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | = | 2 | ベルギー |
| 19)7 | NAM | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | ナミビア |
| 19)7 | QAT | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | カタール |
| 19)7 | ISR | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | イスラエル |
| 22)6 | NED | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | オランダ |
| 22)6 | SUI | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | スイス |
| 24)6 | BRN | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | = | 2 | バーレーン |
| 24)6 | RSA | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | = | 2 | 南アフリカ |
| 26)5 | KOR | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | 韓国 |
| 26)5 | POL | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | ポーランド |
| 26)5 | SWE | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | スウェーデン |
| 26)5 | CAN | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | カナダ |
| 26)5 | LES | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | レソト |
| 31)2 | FRA | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | = | 1 | フランス |
| 32)1 | ALG | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 1 | アルジェリア |
| 32)1 | RUS | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 1 | ロシア |
| 32)1 | URS | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 1 | ソ連 |
23年ブダペストでもエチオピアの3・6位に対し、ケニアは8位のみで点差が広がった。
ブダペストでウガンダが1・5位で12点を加算して8位から6位に浮上。
日本は、エチオピア、ケニアに次いで3位だが、09年ベルリン大会終了時点ではトップだった。
以下に23年大会終了時点の得点の上位5国について、累計得点と順位の推移をまとめてみた。
| 年 | JPN | KEN | ETH | ITA | ESP | 他の上位国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 未入賞 | 未入賞 | 2)7 | 7)2 | 未入賞 | 1)8 AUS |
| 1987年 | 未入賞 | 3)8 | 4)7 | 2)10 | 未入賞 | 1)13 AUS |
| 1991年 | 4)12 | 5)8 | 6)7 | 2)14 | 未入賞 | 1)14 DJI |
| 1993年 | 1)16 | 6)10 | 7)7 | 4)14 | 未入賞 | 2)14 USA |
| 1995年 | 1)16 | 8)10 | 11)7 | 6)14 | 2)15 | 3)14 USA |
| 1997年 | 4)16 | 9)10 | 12)7 | 2)21 | 1)33 | 3)20 AUS |
| 1999年 | 3)27 | 9)10 | 12)7 | 2)32 | 1)42 | 4)20 AUS |
| 2001年 | 3)32 | 10)17 | 4)22 | 2)38 | 1)42 | 5)20 AUS |
| 2003年 | 3)36 | 6)18 | 4)22 | 2)47 | 1)49 | 5)20 AUS |
| 2005年 | 2)47 | 5)20 | 4)22 | 3)47 | 1)50 | 6)20 AUS |
| 2007年 | 1)56 | 4)29 | 5)22 | 3)47 | 2)50 | 6)20 AUS |
| 2009年 | 1)59 | 3)48 | 5)33 | 4)47 | 2)51 | 6)21 MAR |
| 2011年 | 2)62 | 1)72 | 5)39 | 4)49 | 3)51 | 6)21 MAR |
| 2013年 | 2)66 | 1)72 | 3)58 | 5)49 | 4)51 | 6)21 MAR |
| 2015年 | 3)66 | 1)72 | 2)67 | 4)55 | 5)51 | 6)21 MAR |
| 2017年 | 3)66 | 1)85 | 2)74 | 4)58 | 5)51 | 6)24 TAN |
| 2019年 | 3)66 | 1)91 | 2)89 | 4)58 | 5)51 | 6)27 MAR |
| 2022年 | 3)66 | 2)95 | 1)107 | 4)58 | 5)51 | 6)27 MAR |
| 2023年 | 3)66 | 2)96 | 1)116 | 4)58 | 5)51 | 6)33 UGA |
| 大会回数(西暦年) | JPN | KEN | ETH | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5回(1983~1995) | 16 | 10 | 7 | 14 | 15 |
| 6~10回(1997~2005) | 31 | 10 | 15 | 33 | 35 |
| 11~15回(2007~2015) | 19 | 52 | 45 | 8 | 1 |
| 16~18回(2017~2023) | 0 | 24 | 49 | 3 | 0 |
| 合計得点 | 66 | 96 | 116 | 58 | 51 |
1983年から始まった世界選手権ではエチオピア、ケニア、モロッコ、タンザニア、ウガンダとトップ10のうち半数をアフリカ勢が占めている。五輪では「131点」で断然トップのアメリカは「14点」で13位にとどまっている。
参考までに五輪の国別得点は以下の通り。
1980年までは6位入賞だったが、ここでは84年からと同じく8位までの順位で得点を集計した。
【五輪での国別得点(2024年大会まで)】
| 順)点 | 国名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | 8位以内数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)131 | USA | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | = | 30 | アメリカ |
| 2)89 | JPN | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ・ | 1 | = | 20 | 日本 |
| 3)83 | ETH | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ・ | = | 15 | エチオピア |
| 4)83 | GBR | ・ | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | = | 19 | イギリス |
| 5)76 | KEN | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | = | 13 | ケニア |
| 6)63 | FIN | 2 | ・ | 3 | 2 | 4 | ・ | 1 | 1 | = | 13 | フィンランド |
| 7)47 | FRA | 3 | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 2 | = | 9 | フランス |
| 8)42 | RSA | 2 | 2 | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | 1 | = | 8 | 南アフリカ |
| 9)40 | GRE | 1 | 1 | ・ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | = | 10 | ギリシャ |
| 10)39 | ITA | 2 | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | = | 8 | イタリア |
| 11)33 | BEL | ・ | 2 | 2 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | = | 6 | ベルギー |
| 12)32 | SWE | ・ | 1 | 2 | 1 | ・ | 1 | 1 | 3 | = | 9 | スウェーデン |
| 13)30 | ARG | 2 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | = | 5 | アルゼンチン |
| 14)28 | URS | ・ | ・ | 1 | 2 | 2 | ・ | 2 | 1 | = | 8 | ソ連 |
| 15)26 | CAN | 1 | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | 2 | ・ | = | 7 | カナダ |
| 16)25 | KOR | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 3 | 韓国 |
| 17)22 | GER | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 2 | ドイツ |
| 18)21 | UGA | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | = | 4 | ウガンダ |
| 19)20 | MAR | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | = | 5 | モロッコ |
| 20)16 | AUS | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | 2 | 1 | = | 6 | オーストラリア |
| 21)13 | NZL | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 3 | ニュージーランド |
| 22)12 | TCH/CZE | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | = | 3 | チェコスロバキア/チェコ |
| 23)12 | HUN | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | = | 3 | ハンガリー |
| 24)11 | BRA | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | = | 3 | ブラジル |
| 25)10 | CHI | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | = | 2 | チリ |
| 26)9 | POR | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 2 | ポルトガル |
| 27)9 | TAN | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | = | 3 | タンザニア |
| 28)8 | ESP | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | = | 2 | スペイン |
| 29)7 | EST | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | エストニア |
| 29)7 | IRL | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | アイルランド |
| 29)7 | NED | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | オランダ |
| 29)7 | YUG/SRB | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | ユーゴスラビア/セルビア |
| 29)7 | ISR | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | イスラエル |
| 34)7 | DJI | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 1 | ジブチ |
| 35)7 | DEN | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 1 | = | 3 | デンマーク |
| 35)7 | MEX | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 1 | = | 3 | メキシコ |
| 37)6 | ERI | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 2 | エリトリア |
| 38)5 | CUB | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | キューバ |
| 38)5 | TUR | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | トルコ |
| 38)5 | LES | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | = | 1 | レソト |
| 41)5 | SUI | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | = | 2 | スイス |
| 42)2 | LES | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | = | 1 | レスト |
| 42)2 | POL | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | = | 1 | ポーランド |
| 42)2 | ZIM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | = | 1 | ジンバブエ |
| 45)1 | NOR | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | = | 1 | ノルウェー |
が、五輪は1896年の第1回大会から直近のパリまでに128年の歴史を刻んできただけに、1956年が初参加のケニアとエチオピアの得点は、初期の頃から参加しているアメリカ、日本には届いていない。しかし24年パリでエチオピアが優勝と5位となってイギリスに追いついて3位に上がってきた。
五輪2位、世界選手権も3位に位置している「マラソン日本」は、よく頑張っている。しかし、ケニア、エチオピアが今後も得点をどんどん積み重ねていくことは間違いない。他国に抜かれることなく、何とか3位の位置をキープしていってもらいたい。
◆各年の世界100傑内の国別人数◆
コロナの影響で主要なレースの中止が多かった20年と21年を除き、この10年あまりは、ケニアとエチオピアの2国で100傑中の8~9割前後を占めている。00年の段階では両国のシェアは5割に満たなかったが、10年には9割近くに達した。その中で日本は孤軍奮闘で頑張っているといえよう。2000年以降の5年毎と2016年からの1年毎の各年の世界100傑に占める国別人数は以下の通り。
| 年 | 100位 | KEN | ETH | JPN | UGA | MAR | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.11.23. | 40 | 6 | 13 | 0 | 2 | 39(18国) |
| 2005 | 2.11.24. | 52 | 9 | 10 | 0 | 0 | 28(13国) |
| 2010 | 2.09.31. | 57 | 29 | 0 | 1 | 5 | 8(6国) |
| 2015 | 2.09.14. | 60 | 31 | 3 | 1 | 0 | 6(5国) |
| 2016 | 2.09.28. | 67 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4(4国) |
| 2017 | 2.09.11. | 61 | 26 | 4 | 1 | 1 | 7(9国) |
| 2018 | 2.08.46. | 50 | 26 | 8 | 1 | 2 | 13(10国) |
| 2019 | 2.07.58. | 44 | 39 | 1 | 2 | 2 | 13(10国) |
| 2020 | 2.08.46. | 21 | 43 | 18 | 1 | 2 | 15(9国) |
| 2021 | 2.07.40. | 39 | 29 | 11 | 2 | 2 | 17(8国。ERIが「9名」で4位) |
| 2022 | 2.07.12. | 38 | 38 | 1 | 2 | 2 | 19(13国。ERIが「5名」で3位。FRA・TANが「2名」) |
| 2023 | 2.06.55. | 36 | 35 | 5 | 1 | 2 | 21(14国。FRAが「4名」で4位。ISRが「3名」で5位) |
| 2024 | 2.06.54. | 39 | 32 | 7 | 1 | 1 | 22(19国。ERI・GER・ISR・ITAが「3名」で4位タイ) |
| 2025 | 2.07.18. | 35 | 30 | 14 | 2 | 3 | 16(18国。ERI・MARが「3名」で4位タイ。GER・MARが「2名」) |
ケニアとエチオピア以外にもモロッコ、ウガンダ、エリトリアなど東アフリカ勢が進出してきている。
また、国籍変更でケニアやエチオピアなどから中東やヨーロッパの国に移った選手も増えてきている。
そんな中、日本は健闘している。
記録では世界をリードするケニア勢だが、13・15年の世界選手権では誰も入賞できず。22年オレゴン5位、23年ブダペスト8位、24年パリ五輪も3位で複数入賞はできていない。
「フラットなコース」「涼しい気温」のいい条件の中でペースメーカーが30㎞付近までハイペースで先導する「高速レース」では好タイムを量産しているが、真夏でペースメーカーのいない「勝負優先」の世界選手権や五輪では、なかなか持ちタイム通りにはいかないことも多いようだ。
16年リオ五輪以降の至近7回の世界大会での東アフリカやそれらの国にルーツを持たない選手の入賞は、16年リオ五輪が2名(3・6位)、17年ロンドン世界選手権が2名(4・6位)、19年ドーハ世界選手権が2名(4・5位)、21年東京五輪が2名(6・7位)、22年オレゴン世界選手権が3名(3・4・8位)、23年ブダペスト世界選手権が3名(2・4・7位)、24年パリ五輪が4名(4・6・7・8位)だった。持ちタイムでは大きな差があっても、夏場でペースメーカーが不在の五輪や世界選手権では、東アフリカ系以外の選手も8位以内に毎回2名は入っている。つまり、日本勢にもチャンスがあるということだ。
日本人トリオを上回るタイムの選手が世界リストで何十人いようとも、世界選手権には前回優勝のウガンダからマックス4名、ケニアとエチオピアからは3名ずつしか出場してこない。他のアフリカ勢などに競り勝てれば、東京五輪の大迫、パリ五輪の赤﨑のように「入賞」がみえてくる。
◆五輪&世界選手権の気象状況と記録◆
以下の「表」に1983年以降の「世界選手権」と「五輪」での「気温・湿度」と「優勝・3位・8位の記録」「完走率」を示した。夏場に行われる世界選手権と五輪の1983年以降の気温と湿度、1・3・8位の記録とトップの前後半タイム、完走率をまとめた。
・気象状況は、リザルトに記載されているもの。
・リザルトに記載がないものは、世界陸連発行の資料(Statistics Handbook)に掲載のデータ。
・それにもないものは、両陸上専門月刊誌に掲載された記事のデータ。
日本国内のレースでは、リザルト用紙に「スタート時」「5㎞地点」「10㎞地点」などの「天候」「気温」「湿度」「風向」「風速」が細かく記載されることが多いが、海外では「天候」の記載もあまりなく、「スタート時と終了時」あるいは「スタート時」の「気温と湿度」のみだったりがほとんどだ。また「終了時」もトップ選手のフィニッシュ時点の場合であったり最終走者のフィニッシュ時点の場合であったりする。
「1位・3位・8位」の記録については、数年後に「ドーピングで失格」などで繰り上がった場合の修正をきちんとできていない場合があるかもしれないことをお断りしておく。
「完走率(完走者/出場者)」は、のちに「ドーピング違反」などで「失格」となった者のうち、フィニッシュラインを越えたことが確かな者については「完走」として扱った。
【1983年以降の世界選手権と五輪の気温と湿度、1・3・8位の記録とトップの前後半タイム、完走率】
・「前半」は、その時点でトップの選手の通過タイムで優勝者のものとは限らない。
・「◎」は、各項目の最高記録。
| 年 | スタート時→終了時 | 優勝記録 | (前半+後半/前後半差) | 3位記録 | 8位記録 | 完走率(完走者/出場者) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 15℃・35%→?℃・?% | 2.10.03. | (??.??.+??.??./????) | 2.10.37. | 2.11.15. | 75.3%(63/81) |
| 1984五輪 | 27℃・?%→?℃・?% | 2.09.21. | (??.??.+??.??./????) | 2.09.58. | 2.11.39. | 72.2%(78/108) |
| 1987 | 21℃・83%→22℃・74% | 2.11.48. | (65.37.+66.11./▼0.34.) | 2.12.40. | 2.14.41. | 72.3%(47/65) |
| 1988五輪 | 25℃・74%→?℃・?% | 2.10.32. | (64.49.+65.43./▼0.54.) | 2.10.59. | 2.13.07. | 80.3%(98/122) |
| 1991 | 26℃・73%→28℃・58% | 2.14.57. | (66.25.+68.32./▼2.07.) | 2.15.36. | 2.17.03. | 60.0%(36/60) |
| 1992五輪 | 25℃・72%→?℃・?% | 2.13.23. | (67.22.+66.01./△1.21.) | 2.14.00. | 2.14.42. | 79.1%(87/110) |
| 1993 | 25℃・63%→25℃・63% | 2.13.57. | (66.30.+67.27./▼0.57.) | 2.15.12. | 2.18.52. | 63.2%(43/68) |
| 1995 | 26℃・43%→?℃・?% | 2.11.41. | (66.54.+64.47./△2.07.) | 2.12.49. | 2.16.13. | 68.8%(53/77) |
| 1996五輪 | 23℃・92%→?℃・?% | 2.12.36. | (67.36.+65.00./△2.36.) | 2.12.36. | 2.14.55. | 89.5%(111/124) |
| 1997 | 29℃・48%→?℃・?% | 2.13.16. | (67.08.+66.08./△1.00.) | 2.14.16. | 2.17.44. | 64.8%(70/108) |
| 1999 | 29℃・43%→28℃・?% | 2.13.36. | (67.24.+66.12./△1.12.) | 2.14.07. | 2.16.17. | 81.3%(65/80) |
| 2000五輪 | 21℃・18%→?℃・?% | 2.10.11. | (65.02.+65.09./▼0.07.) | 2.11.10. | 2.14.04. | 81.0%(81/100) |
| 2001 | 19℃・58%→28℃・?% | 2.12.42. | (66.59.+65.43./△1.16.) | 2.13.18. | 2.17.05. | 76.0%(73/96) |
| 2003 | 15℃・72%→?℃・?% | 2.08.31. | (64.45.+63.46./△0.59.) | 2.09.14. | 2.10.35. | 77.5%(69/89) |
| 2004五輪 | 30℃・39%→?℃・?% | 2.10.55. | (67.23.+63.32./△3.52.) | 2.12.11. | 2.14.17. | 80.2%(81/101) |
| 2005 | 17℃・88%→17℃・88% | 2.10.10. | (64.17.+65.53./▼1.36.) | 2.11.16. | 2.12.51. | 64.2%(61/95) |
| 2007 | 28℃・81%→33℃・67% | 2.15.59. | (68.29.+67.30./△0.59.) | 2.17.25. | 2.19.21. | 67.1%(57/85) |
| 2008五輪 | 24℃・52%→30℃・39% | 2.06.32. | (62.34.+63.58./▼1.24.) | 2.10.00. | 2.11.11. | 80.0%(76/95) |
| 2009 | 18℃・73%→21℃・49% | 2.06.54. | (63.03.+63.51./▼0.48.) | 2.08.35. | 2.14.04. | 76.9%(70/91) |
| 2011 | 26℃・56%→29℃・47% | 2.07.38. | (65.07.+62.31./△2.36.) | 2.10.32. | 2.11.57. | 76.1%(51/67) |
| 2012五輪 | 23℃・78%→25℃←途中 | 2.08.01. | (63.15.+64.46./▼1.31.) | 2.09.37. | 2.12.17. | 81.0%(85/105) |
| 2013 | 23℃・38%→23℃・38% | 2.09.51. | (65.12.+64.39./△0.33.) | 2.10.23. | 2.11.43. | 72.9%(51/70) |
| 2015 | 22℃・73%→?℃・?% | 2.12.28. | (66.52.+65.36./△1.16.) | 2.13.30. | 2.14.54. | 65.6%(42/64) |
| 2016五輪 | 24℃・?%→?℃・?% | 2.08.44. | (65.55.+62.49./△3.06.) | 2.10.05. | 2.11.49. | 89.7%◎(139/155) |
| 2017 | 18℃・60%→?℃・?% | 2.08.27. | (65.28.+62.59./△2.29.) | 2.09.51. | 2.12.16. | 72.4%(71/98) |
| 2019 | 29℃・51%→29℃・51% | 2.10.40. | (65.57.+64.43./△1.14.) | 2.10.51. | 2.11.49. | 75.3%(55/73) |
| 2021五輪 | 26℃・80%→27℃・77% | 2.08.38. | (65.13.+63.25./△1.48.) | 2.10.00. | 2.11.41. | 71.7%(76/106) |
| 2022 | 13℃・88%→16℃・79% | 2.05.36.◎ | (64.08.+61.28./△2.40.) | 2.06.48.◎ | 2.07.35.◎ | 87.1%(54/62) |
| 2023 | 22℃・77%→28℃・61% | 2.08.53. | (65.02.+63.51./△1.11.) | 2.09.19. | 2.10.47. | 71.4%(60/84) |
| 2024五輪 | 17℃・74%→22℃・57% | 2.06.26. | (64.51.+61.35./△3.16.) | 2.07.00. | 2.08.12. | 87.7%(71/81) |
| 最高記録 | 2.05.36.(22) | 2.06.48.(22) | 2.07.35.(22) | 89.7%(16)=最高完走率 | ||
| 最低記録 | 2.15.59.(07) | 2.17.25.(07) | 2.19.21.(07) | 60.0%(91)=最低完走率 | ||
| 世選最高記録 | 2.05.36.(22) | 2.06.48.(22) | 2.07.35.(22) | |||
| 五輪最高記録 | 2.06.26.(24) | 2.07.00.(24) | 2.08.12.(24) |
前後半のタイムが判明している28大会のうち前半の方が後半よりも速かったのは9大会(32.1%)で、残る19大会(67.9%)は、後半の方が速い「ネガティブ・スプリット」だった。95年以降は23大会中18回(78.3%)が後半にペースアップしていて、13年以降の至近9大会はすべて後半の方が速い。
前後半の差が最も大きかったのは、涼しい中での24年パリ五輪で後半の方が3分16秒も速く、同じく涼しかった22年オレゴン世界選手権も後半が2分40秒速かった。パリ五輪の30km以降の5km毎は、14分02秒-14分48秒-6分24秒(5km換算14分35秒)で残り12.195kmは35分14秒(10km換算28分53秒5)。また、オレゴンの30㎞以降は、14分12秒-14分09秒-6分06秒(5㎞換算13分54秒)で残り12.195kmは34分27秒(10km換算28分15秒)で押し切っている。トラック10000mの24年日本100位は28分17秒90で、28分15秒は87位相当。30kmを走ってきたあとに、そんなスピードでカバーできなければ涼しい条件下での「世界の金メダル」は手にすることができないのである。
◆9月15日の東京の過去3年間の気象状況◆
レースがスタートするのは、9月15日の午前8時00分。過去3年間の1時間ごとの気象状況を調べてみたのが下記だ。
【過去3年間の9月15日の東京の気象状況】
| 時刻 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 8時00分 | 晴・30.4℃・74% | 晴・28.9℃・80% | 曇・22.9℃・72% |
| 9時00分 | 晴・31.5℃・65% | 曇・30.4℃・74% | 曇・23.2℃・73% |
| 10時00分 | 晴・32.9℃・62% | 曇・31.2℃・67% | 曇・24.0℃・73% |
◆気温による記録の低下率◆
五輪や世界選手権はペースメーカー不在で「記録ではなく勝負」のレース。といっても持ちタイムがいい選手ほど、暑い中でどんなペースになろうとも「余裕」があることは確かだろう。
気温による記録の低下率に関して、これまでにも何度か紹介したことがあるデータを示す。
1960年代から70年代にかけての古いものだが、故・高橋進氏の研究によって、「気温がマラソンの記録に及ぼす影響」のデータが示されている(「マラソン(講談社。1981年)」)。
下表がそれだ。
24年パリ五輪選手選考に関して日本陸連が示した「代表内定条件」は、「23年10月のMGC(マラソン・グランド・チャンピオンシップ)で、1・2位が内定」。「3人目」は24年3月までの指定レースで「2時間05分50秒以内」で走った中で最も記録が良かった選手というものだった。今回の東京世界選手権代表のエントリー記録&自己ベストは、2時間05分16秒、同05分39秒、同06分33秒でその平均は、何と「2時間05分49秒33」で、パリ五輪の3人目の選考基準記録とピタリ同じ。
そんなことで、下記の「推定される記録」は、筆者(野口)が、「2時間05分50秒」を基準に、高橋氏の示した阻害率から計算した記録の範囲である。
【気温によって記録が阻害される率】
| 気温 | 暑さに強い選手 | 暑さに弱い選手 | 推定される記録2.05.50.基準 |
|---|---|---|---|
| 14℃ | 0.00% | 0.20% | 2.05.50.~2.06.05. |
| 15℃ | 0.00% | 0.50% | 2.05.50.~2.06.28. |
| 16℃ | 0.00% | 1.00% | 2.05.50.~2.07.06. |
| 17℃ | 0.00% | 2.00% | 2.05.50.~2.08.21. |
| 18℃ | 0.00% | 3.00% | 2.05.50.~2.09.37. |
| 19℃ | 0.30% | 3.50% | 2.06.13.~2.10.15. |
| 20℃ | 0.50% | 4.00% | 2.06.28.~2.10.52. |
| 21℃ | 1.00% | 4.50% | 2.07.06.~2.11.30. |
| 22℃ | 1.00% | 5.00% | 2.07.06.~2.12.08. |
| 23℃ | 1.50% | 6.00% | 2.07.44.~2.13.23. |
| 24℃ | 2.00% | 6.50% | 2.08.21.~2.14.01. |
| 25℃ | 2.50% | 7.00% | 2.08.59.~2.14.39. |
| 26℃ | 3.00% | 7.50% | 2.09.37.~2.15.17. |
| 27℃ | 3.50% | 8.00% | 2.10.15.~2.15.54. |
| 28℃ | 4.00% | 9.00% | 2.10.52.~2.17.10. |
| 29℃ | 5.00% | 10.00% | 2.12.08.~2.18.25. |
| 30℃ | 6.00% | 11.00% | 2.13.23.~2.19.41. |
| 31℃ | 7.00% | 12.00% | 2.14.39.~2.20.56. |
| 32℃ | 8.00% | 13.00% | 2.15.54.~2.22.12. |
| 33℃ | 9.00% | 14.00% | 2.17.10.~2.23.27. |
| 34℃ | 10.00% | 15.00% | 2.18.25.~2.24.43. |
| 35℃ | 11.00% | 16.00% | 2.19.41.~2.25.58. |
先に示した通り、過去3年間のデータからすると今回の東京では30℃前後で湿度も60~80%くらいの中でのレースになる可能性が高そうだ。
「暑さに強い選手」であっても、その阻害率は5%前後かそれ以上、「暑さに弱い選手」であれば10%前後かそれ以上くらいとなり、「暑さにやられて後半に大きく失速」ということもありそだ。
25℃を超えるレースでは前半がスローペースになることが多いが、今回もそうなるかもしれない。
先にも述べたが、同じ程度の気温であっても、当日が「晴れ」か「曇り」か「雨」かによって、展開は大きく変わりそうだ。
「メダル」のためには、前半がどうであれ後半の30km過ぎからは14分台半ばか前半の一気のスピードアップに対応しなければならないようである。
野口純正(国際陸上競技統計者協会[ATFS]会員)
写真提供:アフロスポーツ
【東京2025世界陸上】9月13日~21日 国立競技場開催

>>https://www.jaaf.or.jp/wch/tokyo2025/
◆期日:2025年9月13日(土)~21日(日)
◆会場:国立競技場(東京)
◆チケット情報:https://tokyo25-lp.pia.jp/
【東京2025世界陸上】応援メッセージキャンペーン

夢の舞台に立ち、世界に挑む選手たちに向けた「応援メッセージ」を大募集します!
いただいたメッセージは、選手のプロフィールページや本連盟公式ウェブサイにて紹介し選手へ届けます。
皆様からのメッセージは、サンライズレッドをまとい世界の強豪と戦う選手たちにとって大きな力になるはずです!
たくさんのエールをお待ちしております。
▼こちらから▼
https://www.jaaf.or.jp/wch/tokyo2025/news/article/22465/
【国立満員プロジェクト】日本代表を応援!
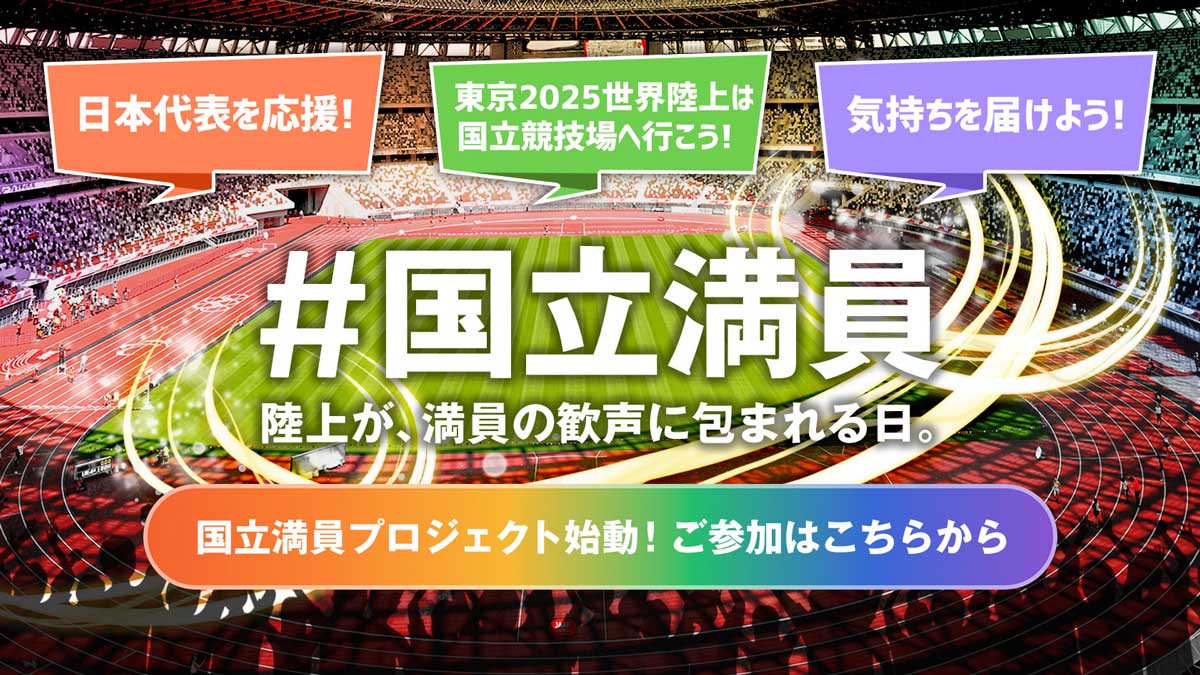
東京2025世界陸上は国立競技場へ行こう!
あなたの「行こう!」の声が、応援する気持ちが、次の誰かを動かします。
抽選で、日本代表選手サイン入りグッズや応援タオルをプレゼント!ぜひご参加ください!