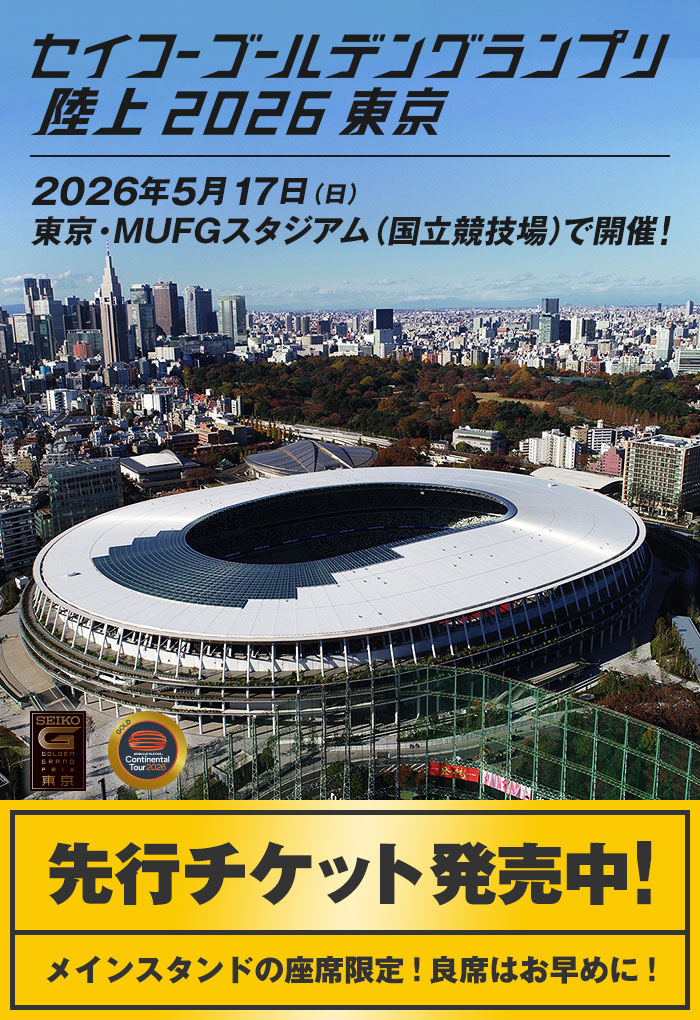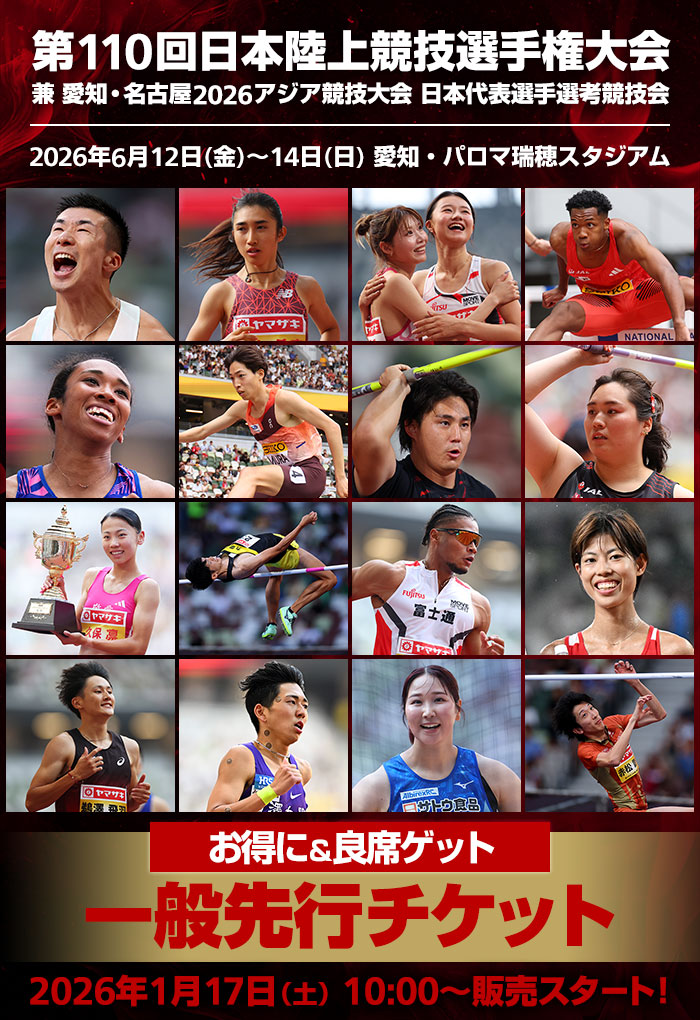7月に開催された「2025年度JAAF公認ジュニアコーチ養成講習会」には、全国から53名の受講者が参加。3日間にわたって、コーチングに求められるさまざまな知識や技能を学びました。ここでは、普段、異なる立ち位置で陸上現場にかかわっている4名の参加者にインタビュー。講習を受けての感想や今後への思いをお聞きしました。
文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)
【受講者コメント】
◎奥谷 亘(SUBARU)

現在、実業団チームで監督を務めています。実業団では、大会に出ていくに当たって、チーム内にコーチ3(公認コーチ)の有資格者が必要というルールが何年か前にできていて、それに伴い、まずは次世代のコーチたちからということで、若い指導者を受講させてきたいました。ただ、コーチングに携わる以上は、きちんと資格を取っておくべき。そういう時代になっていることは感じていたので、自分も受講しようと決心しました。推薦で公認コーチの受講ができる立場ではあったのですが、申し込みの期間が終わっていて…(笑)。でも、本来はコーチ1(ジュニアコーチ)から取っていくべきことでもあるので、ジュニアコーチから受けていこうと、この講習に申し込みました。
実際に受講してみて、「自分が知っていたのは、陸上競技の一部だったんだな」ということを実感しましたね。競技者として長距離・マラソンに取り組み、引退後も長い距離の指導に当たってきたわけですが、陸上競技に携わっている人間でありながらも、長距離の一部分でしか関われていなかったのだと思いました。近年では子どもたちと関わっていく機会も増えているので、正しい知識と情報が必要です。自身に不足している点があったことを反省しましたし、いろいろな場面で大きな気づきを得ることができました。
栄養や障害、トレーニング計画などの理論面については、細かな数値までは抑えることはできていなかったものの、基本的な面は正しく理解していることが再確認できました。一方で、実技で経験することになった他種目については、技術の高さとかコーチであれば知っておくべき技術論みたいなところに関する知識を全く持っていなかったので、改めてきちんと学べたことは、ものすごく刺激になりましたね。自身のコーチングを改めて見直していくうえでも、非常によい機会になったと思います。
◎大西 大(遠軽町立田原中学校/EXIA Running Club)

中学校の保健体育教師として、これまで20年以上、中学校の陸上部の指導をしてきました。ただ、オホーツクのほうでは部活動の地域展開が進んでいて、ちょうど昨年度のタイミングで転勤となったことをもあり、これからは部活動としてではなく自分でやろうと決め、今年の4月に教え子たちと一緒にクラブと少年団を立ち上げたんです。なので、今も中学校教員の立場ではあるのですが、クラブを運営していくためには資格が必要ということで、ジュニアコーチを受講することになりました。札幌会場で受けることもできたのですが、ナショナルトレーニングセンターには来たことがなかったので、「せっかくなら、日本のトップ選手が利用する素晴らしい施設を利用してみたい」と思い(笑)、こちらの(陸連特設)講習を受けさせていただきました。
集まった受講者の皆さんは、私のように小・中学校世代の指導者もいれば、高校の指導に当たっている方、また、実業団の有名な監督やオリンピック選手もいる幅広さ。そのなかで、みんなが同じ目標に向かって一緒に講習できたことは、非常に刺激的で、面白かったです。
私自身がやってきたのは中・長距離でしたが、中学校部活動では、すべてのジャンルの指導にあたってきました。立ち上げたクラブチームも、現時点では短距離や中長距離、やってハードルくらいまでで、跳躍や投てき種目は、まだ環境が整っていないこともあり、対応することができていませんが、数年内には子どもたちが陸上競技全般に取り組めるようにするつもりです。
そういう意味で、理論や各種目の実技を改めて受けたことは、良い学び直しの機会になりましたね。特に、さまざまな場面で強調されていた安全管理についての対応は、その大切さを再確認させてもらえました。やっぱりスポーツを楽しむためには、まずは安全であることが最低限必要で、かつ最重要課題。その点は、今までも常に心掛けてきたことですが、この講習で改めて認識することができました。受講して良かったです。
◎岸本 鷹幸(富士通)

受講することにしたのは、「陸上のこと、もうちょっと知っておこうかな」という単純な思いから。これまで選手として長く400mハードルに取り組み、オリンピックや世界選手権にも出場してきましたが、次のキャリアを考えていかなければならない時期を迎えています(注:8月6日、9月7日限りで現役からの引退を発表)。今後について、具体的に何か決まっているわけではないのですが、もし、指導する立場となる機会があったときには、必要なコーチ資格はすでに持っている状態にしておきたいなという気持ちもありました。まずは改めて「陸上をちゃんと勉強しておきたいな」という思いで参加しました。
「いやあ、受講しておいてよかった!」というのが、終えてみての率直な感想です。いかに、自分が小さな知識で陸上をやってきたのかということを痛感させられましたね。選手として、ハードルのことや、いわゆる理論の部分は詳しくても、特の種目については、全く経験したことのないものもあったので、すごく新鮮で…(笑)。今さらになって、「ああ、陸上って、こうなんだ!」という楽しさを改めて知ることができました。
また、ほかの種目を経験していくなかで、「これは、トレーニングに生かせることができるな」という事柄も多くあったので、「もっと早く受講しておけばよかったな」という気持ち。この経験をもう少し若い年代でしていれば、もっと広い視点で、ハードルを突き詰めていくことができたのではないかと思うんです。そういう意味では、それなりのキャリアを積んできた選手にも勧めたいです。
そのほかでは、特に「安全管理」についての面は、衝撃に近いところがありましたね。自分のなかで、陸上現場の事故というと投てきで起きやすいと勝手に思い込んでいたのですが、ハードルでも死亡事故が起きる危険があることや、用器具の使い方や置き方が事故につながる恐れもあるというのを聞いて、「知ることができてよかったな」と思いましたし、そういった点への配慮があって初めて陸上競技が成り立つのだなということを実感しました。
自分の場合は、「ハードルなら任せてください!」という状況ですが、あくまでもハードルだけの知識で、それだけではまだまだ足りないと思うんです。コーチングに携わっていくにしても、あるいはイベント等で参加者に声をかけるにしても、「陸上」として求められる、必要な基本的知識は蓄えておくことは必要だと思います。日程はなかなかハードでしたが(笑)、いろいろな意味で、受講して本当に良かったです。充実した3日間でした。
◎藤﨑 ありす(BEAT AC TOKYO)

現在、クラブチームのランニングスクールで、キッズから小学校6年生までの指導に当たっています。「走る」ことは、陸上だけでなくても、サッカーやバスケットボールなど、ほかの競技にも生きてくる大切な要素。そういった面で、この年代の子どもたちには、どのスポーツに取り組むことになっても役立つように走ることの基本を正しく身につけてもらうことと、走ることの楽しさや、「できた! やった!」という達成感を知ってもらいたいという思いで取り組んでいます。
今回、講習を受けることにした一番のきっかけは、試合によっては、コーチ資格が帯同の条件となっている大会があり、将来的にはそれが標準になるのだろうなと考えたからです。スタートコーチの資格は、すでに取得しているのですが、もう少し専門的なところもきちんと学んでおきたいと思い、ジュニアコーチの受講を決めました。
スタートコーチのときは、どちらかというと講義が多くて、実技は走・跳・投全体の基本的な内容が中心だったのですが、ジュニアコーチでは実技講習の時間が多くなり、しかも、それぞれの種目について、基本的な知識や技術を丁寧に教えてもらうことができました。そこが大きく違っていたように思います。
私は、高校・大学と短距離をやっていたのですが、短距離以外の種目には、これまで触れたことがなかったんです。特にフィールド種目は、それこそ用具の持ち方の段階から、初めて経験することばかりでした。なので、まずはフォームなどの基本的な動きを正確に理解して、自分がその形をきちんとできるようになることを意識して取り組みました。ドリルなどでは、初めて挑戦する動きも多くて、今は少し筋肉痛も出てきていますが、きちんと学ぶことができたのは貴重でしたし、とても新鮮で、楽しく取り組めた3日間でした。機会があれば、次は公認コーチの資格にも挑戦してみたいですね。
>>【JAAF公認ジュニアコーチ養成講習会】全国から53名が参加し東京で開催
日本陸連のコーチ資格概要
▼JAAF公認コーチ:https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/
▼JAAF公認ジュニアコーチ:
https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/juniorcoach.html
▼JAAF公認スタートコーチ:
https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/startcoach.html