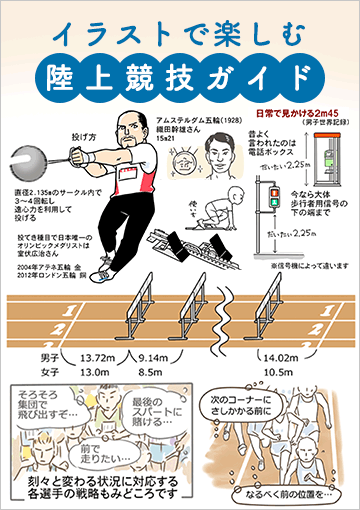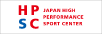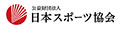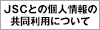2020年東京オリンピックと、その後の国際大会での活躍が大いに期待できる次世代の競技者を強化育成することを目指して2014-2015年からスタートした「ダイヤモンドアスリート」制度は、この秋から6期目に入っています。日本陸連では、継続競技者6名に、2名の新規競技者を選出。11月25日に、この8名を「第6期(2019-2020)ダイヤモンドアスリート」とする認定式を行ったのちに、第1回リーダーシッププログラムを実施しました。
リーダーシッププログラムは、ダイヤモンドアスリートに提供されるプログラムの「測定・研修プログラム」の1つとして位置づけられている研修( http://www.jaaf.or.jp/diamond/program/ )で、「競技力向上だけではなく、豊かな人間性を持つ国際人育成のための個を重視した育成プログラムの中でリーダーシップ教育と位置づけて行い、国際的なリーダーシップを発揮できるアスリートの育成を目指す」ことを目的に、東京マラソン財団スポーツレガシー事業として運営されています。
2部構成で行われた第1回は、例年同様、第1部をメディアに公開。ラグビー元日本代表キャプテンの廣瀬俊朗さん(株式会社HiRAKU代表取締役)を迎え、このプログラムを監修する為末大さん(東京マラソン財団スポーツレガシー事業運営委員、男子400mH日本記録保持者、2001年・2005年世界選手権銅メダリスト)との対談が行われました。
プログラムには、学業の都合で欠席した中村健太郎選手(清風南海高)、鵜澤飛羽選手(築館高)を除く第6期ダイヤモンドアスリート(塚本ジャスティン惇平選手:東洋大、クレイ・アーロン竜波選手:相洋高、海鋒泰輝選手:日本大、出口晴翔選手:東福岡高、小林歩未選手:筑波大、藤原孝輝選手:洛南高)の6名が出席。このほか、歴代修了生の宮本大輔選手(東洋大)、藤井菜々子選手(エディオン)、橋岡優輝選手(日本大)、江島雅紀選手(日本大)、北口榛花選手(日本大)、山下潤選手(筑波大)、平松祐司選手(辰野)も参加しました。
ここでは、その対談の模様をダイジェストでご紹介します。
2019-2020ダイヤモンドアスリート
第1回リーダーシッププログラム(第1部)
対談:廣瀬俊朗×為末 大
1981年生まれの廣瀬俊朗さんは、大阪府出身。5歳からラグビーを始めて、大阪・北野高校を経て慶應大学に進み、その間に、高校日本代表、U19日本代表に選出。高校・大学でもキャプテンを務めました。大学を卒業した2004年に東芝に入社し、東芝ブレイブルーパスの一員として、2年目からレギュラーとして活躍、2007年からはキャプテンを務め、2度のトップリーグプレーオフ優勝に導きました。日本代表チームには、2007年に初選出されたのち、5年ぶりに選出された2012年からはキャプテンとして、当時、日本代表を「勝つチームにする」ことを掲げてヘッドコーチに就任したエディー・ジョーンズ氏のもと、「ハードワーク」として名を馳せた厳しい強化体制のなかでチームを牽引し、キャプテンを交替した2014年からは後任となったリーチ・マイケル選手をサポート。2015年ラグビーワールドカップイングランド大会では、自身の出場は叶わなかったものの、代表メンバーとしてチームを支え、予選トーナメントで優勝候補の南アフリカを破る大金星を上げて世界中を驚愕させた初戦を含めて、日本代表史上初となる同一大会3勝に貢献しました。
引退後は、日本ラグビーフットボール選手会を創設して初代会長を務めたり、コーチ、講演、解説を務めたりするなど幅広い活動でラグビー界をバックアップしています。2019年日本大会に向けては、ラグビーワールドカップ2019アンバサダーを務めたほか、開幕直前となる2019年7月期のTBS系ドラマ「ノーサイドゲーム」に主要登場人物として出演するなどして、2019年日本大会の盛り上げに尽力。その一方で、引退後にはビジネス・ブレークスルー大学大学院に入学して経営学に取り組み、2019年9月にはMBAも取得。ビジネスパーソンとしての今後の活躍も期待されている人物です。
為末さんが聞き手となる形で行われた対談の導入は、まず、廣瀬さんが俳優デビューを果たした「ノーサイドゲーム」の話題から。社会人ラグビーチームを描いたこのドラマが人気を博したことによって、従来のラグビー界には少なかった新たなファン層ができた話などが紹介されたほか、この夏、行われたワールドカップ日本大会が、どのような過程を経て、熱狂的な注目度を集めるに至ったのかなどが明かされたのちに本題へ。「競技経歴」「自分らしさとキャプテン」「マインドセットを変える」「競技の特性」「プレッシャーとの向き合い方」「組織論」「セカンドキャリア」「リーダーシップ」などをキーワードに対談が展開。最後に、ダイヤモンドアスリートたちからの質問に、廣瀬さんが答えていくというボリュームのある内容となりました。
◎競技者としての経歴
為末:まず、廣瀬さんがどのように競技人生を送ってきて、今に至るかを伺っていきたいと思います。最初からラグビーだったのですか?
廣瀬:5歳からスタートしたのですが、最初はラグビースクールでやっていました。小学校はサッカーを平日にやって、たまにバスケ(バスケットボール)をやってまたラグビーをやってみたいな、そういう生活でしたね。基本、ずっとラグビーをやっているのですが、いろいろなスポーツもやりながら、あとは母親がピアノをやっていたので、僕はバイオリンをちょっとやってみて…みたいな感じで音楽もやっていました。そういえば、父親は陸上やっていたんです。短距離をやっていて、だから足はそれなりに速かった。中学も高校も公立で、高校は北野高校という公立高校に行ったので、競技に専念するというよりも勉強も両方頑張っていましたね。大学も慶應に行って、それも理工学部だったので、研究しながらラグビーをするという感じ。社会人になってようやく「それまでは両立できたけれど、社会人では難しいのかな」と、そこで初めて道を絞りました。ラグビーだけやって、引退したらビジネスやろうとか、こういうことをやろうと。
為末:子どものときは、(競技能力は)優れていたのですか?
廣瀬:そんなにでもかったですね。僕らのラグビースクールはもう“エンジョイラグビー”。楽しくやればいい、勝つことはあまり大事じゃない、楽しくできて友達できて、相手を大事にしようみたいな、そんなスタンスでしたから。
為末:「自分は、ほかの人と違うんじゃないか」と思ったのは何歳くらいから?
廣瀬:どこと比べるのかにもよりますが、それなりに…中学生くらいですかね。大阪府の選抜に呼んでもらったりしたあたりでしょうか。
為末:なるほど。でも本気になったのは大学…というよりは社会人になってからだった。
廣瀬:そうですね。大学から社会人になってからです。
為末:伺っていて、まず大きな分岐点というのは、社会人になっても競技をやっていく道を選んだところでしょうか。ラグビーの場合は、陸上ほどトップだから将来も競技を続けるというわけではなく、(大学で)すんなり引退しちゃって、ビジネスの世界に行く人というのがけっこういるんですね。これは、陸上界だとちょっとピンと来ない感じがあるのですが、要するに、大学で競技をやめて、金融の世界で成功している人がけっこう多いわけです。たぶん慶應大学であれば、スポーツで成功しているよりも、ずっと大きなお金を動かしていて、(高い報酬を)もらっているような人たちや、ビジネスの世界でバリバリ働いている人をみることも多かったと思うのですが、そのなかで、なぜ、ラグビーを続けることを選んだのですか?
廣瀬:陸上もそうだと思うけれど、ラグビーは若いときしかできないなと思って。ビジネスは30歳を越えて、40代になってからでも、やろうと思えばできるのかなと思ったときに、「今しかできないラグビーをやろう」と考えました。それで社会人になるとき「4年で辞める」と思って入ったんです、東芝に。ただ、キャプテンとかいろいろなタイトルがついたりして、結局10年以上やっちゃったんですけど(笑)、最初は「今できることをやろう」ということと、あとは(大学)4年生の最後の試合であまりいい試合ができなかったことが影響しています。このとき関東学院大学が優勝したのですが、そのチームが本当に素晴らしくて、「こんなチームがつくれるんだ」と感じたときに、もうちょっとラグビーの世界を見たいなと思った。その2つで続けようと思いましたね。
為末:僕の記憶では、当時、日本のラグビーは、世界で(戦っていくの)はちょっと厳しいし、かつ社会的な人気の面でも、すごく人気があった1980年代とか70年代のころとは違ってきている時代だったと思うのですが、迷いはなかったのですか?
廣瀬:ラグビーが好きというのと、今やれることをやろうというのがあったけれど、もしかしたら無知で、自分の見えている世界のなかで決断したというところもあるかもしれませんね。そういう世界の状況を客観的に見られていたら、もうちょっと迷ったかもしれません。

◎リーダーシップと自分らしさ
為末:チーム競技というのは、チームのなかで自分が何役をやるかによってチームの空気が変わったり、みんなの話し合いや意識決定が変わったりするという意味で、“オフ・ザ・ピッチ”での振る舞いもけっこう重要な気がするのですが、そのあたり、高校、大学、社会人になっていくにつれて、自分は何役をやるべきとか、どんなふうに考えてきたのですか?
廣瀬:僕は、タイトル…役割はキャプテンなんですけど、ぐいぐい引っ張っていくというタイプじゃなくて、どちらかというとみんなが活躍できる居場所みたいなものをつくる、環境をつくるキャプテンというような、そんな役割でした。なので、あんまり話の中心にいるわけでもなくて、どちらかというと、「何をしたい?」「どんなチームをつくりたい?」「どんな人間になりたい?」とか、そんなことを聞くタイプでしたね。
為末:みんなの話を聞いて、調和をとっていく形ですね。反対に、自分が決めて、ぐいぐい引っ張って「俺についてこい」というリーダーシップもあるじゃないですか? それに憧れたり、自分がそうなれないかとチャレンジしたりしたことはなかった?
廣瀬:憧れはありましたけど、でも、どこかで気づくんですよね、「そっち(のタイプ)にはなれない」「あまり好きじゃない」というか、「自分らしくない」ということを。そうなると、やっぱりこっちだな、と。
為末:同世代のそういう、いわゆる強いリーダーシップを発揮して強くなっているチームを見て「俺は、こういうリーダーシップだから勝てないんじゃないか」と迷ったことはないですか?
廣瀬:まあ、ほとんど負け続けていたんで、僕の人生は(笑)。慶應のときも全然勝てませんでしたし、だから、ずっとあまり自信はないまま社会人になりました。社会人になったとき、僕の前に冨岡(鉄平)さんというキャプテンがいたのですが、彼が環境をつくることも、ぐいぐい引っ張ることも両方やっている人で、僕は最初、彼の真似をしようとして失敗したんです。「東芝のキャプテンは彼」みたいなイメージだったので、そうならないといけないのかなと思って。で、失敗して、自分らしさみたいな形からいくと、うまくいくようになった。それで完璧な人間なんていなくて、完璧じゃないところに「人」の魅力を感じて、助けてあげようと(周りが)思うのかな、と。だから、リーダーも完璧じゃなくてもよくて、それよりも自分らしくいることのほうが大事なのかなと思うようになりました。
為末:とはいえ、若いころは、それはけっこう難しくなかったですか?
廣瀬:そうですけど、完璧にはなれないと思うんですよね、一生。もちろん(足りないところを)補っていくとか、リーダーとして成長したいという視点は必要なのでしょうが、でも、最終的には「自分は自分」というスタイルをきっちりと持ちながら、いろいろな経験を重ねて成長していくというのがいいのかなと思いますね。
◎「世界で戦えるチーム」への変容
為末:キャプテンをやっていて、一番難しかった局面というのはどういうところでしたか? これは話せる範囲で…(笑)。
廣瀬:一番難しい…というかプレッシャーがあったのは、日本代表の監督(ヘッドコーチ;HC)がエディー・ジョーンズさんだったときでしょうか。
為末:ちょっとその“エディー時代”の話を伺いましょうか。エディー・ジョーンズさんというのは、前回の2015年ワールドカップまで日本代表監督を務め、前回大会で強豪の南アフリカに勝つという大金星を上げるまでに日本チームを導いた人なのですが、そこに至るまで(の強化の過程)が本当に厳しくて、選手たちの暴動が起きるんじゃないかというような話もあったりしたほどでした。あのエディー時代というのはどういう感じで始まっていった?
廣瀬:そもそも僕たち(日本代表チーム)って、ずっと勝ったことがなかったので、マインドセットがすごく弱かったんですね。そんなチームを変えないといけないというところからスタートしたので、当然エディーさんもきつくあたるわけです。それが、最初は僕たちにとっては自己否定されるみたいな形になりました。
為末:具体的にはどんな感じだったの?
廣瀬:今まで20何年間勝っていないチームが勝とうとしているのに、プロセスを変えないで勝てるわけがないだろうと言われて…。
為末:なるほど。そんな優しい言い方ではないよね?(笑)
廣瀬:はい(笑)、もっとですね。すごくいろいろなことやり合って、本当に大変でした。でも、そうはいっても、そこで頑張れたのは、「日本のチームを変えたい」とか「憧れの存在になろう」という大義の部分が一致していたから。だから過程はいろいろな思いがあっても、そこは目をつぶってやっていこうと。
為末:何を一番変えようとしたのですか?
廣瀬:「日本人は負けて当たり前」みたいなところです。僕らは「経験ある選手に勝てないとか、速い選手に勝てないとか、大きい選手は勝てないとか、と言い訳ばかりしていました。。あと、エディーさんは「できないことに日本人はフォーカスする」と言っておられた。体重が軽いから仕方ないと言うのではなく、足が短いなら寝て起きるのは速い、体重の軽い人はフィットネス(レベル)を上げろと、「言われてみたらそうだよな」みたいなところを言われました。そして、それに「ジャパンウエイ」という言葉をつけてくれて、そこが僕たちのオリジナリティとなった。これをやったら強くなれるかなみたいなところをエディーさんがつくってくれたわけです。
為末:じゃあ、一番は、マインドセットを変えたことが…。
廣瀬:はい。大きかったと思いますね。僕たちはいつもそこでブレーキをかけてしまっていましたから。もしかしたら、100m走で言う「10秒の壁」みたいなものかもしれません。できないと思っていたことでも、誰かが1回いけば、続く人が出てくるじゃないですか。そこで何かマインドのブレーキがとれたんじゃないかなと。僕たちの場合は、そこをエディーさんが取っ払ってくれたわけです。あとはスポーツ心理学の荒木香織さんがメンタルコーチとしてサポートしてくれたので、そういうのがよかったのかなと思いますね。
為末:前回大会のときまでにマインドセットが変わったことで、それが今の日本代表につながっているものってあると思いますか? 僕は見ていて、そのあたりから日本代表が「世界の中の日本」という形で戦っているようになったと感じたのですが。
廣瀬:仰る通りですね。それまでは日本の中でしか見ていなかった、もしくは、世界の列強に対して勝つとかどうやって戦っていくかというようなイメージはなかったのですが、エディーさんがつくってくれたスタンダードが「世界」で、それは(エディー体制となった)2012年度からずっと培ってきて、2015年に結果が出た。そのベースを持って2015年から2019年まで行けたので、今回は、本当に上積みがあったなと思いますね。
為末:じゃあ、やはりその「ジャパンウエイ」というのをつくったのが大きいわけですね。そのときにエディーさんが定義した「ジャパンウエイ」、つまり「日本の強みはこれ」というのは何だったんですか?
廣瀬:フィジカル的なところは、「低さ」ですね。足が短いから低いプレーもできやすいし、実際に身長も低いですし。対戦する(身長の)大きい選手は低い格好をされると嫌がるわけです。あとは体重が軽いぶん「運動量」ですね。体重がある人は走るのを嫌がりますが、日本人の選手は走り回れるんで、インプレーの時間を増やそうみたいな…。
為末:インプレーとは?
廣瀬:40分(ハーフ内)のプレーできる時間を増やそうということですね。ボールがタッチ(ライン)を出ると時計は進むので、その間、休めることになるけれど、だけど、タッチを出さなければ、相手はずっと走らないといけなくなるので疲れるわけです。このあたりは僕たちのオリジナルということですね。あとはマインド的には、日本人は「このために頑張ろう」みたいなときは、すごく1つにまとまって大きな力を出すことができます。もしくは、「何かを堪え忍ぶ」というときに日本人らしさがある。そういったところは強みといえます。これは、グラウンド外も含めてですね。
為末:じゃあ、エディーさんに堪え忍ぶというのも…(笑)。
廣瀬:それによっても、まとまった気がしますね。「対エディーさん」みたいなところは、けっこうありましたから…(笑)。一方で、ワールドカップの前に、エディーさんが大会終了後に辞めることが発表されたわけですが、そのときに、ここまで強くしてくれたエディーさんをいい形で送り出したいなという感謝の気持ちに変わったんですね。それによってチームがさらにまとまって、勝ちにいった気がします。
為末:自分たちが何者であるかを知って、定義して、それを弱みじゃなくて強みに捉え直すというのは、すごく大きなポイントなんですね。
廣瀬:そう思います。弱みを悲観するというよりも、強みを活かしていくしていくことが、僕は大事なポイントのような気がしますね。
『【ダイヤモンドアスリート】第6期(2019-2020)第1回リーダーシッププログラム vol.2』に続く…
>>ダイヤモンドアスリート特設サイトはこちら
関連ニュース
-
2025.12.19(金)
【ダイヤモンドアスリート】第1回リーダーシッププログラムレポート②:サニブラウンアブデルハキームが語る「アスリートとしての社会貢献」
選手 -
2025.12.18(木)
【ダイヤモンドアスリート】第1回リーダーシッププログラムレポート①:サニブラウンアブデルハキームが語る「日の丸を背負って戦うこと」
選手 -
2025.12.11(木)
【ダイヤモンドアスリート】第12期認定式・修了式レポート&コメント:国際人を目指し、未来の原石たちが決意を語る
選手 -
2025.12.09(火)
【ダイヤモンドアスリート】ドルーリー朱瑛里がワシントン大学への進学意思を発表!北口・澤田の背中を追いかけ、世界との懸け橋となる国際人へ
選手 -
2025.11.29(土)
【日本陸連 アスレティックス・アワード2025】東京世界陸上銅メダリストの藤井菜々子が女子競歩初のアスリート・オブ・ザ・イヤーに!
選手