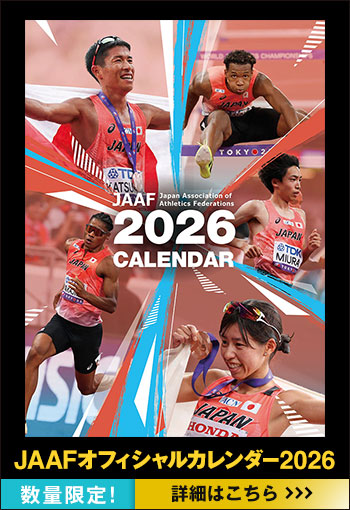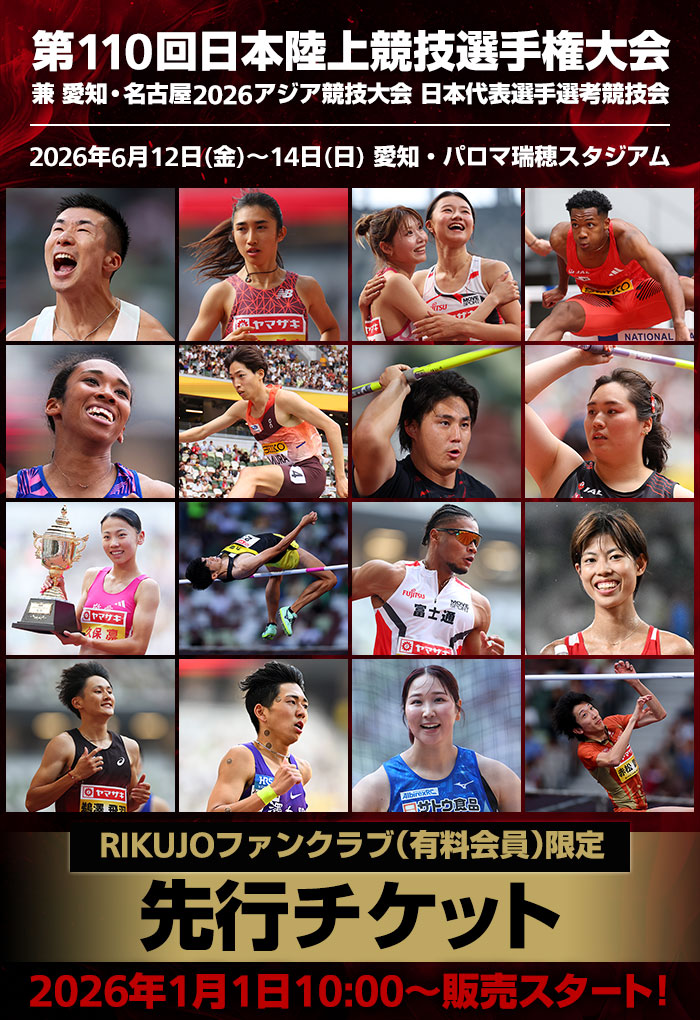日清食品カップ 第41回全国小学生陸上競技交流大会が11月1~3日に開催されました。この大会は創設当初から夏休み中の8月中~下旬に実施してきましたが、深刻な暑熱問題の観点から、他の本連盟主催大会に先駆けて議論を行い、2018年度の段階で8月開催を避けることを決め、以降は、可能な限り9月以降に開催できるよう努力してきました。本年は11月最初の連休を利用する日程での開催に。都道府県ごとに代表選手と指導者が選手団を編成し、2年ぶりに会場となった神奈川・日産スタジアムで競技会に臨んだほか、指導者研修会やミュージアム見学などに参加。全3日間の日程で交流しました。
日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会(以下、全国小学生陸上)は、小学生が、すべてのスポーツの基本である「走る・跳ぶ・投げる」の技能を身につけていくなかで陸上の楽しさに触れること、チームでの活動を経験するなかで友達との良い関係つくりやマナーを育むこと、小学生年代の指導にあたるコーチの研鑽を図ることを目的として、日本陸連が1985年に『全国少年少女リレー競走大会』の名称でスタートさせました。1992年の第8回大会から日清食品カップ全国小学生リレー競走大会に、そして、1994年の第10回大会からは、名称に「交流」の言葉が入った現大会名で実施されています。
競技会だけでなく、研修・交流も兼ねての実施であるため、全日程は2泊3日で組まれています。集合日となる1日目は会場での前日練習と指導者研修会が行われ、2日目に都道府県の各代表選手が出場する全国交流大会と指導者交流会を実施。最終日には、インスタントラーメンの発明で地球の食文化を革新したことで知られる日清食品創業者・安藤百福氏の創造的思考に触れることができる体験型ミュージアム「カップヌードルミュージアム 横浜」を見学して各都道府県に帰るスケジュールです。
今回は、指導者研修会と全国交流大会をレポート。まずは2日目に実施された第41回全国交流大会の模様からご紹介しましょう(指導者研修会の様子は、次回ご紹介します)。

第41回全国交流大会
全国小学生陸上2日目となる11月2日。この日は、日産スタジアムで全国交流大会が行われます。神奈川県の新横浜では、午前7時を過ぎたあたりから都道府県の各代表選手団が、それぞれに宿泊先のホテルを出発。秋が深まったことを感じさせる少しひんやりした空気のなか、チームユニフォームをまとった色とりどりの集団が、会場の日産スタジアムへと移動していく光景が見られました。小学校5年生および6年生が参加対象となっている全国交流大会で現在実施されているのは、5年生100m(男子・女子)、6年生100m(男子・女子)、80mハードルと走高跳の2種目で合計得点を競うコンバインドA(男子・女子)、走幅跳とジャベリックボール投の2種目で合計得点を競うコンバインドB(男子・女子)、男女各3選手でチームを組み、そのうちの男女各2選手でバトンをつなぐ混合4×100mリレーの全9種目。選考対象大会として6~7月に各地で実施された都道府県交流大会を経て、各都道府県陸上競技協会が、個人種目各1名および混合リレー1チーム(6名)の代表選手を選出します。こうして、都道府県ごとに監督(1名)・コーチ(3名)・選手(14名)からなる選手団が編成され、この全国交流大会に集まりました。
午前10時からの競技開始に先立ち、会場では午前9時から開会式が行われました。各選手団ともに、開会式には、ウォーミングアップ実施中の者を除く選手と指導者が参加。今年から初めて、大会公式YouTubeチャンネルでのライブ配信が導入されたこともあり、北海道から順に行われた入場では、大会バックボード前で各選手団が配信用カメラに向かってポーズをとってから場内に移動すると同時に、優秀な少年少女陸上競技指導者に贈られる「安藤百福記念章」受賞者を都道府県ごとに紹介していくスタイルが採用されました。

開会式では、主催者代表挨拶として有森裕子日本陸連会長からのビデオメッセージが流れたあと、後援・協賛社を代表して、第1回からこの大会をサポートする公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団の理事長で、日清食品ホールディングス株式会社CEOの安藤宏基さんが挨拶に立ち、参加した都道府県選手団を激励しました。
続いて選手宣誓が行われました。今年は、栃木県代表である稲荷山恭吾選手と上野結香選手の2人が選手代表として登壇。宇宙飛行士で、カップヌードルミュージアム 横浜の名誉館長を務める野口聡一さん(公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団理事)に向けて、「今年、東京で世界陸上が開かれました。そこで目にしたのは、選手が全力で挑戦する姿でした。私たちも全国から集まった同じ夢を持つ仲間と同じフィールドに立ち、全力で競いあうなかで、互いを尊重し、友情を深めたいと思います。そして今まで支えてくださった家族、コーチ、大会関係者など多くの方々に感謝し、一人一人の挑戦が未来を拓く力になることを信じて競技することを誓います」と力強く宣誓しました。

この大会では、毎年多くのトップアスリートが、小学生アスリートたちを応援すべく、さまざまな形で協力してくれることも特徴です。今年も豪華な顔ぶれがずらりと揃う形となりました。
今回初めて実施されたライブ配信では、北京オリンピック男子4×100mリレー銀メダリストの塚原直貴さん(ザ・ファースト)、この全国小学生陸上の“OG”で走幅跳と100mハードルで活躍した井村久美子さん(イムラアスリートアカデミー)、十種競技で活躍し、400mハードルでもオリンピックに出場している中村明彦さん(スズキ)、モスクワ世界選手権女子マラソン銅メダル獲得をはじめ、トラックからマラソンまで長年日本のエースとして活躍した福士加代子さん(ワコール)という名オリンピアン4名が解説を務める豪華ラインナップが実現。全力で挑んだ小学生アスリートたちのパフォーマンスや、その魅力を視聴者に伝えました。
<<ライブ配信アーカイブ映像はこちら>>
また、日産スタジアムでは、ゲストとして、多くの現役トップアスリートたちが次々と登場し、会場を沸かせました。1日を通して大会をサポートするナビゲーターを務めたのは、男子十種競技で今年のアジア選手権で銅メダルを獲得した奥田啓祐選手(ウィザス)と女子七種競技で日本選手権初優勝を果たした田中友梨選手(スズキ)の2選手。この大会の“混成競技”であるコンバインド種目では、直接ピットに出向いて間近で選手たちを応援する場面もありました(奥田選手と田中選手のコメントは、別記をご覧ください)。
このほか、日本人で初めて女子100mハードルで13秒の壁を突破した寺田明日香選手(ジャパンクリエイト、東京オリンピックセミファイナリスト)、東京世界選手権女子200mで準決勝進出を果たすとともに同男女混合4×400mリレーで8位に入賞した井戸アビゲイル風果選手(東邦銀行)の、“全国小学生陸上OGコンビ”に加えて、東京世界選手権男子35km競歩で銅メダルを獲得した勝木隼人選手(自衛隊体育学校)、東京世界選手権男子110mハードル5位で、今年、日本人初の12秒台(12秒92)の日本記録をマークして今季世界リスト2位となった村竹ラシッド選手(JAL)、男子走高跳日本記録保持者(2m35)で東京オリンピックファイナリストの戸邉直人選手(JAL)の5名もプレゼンターとして来場。選手の表彰だけでなく、競技の合間に場内インタビューに協力するなどして、大会を大いに盛り上げました(寺田選手、井戸選手のコメントは、別記をご覧ください)。
全国大会として9種目が行われた競技についても、ご紹介しましょう。競技はすべて2025年度日本陸連規則に準じて実施されますが、参加者の年齢段階を踏まえて、発育発達や教育的な配慮をとったなかで行われることが特徴です。例えば、同じ競技者が2回不正スタートをした場合は、その競技者は失格となりますが、通常であれば出場できなくなるところを、オープン参加の扱いでレースを走ることができるようにしています。また、コンバインドAで実施する走高跳の跳躍方法は、「はさみ跳び」に限定して、マットへの着地が背中や腰からとなった場合は無効試技と判定されるほか、コンバインドBで行われるジャベリックボール投では、助走距離は15m以内、オーバーハンドスローで投げることが決められています。

コンバインド種目以外のトラック種目は、すべて予選が行われ、上位24選手(リレーはチーム)が記録順にA・B・Cの3つの決勝に進出することができ、そして、コンバインド種目も含めて、24位までに賞状が授与されます。各選手が参加できるのはリレーも含めて1種目のみに限定されている一方で、混合4×100mリレーのメンバーで、リレーに出場しなかった競技者も、男女別に実施される友好レース(100m)に出場できる仕組み。つまり、参加した全員が競技に出場できるよう配慮されているのです。

記録としては、今大会では、6年100mの男子・女子と、男子コンバインドA、男子コンバインドBの4種目で、のべ5つの大会新・タイ記録がアナウンスされました。まず、6年男子100mの予選で、目野惺大選手(御井陸上・福岡)が11秒63(+0.4)の大会新記録をマーク。目野選手はA決勝でも11秒72(+0.6)の大会タイ記録で走り、レースを制しています。6年女子100mでは、平田キトゥン奈桜実選手(YKSS・香川)がA決勝で12秒33(+0.1)の大会新記録を樹立して1位を占めました。男子コンバインドAを大会新記録で制したのは佐藤一志選手(Happiness AC・神奈川)。走高跳1m47、80mハードル11秒98(+0.3)のパフォーマンスで合計2524点を獲得しました。女子コンバインドBでは、ジャベリックボール投で55m71、走幅跳で4m64(-0.4)をマークした三野涼穂選手(ちはやAC・神奈川)が2265点の大会新記録で1位となっています。

このほか、5年男子100mは上田祥万選手(亀岡陸上教室・京都)が12秒49(+0.5)で、5年女子100mは佐藤愛唯(おいらせAC・青森)が13秒20(-0.2)で、それぞれA決勝で1位に。また、男子コンバインドBは鈴木琉空選手(佐久ドリーム・長野)が2540点(走幅跳5m37<+0.8>、ジャベリックボール投59m21)で、女子コンバインドAは櫻井咲楽選手(KINGDOM AC・三重)が2415点(80mハードル12秒08<-0.2>、走高跳1m39)で制しました。
各都道府県交流大会を制したチームが代表となって、全47チームで競う混合4×100mリレーを制したのは、長野県代表のChinoAs。1走から五味華選手、佐藤華香選手、岩下琉心選手、小林慶彦選手とバトンをつなぎ、アンカーで逆転して51秒07でフィニッシュしました。

スタジアム内で競技が進行するなか、出場選手だけでなく来場する子どもたち誰もが楽しめるエリアも用意されました。観客席への入退場口となる西ゲートの一角で、「キッズデカスロンチャレンジ®」が実施されたのです。「キッズデカスロンチャレンジ®」は、十種競技(デカスロン)に因んで命名されたさまざまな種類の基本運動(走・跳・投)にチャレンジする日本陸連の子ども向けプログラム。

「すべての人が、すべてのライフステージにおいて、陸上を楽しめる環境をつくる」ことを目指したウェルネス陸上の実現に向けた施策の一環として、国内主要大会のサブイベントとして実施され、「デカチャレ」の愛称で親しまれています。今回は、10m走チャレンジ(10mダッシュのタイムを光電管で測定する「走」プログラム)、ミニハードル走(3台のミニハードルを越えることに挑戦する「走」プログラム)、トリプルジャンプ(立ち幅跳び3回で、どれだけ跳べるか挑戦する「跳」プログラム)、バッゴー(穴が空いた斜度のあるバッゴーボード目がけて、ビーンバッグを投げる「投」プログラム)、たまごポケット(チキンラーメンの麺を描いたボード中央の穴に、卵を模した黄色いボールを投げ入れられるかに挑戦する「投」プログラム)の5種目を実施。大会に出場した都道府県代表選手のほか、観戦や応援で来場した小学生以下の子どもたちが、夢中になって、楽しそうに挑戦していました。

また、この大会では、2022年の第38回大会から、大会前に募集した「小学生リポーター」が活動するプログラムも実施しています。これは小学生が「リポーター」という普段とは異なる立場で大会に参加し、選手を応援したり、大会を盛り上げたりするほか、インタビュアーやアナウンスなど、さまざまな事柄にチャレンジするなかで、陸上の楽しさや魅力を再発見し、それらを多くの人に向けて発信してもらおうとする取り組みです。今年も、選考により6人の小学生が採用され、Teamアスリオン(中村泰士さん、松下颯我さん、粳田旺芽さん)とTeamひよこちゃん(藤谷蘭さん、石田梨央さん、柴田結彩さん)として活動しました(小学生リポーターの活動報告は、後日、改めて本サイトに掲載の予定です)。

「交流」を大切にするこの大会ならではのプログラムでもあり、また、参加する選手たちの大きな楽しみの1つとなっているのが、大会の最後に行われるフレンドシップパーティーといえるでしょう。全競技が終了すると、選手団全員が参加者Tシャツを着用して、第1~2コーナーのインフィールドに大集合! 交流の時間が始まりました。まず、ライブ配信で解説を務めた中村さんと井村さんが司会者から紹介されました。大会の感想を求められた中村さんは、「試合のときはどうしても緊張した様子の人が多いのですが、今大会ではみんなの笑顔が見られたことが印象的でした」とコメント。井村さんは、「皆さんは都道府県大会を7月ごろにやっています。それから身体も成長しているので、助走とかを合わせたりするのが大変だろうなと考えていたのですが、ちゃんと合わせているのがすごいなと思いました」と選手たちをねぎらいました。

そのあと、開会式から競技の模様をまとめたダイジェストムービーが大型ビジョンに流れ、全員で視聴して、楽しかった1日を改めて共有したところで、ゲストアスリートの井戸選手、勝木選手、戸邉選手、村竹選手、奥田選手、田中選手の6選手が登場し、会場はさらに盛り上がります。司会者からのインタビューに答えた村竹選手は、大会を見ての感想を求められて「一アスリートとして、すごく刺激をもらった」と話し、「参加している小学生アスリートへのアドバイスを」というリクエストに応えて、「もう自分の得意な種目が見つかっている人は、それを続けてほしい。また、もっと合う種目があるかもしれません。ぜひ、いろいろな種目にチャレンジして、得意な種目、好きな種目を見つけてもらえたらなと思います」と呼びかけました。

続いて行われたのは、ゲストアスリートによるデモンストレーションです。まずは、世界選手権銅メダリストの勝木選手による競歩のデモンストレーション。第1コーナーからスタートして80mほどの距離を、小学生リポーターの粳田さんと石田さんと勝負することに。さらに、“やる気満々!”といった様子で、先にスタート地点で待ち構えていた日本陸連マスコットキャラクターのアスリオンも加わっての対決となりました。日本陸指導者養成委員会の岸政智インスペクター(ディレクター)が、競歩の特徴やルール、デモンストレーションを見るときのポイントを説明したのちに、レースはスタート。序盤は他選手の様子を気にしつつ、歩き始めた勝木選手ですが、のびやかな美しい歩型を披露すると、終盤にはぐんとスピードアップも見せて、“ぶっちぎり”で先着しました。これに続いたのは小学生リポーターの2人。レース後に動画を見た勝木選手が「ルールと簡単な歩き方を事前に伝えてはいたのですが、あんなにきちんと歩けるなんて…。きっと練習してくれたはず。嬉しいですね」と喜んだほど、正しい動きを意識したフォームでフィニッシュしました。また、この3人からはかなり後れる形となったアスリオンも、独特のフォームではあったものの、最後まできちんと歩ききって競争を終えました。

次に行われたデモンストレーションは、2m35の日本記録を持つ戸邉選手による走高跳です。普段は、背面跳びで競技を行う戸邉選手ですが、「今日は、みんなと同じはさみ跳びで、170cmを跳びたいと思います」と、小学生が取り組むはさみ跳びを選択。「走高跳は、助走のリズムがとても大切な競技なので、今日の僕の跳躍も、助走から踏み切りにかけてのリズムに注目してください」と呼びかけてピットに立ちました。見守る小学生たちの集団のなかから助走を開始した戸邉選手は、みんなの手拍子に乗ってテンポアップ。1m70のバーを軽やかにクリアし、「うわあ」という大きな歓声と称賛の拍手を浴びました。跳躍のあとには、混成競技で走高跳に取り組む七種競技の田中選手や十種競技の奥田選手から、跳躍に臨むときに自身が意識していることなども明かされて、小学生アスリートにとっては、跳躍のお手本を間近で見るだけでなく、試技に臨む際のポイントも学ぶ機会となりました。
そのあと続いたゲストアスリートへの質問タイムでは、小学生リポーターの中村さんと藤谷さんが代表で、井戸選手と勝木選手に質問を行いました。「取り組んでいる100m・200m・400mのなかで、一番好きな種目は?」という問いに、「一番好きなのは200m。コーナーから直線に入るところをうまくつなげて、直線でスピードに乗って走る感覚がすごく好きです」と答えたのは井戸選手。また、「競歩をするうえで一番大切だと思うことは?」と聞かれた勝木選手は、「競歩だけでなく全部に言えることだと思うけれど」と前置きしたうえで、「他人の評価をあまり気にすることなく、自分の成長が続くように頑張っていくことだと思います」と答えました。

楽しい時間はあっという間に過ぎて、フレンドシップパーティーも終了の時間に。ゲストアスリートを代表して、最後の挨拶を行った戸邉選手は、「今日は全国大会に出て、嬉しい結果だった人も、悔しい結果だった人もいると思います。でも、この舞台に立っていること自体がもう、みんながここまで努力をしてきた証。頑張った自分自身と一緒に戦った仲間たちに拍手をしましょう」と小学生アスリート全員を称えたうえで、「みんなにとって今日は大きな節目になったと思うけれど、同時に、新たな夢や目標に向かうスタートラインでもあります。今日、経験したことを糧にして、それぞれにまた次の夢や目標に向かって頑張っていってください」とエールを送り、全国交流大会のプログラムを締めくくりました。
【ゲストアスリートコメント】
◎寺田明日香(ジャパンクリエイト)

この大会には、小学校5年生のとき(2000年第16回大会)と6年生のとき(2001年第17回大会)の2回、100mで出場しました。当時は、旧国立競技場で開催されていて、北海道に住んでいたので、国立に足を運べた嬉しさがありましたね。結果は、5年のときも6年のときも2位で、競技成績としては、どちらかというと悔しい思い出のほうが大きいのですが、そこで仲良くなったお友達と住所を交換して、手紙のやりとりをしていました。そのお友達とは今でもつながっていて、“ママ友”として仲良くさせてもらっている子も数人いるんです。大会名に“交流”という言葉がついていますが、本当にいろいろな友達ができた大会だったなと思っています。
出場した皆さんには、「好きで始めた陸上競技だと思うので、全力で楽しんでほしい」とお伝えしたいですね。また、やっているうちに、どんどん「もっと上に行きたい」「強くなりたい」「勝ちたい」という気持ちが強くなっていくと思いますが、「シニアでどうなりたいかいか」とか、「陸上選手として自分がどうなりたいか」みたいなところも、保護者やコーチの皆さんと一緒に考えながら取り組んでいってもらえたらいいなと思います。
<保護者目線で、保護者の皆さんへ小学生アスリートへの接し方のアドバイスを、のリクエストに>
我が家も、娘が今年から陸上を始めたのですが、挙げるとしたら、「聞きすぎないこと」…私もついつい聞きたくなってしまうのですが…(笑)。あとは「独自のアドバイスをしすぎないこと」でしょうか。「見守る」というのが一番難しくて、一番大切なのかなと思います。選手の身体つくりに関しては、お家で食べるごはんがすごく大きいと思うので、ぜひ、見守りながら、おいしいごはんをつくって出していただけたらと思いますし、今、私も頑張っています(笑)。
◎井戸アビゲイル風果(東邦銀行)

この大会には、小学6年生のとき(2013年第29回大会)、4×100mリレー(当時は、5・6年共通女子4×100mリレーで実施)に出場してアンカーを走りました。今日、ここへ来て、そのときに競技場の大きさに(圧倒されて)、ぶるぶる震えて立っていたこと、そして、この大会に勝ち進むまでの仲間たちとの闘いや絆などを思い出しました。
私は、小学生のころ、本当にリレー種目が好きで、4人でアクシデントを経験したり、練習で一緒に頑張ったことができたりという思い出が一つずつ増えていくことが、すごく楽しかったんです。高校や大学になると、新しい技術ができるようになったりタイムが出たりすることも嬉しく思うようになりましたが、小学生のころに好きだった4×100mリレーの思い出が、私のなかでは大きな支えになって、今につながっていると思います。
小学生の皆さんには、「レースすることが楽しい」という気持ちを忘れずにいてほしいなと思いますね。そういう気持ちで試合に出ていけば、長く競技を続けることができますし、小学校のときに出会った友達と、違う場所や違う試合でまた会ったりすると、ずっと(陸上を)やってきてよかったなと思うので、そういう仲間との出会いとかが、陸上を通してできたらいいなと思います。
<自身の小学生時代と比べて、最近の小学生と接した印象と、それを踏まえてのアドバイスを、のリクエストに>
「陸上の知識をもうそこまで知っているんだ」という小学生が多いことに驚かされました。小学生のころは、走る種目が得意で取り組んでいる子も、跳んだり投げたりする種目にも挑戦してほしいです。いろいろな動作をすることで、全身の筋力も上がってきます。さまざまな動きを経験しておくと、そこから先にできることが増えてきます。いろいろな動きを取り入れることをお勧めしたいです。
【ゲストアスリート(ナビゲーター)コメント】
◎奥田啓祐(ウィザス)

全国小学生陸上へのゲスト参加は、これまでにも何度か依頼をいただいていたのですが、なかなか調整がつかず協力することができていませんでした。でも、僕自身もベテランの年代になってきて、何かしらの形で貢献・還元することは大切だなとずっと感じていたんですね。そうしたこともあり、今回、参加させていただくことができました。
ナビゲーターを務めてみての感想ですか? 実は、僕自身は、小学校のときは陸上競技をやっていなかったんです。今日の試合を見ていたら、僕が中学校3年生だったときの記録よりも速い子がいっぱいいる状況で…(笑)。「今後の陸上界って、すごくキラキラしたものになっていくんだろうな」という期待感を持つとともに、「まだまだ僕も負けていられないな」という気持ちになりました。その思いを胸に、これからの冬期練習を頑張りたいなと思いましたね。
来年は、アジア大会を控えていますが、代表入りの条件をクリアできるように、まずは自分のやるべきことをコツコツとやるしか道はないと思っています。今年は、日本選手権1種目の100mでケガをして、多くの方からいただいていた期待に応えることができませんでした。来年は、まずは日本選手権に勝って、そしてアジア大会で活躍したい。皆さんに喜んでもらえるような結果を出していけるように、この冬、しっかりトレーニングしていきます。
◎田中友梨(スズキ)

こうした陸上大会のナビゲーターを務めるのは初めての経験です。もともと多くの人に向かって話すのが得意ではないこともあって、最初は「ちゃんとできるのかな」と少し緊張していました。でも、小学生アスリートの皆さんが、すごく元気に、生き生きと全力で競技に取り組んでいて、その様子が私にも伝わって、本当に楽しく1日を過ごすことができました。
この大会では、コンバインドA・Bとして私が取り組んでいる混成競技が実施されましたし、また、競技場の外では、いろいろな種目に挑戦するデカチャレ(キッズデカスロンチャレンジ)のコーナーもありました。小学生の大会で混成が行われていることを嬉しく思いましたし、実際にピットのすぐそばで応援したり、デカチャレ会場で実際に挑戦してみたりという経験もさせていただきました。
小学生の年代に、シニアのアスリートと間近で接することができるなんて、めったにない機会だと思います。きっと私が小学生の立場だったら、すごく刺激を受けただろうなと思いました。これから将来、「陸上界期待の星」になってくれる子たちが集まったなかで、そういう機会があるのはすごくいいことだな、素敵な試合だなと感じました。また、参加した子どもたちが、シニアの選手たちと接して喜んでいる様子に、「もっと私も、子どもたちに刺激を与えられる存在になりたいな。もっともっと頑張らなきゃな」と、逆に刺激をもらいました。
来年は、名古屋でアジア大会が行われます。アジア大会で活躍することを目指して、この冬季でパフォーマンスの底上げができるよう、しっかりトレーニングに取り組みたいと思っています。
文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)