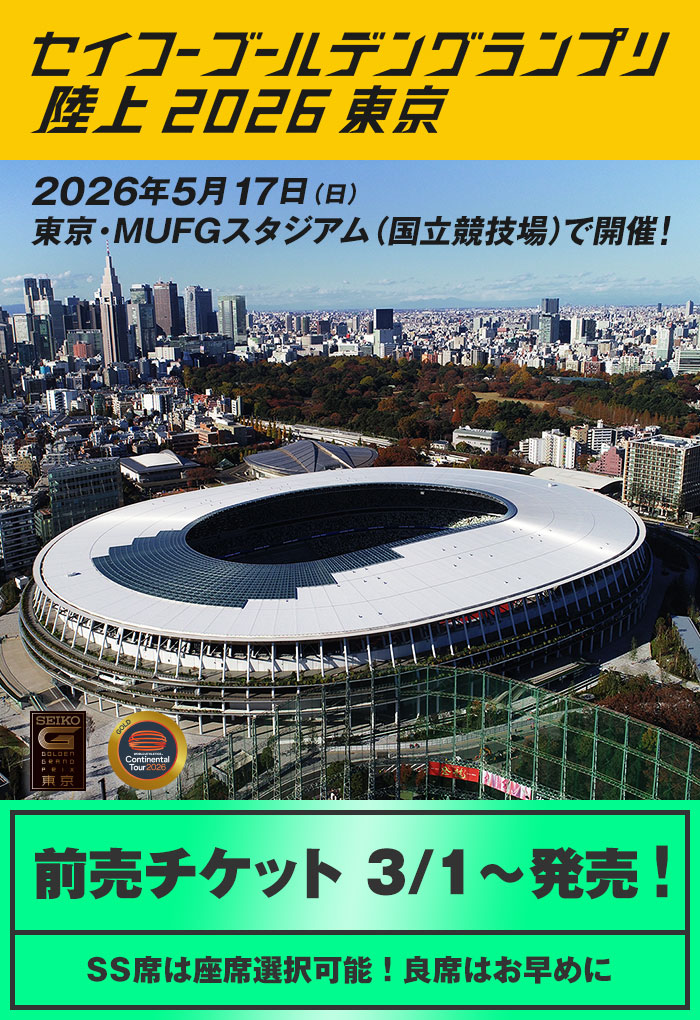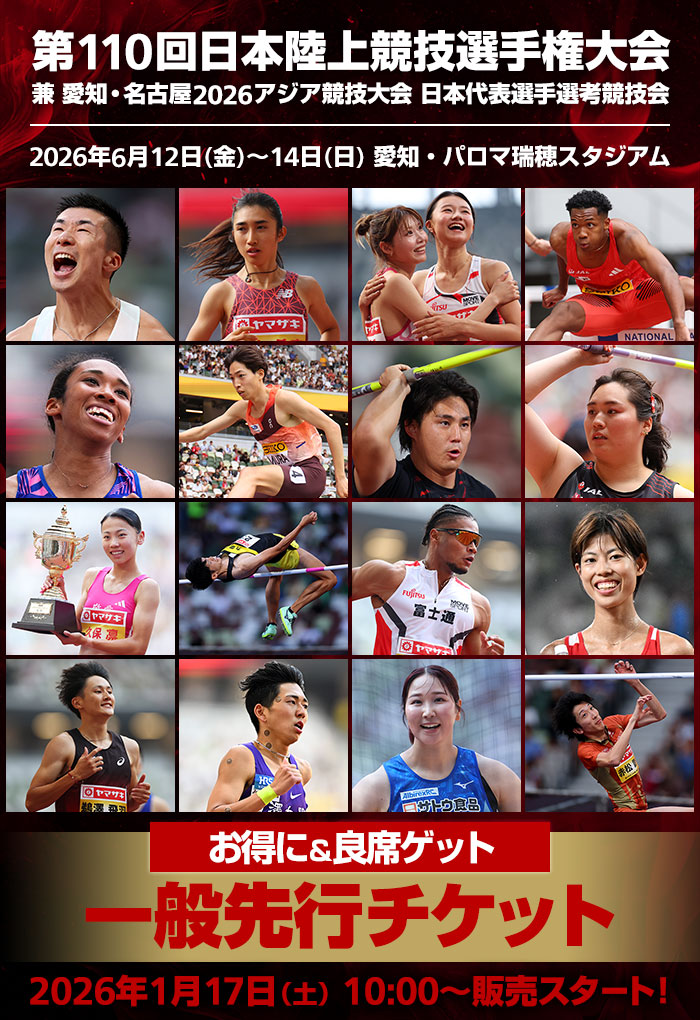東京世界選手権において、男女4種目にフルエントリーを果たした競歩は、銅メダル2、入賞1、日本新記録1の成績を残しました。競歩を担当する谷井孝行ディレクターは、男女35km競歩終了後の9月13日、および男女20km競歩終了後の9月20日に、メディアの取材に応じ、各種目の総括を行いました。
谷井孝行ディレクター(競歩担当)

◎男女35km競歩総括
<男子>勝木隼人(自衛隊体育学校) 3位 2時間29分16秒
川野将虎(旭化成) 18位 2時間37分15秒
丸尾知司(愛知製鋼) 26位 2時間40分29秒
<女子>
梅野倖子(LOCOK) 15位 2時間56分28秒
矢来舞香(千葉興業銀行) 20位 3時間01分27秒
渕瀬真寿美(建装工業) 21位 3時間03分29秒
男子35km競歩は、非常に過酷な環境のなか実施された。気温自体は、スタート時は低かったものの、湿度は高く、時間が経つにつれて気温が上がっていくなか、選手たちは、おそらく最初「意外と涼しいな」と思っていたなか、徐々に暑さを感じてきたといった展開だったのではないかと思っている。そのなかでも、日本人選手がしっかりレースをつくり、入賞圏内、メダルへと徐々に順位を絞りながら、いい展開でレースを進めていってくれたと思う。
終盤はサバイバルレースという形になった。ペースダウンしてしまった川野将虎(旭化成・18位)・丸尾知司(愛知製鋼・26位)に関しては、徐々にというよりは、一気に(ペースが)落ちてしまった。これは脱水などが要因になっていると思う。そんななか勝木隼人(自衛隊体育学校・3位)は、自分の状態を確認しながらレースをつくっていってくれた。メダルというところ…もちろん金メダルを目標にしていたと思うが、確実にメダル圏内…3位以上を取っていくという、非常に素晴らしい展開を繰り広げた。彼は、暑熱の問題についても自身で深く考え、対策はもちろんのこと、暑熱への耐性をつけることに取り組んできていた。それが最終的に生きる形になったと思う。
この35km競歩については、ここまで川野将虎(旭化成)が前回の2023年ブダペスト大会(銅メダル)、前々回の2022年オレゴン大会(銀メダル)と2大会連続でメダルを獲得してきた。日本選手たちは、その川野選手はもちろんのこと、それぞれにメダルを目指していくというところで大変プレッシャーのかかるなか、しっかりと頑張ってくれたと思う。まずは全員がフィニッシュしてくれてよかったと思うし、競歩界の次につながるレースができたのではないかと思う。
女子35km競歩については、梅野倖子(LOCOK・15位)・渕瀬真寿美(建装工業・21位)・矢来舞香(千葉興業銀行・20位)の3名が出場した。まずは、自分自身の展開をしっかりとつくっていくというところで作戦を組み立てた。後半は必ず落ちてくる選手たちがいるというところで、自分自身の設定ペースをキープして、そのなかで順位を上げていこうという戦略で進めていった。そのなかで梅野が15位で日本選手最上位。一時は、入賞も見えるのではないかという期待があったのだが、少し後半にペースダウンが出て、15位にとどまった。
いずれにしても、男女35km競歩に関しては、後半の組み立て方がいかに重要なのかというところを、今回のレースで改めて実感した。選手の実力はもちろんのことながら、そこに向けて、暑さに対してどこまで対策をとれてきたかが、今回の順位を決めた要因ではないかと考えている。
【質疑応答】
Q:50km競歩から35km競歩への種目変更に対する各選手の取り組みについて谷井:今回、男子35kmに出場した代表選手は、全員が東京オリンピックの50kmに出場した選手たちだった。50kmから35kmに変わったことで、よりペースが速くなり、勝木も含めて選手たちは非常に苦労した。そのために20kmに挑戦したり、10000m競歩などトラック種目への出場機会を増やしたり、そういった対策をとっていくのと並行して、厚底シューズの使用にも挑戦。この5年間ほどは、50km競歩を主戦場としてきた選手たちにとって、非常に多くのチャレンジが必要だったのではないかと思う。特に勝木については、50kmのころからスピードで押していくよりは、ゆっくりしたペースで入り、後半徐々に上げて順位を取っていくタイプの選手だったので、先頭集団でレースを組み立てていく現在の彼の姿は想像できなかった。そうしたところに、本人の努力と苦労、そして成長を感じている。私自身、近いところで見てきたなかで、いつもうまくいっていたわけではなく、失敗を多く繰り返しながらも折れずに、しっかりと次に向けて修正していた。そうした粘り強さが彼の特徴だと思う。
Q:今回の35km競歩は、もともと湿度が高かったなか、気温も徐々に上がったことで、途中棄権する選手も多い過酷な環境となった。こうした気象条件のとき、どんなきつさがあるのか。
谷井:気象状況については、ウォーミングアップ時に計測した段階で、80%以上あった状況で、気温は上がりきっていなかったものの、少し動いただけで汗ばむような気候だった。こういう状況の場合は、まず、しっかり給水物を取ることが必要で、また、掛け水よりは氷などを使って深部体温を下げる必要があるレース展開だった。しかしながら今回、序盤から中盤にかけて気温が低かったことによって、けっこうハイペースでレースが進むことになり、それが後半で気温が上がったときにダメージとなってしまった感がある。それは日本選手だけでなく海外選手も同様で、どの選手も徐々にペースダウンするのではなく、一気に失速する形となった。そういう意味で、非常に難しい環境だったと思う。
Q:ロサンゼルスオリンピックではロング種目がなくなるが、今後、ロング種目で培ってきた伝統の強さを、これからの強化にどう落とし込んでいこうと考えているか?
谷井:2026年から、競歩の距離はマラソンとハーフマラソンの距離に変更され、ロサンゼルスオリンピックに関しては、すでにハーフマラソン競歩の1種目のみになることが決まっている。そういったところでは、それぞれが目指すところや考え方が変わってくることもあるとは思うが、35kmを主体にしながら、20kmも歩いてきている選手も多く存在する。同様にロング種目をハーフマラソンに落とし込んでもらいたいと思うし、ハーフマラソンを目指している選手に関しても、ロング種目にチャレンジすることで、ロング種目に必要なものを獲得して、それをハーフマラソンに役立ててもらいたいなと考えている。(種目変更については)必ずしも悲観的ではなく、マラソン競歩、ハーフマラソン競歩で今後もメダルを獲得できるよう頑張っていきたい。
◎男女20km競歩総括
<男子>吉川絢斗(サンベルクス) 7位 1時間19分46秒
丸尾知司(愛知製鋼) 9位 1時間20分09秒
山西利和(愛知製鋼) 28位 1時間22分39秒
<女子>
藤井菜々子(エディオン、ダイヤモンドアスリート修了生) 3位 1時間26分18秒=日本新記録
岡田久美子(富士通) 18位 1時間30分12秒
柳井綾音(立命館大学) 37位 1時間35分44秒
自国開催ということで、本当に多くの方々が応援に来てくださった。まず、そのことを心から感謝したい。たくさんの声援があったことで、選手たちもそれに後押しされるかのように最後まで歩くことができたのではないかと思う。
女子20km競歩では、藤井菜々子(エディオン、ダイヤモンドアスリート修了生)がみごと銅メダルを獲得した。女子競歩のメダル獲得は、史上初。本当に快挙を成し遂げてくれた。また、1時間26分18秒の日本新記録も樹立。勝負・記録ともに自身の最大限のパフォーマンスを発揮したといえる。藤井は、昨年パリオリンピックにおいて、ペナルティーゾーンに入る悔しい経験があったなかで、この1年、フォームの修正をはじめ、強化に取り組んできた。故障も含めて、ここまで苦しい場面がたくさんあったなか、自身の競技に向き合い続けた成果がメダルとして形になったといえる。個人的にもすごく感動したし、嬉しく思った。
また、岡田も、自身のペースを確認しながら、しっかりと力を振り絞ってくれたと思うし、柳井に関しても脚に不安があったなか、最後までフィニッシュを目指してくれた。そういった選手たちの頑張りは、応援に来てくださった皆さんの声が、大きな力になっていたのではないかと思う。
男子20km競歩については、山西は、(ペナルティーにより)ピットレーンに入ってしまう形となった。しかし、これは、攻めた結果――攻めていくなかで自身のパフォーマンスをしっかり出そうとした結果だと思っている。この点については、強化として何かできたのではないか、もっといろいろなことをやってあげられたのではないかと、自分自身にも反省の思いがあり、その反省を、今後の強化につなげていかなければと感じている。なので、山西に関しては、メダルを目指すというレースをしてくれたし、そこに向けて(過程の段階も含めて)真摯に取り組んできてくれた。非常に頑張ってくれたと思っている。
7位入賞を果たした吉川については、ある意味、戦略通りの結果が出せたのではないかと思っている。レース序盤は中段から少し後ろのあたりで自分のペースをしっかりつくって、そこで後半上げていくことが彼の戦略であったのだが、落ち着いたレース運びで、先頭集団から落ちてきた選手たちを、1人、また1人とうまくとらえながら順位を上げて、きっちりと入賞を果たしてくれた。この20km競歩で若い芽が一つ、入賞という成果を出してくれたことは、今後の競歩界の明るい未来につながっていくと思っている。
初日の35km競歩に続いての出場し、9位でのフィニッシュとなった丸尾も、本当に健闘してくれたと思う。「入賞となる8位まであと一歩」ということに本人も悔しさは大きいと思うが、死力を尽くして、ぎりぎりのところで戦ってくれていた。35kmを終えてからの1週間で、やれることをすべてやり、メンタル面も含めて再び戦える状態に仕上げて20kmに臨んでくれた。
強化の立場としては、欲を言うなら「あと一歩」という気持ちはある。しかし、今はまず、全力を尽くしてくれた選手たちに感謝したい。
【質疑応答】
Q:男子に後れをとっていると言われることもあった女子で、メダルを獲得できたことへの思いは?谷井:「後れをとっている」と思われがちだが、女子もこれまでに世界大会で入賞実績を残してきている。また、そのなかで藤井は、2019年ドーハ(7位)、2022年オレゴン(6位)と、過去の世界選手権において、しっかり成績を残してきた選手。そういった意味では「どこかのタイミングで(メダルは取れる)」と密かに思っていた。そういったなかで自国開催の今大会でメダルを獲得してくれたという点で、「(強い運を)持ってるな」と思うし、この大会にしっかりピークを合わせてきたところに彼女の成長と実力を感じている。レース後、藤井は満足しておらず、「今回のレースも、まだまだ課題があった」と話していた。今後、さらなるレベルアップをしてくれるのではないかと期待している。
Q:今大会を最後にすると明言している岡田選手の結果について
谷井:岡田の存在抜きに、今の女子競歩はないと思っている。藤井にとっても、岡田の存在は非常に大きかったし、柳井はじめ、ほかの女子選手にとっても岡田は大きな存在。彼女が女子競歩界を牽引してくれたことで、彼女に憧れて、目標にして、追いついて追い越そうという気持ちが周りの選手にあったからこそ、今回の藤井のメダルはあったと思っているし、そのなかで、岡田も最後までしっかり歩いてくれた。
Q:女子の強化について、これまでの取り組みと今後について
谷井:(自身が担当になってからは)コミュニケーションの機会を増やしてきた。そのなかで、各選手が抱えている問題を聞いたり、相談を受けたりしながら、強化を進めてきたが、まだまだ層を厚くすることが必要と考えている。今回、20kmは、藤井、岡田、柳井が代表に選ばれたが、そこに並んで追いつく選手が一人でも増えていってほしいと思っているし、それが強い競歩界を継続していく大事なところになると思っている。
Q:山西選手は、約1年かけて今年の日本選手権まで世界記録をマークしたが、うまく行かなかった今大会は、どう違っていたのか?
谷井:競歩のフォームは、日々、変化がある。ずっと同じフォームでいられるかといったらそうではないし、その都度変わっていくもの。そこに対して、競歩選手は、自分自身の最高のフォームを求めて取り組んでいるところがある。今回の山西の場合は、良い状態だったとき(日本選手権)に比べると、少しキックアップ(離地後に足の跳ね上がりが大きくなること)があったり、膝の振りだしが高かったりするところが出て、特に、勝負所での場面で、その動きが目立つ形になってしまったのではないかと思う。これに関しては、本当に攻めたうえでの結果。ただ、勝負所で警告や注意が出ないというのは、勝負をしていくうえで非常に大事なところでもあるので、強化としては、そこを次の課題として、しっかり根づかせていきたい。
※本内容は、9月13日・20日に実施した囲み取材において、谷井孝行ディレクターが発言した内容をまとめました。より明瞭に伝えることを目的として、一部、修正、編集、補足説明を施しています。
写真・文:児玉育美(JAAFメディチーム)