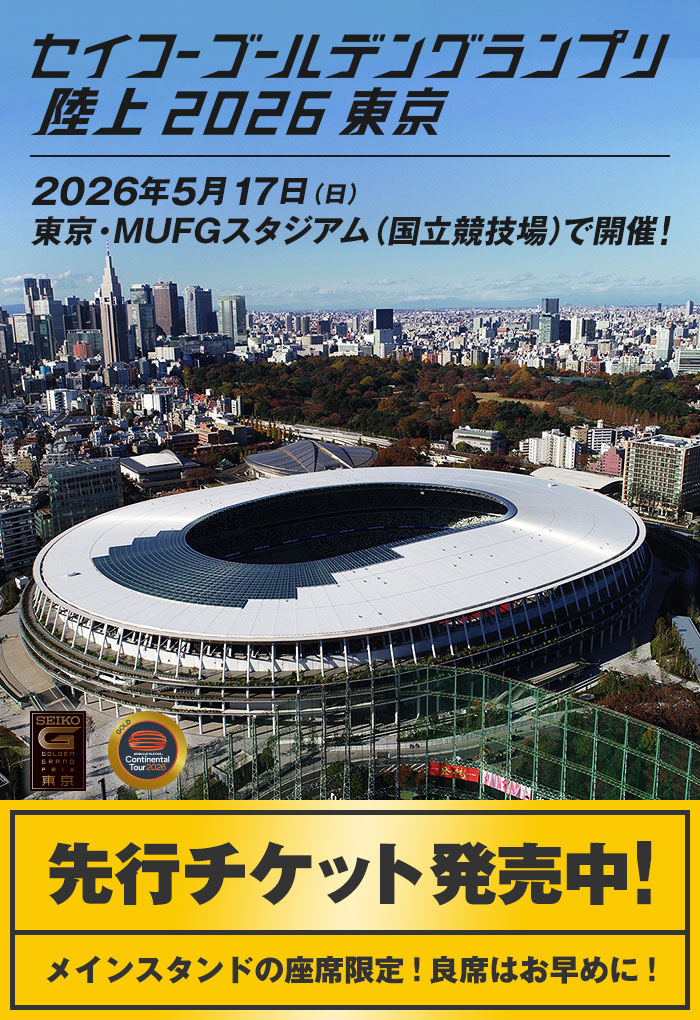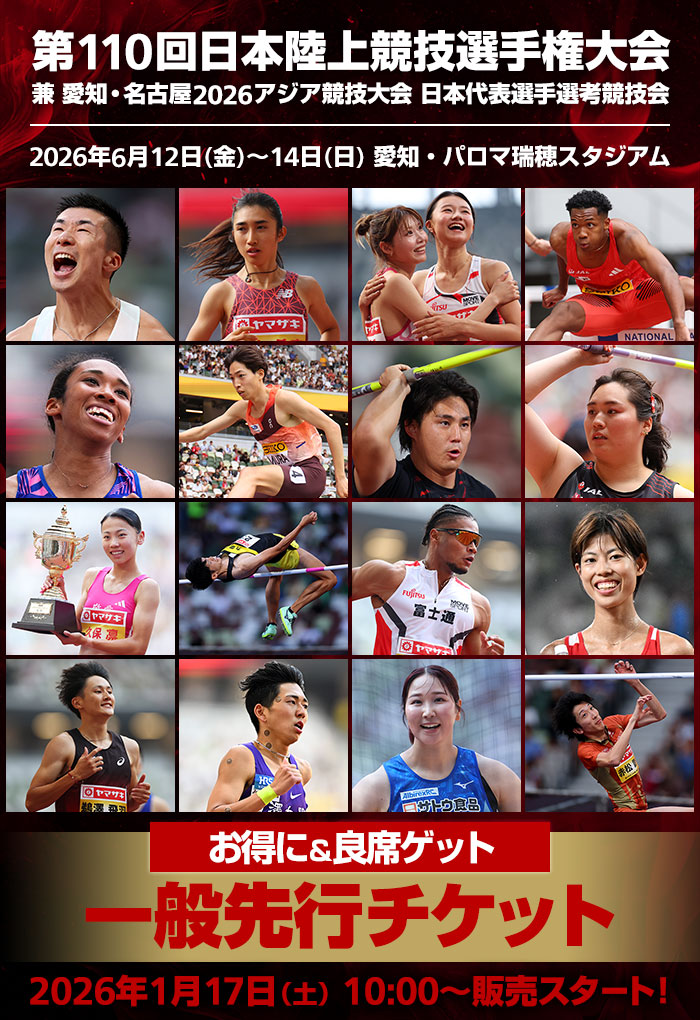東京世界選手権では、大会2日目の9月14日に女子マラソンを、3日目の9月15日に男子マラソンが行われ、日本は、女子は7位に、男子は11位が最高となる成績を残しました。特に暑熱環境下での悪影響を懸念して、大会前からさまざまな対策を講じてきた両種目について、高岡寿成シニアディレクターが総括しました。
高岡寿成シニアディレクター(マラソン担当)
今回の世界選手権男女マラソンでは、女子は小林香菜(大塚製薬)が2時間28分50秒で7位入賞を果たしたほか、佐藤早也伽(積水化学)が13位(2時間31分15秒)、安藤友香(しまむら)が28位(2時間35分37秒)の成績を上げた。また、男子においては、近藤亮太(三菱重工)の11位(2時間10分53秒)を筆頭に、小山直城(Honda)が23位(2時間13分42秒)、吉田祐也((GMOインターネットGrp)が34位(2時間16分58秒)の結果を残している。複数年にわたり異なる入賞者を出せた
女子で入賞者が出せたこと、また、その入賞者が、昨年のパリオリンピックで入賞(6位)した鈴木優花(第一生命グループ)ではなく、小林であったことに価値があると考えている。つまり、オリンピック、世界選手権と、大会こそ違うが2年連続して異なる日本選手が世界大会で入賞できたことは、日本チームの力を示せたといえるのではないかと感じている。これは、入賞には届かなかったものの男子にも言えること。前回の2023年ブダペスト大会では山下一貴(三菱重工)が11位の成績を残したが、今回は所属チームが同じで、順位も同じながら、近藤という異なる選手が活躍した。男子については、昨年のパリオリンピックは赤﨑暁(九電工)が6位入賞を果たしている。このように複数年にわたって、異なる選手が活躍できているところは、日本チームの層の厚さを感じてもらえる部分ではないかと考える。暑熱対策は科学委員会蓄積の長年の知見を活用
私たち強化委員会としては、この大会に向けては、男女ともに、特に暑熱対策を最大の懸念材料と認識し、徹底的な準備を積み重ねてきた。実際に行ってきた内容の背景には、科学委員会が長年にわたって積み重ねてきた貴重かつ豊富な情報や知見がベースになっている。科学委員会は、この時期に東京で開催される本大会において想定される条件を詳細に分析・計算したうえで、必要な対策を私たちに提示してくれた。今回、女子、男子と、それぞれに気象状況は違っていたが、準備の局面で実施してきた設定は、ほぼ実際と同じような条件のなかでの対策がとれていたと思う。我々としては、これらの情報を、チームごとで進めてもらった個別の強化において十二分に生かせるよう、セミナー等も実施して知識の共有を図ってきた。個の特性を重視したチーム単位での強化戦略
前述した科学的な知見のほか、前述のセミナーでは、九電工の綾部健二氏に、赤崎の暑熱対策を公開していただくことができたので、これを成功例の一つとして各チームで戦略を練った。当然、選手には個人差があるので、例えば、小林の場合は専任コーチの河野匡氏(大塚製薬)が、小林の特性や状態を見ながらアレンジして準備されたのではないか。具体的な詳細は把握していないが、おそらくは各チームにおいて、そうした形で活用されたのではないかとみている。競技者として、そしてコーチとしての私自身の経験も含めて言えるのは、「夏マラソンは、本当に難しい」ということ。成功させるためには、練習の段階と、コンディショニングの段階と,レースの組み立てとを、複合的に、総合的にみていく必要があり、さらにそれらは、選手当事者ごとに異なってくる。このため大会に向けてた具体的な強化と同じく、当日のレース戦略についても、ナショナルチームとして私が立てるのではなく、選手の「今」の状態に合わせる形で、各所属チームのなかでやってもらう方法を採った。一方で、例えば、給水に失敗したときなどに、日本チームのなかで渡せるように内容物の共有しておくなどについては、強化委員会のほうから提示した。そうしたチームジャパンとして共有できる部分と、チーム戦略として共有できない部分という2本の柱を明確にして対策をとることで、それぞれが最善の策をとって、レースを進めていくことができたのではないか。その結果、女子においては入賞者を出すことができたと思っている。
チームジャパンとしての競歩との連携
同じロード種目ということで、初日に種目が行われた競歩ブロックからも情報をもらった。例えば、給水エリアについて、テーブルのサイズや配置の仕方や距離感、給水用のスポンジはどんな状態なのか、氷はどんな形で提供されるのかなどの本当に基本的なところを、1日目の35km競歩における状況を共有してもらった。また、女子が終わってからは、そこで知り得た情報を踏まえて、さらに工夫が必要な点はないかを検討し、翌日の男子に生かした。私たちがマラソンで得た情報や気づいた事柄は、このあと、競歩ブロックとも共有を行い、9月20日に行われる男女20km競歩で活用してもらえるようにしようと思っている。このように、マラソンだけでなく、競歩とも連携をとれたことは、チームジャパンとして、これからも積極的に取り組んでいきたい。
各選手の競技結果について
まず、女子について。7位入賞を果たした小林については、本当に驚かされてばかりいるという感じである。今年の大阪国際女子マラソン、その前の防府マラソンのときもそうだったが、今回の結果で、彼女が持つ可能性の大きさを改めて感じるとともに、これまでの豊富な練習量を含めて、「やはり結果を残すためには必要になる部分、核となる部分もあるのだな」ということも再確認できた。「いろいろな気づきを与えてくれる」のが、彼女のレースであるのかなと思っている。佐藤・安藤については、「コンディションを読む難しさ」ということを感じた。ここまで順調に練習できてきたと聞いていたので、それが「コンディションを読む」という面で攻め方が変わったのではないかと考える。女子が今後、さらに上を目指すのであれば、「勝負できる位置にいる力、いられる力」が求められることになるが、ひとまずは3大会ぶりの入賞を含めて、3選手がある程度の順位を確保してくれたことは、次につながると思った。
男子については、気温や湿度は、女子よりも低かったものの、晴れ間ができたことで直射日光にさらされる状況下となる場面があった。もちろん選手の感じ方はそれぞれに異なるだろうが、日に当たることで体感気温は高くなるはず。今後、当事者がスタッフも含めての振り返りが必要になるが、レースを見守った印象としては、女子とは少し異なるコンディションの過酷さがあったのではないかと推測している。「女子のように、なんとか入賞してほしい」という気持ちでレースは見ていた。そこに及ばず残念ではあったが、2回目のマラソンにして11位の成績を残した近藤はもちろんのこと、小山・吉田も含めて、3選手とも、よく頑張ってくれたと思う。
地の利が大きな強みに
――コース特性の把握、温かな声援
この大会では、自国開催であったことが大いに生かされていたと感じている。まずは、コースについて。MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)で走ったことのあるコースであることは強みだと思っている。下見などでのジョグだけでなく、(レースペースで)走ったことがあるかどうかは、上り坂の対応含めてよかったのかなと思う。コース下見については、今回、ナショナルチームとして一堂に会して行うことはせず、個人の計画に沿って各チームでやっていただいている。もう一つは、地元ということでの声援の大きさ。これは、小林がレース後のインタビューで話していたが、沿道でも、そして競技場でも、本当に多くの方が足を運んでくださり、日本選手に対して声援を送ってくださった。このことが選手たちの背中を押し、大きな力になったと感じている。改めて感謝したい。
文:児玉育美(JAAFメディアチーム)
写真提供:アフロスポーツ