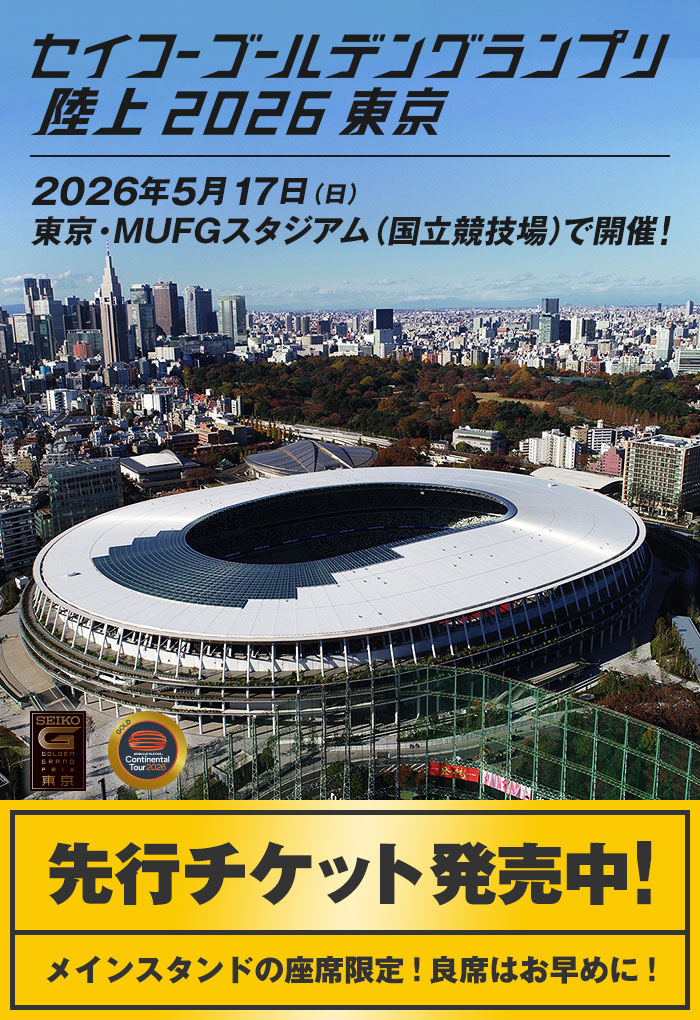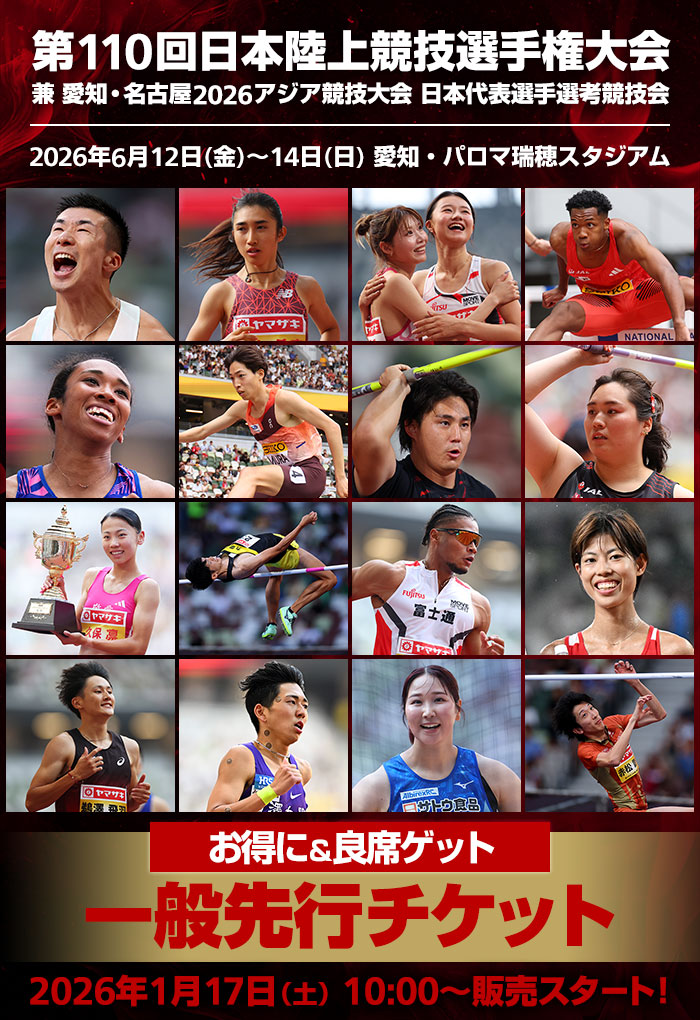日本陸連は、8月22日、東京都内において、育成年代の競技会ガイドラインに関するメディアブリーフィングを行いました。育成年代の競技会ガイドラインについては、すでに本年3月の段階で、2025年度の策定を目指して進めていくことが示されています。田﨑博道専務理事と山崎一彦強化委員長が登壇して、記者会見方式で実施した今回のブリーフィングは、ここまで行ってきた各対応の経過と現在の状況を伝える、いわば「中間報告」に加えて、ガイドラインの柱である競技会スケジュールと仕組みの根本改善について、具体的な改革案も示しながら、その重要性・方向性を改めて説明する場として設けられました。
ここでは、山崎一彦強化委員長が語った「目指すべき競技会システムのあり方」についてご紹介します。
>>「育成年代の競技会ガイドライン」に関するメディアブリーフィングレポート➀
目指すべき競技会システムのあり方と育成年代の考え方(要旨)
◎山崎一彦強化委員長

私たちは、2016年に「タレントトランスファーガイド」(https://www.jaaf.or.jp/development/ttmguide/)、2018年に「競技者育成指針」(https://www.jaaf.or.jp/development/model/)を発表している。タレントトランスファーとは、簡単にいえば、ほかの競技から転向して陸上に取り組んだり、たくさんある陸上のなかで種目を変えたりしていくこと。取り組む種目を変えていくなかで自身の適性を見極め、長く陸上を続けてほしいという願いを込めて作成したガイドラインである。
また、競技者育成指針については、今日、話をする内容の総枠といえるもの。総枠ゆえに具体的な話が見えづらいのだが、いろいろなワーキングを重ねたうえで、「具体的にこういうふうになったらいいよね」というところを示している。発表してもう7年、構想の段階から考えると10年以上が経過している。決して付け焼き刃的に何かを言っているわけではなく、今までもずっと提示して、言い続けてきたことである。
それが、今、動きだすことになったのは、「限界が来た」からだと受け止めてもらいたい。今回、暑熱の対策が待ったなしとなったことが直接の要因となっているし、実際に、その対応についてがクローズアップされたが、そもそも、この競技者育成指針に沿った適切な措置をとることができてきていれば、暑熱の問題もクリアできていたと考えている。少なくとも、今回のような事態…競技スケジュールが急にころころ変わるとか、競技運営の方々、選手や参加する関係者に迷惑がかかるとか、インフラも費用も負担がかかるなどの事態は避けられたのではないか。もう少し、私たちがしっかりと実行に移していれば、なんとかすることができていたのではないかと感じている。
そう捉えると、この問題を考えていくうえで行き着くところは、「目指すべき競技会システムのあり方」ということになる。
◎なぜ競技会スケジュールの見直しが必要か
育成年代で記録が出たときに、なぜ、同時に「あの選手はやり過ぎだから、(将来は)ちょっと厳しいよね」という声が出てしまうのか? その「やり過ぎ」は、目標とする大会に向かうために生じている。つまり、勝つためにやり過ぎなければならない競技会のあり方自体に問題がある。その競技会システムを見直すべきではないか。日本陸連としては、まず、子どもたちが安心・安全に、長く競技を続けていけるような競技会システムのあり方を考え、そして、その延長線上で、オリンピックや世界選手権で活躍するような選手まで網羅していけるようにすることを目指している。この観点に立って、競技会システムを考えていく際には、陸上競技が世界的に展開されている「ワールドスポーツ」であることから、国際基準と育成基準を明確にすることが必要であると考えた。インターハイで結果を残し、インカレや日本選手権で結果を残して、いよいよ世界へ出て行ったとき、「え、日本の競技会とは、やり方が違う」と戸惑う選手は多い。私自身も現役時代にそう思った一人だが、そのころから30年も経っているのに、今の選手たちも同じ思いをしているというのはおかしいのではないか。つまりは、国際基準を意識した取り組みが日本では今もできていない、ということになる。国際競争力をつけるためには、国際基準に則った競技運営、競技施設、強化育成が必要で、そのための基準を考えていく必要がある。
そして、育成年代においては、将来的にその国際基準につながっていくための基準が必要となる。それらと合わせて、私たち独自の戦略や日本の社会状況に合わせていくというのが必要な考え方。その視点で今ある競技会システムをみてみると、国際的なトレンドから外れている可能性もあるし、国際競技力をつける際の障壁になっていることもあると思う。
具体的に競技会スケジュールを改善していく際、育成年代は2シーズン制で行きたいと考えている。そこには、先ほど田﨑専務理事が述べたように酷暑によって開催自体が危険となっている7~8月を避けることが前提となるが、「どのくらいの強度で、どのくらいの陸上競技に携わって、どのくらいの時間を費やしていくと、子どもたちは、そのあとも競技をやってくれるか」「ハイパフォーマンスにつながっていくのか」「陸上競技をやってよかったと思ってもらえるようになるのか」「そのあとの進路をどうするか」といった事柄も考えての提示である。
◎現行競技会システムの課題
私たちが置かれている現状を分析していくと、次のような課題が出てくる。・勝ち抜きシステムの弊害:功罪両方あるが、弊害は、勝ち進むために、育成年代に1つの種目が高度専門化されてしまうこと。それは私たちの出している競技者育成指針とは真逆となるもので、しかし、現在のシステムでは、そこに乗らなくてはならないという状況が生じている。
・暑熱問題の対症療法:暑熱の問題について、前述したような対症療法的な措置に追われてしまう。
・育成年代での心身の過剰な負担:何日間にもわたり実施するいわゆるチャンピオンシップ型の試合形式は、心身ともに疲労感が大きい。それは、選手だけでなく関わる人々すべてにいえる。そういう状態を、育成年代から過度に経験する状態は好ましくない。準備期間も含めて、もっと短く、心身的な負担を軽くすることが必要。
・陸上競技ができる場所・機会の減少:陸上目線でいうと、サッカーやラクビーで使う芝生の保護でフィールドに立ち入ることができない、あるいは予約が取れないなどの理由で、陸上ができる場所や機会が減ってきている。
・インターハイデフォルト:日本における陸上競技の母集団として一番大きいのは高校生。このことによって、競技運営も、関わる人々の考え方も、すべてにおいてインターハイが軸…つまりデフォルトとなっている。しかし、海外では、インターハイがなくても金メダルを取る人たちがたくさんいるわけで、私たちの考え方そのものにバイアスがかかっている可能性がある。確かに、多くの人が参加してタレントプールを増やす機会は大切だが、それと国際競争力を高めることとが分断されていないか、本当にその仕組みでよいのかを疑ってみる必要がある。
・固定化された競技会システム:競技会システムが一度固定化されてしまうと、それを変えていくことが難しい。海外の競技会を経験して、「あんなに応援があって、本当に競技しやすい」「見ていて楽しい、面白い」という声はよく挙がるが、では日本だとなぜ、そう変えていくことができないのか。「アスリートセンタード」を、その理由とする向きもあるが、今は、さまざまな人が競技に関わることで、みんながハッピーになることが求められている時代。「する人」への配慮だけが強すぎる仕組みによって、結果として、選手の価値が伝わらない可能性があるのなら、その固定化された競技会システムは再考する必要がある。
このほかにも、競技会運営の肥大化、審判やボランティアの高齢化・減少、全国規模競技会の赤字運営、公認・施設用器具維持の困難、主要競技会での観客の少なさ、陸上競技に携わる人の減少、地域競技会運営・施設の限界など、現行の競技会システムは、さまざまな課題を多く抱えている。これらを少しでも改善して「次世代を尊重した施設と運営」を目指していくことが求められている。
こうした現行競技会システムの課題を鑑みつつ、私たちは、国際競争力に合った競技運営・競技施設・強化育成の実現に寄与するような競技会システムの改革に取り組んでいこうとしている。その方向性を網羅した「育成年代における競技会ガイドライン」は、4月の段階でご説明した通り、2025年度中の策定を予定している。
◎改善で目指すこと
育成年代の競技会スケジュールと仕組みを改善していくうえで、私たちは、①国際競技会での競技力発揮につながる国内競技会の競技進行、②シニア期の最高業績・最適種目選択(タレントトランスファー)を意図した種目ロードマップ、③加盟団体・関係団体の活性化・連携によるタレントプールの拡充、の3つを目指そうとしている。①国際競技会での競技力発揮につながる国内競技会の競技進行
国際基準に則ったものに変えることで、選手が国際大会に出ていったとき、国内基準との違いに驚かない、迷わないようにしたいということが大前提にある。具体的な改革の方向性としては、
・1レース(1試技)のパフォーマンスが最大化されるタイムテーブル、
・競技会システムがトレーニングのプロセスに反映される仕組み、
・有望育成競技者の競技会過多の防止と国際競技会への挑戦推奨、
・各種公認競技場の育成や現状に応じた多種多様化、
・育成年代における大会期間・競技時間の短縮、
などを挙げることができる。
例えば、現行の国内大会でみられる予選・準決勝・決勝と1日に何本も走るようなタイムテーブルは、オリンピックではあり得ない。その理由は最大限のパフォーマンスを出せなくなるから。そう考えると「勝つために、最大のパフォーマンスを出さない戦術が必要となる(現行の)仕組みでいいのか」ということになる。オリンピックでの「勝つ戦術」と、日本の育成年代での「勝つ戦術」が違っている。こういう矛盾が生じないようにしていかなければならない。
②シニア期の最高業績・最適種目選択を意図した種目ロードマップ
将来的に、シニア期で最高の成績を残せるようにすることを期して、最適種目の選択(タレントトランスファー)をできるようなロードマップにしたい。改革の具体的な方向性としては、以下を挙げることができる。
・競技会システムがトレーニングのプロセスに反映される仕組み
・WA実施種目(オリンピック種目)と育成戦略種目の構造的配置(ダブルスタンダード)
・準備期間の短縮と多種目への挑戦
例えば、今、なぜ、育成年代で300mとか、300mハードルという距離の種目をやっているのか。「中途半端だ」「わかりにくい」という声もあるけれど、よく考えてみれば理解できること。育成年代での400mの練習では、400mは走らない。なぜなら負荷が大きいから。トレーニングのプロセスも含めて、練習でも無理なく実施できる距離が、育成年代における適性距離と考えるべきではないか。それはトレーニングとパフォーマンスの関連性からも、ケガやバーンアウトのリスクも考えても妥当であるといえる。
実際に、今、日本のトップで、オリンピックで活躍している400mの選手たちは、高校時代に飛び抜けた活躍を残していない者が多い。その背景には、インターハイで勝つために求められる要素と、オリンピックで活躍するために求められていることが違っている可能性がある。現在、私たち強化では「200mを走れる選手たちがオリンピックに結びつく」という認識。育成年代にインターハイで勝ち抜きやすい「前半を抑えて、後半で順位を上げて着順を取っていく」戦術しか経験していないと、シニアになった時にはリレー等の適応が難しくなる。
ここで大切になってくるのが「種目ロードマップ」。育成年代では、「200mの全力疾走がきちんとできる人」「今の練習量だから300mまでだが、これからトレーニングをしていけば400mで大成する人」を目指していきたい。
こういう視点でみると、最適種目の選択というのは、例えば、レースペースがシニア期と育成年代とであまりにも乖離しないことが大事とか、走幅跳において助走スピードの高さがパフォーマンスに直結するエビデンスを考えると、絶対スピードの獲得を目指して100mなどでスプリントを磨いておくとか、または身体が小さくても鉛直方向に跳ぶ力を有していたら、その後、ハードルや走幅跳で能力を発揮するようになるとかのような展開が見込めるというような観点が浮かび上がってくる。これは長距離でも同じで、最初からマラソンをやっていくよりは、短い距離から取り組み、最終的にマラソンで結果を残せるようにするほうがよいことがわかってきている。もちろん、すべてが解明されているわけではないが、ある程度わかっていることを重要視して、ロードマップをきちんと描いていく必要がある。
③各連合・連盟・地域団体の活性化・連携によるタレントプールの拡充
ロードマップを描いていくうえで重要になってくるのが、中学校や高校の大会のあり方。そこで出てくるのがこの項目となる。実際には、手つかずの事柄が多く、先ほど田﨑専務理事が述べたインターハイ会期見直しのケースでもわかるように、当該する団体と私たちとの見解に相違があることも明確になってきたという段階。これから関係する皆さんと議論を深め、協力しながら、実現していかなければならない。
目指したいのは、育成年代にかかわる関係団体と連携し、一緒にタレントプールを拡充していくことで、実現に向けては、
・安全な競技環境・競技運営の整備、
・地域(ブロック)競技会の活性化、
・各種公認競技場の育成や現状に応じた多種多様化、
・育成年代における大会期間・競技時間の短縮、
・育成年代が種目参加しやすい競技会・施設設定、
などが、具体的な方向性となっていく。
例えば、インターハイの場合、従来の時期の開催が、暑熱問題で安全な競技環境・競技運営が整えられない状況にあることを考えると、それは、タレントプールの拡充にはならないという視点で再考すべき。上記①②の観点でとらえても、「無理なく、安全にやる」こと、「育成年代後も競技を継続する、できる人が増える」こと、さらには、「オリンピックまで通じていく選手が育つ」ことが、目指すタレントプールの拡充である。もちろん、個々の団体における運営方針はあるだろうが、タレントプールの拡充という共通項を軸に考えていくことが必要になる。
◎「叩かれ台」としての育成年代の年間競技会スケジュール案
育成年代の競技会スケジュールに関しては、実は、10年以上前からワーキングチームをつくって議論してきたことである。具体的にどんなスケジュールにしていけばよいのかとなったときに、高校生でいうなら、インターハイ(全国大会)の日程だけを変えれば良いということではなく、全体のスケジュールを変えることが、先ほど申し上げた目指す育成のあり方になるし、ハイパフォーマンス…オリンピックでメダルを取ることにもつながっていくため、非常に重要と考えている。また、これは、「今、現在」考えていることであり、10年後、20年度には、取り巻く環境すべてが変わっている可能性もある。ただ、今回やろうとしているのは、これまで何十年も変わっていない、問題があると指摘されながらも変えることができずにきたこのスケジュールを、こうやっていろいろな問題を明らかにしたうえで、なんとかして変えていこうということ。日本でずっと続いてきた従来の年間スケジュールでの競技会システムは、ある意味、すでに壊れている。私たちは、この「壊れている」という認識を持って臨みたいと思っている。
8月20日の理事会では、ここまで説明した現行システムの課題や、これから目指していくべき方向性とともに、育成年代で最も育成年代であり競技人口の多い中高校生のうち、特に改革が必要とされる高校生における年間スケジュールの構想案を示した。田﨑専務理事も述べたように「叩き台=叩かれ台」で、これをそのまま通そうとしているわけではない。理事会でも、この案自体のコンセンサスが得られたというのではなく、この案の検討を含めて、さまざまなことにトライしていくことに関して承諾を得ている。
「叩き台=叩かれ台」は、具体的には、以下の視点での構想である。
・育成年代の競技会スケジュールは2シーズン制で:WBGT(暑さ指数)が31℃以上となる可能性が極めて高い7~8月は競技会を行わないという暑熱対策の意図も含めて、育成年代は2シーズン制とする。オリンピックや世界選手権の日本代表を目指していくシニアについては、ワールドカレンダーに合わせてのスケジュールとなるため、臨機応変に進めていかざるを得ないことになるが、そこは、先ほど述べた国際基準と育成基準ということで分けて考えることになる。
・インターハイは、7月・8月以外での開催に:WBGTが31℃以上になったら競技は中止という大前提となったとき、そのことに振り回される時期を外して開催するべき。現段階では少なくとも7~8月に中断なしでの開催は難しいため、「叩かれ台」では6月を挙げた。しかし、気候のことなので、今後どうなるかはわからない。社会状況の変化によっても変えていく必要があることだと思う。
・準備期間の短縮を意図した6月開催:インターハイ6月開催を提示したのは、7~8月に実施できないというのもあるが、「準備期間を短くする」ことも意図している。チャンピオンシップでの勝ち抜き戦は、早い年代から1つの種目に力を傾注していく「早期高度化」を引き起こす。これを過度に長期化させないことを目指したい。勝ち抜き戦の期間を短くすることでトレーニングプロセスとしての準備期間自体を短くし、選手に過度な負担をかけないようにする。また、別の種目にも挑戦できるような仕組みにすることによってタレントトランスファーをしやすい状況をつくる。
また、「過度の負担をかけない」という点で、国際競技会に出場していくであろう有望選手の競技会過多を防ぐためにターゲットナンバーを制を用いて、記録の良い者は都道府県大会の段階でインターハイ出場権を獲得できるようにする。このグループは、U20世界選手権等にもかかわってくる層なので、その大会を選んでもらってもよいし、会期がずれるならインターハイと両方を無理なく目指せるようにする。
このほかブロック大会に進んだ人たちは、例えば優勝者等、条件付きターゲットナンバーなどを設定してブロック大会からもインターハイに行ける層をつくる。
・進路との兼ね合い:高校3年生の場合は、進路を考えて動いていく非常に大切な時期となる。インターハイが6月で終わるのと、8月またはそれ以降まで引っ張るのとでは、受験を考えたときの負担は大きく違ってくるものと考える。
・2シーズン目はオープンエントリー制で:勝ち抜きとなる前半のシーズンは、最初に決めた種目で戦っていくことになるが、後半のシーズンは、同じ種目でも良いが、別の種目にトライしてみるなど可能性を広げることが可能な種目選択で競技会に挑戦できるようにする。トップを目指していく層は、秋にU20日本選手権やU18・U16大会を配置することで、それを目指していくことができるし、それ以外の層の人たちは、新人戦という形で都道府県大会、ブロック大会に臨み、ターゲットナンバー制を用いて都道府県の新人戦からU18・U16大会に出場していけるようにする。
メディアとの質疑応答・意見交換
田﨑専務理事および山崎強化委員長の説明が終わったところで、参加したメディアとの質疑応答が行われました。そのなかには「高体連専門部から提示された3案というのはどんなものか」「高体連本部との議論が平行線のままとなった場合、インターハイの主催から降りることもあるのか、その場合、記録は公認されるのか」といった質問も。これらに対して、田﨑専務は、「8月6日に高体連専門部として提示いただいた案は、①会期を9月にする、②必要な暑熱対策をとって、従来通り7~8月に実施する、③会場を固定する、の3つ。これらも含めて検討していくために、8月19日の段階で、文書での提出をお願いした」と答えました。また、そのなかで同陸上専門部長を通じて伝えられた「2028年までは日程をずらすことは極めて困難」とする高体連本部の意向も踏まえて、「高体連のなか(本部と陸上専門部)でも統一がとれていないところがあるのが現状」という見解も示し、だからこそ、「我々は、ここで皆さんに示した“叩かれ台”も出したうえで、これからさらに意見交換しながら話を詰めていく、働きかけていく」とコメント。広島インターハイにおいて生じた全関係者の心身への負担や費用面の負担等を考えあわせると、高体連本部の示す2028年まで従来通りとなった場合に、「本当に、それで開催ができるのかということを、詳細まで突き詰めて考えたうえでなければ、“わかりました。やりましょう”という話はできない」と述べ、主催・公認という点についても、「3月の段階で組織決定していることなので、方向性は変えない。今年度の7~8月については、“原則”という言葉を用いて、可能な限り環境を整えていくよう必死に方策を考えて対応してきたが、2026年度以降についは、当初の方針にあてはめて考えることになる」と回答。「3月の段階で、暑熱対策がクリアできないのであれば主催はしないと言っているので、主催はできなくなるし、その場合、仕組みとしては公認もできなくなる」と述べました。
そして、「主催しない、公認できない」ということの重大さは、充分に理解し、受け止めているし、そうなった場合の影響を強く懸念している」としながらも、「主催するとなったときには、主催責任がある。主催する以上は、アスリートだけでなく、観客や競技役員、補助員、ボランディアの方、さらには設営や警備など、大会にかかわるあらゆるすべての方々に対する責任がある。その観点は決して忘れてはならない」と、ナショナルフェデレーションとしての立場を示しました。
また、山崎強化委員長が説明した「叩かれ台」に対して挙がった、「陸連が示す国際競技力向上という目標から考えると、いわゆる“エリート層”が念頭にあるのでは? あらゆるレベルの競技者も包括できるものとして考えているのか?」の問いに対して、山崎委員長は、「これらの見直しは、育成の基盤となる“タレントプール拡充”を非常に大切と捉えているからのこと。私たちの根底には、“トップを育てるうえでも、まずは育成がきちんとしていなければダメ”という考えがあるし、そのことはずっと言い続けてきた」と答えました。
さらに、「インターハイのあり方が変わってしまうことで、子どもたちのモチベーションに影響するのでは?」「インターハイで勝ちきることも、選手の強さを形づくるうえで大きな要素ではないか」等、さまざまな見解が示され、質疑応答というよりは、互いの意見が取り交わされる場面もありました。そうしたやりとりも踏まえて田﨑専務は、「誰かが“こうだ”と言えば、必ず別の意見も出てくる。それらを、“本来どうすべきか”というところにぶつけてみて、そのなかで最適な解を出していこうと努力していくことが大切なのだと思う。問題の指摘ばかりをするのではなく、具体的なものに落とし込みながら議論していくことによって、“やってみようか”という案も出てくるし、解も出てくるのではないか」と述べました。
「叩かれ台」とする構想案について、「インターハイは、私たちも通って来た道で、本当に熱くなる大会。経験した人の声を聞けば、“よかった”となるのは当然で、この“叩かれ台”を出すと批判は必ず出ると思っている」と山崎強化委員長。しかし、育成年代で勝つことや記録を求めることの過熱化が、その後の競技継続を阻む要因となっていることや、競技力の向上につながっていないこと、その過熱を生む競技会スケジュールを見直すべきではないかという声は、以前から陸上界の課題となっていたことで、「変える、変えると言いながら、結局変わらないまま、30年近く経っている。もちろん、暑熱の問題は、ここまで予測していなかったとは思うけれど、それだけ実際に変えることが難しかったのだと思う」と述べました。「ただし、日本以外に目を向けると、ほかにも選択肢がある。そういう視点も加えて、どう変えていくのがよいかを、みんなで考えることが必要」と述べ、インターハイの意義や価値を大切にしながらも、気候も含む現代の社会情勢に合わせて、課題を解消していく取り組みの重要性を訴えました。
インターハイ会期の議論は、ここで示された「叩かれ台」も提示し、今後も引き続き高体連との協議を深めていくとのこと。また、この取り組みは、高校年代だけでなく、中学校年代についても、すでに関係者間での検討は始まっており、これまで8月に開催されてきた全日本中学校選手権をはじめとして、中学校期における競技会システムについても、今後、策定されるガイドラインに則って「一人でも多くの競技者に、少しでも長く陸上競技を続けてもらうために」を実現させるための議論や検討を進めていく計画であることが示されました。
※本稿は、8月22日に、メディアに向けて実施したブリーフィングの内容をまとめたものです。明瞭化を目的として、説明を補足する、構成を変えるなどの編集を行いました。また、質疑応答に関しては、挙がった声のなかから、冒頭説明では示されなかった点を中心にピックアップし、要約する形でまとめています。
>>「育成年代の競技会ガイドライン」に関するメディアブリーフィングレポート➀
文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)
【関連資料】
■JAAF 競技者育成指針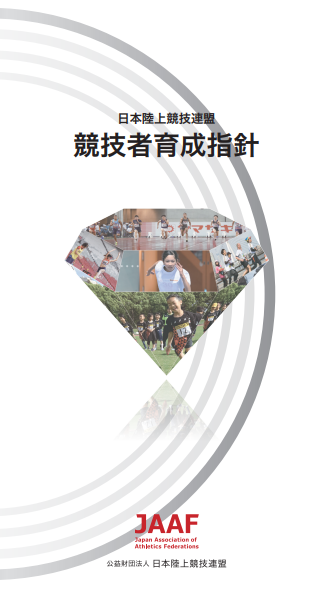
>>https://www.jaaf.or.jp/development/model/
■タレントトランスファー
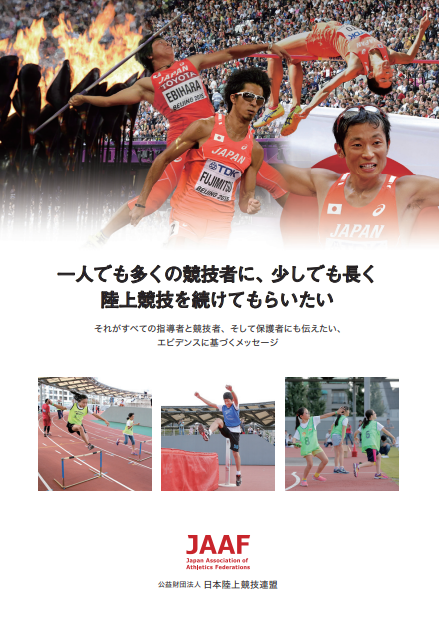
>>https://www.jaaf.or.jp/development/ttmguide/