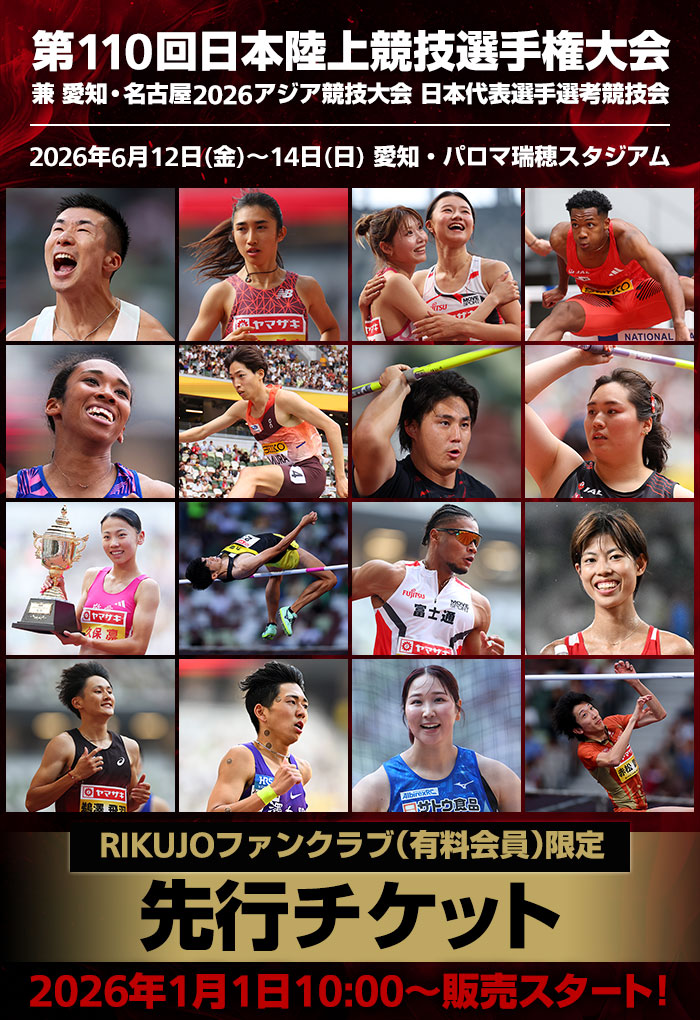活動のミッションに「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」を掲げる日本陸連では、これらを遂行していくうえで、陸上競技に関わるすべての人が、スポーツを通じて心も身体も満たされたウェルビーイング(Well-being)な状態であることを重要と捉えています。そして、この実現に向けて、リーフレットを作成・配布するなど( https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/ )、アスリートはもちろん、アスリートを支えるすべての人が、正しく競技と向き合い、アスリートの健康を守るための知識や学びを深めていけるきっかけつくりに取り組んできました。今年は、その活動の幅を、さまざまな形でさらに広げていくことを計画しています。
1月11日には、翌日に開催される全国都道府県対抗女子駅伝に併せて、一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業協力のもと、『プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」』と題したセミナーを、京都市内で開催しました。
本セミナーの内容について、全五回に分けてお届けします。
今回は、その第三回目となります。
◎テーマ2:女性アスリート特有の課題
「月経周期とコンディション」
須永:まずこのテーマでは、弘山さんにお聞きしたい。男性指導者が女性アスリートを指導する際、実際にどのようなアプローチをしているのか?弘山:気を遣うタイプではないので、私はストレートに言ってしまうことが多いが、口にしなくてもいいやり方としては、日誌の利用がある。選手が月経周期を記録した日誌を提出し、指導者はそれを見て、「今、何日目だな」「少し遅れているな」「月経前だから身体が重いのかもしれない」などを把握する。それによって、練習でうまくいかなかった場合でも、「月経前で、ちょっと身体が動かないのかもしれないね」といった感じで選手を安心させるができる。結局は、そうしたメンタルの部分が結構大きいのではないか。月経に関しては、本当に個人差があり、人によって異なる。それぞれの選手の特徴をまずはきちんと把握することで、その時の走りがどうかに対して、安心させられるようなアプローチを心掛けている。
例えば、妻は狙った試合が月経に当たることがよくあった。2000年のシドニーオリンピックを目指した大阪国際女子マラソンのときも、当日の朝に月経が来た。ただ、彼女の場合は、月経前になると身体が重くなり、動きづらくなるが、来てしまえば走れるようになるタイプ。そういったことを、指導者や身近な人が知っていれば、何か起こったときでも、うまく言葉をかけることができる。月経周期を受け入れてちゃんと前に進んでいくこと、そういう納得感を持って1日を終えていくことが、メンタルヘルスを考えるうえでも良いのではないかと思う。
大切なのは信頼関係と、起こっているのは自分自身ということ。自分のことなのだから、否定したりマイナスに考えたりすることがないようにしてあげるのが周りのサポート(の役目)だと思う。例えば、今日の練習が崩れてしまったとしても、それはもうしょうがないこと。その理由がはっきりしていれば、落ち着いて次に向かっていくことができる。そのあたりのコミュニケーションがうまくできるといいなと考えている。

須永:小林さんは、月経周期とコンディションについては、どうだったか?
小林:私の場合は、中学・高校ではきちんと月経が来ていたが、実は、社会人になってオリンピック(2008年北京大会)を機に、月経が7年間止まっていた。このため、周期というよりは、月経が来ないことに悩んでいた。ただ、月経が止まったのが中学・高校年代ではなく、社会人になってからだったので、すぐに監督に相談して、産婦人科に通って薬を処方してもらい、ピルを飲みながら練習を継続することができた。しかし、その一方で、月経が来ないということに対して強い危機感があり、そのことによる精神的なストレスが非常に大きかった。そのストレスが、競技力にかなり影響したなと感じている。今、いろいろな取材をしているが、私の周りでは、月経が来ていない中高生の例がとても多い。取り返しのつかない時間なので、そこを放置してはならないと思う。
実は、イベントや講習会などの質疑応答の場で中高生の女子選手から挙がるのは、食べることに関する内容がほとんど。私としては走りや技術に関することを聞いてくれるようであってほしいと思うのだが、おそらく自身の日常的な意識が体重管理に向いているために、トップ選手がどれだけ食べることを我慢しているのかを知りたいのだと思う。また、体重管理が目標になってしまっていて、競技にうまく直結していない選手や、「痩せなければいけない、そのために食べるのを我慢しなければいけない」という負のサイクルに陥ってしまっている選手、月経が来ていない選手が本当に多い。そこをどうにか改善していくことはできないか。中高生に響いてほしいなと強く感じている。

有森:我慢して何かをさせることの効果というのは、実はほとんどないというのが本当のところ。その気持ちで頑張れる期間は短くて、どうしてもどこかで弾けてしまう。本当の意味で「これから」というときに、身体だけでなくメンタルもダメージを受けていて、伸びていかなくなるパターンがあることを、もっと現場は知る必要があるし、選手本人にも「我慢してできることは限られている」ことを理解させるべき。我慢ではなく、納得して取り組むことが大事だが、そのためには、教えるほうも教えられる側も、ちゃんとコミュニケーションをとらなくてはならない。そこができていないままでの関係性のなか出てくる結果は、長くは持たないものといえる。
私自身は、我慢をした経験がない。それは、自分がやるからには意味とイメージを持ってやることにしていて、そこに自分の目標を乗せていたから。納得するために「なんでこれをやるのか?」「なんのための練習なのか?」「どうして?」と、しつこいくらい聞いていたし、そこを納得して、「このためにやってきたのだから」と思えるようになれば、しめたものと考えていた。
だから、選手本人も考え、教えるほうも考え、そのうえで「納得したね。じゃあ、やろう」という取り組み方になれば、「我慢する」という言葉自体がなくなるなかで、互いに伸びていくことができるはず。二人の話を聞いていて、そういう指導があってほしいなと感じた。
須永:本当に、そういう選手こそ、伸びていくのだろうなと思う。今、指導者の皆さんは、選手を育てているわけだが、その選手のなかにも将来の指導者にもなっていく人が出てくる。「自分がどういう指導を受けたか」ということは、その先にも繋がっていくわけで、今の話を聞いて、コミュニケーションをとることの重要性を改めて実感した。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
今後の掲載予定
#4 パネルディスカッション
鉄不足と貧血「鉄不足がパフォーマンスと健康に与える影響」
#5 パネルディスカッション
精神的健康とモチベーションの維持「長距離選手におけるメンタルヘルスと社会的サポートの重要性」
準備でき次第、順次掲載をしていきます!
ウェルビーイングリーフレット
https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/
関連ニュース
-
2025.07.01(火)
【アスリート委員会】が迷惑撮影に対する声明を発表しました!
委員会 -
2025.05.28(水)
指導者セミナー ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」
その他 -
2025.03.07(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#5
その他 -
2025.02.28(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#4
その他 -
2025.02.21(金)
【Well-being指導者向けセミナー 受講者募集】『ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」』
その他