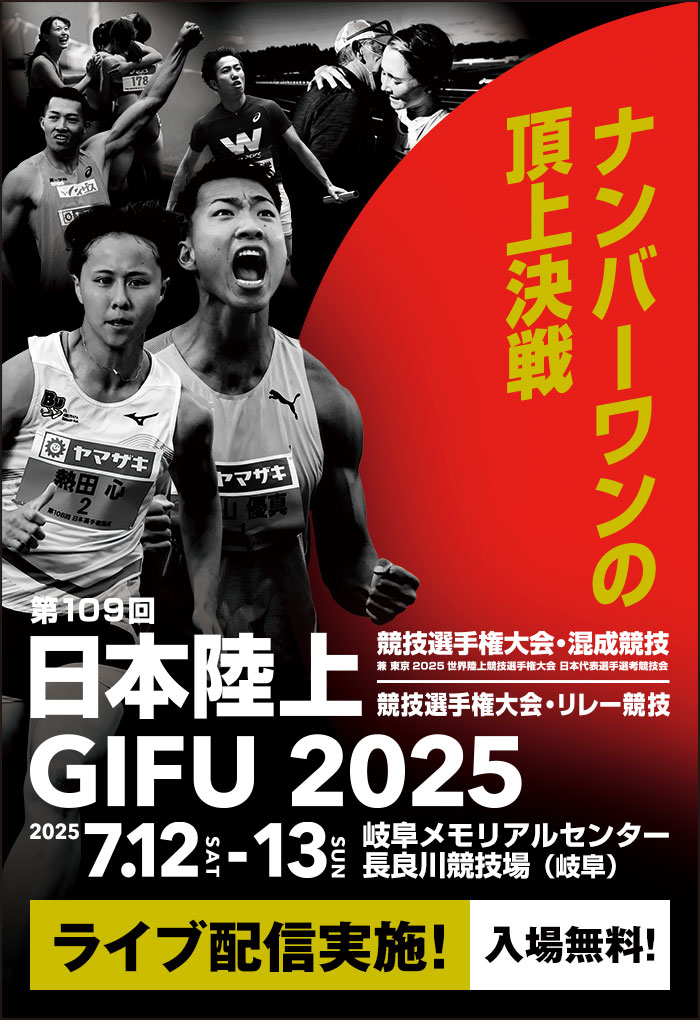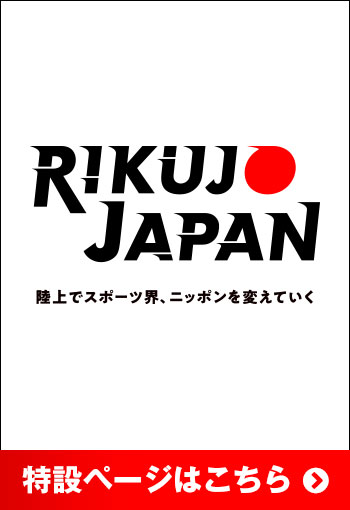U20オリンピック育成競技者研修合宿は、日本陸連が、有望競技者の新しい能力の発掘すること、対象競技者がオリンピック育成競技者としての自覚を高めること、国際的な視野を育むこと、来年U20カテゴリーの国際競技会での活躍することを目的として、強化委員会のなかの強化育成部が冬季シーズンを利用して実施している取り組みです。
この合宿の特徴は、単なる強化トレーニングを目的としたものではないこと。日本陸連で策定している競技者育成指針(https://www.jaaf.or.jp/development/model/)に則ったプログラムを組み、成長期まっただなかにあるU20年代競技者の個人差や将来的な種目選択に向けて、種目の変更(トランスファー)を容易にするような身体や動きをつくるトレーニングを推進するほか、体力測定の結果や、測定結果の読み取り方、スポーツを通じてウェルビーイング(精神的、身体的、社会的に良好な状態にあること)を実現する考え方、中高生年代のアスリートが直面する身体の変化を学ぶ研修など、さまざまな座学も行われています。
また、強化育成部では、この年代の指導者に向けて、「将来的に、世界水準で長く戦っていくことのできる競技者を育成するために、U20年代に必要となる強化育成の方向性」を、多くの指導者と共有し、その方針を広く知らしめていくことにも取り組んでいます。1月13~16日の日程で行われた第2回U20オリンピック育成競技者研修合宿では、指定競技者とその指導者のほかに、一般指導者を対象とした「視察参加」という新たな参加枠を設定。1月13日には、開講式の前に、日本陸連強化委員会シニアディレクターで、強化育成部門を率いる杉井將彦シニアディレクターが、これら参加指導者を対象に、日本陸連が進めていこうとしているU20年代の強化育成方針を説明しました。ここでは、杉井シニアディレクターが述べた内容を、ご紹介しましょう。
日本陸連が目指す強化育成の方針と、強化育成で求められる戦略について
杉井將彦(日本陸連強化委員会シニアディレクター)
今日は、せっかく私たちの合宿に参加していただいたので、この機会に。強化育成部がどんな考えで活動しているかを、皆さんに、お伝えしたい。私は、今年62歳になるが、強化育成の活動には25歳のころから長く関わってきている。育成部の活動は、かつてはこうした合宿のコーチや世界ジュニア選手権(現U20世界選手権)などの国際大会のコーチ派遣などがメインで、それ以外の活動はほとんどないという状況であったが、現在強化委員長を務めている山崎一彦委員長が、この育成部のトップになったときから、強化育成部としての基本方針をしっかり示して取り組むようになった。その方針は、ダイヤモンドアスリートプログラムとU20オリンピック育成競技者の強化が二本柱。これらに加えて、指導者における中長期的指導への理解、競技者が国際的に活躍できるような育成、有望競技者の新しい能力の発掘を促進するといったものがあり、現在は、それらをポイントとして活動している。
育成年代の世界大会で突きつけられた日本の課題
とはいえ、私もまだ現役の高校教員で、高校年代における指導の現場で何が起きているかというと、私自身、「インターハイで勝つために」「インターハイで総合優勝するために」「高校記録をつくるために」、ただそれだけに特化した取り組みをしてきた。インターハイで特徴的なタイムテーブルで例を挙げると、400mは大会初日に1日3本(予選・準決勝・決勝)のレースが行われる。この3本目(決勝)に結果を出すためには何をしたらいいのかを模索して、そのために頑張ってきた。一方で、育成部の委員として、世界ユース選手権(その後、U18世界選手権として開催。2017年で実施を終了)等の国際大会へ帯同する機会を得たわけだが、そこで見た光景は、日本とは異なることがたくさんあった。ここでは400mを例に紹介したい。
世界ユース選手権では、スタート直後から全力で走る選手が他国にはたくさんいた。日本選手はスタートで完全に後れてしまうが、その飛び出した選手は200mを過ぎたところで急激に失速し、最後はふらふらになってフィニッシュし、日本選手はその間隙を縫って、いわば「非常に賢いレース」展開でメダルを獲得。当時はそれを「さすが日本選手」と誇らしく思っていた。
これが次の年代にあたるU20世界選手権になると、少し様子が変わってくる。スタート直後の状態はU18と同じだが、200m過ぎで失速していた選手たちのスピードが、300~350m付近まで維持できるようになっていた。そうなると日本選手はかなり分が悪くなってくる。
そして、シニアの400mレースは、皆さんもオリンピックや世界選手権の放映などでご存じだと思う。100mを9秒台で走る選手が、一気にスピードを上げて走り、そのスピードで最後まで走りきってしまう。日本人の全く歯が立たない種目になってしまった。
こういった状況を目の当たりにして、もっと前半から全力で走れるようにしていかなければと、育成部として、300mや300mハードルという種目を実施するなど、いろいろな取り組みをしてきたわけだが、現実にはインターハイにおける「1日3本の勝負」は変わらず存在している。私の教え子には400mで日本選手権を制した選手が2人いて、2年連続で違う選手がタイトルを獲得したのだが、その2人は1日1本のレースとなる日本選手権では日本ジュニア記録(現U20日本記録)や非常に速いタイムで優勝できたのに、1日3本行われるインターハイでは負けている。つまり、両大会を勝つために求められる能力が違っているということを意味する。
私たちは世界ユース選手権などの帯同で、日本のジュニア選手の指導は、世界でもトップレベルだと自負していた。確かにメダルをたくさん獲得し、メダルテーブルでもプレイシングテーブルでも上位に入っている。また、担当した選手の多くが表彰台に立ち、なかには君が代を流してくれた選手もいた。そのときは「本当に幸せだな」と思っていたが、本当にそうだったのか。ここで示した400mの例だけでも、少し引いた視点で見てみると、とても考えさせられてしまう。
本当に目指すべきはなんなのか。私たちの選手が最終的に目指す(シニアの)世界大会でメダルを取るために、私たちの選手が世界大会で入賞するために、私たちの選手がシニアの日本代表になるために、私たちの選手がずっと活躍するために…、私たちは今、何をすべきなのかということを考えていかなくてはいけないのでないかと思う。
国内の精度の高さが世界に出たとき壁を高くする
現在、国内で育成年代の選手が目指す大会としては、国スポ(国民スポーツ大会、旧国民体育大会:国体)、全中(全日本中学校選手権)、インターハイ、そして日本陸連が主催しているU18・U16大会がある。これらは毎年同じルールのなかで実施しているので、長く取り組んでいる先生方は、これら大会に向けて、成功体験のなかから、または過去の失敗から、その指導を、どんどん無駄のない、そこで成果を残すことに特化した内容にしてきているのではないか。少なくとも私はそうで、そのためだけに、本当に無駄なく取り組みを進めていたと思う。それは、競技会の運営についても同じといえる。会場を変えても同じことを繰り返しているので、結果的にミスのない、非常に精度の高い、世界でもトップクラスの競技会が開催できている。これは国内の競技会全般にいえることで、例えば、秋になると長距離競技会が数多く開催され、その一つ一つが非常に効率良く、記録の出る大会として実施されるようになっている。
しかし、世界では、日本人が日本国内で出した記録を、実は価値あるものとして認めていないという現実がある。日本での記録ではなく、海外で、どのようなパフォーマンスを出しているかというところが評価の基準になっている。前回のこの合宿で山崎強化委員長が報告したが、昨年のパリオリンピックでは、トップエイトの成績を残した競技者は、男女トラック・フィールドともに、高い自己記録達成率を残していた。つまり、自己記録を更新するくらいでないと、そこに到達する結果は得られないということである。にもかかわらず、今までの日本人の課題は、オリンピックや世界選手権でなかなか結果を出せないということで、今回も、そういう選手がたくさんいた。
「世界で勝負をするレベルに到達したときに何が起きるか」ということは、山崎強化委員長が育成部の責任者だったころ、アスリートとしての自身の経験も交えながら熱く語ってくれた。多くの日本人アスリートはまず文化の壁にぶつかる。それは言語だけでなく文化全般にわたるもので、日本国内では当たり前だったことが、海外に行くと全く通用しなくなる。例えば、皆さんは、大事な試合の前に、全く知らない、言葉も通じない選手とルームシェアできるだろうか? 世界を転戦しているトップ選手は、それを当たり前のこととしてやっているなかでパフォーマンスを出し続けているのである。
そうした理由から、私たちは育成年代の段階で、ワールドワイドな感覚を身につけることを目指し、「海外に出て行こう」「もっともっと海外に目を向けよう」「国内に目を向けてインターハイや全中に特化するのではなく、外に向かって自分たちの活動を広げていこう」という方針を打ち出した。それは、育成年代の今、やっておかないと、勝負するときになってからでは間に合わないことだから。できるだけ若いときに海外へ行って、文化の壁をできるだけなくすような、そんな取り組みをしなければならないという考え方である。そういう方針で取り組み始めた最初の年代が、男子短距離の飯塚翔太選手(現ミズノ)あたり。アメリカやオーストラリアへ2週間前後の合宿に行き、自分たちで食事をつくり、そこで生活をしながらトレーニングに取り組んだ。そうした彼らの地道な努力が、シニアになってからの結果に、徐々に反映されるようになった。
昨年は、ペルーのリマでU20世界選手権が開催されたが、その1つ前の2022年にはコロンビアのカリで、U20世界選手権が行われた。日本チームは、コロナ禍の影響でその前回大会への参加を取りやめていたため、久しぶりの参加となったわけだが、2015年に世界ユース選手権が行われたことから、「勝手知ったる場所」という思いで臨んだが、いざ現地に行ってみると愕然とした。それは、世界大会の会場であるというのに、サブトラックにオールウェザーが敷かれておらず、アスファルトがむき出しのままになっていたから。内戦などの影響でオールウェーマットの輸送が遅れ、届くには届いたものの設置が間に合わなかったということだった。
もし、皆さんがインターハイ会場に行って、サブトラックにオールウェザーが敷かれていなかったら、「しょうがないね」で済むだろうか? 日本でだったら済ませることはできないはず。日本チームのコーチや選手は、みんなそんな感覚だった。コーチ陣は毎日のように、「いつ敷かれるんだ」「どうすればいいんだ」と問合せに行ったし、選手のなかにはいつも通りのことができないので半べそをかいている者もいた。一方で、アフリカの長距離選手たちは和やかな雰囲気で笑いながらトレーニングしていたし、他国の選手たちも文句を言うわけでもなく、やれることをやっていた。つまり、世界大会で結果を残すためには、そういう状態であったとして、そのなかで自己記録を更新するような準備をしていかなくてはならないわけである。
日本で当たり前だと思っていることは、実は当たり前ではない。陸上が盛んなヨーロッパの競技会であっても、サブトラックがないのは普通のこと。テニスコートでハードルを跳んでいる選手を見たこともある。そういったことも含めて、私たちは早い段階で、そうした条件かも経験しておかなければならない。
実情にそぐわない設定やルールを変えるという選択
国スポは、昨年、第78回大会が行われたが、この大会の旧称である国体は戦後2年目に始まっている。また、インターハイは戦後4年目に始まっている。戦争で廃墟となって、何もなくなっていた日本で、その2年後や4年後に全国大会を開催させた人たちを思うと、その行動力と先見性には本当に驚かされる。準備期間から考えたら80年も続いているわけで、本当に素晴しいことだといえよう。しかし、インターハイで区分されている11ブロックはどうやって決まったのか? このルールを80年間ずっと守ってきたけれど、本当にそれでよかったのか? ワールドアスレティックスは、育成段階の競技会は、毎回ルールを変え、いろいろなチャレンジをしながら開催している。その理由は、ハードルの高さやインターバル距離の設定や投てき物の重さなどを変えることで、筋力のない年代の選手たちに、その世代でなければ身につかない技術を、その設定にすることで身につけてさせようとしているから。育成段階に合った取り組みを、常に模索しているわけである。
もう一つ例を挙げるなら、2018年にアルゼンチンのブエノスアイレスでユースオリンピックに帯同したときの経験をご紹介しよう。会場で、「競技は、ステージ1とステージ2の合計で決まる」というルールが説明されたのだが、私はそのとき、すぐに意味がわからなかった。「予選と決勝か?」と尋ねたら、「いや、ステージ1とステージ2。全員が2回走って、その合計で勝負を決める」と言う。また、中長距離のステージ2はクロスカントリーで、全種目一斉にスタートすることや、合計ポイントが同じ場合はクロスカントリーの結果が優先されることがルールになっていた。つまり、そこにはっきりと「クロスカントリーが大切なんだ」という方針が示されていたのだ。
私たちも、そういった取り組みが必要なのではないか。そして、育成段階の競技者に対して、そうした方針を、きちんと示していかなければならないのではないかと思う。現在、各種目66人が参加するインターハイは、それによって非常に大きな競技会になっている。しかし、本当に66人でいいのか? 私も一高校教員として参加してきたころは、なんの疑問もなくやってきたが、本部役員の立場で実情を見たとき、いろいろな点に問題を感じるようになった。
例えば、バー競技(走高跳・棒高跳)の競技結果を見ると、25人がノーマーク(記録なし)。全国大会に出た66人のうち25人もの選手を記録なしで帰らせているわけである。最初の高さが設定ミスではないかと問うと、そうしないと時間内に競技を終えられないという答えだった。時間的な都合で生じる無理はトラック種目にもある。さらには本来であれば出場できる力を持つ選手が、地区大会を通過できずに出てこられないのもよくあるケースであろう。6府県で競わなければならない近畿大会を通過するのがどれだけ大変か…。また、関東では南と北を同じ会場で実施していて「北だったら行けたのに」「南だったら行けたのに」という事態が多々起こる。教育的配慮という面で、それはどうなのか…。こうした課題を前にして、「誰もが“なんで?”と思っているようなことを、どうして変えていこうとしないのか?」ということを考えるようになってきた。
それもあって、日本陸連で企画する大会については、「ターゲットナンバー40」という設定で実施している。もちろん、お叱りの声もある。「準決勝をやれば、もっと参加できるのに」ということは、ずっと言われてきている。それでもターゲットナンバー40にこだわるのは、予選と決勝で終えることのできる最大数であるから。そうであれば1日1本に設定するタイムテーブルも組むことができる。世界大会で行われているように、その1本のために全力で臨んでいくレースができるのだ。
インターハイでは、サブトラックで日傘の使用を禁止するルールがある。雨天時の傘は許されているが日傘は禁止。人が多いので危険だからというのがその理由だが、熱中症が深刻な問題になっているなか、暑熱対策を考えたらあり得ないこと。1種目66人と参加者が多いから変えられないのなら、そもそもの出場人数を変えていくことも考えるべきではないかと思う。
このほか、私たちは、競技会の実施において、相対年齢強化に対する取り組みをしているが、これについても、中学校の先生方からは厳しいお叱りを受けた。「全中のリベンジを、ジュニアオリンピック(2018年度から学年別のクラス分けを廃止)で考えていたのに、U16にしたら高校生が出てくる。ずるいじゃないか」と。確かに、そこだけ見たら、そうかもしれない。しかし、長い目線で見たときには、その設定を選択する理由が明確にあった。
全中に参加する選手の生まれ月を見ると4~8月生まれが多く、特に男子選手で顕著になる。それはインターハイになると、10月生まれくらいまでになってくるが、全体でみたとき1~3月生まれに凹みが生じているという現実があり、それは、その層のタレントが早い段階で、「通用しない」と自分で判断し、ドロップアウトしていることによって起きている。育成年代に設定の切り口を変えることで、早生まれの子どもが活躍する場面ができれば、有望なタレントが上のカテゴリーまで競技を継続してくれるのではないかという期待が、背景にあるのだ。
厳しい状況におかれている「陸上」育成年代に本当に必要な強化とは?
全中やインターハイ、国スポといった国内競技会で優勝者を決めることは、その年代の指導者にとっては最大の目標なので、「世界に目を向けろ」と言われても、かけ離れ過ぎていてピンと来ないという人もいるかもしれない。しかし、全く関係のないことなのかということを、最後に少し話をさせていただきたい。この年末年始も、たくさんのスポーツ選手がメディアで取り上げられた。オリンピックがあった2024年を回顧する報道番組への出演のほか、バラエティ番組などにもゲストとして多くのトップ選手が出演していた。我が陸上競技からは、ダイヤモンドアスリート修了生でもある北口榛花選手(JAL)やサニブラウンアブデルハキーム選手(東レ)が出演。特に北口選手は、本当に多くに出演していて、そのたびにオリンピックで金メダルを獲得したときの映像が流れ、結果として、陸上競技というスポーツに脚光が集まることになった。それはまさに北口選手のおかげといえるだろう。もし、彼女がいなかったら、出演したのは別の競技の選手であったはず。なぜなら、金メダリストはたくさんいるからである。
私たち陸上は、今、非常に厳しい状況に置かれている。なぜなら、陸上の競技人口を支えている一番大事な土台であった学校部活動が、地域移行という形で廃止されていこうとしているから。今までとは違う形で競技人口を確保しなければならなくなってきている。それが、本当にいいことかどうかは別として、世の中はすでにそういう方向に動いている。
今、日本人が一番知っているスポーツ選手は、アメリカ大リーグで活躍する野球の大谷翔平選手だと思う。それに続くのは、バスケットボールの八村塁選手あたりか。以前に比べるとサッカー選手は減ってきているかもしれない。錦織圭選手や大坂なおみ選手の活躍が注目されてきたテニスも、最近は露出が減っている。そんななか、旬なところで、北口選手がそこに入ってきている。
これから育成年代の競技人口を増やしていこうとするのなら、社会に影響力のある競技であるかどうかによって変わってくるのではないか。そこは、メディアに取り上げられるスター選手がどのくらいいるか、あるいは高額な報酬が見込まれるような夢の対象となる競技であるかにかかってくると思う。
陸上競技の場合は、競技の特性上、世界の舞台で選手が活躍することが非常に大きな鍵になってくると考える。北口選手のような新聞の一面やネットやニュース番組のトップを飾るようなパフォーマンスと影響力を持つ競技者を出していけるか。それを果たすためには、将来的に国際大会でしっかりと活躍していけるような、そういった育成段階の強化をしていかなければならない。
その道筋もあるうえで、国内で全中やインターハイが開催されれば、多くの育成年代が、中学日本一、高校日本一を目指しながらも、今までとは様相が変わっていくのではないかと思う。これからは、暑熱対策も含めて大きく様変わりしていくはずだが、ぜひ、現場で指導に当たる方々の理解をいただきたい。
私たち育成段階の指導者が目指すべきは、育成段階の競技力向上が、日本記録の向上にまずはつながることが大きいかなと考えている。現在、各世代のトップのレベルが上がれば上がるほど、皆さんが思っている以上にドロップアウトする競技者が増えてきている。例えば、女子の中学生が100mで11秒5を切ったとする。そのこと自体は本当に素晴しいこと。ただ、一方で、25歳になったときに11秒2で走るポテンシャルを持った高身長の選手が、成長期にある中学生の段階ではまだ身体が動かせなくてベスト記録が12秒3だったとしたら、その選手は、自分が将来、スプリンターとして活躍する姿を思い描くのは難しいのではないかと思う。そういった選手も含めて、1人でも多くのタレントを引き上げ、世界に通じていくような育成年代の強化を構築していきたい。強化育成部は、そういう考えで取り組んでいる。今回の合宿における各プログラムも、この点を踏まえながら見学していただければ、私たちの考え方や目指していることを、より深く理解していただけると思う。
※本稿は、1月13日のU20オリンピック育成競技者研修合宿に先立ち、杉井將彦シニアディレクターが、指導者に向けて行った育成年代の強化における課題と強化育成部の方針説明をまとめたものです。文章で読んだときに、より意図が明確に伝わることを目的とした編集を加えています。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
▼ダイヤモンドアスリート 特設サイト
https://www.jaaf.or.jp/diamond/
▼陸上日本代表特設サイト
https://www.jaaf.or.jp/teamjapan/
▼チーム JAPAN
https://www.jaaf.or.jp/athletes/?event=1
▼競技者育成指針
https://www.jaaf.or.jp/development/model