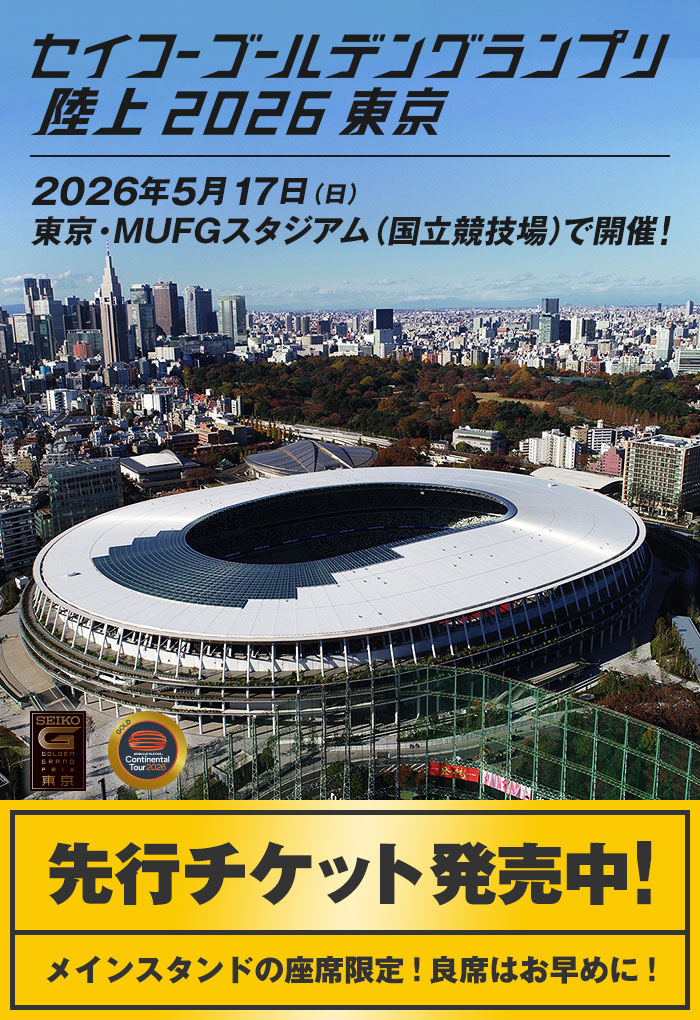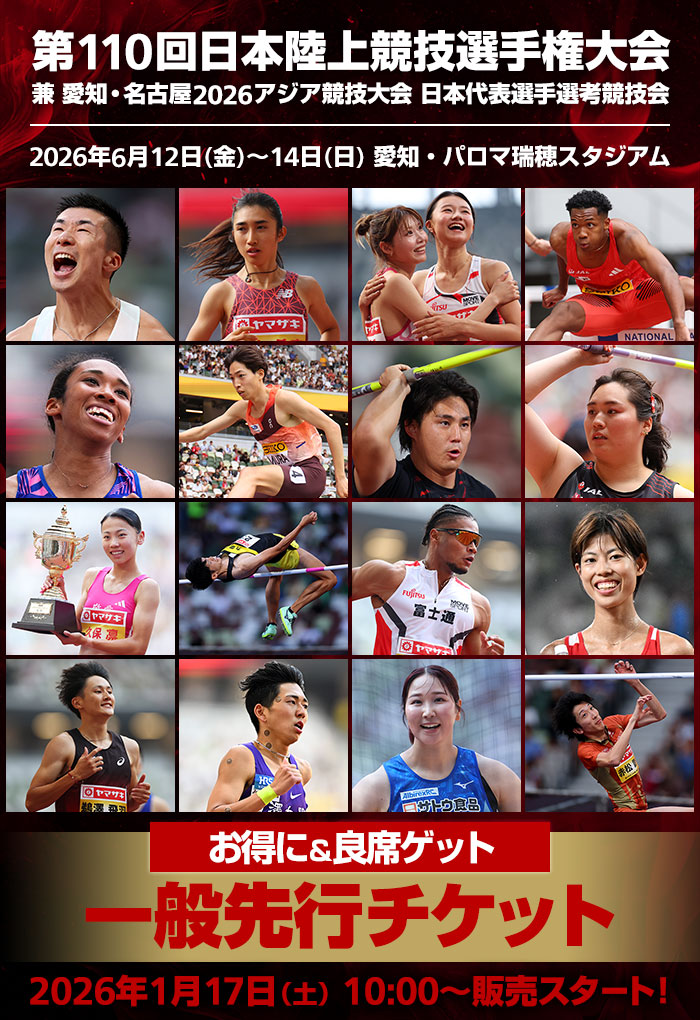日本陸連では、すべての人が、スポーツを通じて心も身体も満たされたウェルビーイング(Well-being)な状態で陸上競技に関わっていけるようにすることを目指し、アスリートの健康を守るための知識や学びを深めていく活動を進めています。
3月20日には、指導者を対象としたセミナー『ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」』を、オンライン形式で開催しました。
今回のセミナーは、一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業の協力のもと、日本陸連および日本スポーツ協会公認スポーツ指導者を中心とする陸上の現場で指導に関わる人々を対象に開かれました。セミナーは2部構成での展開で、第1部では「身体的Well-beingの視点から」、また、第2部では「心理的Well-beingの視点から」、それぞれ講義とディスカッションを行っていくプログラムです。
冒頭で主催者を代表して、日本陸連においてウェルビーイング実現に向けた取り組みを推進している有森裕子副会長が挨拶に立ちました。有森副会長は、日本陸連がウェルビーイングをスポーツにおいて非常に重要な事柄と捉えて、正しい知識や情報を発信すべく今年からセミナーを始めていることや、その第1回として、1月の全国都道府県女子駅伝の際に、『プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」』というタイトルで実施( https://www.jaaf.or.jp/news/article/21363/ )したことを説明。「こうしたセミナーは、今までだと1回で終わることが多かったが、年間を通して多くの指導者、選手、保護者の皆さまに届けていくことで、皆さまにかかわっていただく、そして考えていただく、そして変えていただく、そういった機会をつくっていこうとしている」と述べました。そして、「未来を担うアスリートを、どうやって羽ばたかせて、育てていくか――それが未来の日本のスポーツを支えていくものになる」と訴え、「ウェルビーイングといっても、まだ(概念が)ぼんやりとしていて、“具体的に、何を、どう考えていけばいいのか”と迷ったり、“現場でなかなか取り入れられない”と悩んだりしている指導者も多いはず。今日、この時間を通じて、いろいろな情報に触れ、それらを現場に持ち帰り、素晴らしいアスリートとともに、指導に当たる皆さんも、スポーツを通して健康になっていただきたい」と受講者に呼びかけ、セミナーをスタートさせました。
【第1部:身体的Well-beingの視点から】
<講義>
第1部の講義では、ウェルビーイングについて、身体的な側面にスポットを当て、生理学、医学、栄養学の3つの視点から、それぞれのスペシャリストがレクチャー、そのうえで受講者から寄せられた質問に答えました。最初に登壇したのは、日本陸連科学委員会委員で、日本体育大学教授の須永美歌子氏。「ウェルビーイングに関する基礎講義」「REDsの定義」「月経周期とコンディション」について話を進めていきました。須永氏は、まず「個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること」というウェルビーイングの定義を示したうえで、アスリートの健康を脅かす深刻な問題として国際的にも注視・対策が進められている「スポーツにおける相対的エネルギー不足:REDs(レッズ)」について詳しく解説。REDsに陥っていないかをチェックする方法、REDsに陥らないために留意すること、このREDsから若いアスリートを守るために進められている国際的な取り組みや考え方などを具体的に示していきました。また、女性アスリートの健康を守るうえで重要になってくるとして、月経周期とコンディションに関する話題を取り上げ、正常な月経や月経周期によって生じる体調の変化、月経前症候群などの基礎的な知識や対処の方法なども紹介されました。
続いて、日本陸連医事委員会委員でアイオワ大学准教授の塚原由佳氏が講義を行いました。塚原氏が解説したのは、「鉄不足と貧血」「陸上競技指導者のREDs認識度と栄養指導の実態」の2つ。「鉄不足と貧血」については、鉄不足が起きる原因や鉄不足の基準、どういう状態を貧血と呼ぶのかを説明するとともに、貧血が競技パフォーマンスにどう影響するかも数値を示しながら解説しました。また、日本陸連がガイドラインを設けて防止に取り組んでいる不適切な鉄分注射について、その危険性を改めて提示したうえで、望ましい鉄不足や貧血の防止策や、陥った場合の治療法を紹介。続いて行われた「陸上競技指導者のREDs認識度と栄養指導の実態」の話題では、女性アスリートの三主徴やREDsに関する認識度や、アスリートへの食事制限やサプリメント摂取する指導の有無、アスリートが使用するサプリメントの把握などを調べた調査結果を報告し、REDsの認識度や栄養指導に、課題を持つ指導者もいることが示されました。
第1部の最後に「アスリートの健康を守る栄養補給のポイント」をテーマに講義を行ったのは、日本陸連医事委員会スポーツ栄養部長の浜野純氏です。浜野氏は、「アスリートの健康を守るためには、食事をきちんと考え、栄養補給することが必須」と述べ、アスリートが健康を守るために知っておくべきこととして、①エネルギー不足をどう回避するか、②エネルギー不足によって起こしやすい陸上競技選手の問題点、の2項目について解説していきました。まず、①においては、エネルギー不足が疑われる症状や食習慣によるセルフチェック法、適切な糖質摂取量の算出の仕方や具体的な摂取例、実際に摂りたいごはんの摂取量などが示されたうえで、アスリートにとって大切なエネルギー源は糖質であり、ごはんを主体に毎回の主食+補食でエネルギーを確保すべきであると呼びかけました。また、②については、問題を回避するために留意したいことや、貧血や疲労骨折などを防ぐために意識して摂取したい栄養素やその摂り方などを紹介。特に不足しがちな鉄・カルシウムは意識して摂ることを勧めました。
<栄養に関するディスカッション>

講義に続いて行われたのは、栄養に関するディスカッションです。ここでは、特別ゲストとして招かれていた中村明彦氏が登壇しました。中村氏は、男子十種競技で日本歴代2位となる8180点の自己記録を持ち、長年トップシーンで活躍してきた元アスリート。オリンピックには400mハードルで出場した2012年ロンドン大会に加えて、2016年リオ大会には十種競技で出場。世界選手権には十種競技で2015年北京、2017年ロンドンと、2大会連続出場を果たすなどの実績を残しました。2023年シーズンで競技生活に区切りをつけてからは、指導者の道へ。現在は、スズキアスリートクラブ一般種目のヘッドコーチを務めるほか、母校の中京大学陸上競技部のコーチとして混成競技を担当。また、日本陸連強化委員会においても強化育成部のスタッフとして、アスリートの育成に尽力しています。
このディスカッションでは、浜野氏が司会進行役を務め、
・子どものころ、どんな食事をすることが多かったのか。親からは、食事についてどのような教えを受けたか?
・高校生となり本格的な陸上競技のトレーニングをするなかで、食事の回数や内容に変化はあったか?
・大学時代に食事を自身でコントロールするなかで、気をつけていたことや実践していたことは?
・トップアスリートとして競技力を高めるために、また、ケガをしないために、食事で必要だと感じていたことや考え方は?
・指導者として、食事について選手に話す際に注意していること、実際に話していることは?
と、年代ごとに区切って、そのときどきにおける中村氏の「食への向き合い方」を質問。そこから浮かび上がってきた「ごはんをしっかり食べる」「補食の利用の仕方」「自炊時に心掛けていたこと」「栄養の上手なバランスのとり方」などのポイントに対して、浜野氏が解説を重ねる形で、栄養について考えるときに重要となる事柄を受講者に示していきました。
最後に「小・中学生を対象に指導している方に、何かアドバイスを」という浜野氏からのリクエストに対して、中村氏は、「楽しんで競技をすること、スポーツをすること、記録を高めていくことに一番重要になってくるのは練習。しかし、食事と睡眠をとらなければ、そもそもその練習はできない。そのため“食事と睡眠を抜きにしてスポーツを考えたらダメだよ”ということは、ことあるごとに伝えるようにしている」と回答。健康に競技活動を続けるうえで、「食」がいかに重要であるかを改めて理解できるディスカッションとなりました。
【第2部:心理的Well-beingの視点から】
<講義>
第2部は、ウェルビーイングを、メンタルの側面からみていく講義が行われました。講師を務めたのは、スポーツ心理学者で博士(システムデザイン・マネジメント学)の田中ウルヴェ京氏。シンクロナイズドスイミング(現アーティスティックスイミング)のトップアスリートとして活躍し、1988年ソウルオリンピックにおけるシンクロナイズドスイミングデュエットで銅メダルを獲得した人物です。競技引退後は、日本、フランス、アメリカの3カ国のオリンピック代表チームコーチや国際水泳連盟のアスリート委員を務めて、スポーツ競技現場を経験。また、学術面では、アメリカの大学院でスポーツマネジメントとスポーツ心理学を学び修士を修了したのちに、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科において博士号を取得しています。現在は、慶應義塾大学特任准教授、国際オリンピック委員会(IOC)マーケティング委員、日本スポーツ心理学会認定スポーツメンタルトレーニング上級指導士、IOC認定アスリートキャリアトレーナーなど、さまざまな肩書きを持って、幅広い分野で活躍。トップアスリートはじめアーティスト、経営者、研究者などトップパフォーマーの心理コンサルティングに携わるほか、報道番組のコメンテーター、ラジオ番組のパーソナリティ、数々の著書や訳書の出版などでもよく知られている人物です。今回の講義では、『Well-beingの考え方と実践~アスリートらが実践する心の整え方を事例に~』と題して、「心のウェルビーイングとは何か」を説明したうえで、「心のウェルビーイングが高いとはどういう状態であるか」「実際にどのように考え、どう高めていけばよいのか」を、学術的な背景を交えながら紐解いていきました。さらに、指導に当たるアスリートのウェルビーイングの実現を考えていくのと同時に、「指導者自身も、指導者としての自らのウェルビーイングを考え、実現していくことが大切」と述べ、講義を締めくくりました。
<メンタルに関するディスカッション>
続いて行われたのは、メンタルに関するディスカッションです。ここでは、メインスピーカーとして田中ウルヴェ氏、ゲストスピーカーとして中村氏が登壇。日本陸連医事委員会副委員長で北里大学メディカルセンター精神科副部長の山本宏明氏がファシリテーターを務めて行われました。精神科医である山本氏は、同センターにおいてアスリートのメンタルヘルス支援に携わっており、医学の観点からの「心のウェルビーイング」に詳しいスペシャリストです。山本氏は、まず、中村氏に、田中ウルヴェ氏の講義を聞いての感想を質問。中村氏は、印象に残った箇所として「心戦技体のなかでの心の位置」の説明を挙げ、実力発揮をしていくうえの基盤になるべき心(悩み考える力)について、十種競技という種目の特性を踏まえつつ「自分は、心の部分に対しては、スポットライトを当てられていたのではないかと思った」とアスリート時代を振り返りました。一方で、競技者から指導者へとカテゴリーや属性が変わったなかで、「現在、“自分”というものが置かれた状況によって変わっている状態で、まるで“自分”を工事しているような感覚」と逡巡している思いを明かす場面も。競技者として遭遇したこと、競技者からのキャリアチェンジの過程において遭遇していること、さらには指導者として遭遇していることやこれからどうなっていきたいかなどについて、幅広く意見交換していく形となりました。そのなかで、キーワードとして挙がったのが、「受援力(じゅえんりょく:困ったときに他者に助けを求めることができる力)」「自主性と主体性の違い」といった言葉。受講者たちは、心のウェルビーイングを高めていくうえで受援力が有用であることを認識するとともに、選手を育てていく際には、自発的に取り組む(自主性)だけでなく、「なぜ、どうして」を自ら考えて(主体性)取り組んでいけるような指導が求められることを理解しました。

終盤では、有森副会長も参加。「競技成績の追求とウェルビーイング(健康)の追求について」、オリンピック女子マラソン2大会連続メダリストとして活躍した有森副会長自身の経験や考え方、マラソンの競技特性なども踏まえながらの貴重な意見交換が展開。最後に、事前に寄せられていた「不安や緊張から、思い通りの練習やパフォーマンスが発揮できない場面に遭遇したとき、どんな声がけや寄り添い方をすればよいか?」「ハードルや高跳びを怖がる選手にはどのような指導方法が最適か?」という質問への回答が行われ、ディスカッションが終了しました。
文:児玉育美(JAAFメディアチーム)
関連ニュース
-
2025.07.01(火)
【アスリート委員会】が迷惑撮影に対する声明を発表しました!
委員会 -
2025.03.07(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#5
その他 -
2025.02.28(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#4
その他 -
2025.02.21(金)
【Well-being指導者向けセミナー 受講者募集】『ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」』
その他 -
2025.02.21(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#3
その他