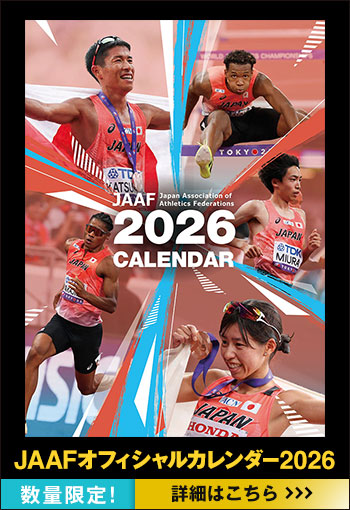「人の多様性を認め、それぞれの自分らしさを活かすこと」を意味するダイバーシティ&インクルージョンを重視する日本陸連では、競技団体としてのダイバーシティ&インクルージョンの実現を期して、関係者に向けた研修活動を展開しています。2月18日には、今年度2回目の研修を開催。研修は、1月31日に行われた1回目と同様に、日本陸連内に設置した会場での対面開催とオンライン視聴のハイブリッド形式で実施され、日本陸連評議員、役員(理事・監事)、事務局職員のほか、加盟団体や協力団体関係者等が全国各地から参加しました。
今回は「女子競技の参加資格に関するWA規定を考える」をテーマに、運動生理学、トレーニング科学研究の第一人者で、日本陸連評議員の伊藤静夫さんを講師に迎えて行われました。伊藤さんは、日本体育協会(現日本スポーツ協会)スポーツ科学研究室で、陸上長距離やスピードスケートなどの測定研究に取り組み、数多くのエビデンスを残してきた人物。室長として長く研究室を率いた同協会退職後は、一般財団法人東京マラソン財団の理事長として活躍(現在は顧問)。また、日本陸連においては、科学委員会や普及育成委員会に名を連ね、科学的な見地に基づくアプローチで長きにわたって連盟の普及事業や指導者養成事業を支えてきたことで知られています。

スポーツ、なかでも競技スポーツでの「女子カテゴリーにおける公平性の担保」は、以前から大きな課題でしたが、ダイバーシティ&インクルージョンの考え方が世界的に浸透していくなかで、より一段と難しさを増すことになってきています。本研修においては、「多様な性のあり方」についてはすでに昨年1月、來田享子日本陸連常務理事がスポーツとジェンダーに関するスペシャリストの立場で、基本的な知識のレクチャーに加えて、陸上を含むスポーツの場面で課題になっている点などを解説しています( https://www.jaaf.or.jp/news/article/19368/ )が、今回は、そこからさらに踏み込んで、ワールドアスレティックス(WA:世界陸連)が規定している女子競技の参加資格に焦点が絞られ、私たちが身を置く陸上界での状況について考えを深める機会となりました。
実は、この研修が開かれた1週前の2月10日に、WAは、女子競技の参加資格に関する規定を変更する方針を発表したばかり。このため研修は「新たな改定案に大幅な変更が見込まれているが、正式な決定・発表には至っていない」という難しいタイミングでの実施となりました。
「女子競技の参加資格について、今までどういう経緯があったか、これからどうしていくかについて、私が知る限りのところをお話しし、日本陸連としてどのように進めていったらよいかを考えてみたい」と伊藤さん。2023年3月にWAが示した現行の規定を、歴史的な経緯を踏まえつつ紹介するとともに、その判断基準にテストステロン値(男性ホルモン)が用いられることになった背景や、その妥当性、実際に問題になっている点。国際オリンピック委員会(IOC)の対応などを解説したうえで、2025年改訂に向けて協議が進められている内容を紹介。そうしたなかにあって、日本陸連としては、どのような点に留意して取り組みを進めていく必要があるのかを述べていきました。
===================
<現行のWA規定に至るまで>
WAが現行の規定(2023年3月改訂分)を設けるまでの流れを大まかにまとめると、次のようになります。
・ 1968年:スポーツ界では、1968年グルノーブル五輪から男女の判断基準として染色体検査を実施。
・ 2000年:染色体検査は倫理的・人権的な理由によりシドニー五輪から廃止に。
・ 2011年:男性ホルモンであるテストステロンの値で規制することになった。国際陸連(現WA)はテストステロン値を採用した理由を公表していないが、女子800mのキャスター・セメンヤ(南アフリカ)が2009年ベルリン世界選手権を圧倒的な力で制したあと性別を疑われ、性分化疾患(DSD:非定型の性分化をしている状態)の影響でテストステロン値が通常より高いと推測されたことに加えて当時、テストステロンや成長ホルモンなど人の体内に存在する天然型生理活性物質によるドーピングへの防止対策が重要課題となり、アンチドーピングの機運が高まっていたことなどが背景にあるといわれている。
・ 2018年:規定の改訂が行われ、適用範囲は全種目から一部種目(400m~1マイル)となったが、テストステロンの上限値が厳格化(10mmol/Lから5mmol/Lへ)された。
・ 2021年:IOCは、守られるべき10項目のフレームワークを示したうえで「トランスジェンダーや身体の性の多様性に対応する参加基準の設定は国際競技団体に委ねる」とする方針を発表。
・ 2023年:WA規定を改訂。テストステロン上限値を2.5mmol/Lに厳格化、適用範囲を全種目としたほか、DSDとトランスジェンダー(性自認が、出生時の生物学的性別と異なること)で規定を分けた(DSD選手は最低24カ月間、テストステロン値を規定以下にすることを条件に参加を認める。トランスジェンダー選手は男性の思春期を経たあとで女性となった場合は女子競技の参加を認めない)。また、規定の対象者はエリートアスリート(WAワールドランキング競技会参加者)に限定し、国内競技については各国陸連で別途規定することなどが盛り込まれた。
===================
性別の区分について、伊藤さんは、こうした経過を辿ってきた点を述べつつ、今までに発表されたさまざまな研究結果などを挙げ、内因性・外因性を問わずテストステロン値が高いことは競技力に有利に働くとする見解もあれば、トップアスリートになるとテストステロン値で男女を線引きすることが非常に困難であることが示されたデータがあることも紹介。明確に区分できる状況に至っていない実情が示されました。さらに、「もう一つ、私が非常に気になるのは、DSDの女性アスリートに対して、あなたはテストステロン値が高いからアンフェアだと軽々しく言っていいのかということ。アンチドーピングの立場から考えると、DSDはドーピングではない。また、トレーニングやコンディショニングよって上げていく(内因性の)テストステロン値と、薬を摂取してテストステロンを高める外因性のドーピングとは明確に区別すべき。このあたりが混同されているというのが偽らざる感想」と述べ、また人権侵害となり得る問題点についても言及しました。
さらに、2011年以降、当時の国際陸連とともにテストステロン値でコントロールする取り組みを進めきたIOCが、2021年に従来の方向性とは異なるフレームワークを発表したことについても触れ、そのうちの一つである「優位性に関する推定を行わないこと」の項目については、「例えば、DSDだから、あるいはトランスジェンダーだから優位というような単純な推定をしてはならないという考え方」と説明。このIOCのシフトチェンジについて、「WAの今の方針とは少し違ってきている。そうした状況にあることを、私たちは理解しておく必要がある」と述べました。
そして、本年2月から改訂に向けて検討が進められている新たなWA規定の話題へ。伊藤さんは、協議に入る時点で検討事項として公表された、①女性カテゴリーの設置理念を明確にする、②現行の参加資格規定を設置理念に基づき改訂する、③DSD規定とトランスジェンダー規定を統合する、④女子カテゴリーに出場する競技者全員に事前検査を実施する、⑤ジェンダー多様性競技者への支援など、問題解決に向け前向きに取り組む、の5項目を挙げ、それぞれを説明。改訂される新たな規定では、③④の判断の基準としてのテストステロンに代わって染色体検査の導入が想定されていることなどを示しました。
また、⑤の項目については、「女子競技の参加資格規定は、エリート競技者が対象となるが、陸上競技そのものはエリートだけがやるわけではないことをWAも十分に認識したうえでの見解」であると示唆。そのうえで、日本陸連が進めていくべき取り組みの方向性として、「WAが示すエリート競技者の層については、まずはフェアネスを確保して進めていくが、それと並行して、一般の人々に対してはインクルージョンの姿勢で対応していくことが求められる」とコメント。「これは口で言うのは簡単だが、実際にどうしていけばいいのかは、本当に難しいことで、みんなで知恵を絞っていかなければならない。しかし、それが我々の目指すところのアスレティックファミリーの拡大であり、ウェルネス陸上の実現につながっていくものだと考えている」と講義を締めくくりました。
伊藤さんの講義のあとには、日本陸連でダイバーシティ&インクルージョンの推進役を担う來田常務理事が進行役を務めて質疑応答が行われました。
「データがはっきりせず、考えれば考えるほど難しいなかで、なんらかの答えを、探しながらでも出していかないと、日本国内で競技ができないDSDやトランスジェンダーの人たちが出てくるということで、今、私たち組織が果たさなければならない役目は非常に重要だということを改めて感じた」という感想を述べた來田常務理事が、ほかの競技団体の対応事例を質問すると、「水泳やボクシングなど、染色体検査を実施する団体もあって、競技団体によって大きく異なっていることがわかる」と伊藤さん。また、対応が異なる状況となった要因にIOCの対応を挙げ、「2021年にIOCがフレームワークは出したけれど、詳細・具体例は各競技団体に委ねた 」ことを示した 。これに対して、「それぞれに競技特性があるということで各団体に任せたわけだが、 IOCとしては、オリンピックムーブメントの精神として人権を無視することはできないので、その立場に立っての対応だと思うが、それにより差異が生じてしまったことは事実であろう 」と來田常務理事も答えました。

続いて、來田常務理事は、1月末にワールドトライアスロンがリリースしたばかりの同団体におけるトランスジェンダーアスリートのための資格規定の改訂内容を紹介しました。ワールドトライアスロンは、オリンピックや世界選手権等のエリート競技では男子・女子のカテゴリーに分けるが、それ以外について、
・エイジグループオープンカテゴリーと名づけて男子競技を廃止し、女子競技を残す、
・男子競技でなくなった年齢別オープンカテゴリーは、男性であろうが女性であろうがトランスジェンダーであろうが誰でも、医学的・法的基準なく参加できる、
・女子カテゴリーは、生まれたときに割り当てられた性別が女性であり、生物学的に女性である人の競技の権利(フェアネス)を守るために残す、
ことになった点を説明。さらに、「ここで問題になるのは、オープンカテゴリーで競技をするトランスジェンダーのアスリートが、エリート競技にどう参加していけるのかということ。この場合は、特にトランスジェンダー女性のケースが問題になる」として、
・該当者は、まずは性自認を宣言し、4年間の移行期間を設ける、
・1~3年目は年齢別オープンカテゴリーに出場。その間、テストステロン値は2.5mmol/Lに抑える
・最後の1年は女子のエリート競技に参加できる、
と、4年の移行期間を設けて該当選手がフェアな存在であることを自他ともに認めつつ、科学的に検証しながらエリート女子に入っていける措置がとられたことを紹介しました。
これに対して、伊藤さんは「ただ、やはりテストステロンが判断基準になっている」と指摘。今回、協議されているWAの改訂において、テストステロンを基準にするのをやめる方向に進んでいるのは、上限値を2.5 mmol/Lにしても線引きが微妙であるうえに、該当選手が2.5mmol/Lに抑えるためには健康であるにも関わらずホルモン療法が必要で倫理的に問題であること。さらに、データをとり続けていくなかで、ホルモン療法で数値を抑えても、最終的に競技力は変わらないという結果が出てきていることが背景になっている点を披露し、來田常務理事も、すでにそういうデータを発表している研究があること、個体差がある報告がなされた論文もあることを示しました。
これらを踏まえて、來田常務理事は、「この件は、まだまだ結論が出なくて、非常に難しい問題。現場で、実際にどういうふうに参加してもらえばいいのだろうと考えている方もたくさんいると思うので、この研修も含めて、これからもさまざまな場で、関心を持って、いろいろな対話をしていければと思う」と総括。「誰もが“陸上競技、好きだよね”と思える世界をつくっていくことが私たちの役目。今日は、そのためにみんなで一緒に知恵を絞っていきたいという思いを強くする機会となった」と、講師の伊藤さんに感謝を伝え、研修を終えました。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
今回は「女子競技の参加資格に関するWA規定を考える」をテーマに、運動生理学、トレーニング科学研究の第一人者で、日本陸連評議員の伊藤静夫さんを講師に迎えて行われました。伊藤さんは、日本体育協会(現日本スポーツ協会)スポーツ科学研究室で、陸上長距離やスピードスケートなどの測定研究に取り組み、数多くのエビデンスを残してきた人物。室長として長く研究室を率いた同協会退職後は、一般財団法人東京マラソン財団の理事長として活躍(現在は顧問)。また、日本陸連においては、科学委員会や普及育成委員会に名を連ね、科学的な見地に基づくアプローチで長きにわたって連盟の普及事業や指導者養成事業を支えてきたことで知られています。

スポーツ、なかでも競技スポーツでの「女子カテゴリーにおける公平性の担保」は、以前から大きな課題でしたが、ダイバーシティ&インクルージョンの考え方が世界的に浸透していくなかで、より一段と難しさを増すことになってきています。本研修においては、「多様な性のあり方」についてはすでに昨年1月、來田享子日本陸連常務理事がスポーツとジェンダーに関するスペシャリストの立場で、基本的な知識のレクチャーに加えて、陸上を含むスポーツの場面で課題になっている点などを解説しています( https://www.jaaf.or.jp/news/article/19368/ )が、今回は、そこからさらに踏み込んで、ワールドアスレティックス(WA:世界陸連)が規定している女子競技の参加資格に焦点が絞られ、私たちが身を置く陸上界での状況について考えを深める機会となりました。
実は、この研修が開かれた1週前の2月10日に、WAは、女子競技の参加資格に関する規定を変更する方針を発表したばかり。このため研修は「新たな改定案に大幅な変更が見込まれているが、正式な決定・発表には至っていない」という難しいタイミングでの実施となりました。
「女子競技の参加資格について、今までどういう経緯があったか、これからどうしていくかについて、私が知る限りのところをお話しし、日本陸連としてどのように進めていったらよいかを考えてみたい」と伊藤さん。2023年3月にWAが示した現行の規定を、歴史的な経緯を踏まえつつ紹介するとともに、その判断基準にテストステロン値(男性ホルモン)が用いられることになった背景や、その妥当性、実際に問題になっている点。国際オリンピック委員会(IOC)の対応などを解説したうえで、2025年改訂に向けて協議が進められている内容を紹介。そうしたなかにあって、日本陸連としては、どのような点に留意して取り組みを進めていく必要があるのかを述べていきました。
===================
<現行のWA規定に至るまで>
WAが現行の規定(2023年3月改訂分)を設けるまでの流れを大まかにまとめると、次のようになります。
・ 1968年:スポーツ界では、1968年グルノーブル五輪から男女の判断基準として染色体検査を実施。
・ 2000年:染色体検査は倫理的・人権的な理由によりシドニー五輪から廃止に。
・ 2011年:男性ホルモンであるテストステロンの値で規制することになった。国際陸連(現WA)はテストステロン値を採用した理由を公表していないが、女子800mのキャスター・セメンヤ(南アフリカ)が2009年ベルリン世界選手権を圧倒的な力で制したあと性別を疑われ、性分化疾患(DSD:非定型の性分化をしている状態)の影響でテストステロン値が通常より高いと推測されたことに加えて当時、テストステロンや成長ホルモンなど人の体内に存在する天然型生理活性物質によるドーピングへの防止対策が重要課題となり、アンチドーピングの機運が高まっていたことなどが背景にあるといわれている。
・ 2018年:規定の改訂が行われ、適用範囲は全種目から一部種目(400m~1マイル)となったが、テストステロンの上限値が厳格化(10mmol/Lから5mmol/Lへ)された。
・ 2021年:IOCは、守られるべき10項目のフレームワークを示したうえで「トランスジェンダーや身体の性の多様性に対応する参加基準の設定は国際競技団体に委ねる」とする方針を発表。
・ 2023年:WA規定を改訂。テストステロン上限値を2.5mmol/Lに厳格化、適用範囲を全種目としたほか、DSDとトランスジェンダー(性自認が、出生時の生物学的性別と異なること)で規定を分けた(DSD選手は最低24カ月間、テストステロン値を規定以下にすることを条件に参加を認める。トランスジェンダー選手は男性の思春期を経たあとで女性となった場合は女子競技の参加を認めない)。また、規定の対象者はエリートアスリート(WAワールドランキング競技会参加者)に限定し、国内競技については各国陸連で別途規定することなどが盛り込まれた。
===================
性別の区分について、伊藤さんは、こうした経過を辿ってきた点を述べつつ、今までに発表されたさまざまな研究結果などを挙げ、内因性・外因性を問わずテストステロン値が高いことは競技力に有利に働くとする見解もあれば、トップアスリートになるとテストステロン値で男女を線引きすることが非常に困難であることが示されたデータがあることも紹介。明確に区分できる状況に至っていない実情が示されました。さらに、「もう一つ、私が非常に気になるのは、DSDの女性アスリートに対して、あなたはテストステロン値が高いからアンフェアだと軽々しく言っていいのかということ。アンチドーピングの立場から考えると、DSDはドーピングではない。また、トレーニングやコンディショニングよって上げていく(内因性の)テストステロン値と、薬を摂取してテストステロンを高める外因性のドーピングとは明確に区別すべき。このあたりが混同されているというのが偽らざる感想」と述べ、また人権侵害となり得る問題点についても言及しました。
さらに、2011年以降、当時の国際陸連とともにテストステロン値でコントロールする取り組みを進めきたIOCが、2021年に従来の方向性とは異なるフレームワークを発表したことについても触れ、そのうちの一つである「優位性に関する推定を行わないこと」の項目については、「例えば、DSDだから、あるいはトランスジェンダーだから優位というような単純な推定をしてはならないという考え方」と説明。このIOCのシフトチェンジについて、「WAの今の方針とは少し違ってきている。そうした状況にあることを、私たちは理解しておく必要がある」と述べました。
そして、本年2月から改訂に向けて検討が進められている新たなWA規定の話題へ。伊藤さんは、協議に入る時点で検討事項として公表された、①女性カテゴリーの設置理念を明確にする、②現行の参加資格規定を設置理念に基づき改訂する、③DSD規定とトランスジェンダー規定を統合する、④女子カテゴリーに出場する競技者全員に事前検査を実施する、⑤ジェンダー多様性競技者への支援など、問題解決に向け前向きに取り組む、の5項目を挙げ、それぞれを説明。改訂される新たな規定では、③④の判断の基準としてのテストステロンに代わって染色体検査の導入が想定されていることなどを示しました。
また、⑤の項目については、「女子競技の参加資格規定は、エリート競技者が対象となるが、陸上競技そのものはエリートだけがやるわけではないことをWAも十分に認識したうえでの見解」であると示唆。そのうえで、日本陸連が進めていくべき取り組みの方向性として、「WAが示すエリート競技者の層については、まずはフェアネスを確保して進めていくが、それと並行して、一般の人々に対してはインクルージョンの姿勢で対応していくことが求められる」とコメント。「これは口で言うのは簡単だが、実際にどうしていけばいいのかは、本当に難しいことで、みんなで知恵を絞っていかなければならない。しかし、それが我々の目指すところのアスレティックファミリーの拡大であり、ウェルネス陸上の実現につながっていくものだと考えている」と講義を締めくくりました。
伊藤さんの講義のあとには、日本陸連でダイバーシティ&インクルージョンの推進役を担う來田常務理事が進行役を務めて質疑応答が行われました。
「データがはっきりせず、考えれば考えるほど難しいなかで、なんらかの答えを、探しながらでも出していかないと、日本国内で競技ができないDSDやトランスジェンダーの人たちが出てくるということで、今、私たち組織が果たさなければならない役目は非常に重要だということを改めて感じた」という感想を述べた來田常務理事が、ほかの競技団体の対応事例を質問すると、「水泳やボクシングなど、染色体検査を実施する団体もあって、競技団体によって大きく異なっていることがわかる」と伊藤さん。また、対応が異なる状況となった要因にIOCの対応を挙げ、「2021年にIOCがフレームワークは出したけれど、詳細・具体例は各競技団体に委ねた 」ことを示した 。これに対して、「それぞれに競技特性があるということで各団体に任せたわけだが、 IOCとしては、オリンピックムーブメントの精神として人権を無視することはできないので、その立場に立っての対応だと思うが、それにより差異が生じてしまったことは事実であろう 」と來田常務理事も答えました。

続いて、來田常務理事は、1月末にワールドトライアスロンがリリースしたばかりの同団体におけるトランスジェンダーアスリートのための資格規定の改訂内容を紹介しました。ワールドトライアスロンは、オリンピックや世界選手権等のエリート競技では男子・女子のカテゴリーに分けるが、それ以外について、
・エイジグループオープンカテゴリーと名づけて男子競技を廃止し、女子競技を残す、
・男子競技でなくなった年齢別オープンカテゴリーは、男性であろうが女性であろうがトランスジェンダーであろうが誰でも、医学的・法的基準なく参加できる、
・女子カテゴリーは、生まれたときに割り当てられた性別が女性であり、生物学的に女性である人の競技の権利(フェアネス)を守るために残す、
ことになった点を説明。さらに、「ここで問題になるのは、オープンカテゴリーで競技をするトランスジェンダーのアスリートが、エリート競技にどう参加していけるのかということ。この場合は、特にトランスジェンダー女性のケースが問題になる」として、
・該当者は、まずは性自認を宣言し、4年間の移行期間を設ける、
・1~3年目は年齢別オープンカテゴリーに出場。その間、テストステロン値は2.5mmol/Lに抑える
・最後の1年は女子のエリート競技に参加できる、
と、4年の移行期間を設けて該当選手がフェアな存在であることを自他ともに認めつつ、科学的に検証しながらエリート女子に入っていける措置がとられたことを紹介しました。
これに対して、伊藤さんは「ただ、やはりテストステロンが判断基準になっている」と指摘。今回、協議されているWAの改訂において、テストステロンを基準にするのをやめる方向に進んでいるのは、上限値を2.5 mmol/Lにしても線引きが微妙であるうえに、該当選手が2.5mmol/Lに抑えるためには健康であるにも関わらずホルモン療法が必要で倫理的に問題であること。さらに、データをとり続けていくなかで、ホルモン療法で数値を抑えても、最終的に競技力は変わらないという結果が出てきていることが背景になっている点を披露し、來田常務理事も、すでにそういうデータを発表している研究があること、個体差がある報告がなされた論文もあることを示しました。
これらを踏まえて、來田常務理事は、「この件は、まだまだ結論が出なくて、非常に難しい問題。現場で、実際にどういうふうに参加してもらえばいいのだろうと考えている方もたくさんいると思うので、この研修も含めて、これからもさまざまな場で、関心を持って、いろいろな対話をしていければと思う」と総括。「誰もが“陸上競技、好きだよね”と思える世界をつくっていくことが私たちの役目。今日は、そのためにみんなで一緒に知恵を絞っていきたいという思いを強くする機会となった」と、講師の伊藤さんに感謝を伝え、研修を終えました。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
関連ニュース
-
2025.10.29(水)
日本陸連が目指す「ダイバーシティ&インクルージョン」の推進「JAAF人権ポリシー」「JAAFインテグリティ行動指針」公表に際して――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより
その他 -
2025.09.10(水)
【レポート】8月8日開催「ダイバーシティ&インクルージョン 高校生ワークショップ」テーマ:インクルーシブな競技の在り方を考える
その他 -
2025.09.09(火)
WAが新たに設けた「女子カテゴリー」参加資格に関する規則への日本陸連の対応 ――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより
その他 -
2025.08.26(火)
ダイバーシティ&インクルージョンの推進「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」の制定について
その他 -
2025.05.27(火)
【レポート】3月11日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」コンプライアンス研修
その他