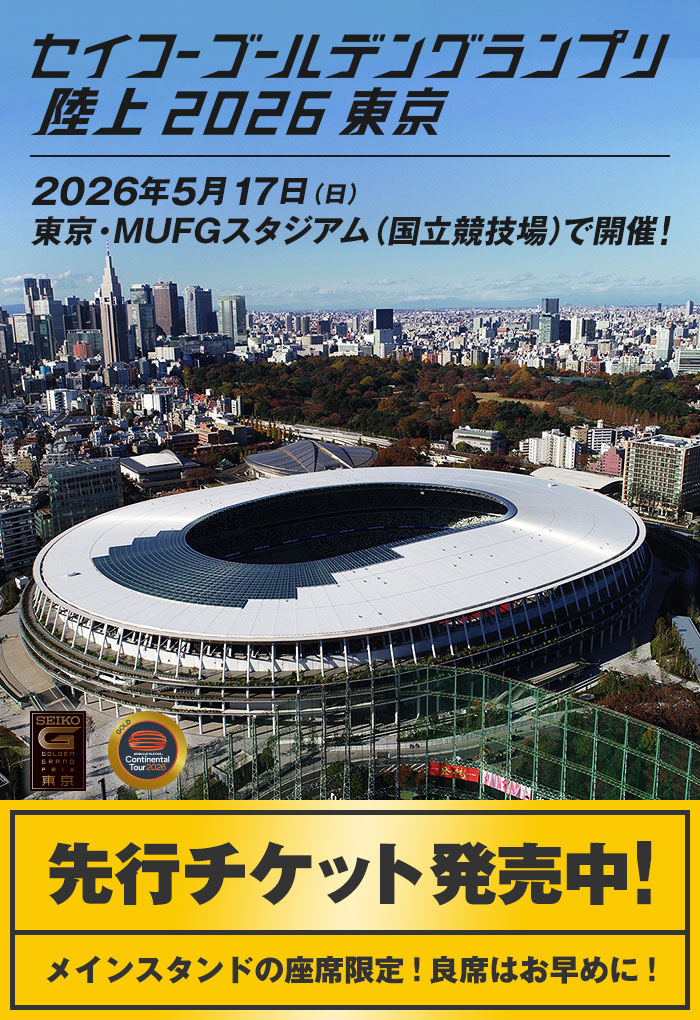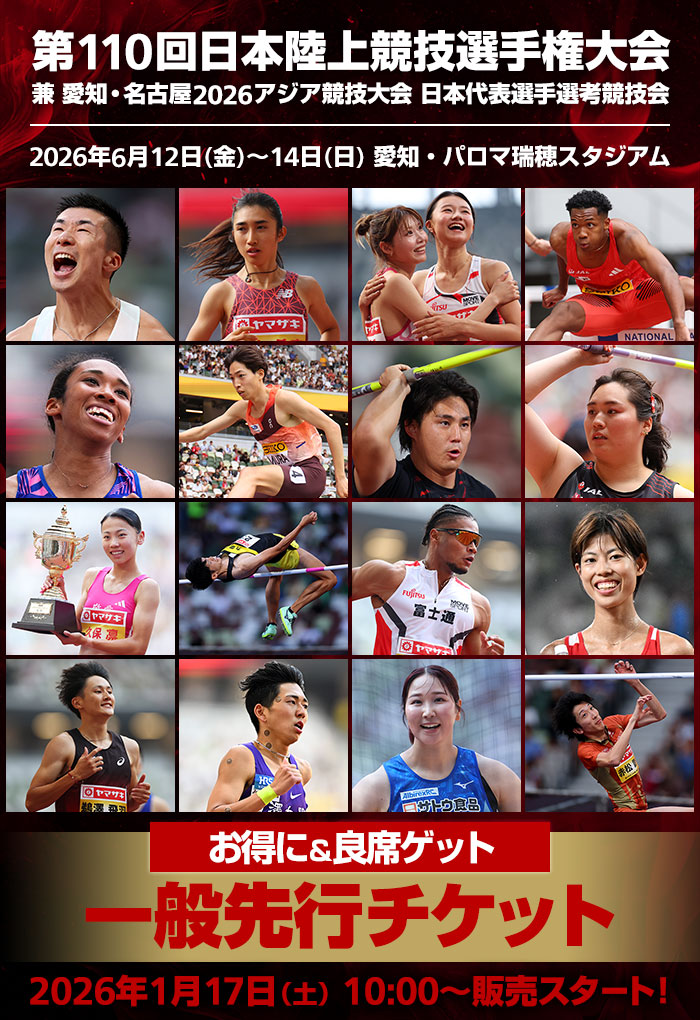活動のミッションに「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」を掲げる日本陸連では、これらを遂行していくうえで、陸上競技に関わるすべての人が、スポーツを通じて心も身体も満たされたウェルビーイング(Well-being)な状態であることを重要と捉えています。そして、この実現に向けて、リーフレットを作成・配布するなど( https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/ )、アスリートはもちろん、アスリートを支えるすべての人が、正しく競技と向き合い、アスリートの健康を守るための知識や学びを深めていけるきっかけつくりに取り組んできました。今年は、その活動の幅を、さまざまな形でさらに広げていくことを計画しています。
1月11日には、翌日に開催される全国都道府県対抗女子駅伝に併せて、一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業協力のもと、『プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」』と題したセミナーを、京都市内で開催しました。
本セミナーの内容について、全五回に分けてお届けします。
今回は、その最終回となります。
◎テーマ4:精神的健康とモチベーションの維持
「長距離選手におけるメンタルヘルスと社会的サポートの重要性」

須永:選手をサポートする側は、なんとかして選手の力になりたいと思うわけだが、具体的にどんなサポートができるのか。大会前のプレッシャーが大きいとき、スランプのとき、あるいはケガが長引いて思うような練習ができないといった局面にあるとき、どういう言葉がけや行動がいいのか。それぞれの考えをお聞きしたい。
小林:私は指導者の経験がないので、選手の立場で言わせていただく。私は、世界で11番(ベルリン世界選手権女子5000m決勝11位)というのが最高成績なのだが、それを上回る先の目標を描けなくなった瞬間に、どこに行ったらいいのか、何をすればいいのかがわからなくなってしまった。練習はして、努力もしているつもりなのだが、まるでハムスターが回し車のなかで走っているような感じになり、全然結果が伴わなくなってしまったという経験をしている。なので、そういうときに、どんな言葉がけをしてもらえていたら、うまく取り組めていたのかなということを今も考える。実際に、そうしたメンタル面のサポートを受けたことがなかったわけだが、そこは選手を支えるうえで、支柱になってくる部分だと感じている。
弘山:私が大事にしているのは、そのとき起こった事象や結果を、客観的に分析して評価して、それが良かったとか悪かったということではなく、「今日は、こういうことだから、こういうなりました」と伝えること。練習で大切なのはタイムではないので、その日の状態の身体に、「今日はこのくらいの強度の負荷をかけようね」ということを話す。それは男子学生を指導していたときも同じだった。タイムがどうこうではなく、その強度に見合ったことがきちんとできたかどうかが、正しい評価であると考えている。
タイムが速くなると嬉しいので、目指していた強度を超えてしまうことが起こりがち。しかし、それは次の練習に影響を及ぼし、結果として徐々に練習が崩れていき、うまく行かなくなることにつながってくる。「今日の練習の目的と、どのレベルの練習をすべきなのか」をはっきりさせるようにするのは、それをなくすため。なので、「もうこれ以上は上げるな、もっと抑えろ」という練習が増えていくようになると、だいたいうまく行く。「もっと頑張れ」「どうしてこんなに走れないんだ」というようなことが増えていくと、調子もモチベーションも下降していく。そのへんの強度のコントロールを指導者ができるかどうかではないかと思う。
頑張ることと、練習がうまく繋がっていくことは違う。よく「点の練習にならないように」と言われるが、「点を線にする」というのは強度のコントロールを意味する。その日の体調がどうであるかを指導者が把握できていないと、強度のコントロールはできない。選手と指導者の間で、事前にきちんと摺り合わせができていることが大事だと考えているし、それが続いていくと調子も上がってくるし、たぶん狙った試合でもきちんと走れるはず。ただ、うまく行かないときも出てくるので、そのときに客観的な分析ができるかというところだと思う。
あと、私がよく言うのは、どんな崩れた練習になっても落ち込むなということ。大学で指導していたときは、うまく行かなかったときに、「だって、今日、全力で走ったよね。努力して頑張ったよね。その結果、ダメだったということは、何か原因があるのだから、そこをちゃんと見つけていこうよ」ということよく話していた。
有森:私も指導者になったことがないので、選手だったころの自分の話になるが、私のように本当に実績のなかった選手が、ここまで来ることはできたのは指導者のおかげ。高校時代には恩師がいて、大学は監督・コーチがいなかったので自己流でやっていたが、実業団で久しぶりに指導を受けることになり、そこでの小出監督の指導によって、大きく伸びることができた。
小出監督というと、たぶん皆さんがイメージするのは、「褒めて育てる」という指導だと思う。だが、全員に対してそういうわけではなく、私も含めて、選手によってみんな違っていた。違うというのは、指導者がコントロールしていたというよりは、監督と選手がどれだけコミュニケーションをとっていたかによるものだったと思う。コミュニケーションによって監督は、その選手のいろいろなことを知り、教えられた私たち選手のほうも監督の考えを理解しながら、最終的に「ここに行きたいね」という目標が合致して、成績に結びつけていっていた。そういうことを考えると、大事だったのはコミュニケーションだったんだなと思う。
もちろんその過程では、いろいろあったし、故障もしたけれど、そのときどきにコミュニケーションによってクリアできたことが多かったと思う。特に故障の多かった私が、ネガティブならずに取り組むことができて復活し、それからのほうが強かった理由を挙げるとしたら、小出監督が「せっかくという言葉をつけろ」と言ってくれたこと。人間面白いもので、「せっかく故障したんだから」と考えたら、「じゃあ、今しかできないことをしよう」とか「神さまが休めと言っているんだから休もう」というポジティブな行動になった。すべてにおいて「せっかく」という言葉をつければ、物事は、ほぼほぼポジティブに向かう。そういうちょっとした積み重ねが、最終的に大崩れしないで、大事な時に合わせていけたかなというのが、私が小出監督の指導で得たものといえる。
メンタルは、そうやって変えていくことができるので、どういう言葉を選ぶかはとても大事。でも、それができるのも、まずはコミュニケーションあってこそではないか。互いに知ろうとする努力、「知ってもらいたい、知りたい」という思いが常にあり、「こうなりたいね」という目標が常に認識できているなかで、今日の練習の反省とか状況の見極めとかが、「できる」ほうへと向いていくのだと思う。

須永:3人に共通していたのは、「目標」という言葉だった。それを、現実的にコミュニケーションをとるなかで、互いに共通した目標をつくり上げていき、達成に向かっていくことの積み重ねが、良いパフォーマンスやモチベーションの向上に繋がることがわかった。今回は4つのテーマについて考えていったが、それぞれにおいて、とても貴重な話や考え方を聞くことができた。パネラーの皆さんに感謝したい。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
五回にわたりウェルビーイングセミナーin京都の内容をお伝えしてきました。
皆様、いかがでしたでしょうか?
ぜひ、皆さんも一度、周りの方々とウェルビーイングについて考えてみていただければと思います。
ウェルビーイングリーフレット
https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/
関連ニュース
-
2025.07.01(火)
【アスリート委員会】が迷惑撮影に対する声明を発表しました!
委員会 -
2025.05.28(水)
指導者セミナー ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」
その他 -
2025.02.28(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#4
その他 -
2025.02.21(金)
【Well-being指導者向けセミナー 受講者募集】『ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」』
その他 -
2025.02.21(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#3
その他