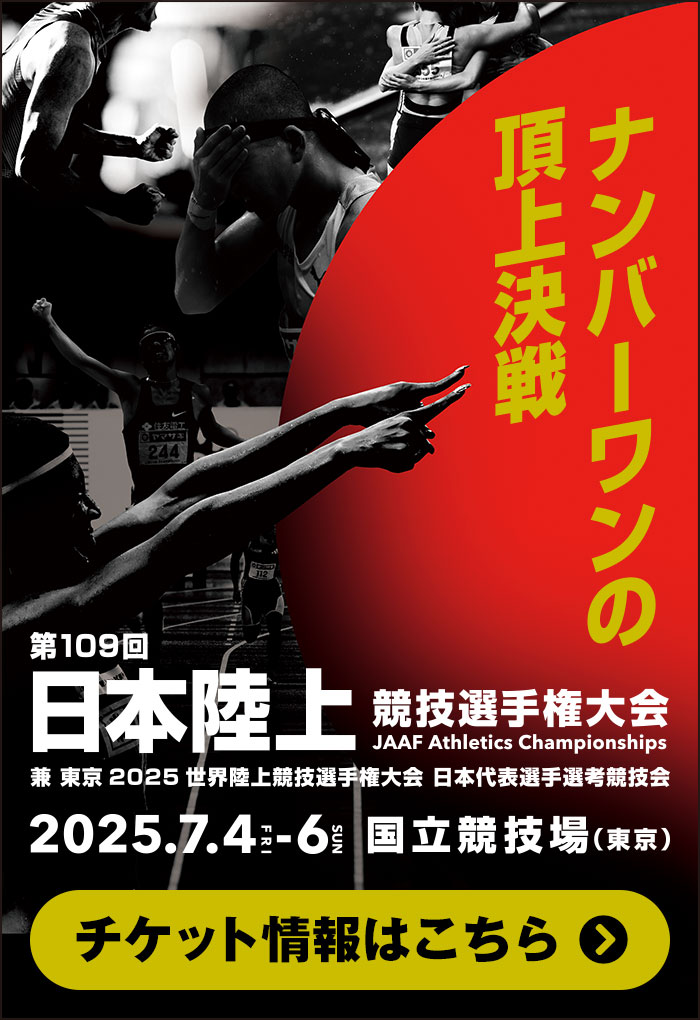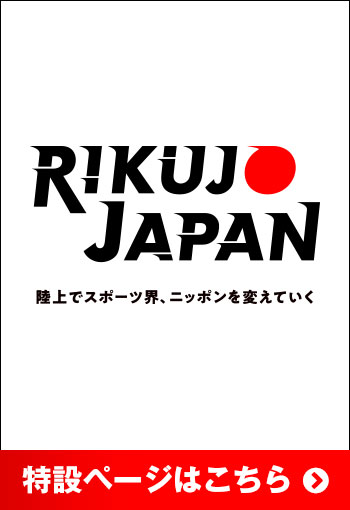活動のミッションに「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」を掲げる日本陸連では、これらを遂行していくうえで、陸上競技に関わるすべての人が、スポーツを通じて心も身体も満たされたウェルビーイング(Well-being)な状態であることを重要と捉えています。そして、この実現に向けて、リーフレットを作成・配布するなど( https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/ )、アスリートはもちろん、アスリートを支えるすべての人が、正しく競技と向き合い、アスリートの健康を守るための知識や学びを深めていけるきっかけつくりに取り組んできました。今年は、その活動の幅を、さまざまな形でさらに広げていくことを計画しています。
1月11日には、翌日に開催される全国都道府県対抗女子駅伝に併せて、一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業協力のもと、『プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」』と題したセミナーを、京都市内で開催しました。
本セミナーの内容について、全五回に分けてお届けします。
今回は、その第二回目となります。
【第2部:パネルディスカッション】
プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」
続いて行われたのが、「プロフェッショナル」によるパネルディスカッションです。有森裕子氏、弘山勉氏、小林祐梨子氏が、講義を行った須永氏とともに登壇しました。日本陸連副会長である有森氏は、競技者としては女子マラソンにおいてオリンピックで2大会連続のメダルを獲得(1992年バルセロナ銀、1996年アトランタ銅)。引退後は、スポーツ界と社会を繋ぐ様々な場面で要職を担い、幅広く活躍していることで知られています。
弘山氏は、競技者として自身も長距離・マラソンで実績を残したのち、その後、指導者として数多くの実績を残してきました。資生堂では、長距離・マラソンで活躍した妻の弘山晴美選手(五輪3大会、世界選手権4大会出場)や世界選手権に出場した藤永佳子選手といったトップランナーを育成したほか、全国実業団女子駅伝優勝を達成。その後、筑波大学の陸上競技部男子駅伝監督に就任し、母校を26年ぶりの箱根駅伝出場に導きました。2024年度からはスターツ陸上部監督に就任。再び、女性長距離競技者の指導にあたっています。
中距離種目で中学生のころから飛び抜けた資質を見せていた小林氏は、兵庫・須磨学園高校時代には1500mで世界ユース選手権や世界ジュニア選手権(現U20世界選手権)でメダルを獲得。さらに日本記録の樹立やアジア大会メダル獲得など、高校年代から日本を代表するトップランナーとして、中・長距離や駅伝で活躍してきました。実業団に進んでからは、2008年に5000mで北京オリンピックに出場。2009年ベルリン世界選手権では、同種目で決勝進出も果たしています。引退後は、スポーツコメンテーター、ランニング教室の指導、講演など多方面で活躍。このセミナーの翌日に控えた全国都道府県女子駅伝でも解説を担当しており、幅広い年代の多くの中長距離女子選手をよく知る人物です。
パネルディスカッションでは、須永氏がファシリテーターを担当。それぞれに異なる立場で陸上競技の現場に詳しいこの3人のプロフェッショナルに問いを立てていくなかで、「アスリートの健康管理とパフォーマンス:相対的エネルギー不足(REDs)のリスクと予防」「女性アスリート特有の課題:月経周期とコンディション」「鉄不足と貧血:鉄不足がパフォーマンスと健康に与える影響」「精神的健康とモチベーションの維持:長距離選手におけるメンタルヘルスと社会的サポートの重要性」というテーマのそれぞれで、3氏の貴重な経験や見識が引き出されていきました。
◎テーマ1:アスリートの健康管理とパフォーマンス
「相対的エネルギー不足(REDs)のリスクと予防」

須永:食事や体重の管理について、自身はどう取り組んでいたか、どういう形が望ましいと考えているか。
小林:私は選手時代、しっかり食べていて、そのおかげか中高校生のときは月経もしっかり来ていたので悩むことはなかった。体重管理については、筋肉量が多い体質だったこともあり、数字を見てストレスを感じないように「私はちょっと重いほうなんだろうな」と自分で前向きに捉えながらやっていた。身体を絞らなければいけないと切り詰めてやっていたわけではなかった。
アスリートとして長く活躍していくために、一番大事な時期は成長期にある中学生と高校生の6年間だと私は思っているが、自分自身はしっかり食べていた。高校は2時間かけて通学していたが、母が作ってくれるお弁当のおかずはいつも10種類。母は栄養に関する資格や免許を持っていたわけではないのだが、「10個入れておけば栄養は整うだろう」と思っていたようで、煮物、酢の物、魚料理、肉料理、卵、フルーツは固定で決まっていて、そこに鉄関係とかいろいろな食材を加えていく感じで、いつも考えて作ってくれていたので、栄養不足とは縁がなかったし、ヘモグロビンの数値も15(g/dL。※陸上選手のヘモグロビン正常下限値は、男性が14.0g/dL、女性は12.0g/dLとされている)台と、貧血になることもなかった。
弘山:私が指導した選手で最高の実績を残したのは妻の弘山晴美になるが、彼女はジュニアから40歳まで現役として競技を続けてきた。「丈夫な身体をつくる」という意味で、彼女の話はモデルになると思う。妻は、小林さんと似ていて筋肉がついているタイプで、それはジュニア期のトレーニングや食事もリンクしていると思うが、「痩せろ」と言われたことが一度もなかったそうで、太っていても叱られたことがない状態で大学まで過ごし、資生堂に入社してきて私が指導することになった。私が指導に当たっている間も、月経が止まったことはなかったし、疲労骨折も一度もない。
彼女の特徴は、体重を量らなかったこと。鏡を見て自分の身体が引き締まっているか、「ぼよん」しているかがバロメーターで、狙った試合に向けて(身体を)研ぎ澄ましていくという感じでずっとやっていたという。その話を聞いた私は、トップアスリートになってからは、彼女には「年に2回、太っていいよ」と話していた。当時は6月に日本選手権があったので、それが終わったら夏の強化合宿が始まるまでガンガン食べて3~4kg太る。その状態で強化トレーニングを積み、秋の狙った大会に向けて身体を絞っていくことをやると、すごくパフォーマンスが上がっていった。それは太った状態でトレーニングすると筋力がつき、走り込むことで同時に持久力も高まり、目指す試合に向けて身体が絞れていくことによって、軽くなって最高のパワーが出せる状態になるから。そういうサイクルを年に2回つくることで、月経も止まらず、丈夫な身体を維持することができていた。1年中、身体を絞って痩せた状態でいると、筋肉がどんどん痩せ細るし、エネルギー不足から骨もスカスカになってしまう。身体が軽くなることで走れるようにはなるが、結局はケガをしてトレーニングを継続できなくなり、パフォーマンスの伸びが止まってしまうというのがエネルギー不足の一番大きな問題だと考えている。妻・晴美のケースは、本当にうまくいった例だろうとは思うが、「そういう例もあるのだ」と皆さんの参考になればと思う。

有森:体重管理について、お二人の話を聞いて、今、問題になっている状態とは全然違うなと感じた人も多かったのではないかと思う。私自身は、実は、全国都道府県女子駅伝に出場した高校1年のときから(競技キャリアが)スタートしている。この大会は、当時、女子の中長距離選手を育成する目的で始まったばかりで、非常に重要な役割を担い、注目もされていたが、当時は、12人ものメンバーを揃えられるチームも少なく、また、走れるようになるための情報も非常に限られていた。そんななかで、まず、単純に「体重を落とすこと」だった。私も高校のころは真夏にたくさん着込んで大汗をかき、走ったあとで体重が落ちていると、実際は干からびただけなのに、「痩せたー」と喜んでいたし、それが不健康であるという情報もないなかで、ちょっとでも走れることを、周りも自分も良しとしていた。
その考えが一番変わったのは、大学を卒業して実業団に入ってからだった。指導してくださった小出義男監督が、「しっかり食べて、しっかり走ろう」「食べないと走れない」という考え方で、「しっかり練習してたくましくなれ。カミソリよりはナタになれ」と言い、そういう身体つくりを目指す人だった。そして自らも「体重が減った減らないではなく、その体重で調子がいいならそれでいい。それ以上、痩せる必要はない」と考えるようになった。なので、体重は量っていたが、減らすことをそんなに気にしていなかったし、体脂肪を測っていたわけでもなかった。
そして実際に、食べられなくなると極端に故障が増えるというのが明らかだった。しっかり食べなければダメ。それを知ったのは実業団に入ってから。時間はかかったけれど、とても大事なことを学んだと思う。そういう意味でも、まさに小林さんや弘山さんの話は納得のいくこと。そういう情報が、現場にぜひ届いてほしい。先ほど、須永先生が話していた、一般の人が痩せるとか見た目やスタイルを気にするのと、本当の意味での健康やスポーツをするなかでの健康とは全然違うんだよということを、現場で取り組んでいる方々に知ってもらいたいなと思う。
須永:先ほどの講義のなかで(IOCの指針に触れた際に)「体重や体組成を測らなくていいのか」という疑問を挙げたが、有森さんが仰った小出監督の「しっかり食べて、しっかり走ろう」という言葉とか、小林さんや弘山さんの話を伺っているうちに、それも一つの在り方で、例えば、体脂肪率1%上がっただけで、変に悩んだり気にしたりしてしまうのなら、計測に固執して観察するのではなく、鏡を見て把握する方法も採るのも、すごく良い方法だなと感じた。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
今後の掲載予定
#3 パネルディスカッション
女性アスリート特有の課題「月経周期とコンディション」
#4 パネルディスカッション
鉄不足と貧血「鉄不足がパフォーマンスと健康に与える影響」
#5 パネルディスカッション
精神的健康とモチベーションの維持「長距離選手におけるメンタルヘルスと社会的サポートの重要性」
準備でき次第、順次掲載をしていきます!
ウェルビーイングリーフレット
https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/
関連ニュース
-
2025.07.01(火)
【アスリート委員会】が迷惑撮影に対する声明を発表しました!
委員会 -
2025.05.28(水)
指導者セミナー ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」
その他 -
2025.03.07(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#5
その他 -
2025.02.28(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#4
その他 -
2025.02.21(金)
【Well-being指導者向けセミナー 受講者募集】『ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」』
その他