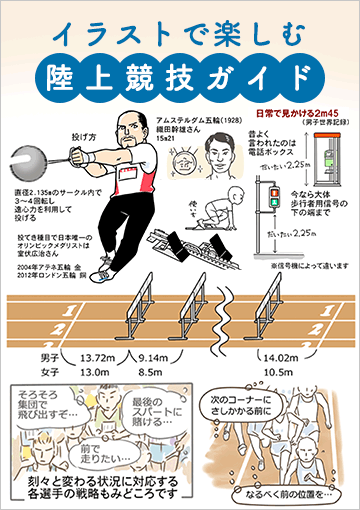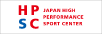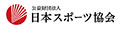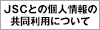いよいよ2020年の幕が開いた。東京五輪まであと半年。2019年は日本新ラッシュに沸いた日本陸上界も、大きな節目の時を迎える。日本陸連の尾縣貢専務理事は日本チーム全体の総監督に就任することが決まり、オリンピック後半にナショナル・スタジアム(国立競技場)で行われる陸上競技で、連日の快進撃を期待したいところ。日本陸上界はこの東京五輪をどう戦い、その後に何を残していくのか。この連載初登場の尾縣専務理事と麻場一徳強化委員長、そしてアスリート委員会から男子棒高跳の澤野大地選手(富士通)に加わってもらい、新春に相応しい前向きな議論をしてもらった。
●構成/月刊陸上競技編集部
●撮影/船越陽一郎
※「月刊陸上競技」にて毎月掲載されています。
.jpg)
出席者(左から)
尾縣貢:専務理事
澤野大地:富士通
麻場一徳:強化委員長
──新年が明けて、東京五輪開幕まであと半年になりました。2020年を迎えた心境はいかがでしょうか。
尾縣 2013年9月に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定してから、さまざまな取り組みをしてきました。例えば、外部の助成を活用した安藤財団グローバルチャレンジプロジェクトや、東京マラソン財団のスポーツレガシー事業の寄付をもとに構築したダイヤモンドアスリートの強化・育成システム、また方法を見直して種目別の強化など。東京五輪は、それらの集大成だと思っています。蒔いた種が実り、収穫の時期ですね。ここまでやってきた強化の成果が問われることはもちろんですが、本当に楽しみです。
麻場 いよいよ〝その時〟が来たな、と。そういう思いです。幸いなことに選手たちが本当にがんばってくれて、良い流れができています。あと数ヵ月ですけど、最後にどれだけ後押しできるか。そこに全力を傾注したいと思います。
澤野 私は「いよいよ来たな」という思いと、「もう来たか」という思いが交錯していますね。やっぱり2013年に東京五輪が決まった時に、ほとんどの選手は「出たい」と思ったはずで、それに向かって選手たちは今、がんばっています。代表選手の選考方法が変わったりしていますので、みんな試行錯誤しながら、日本記録を出したり、世界選手権でメダルを取ったり、選手たちはすごく盛り上がっているところです。楽しみな1年がスタートしましたね。
──東京五輪が決まってから、ここまでの強化の道のりはどう評価されますか。
尾縣 素晴らしいと思います。強化委員会のほうから、いろいろな戦略が、これまで以上に出てきました。例えば、MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)というマラソン代表の選考システム。普通に考えると「一発選考」という発想は今までタブーでしたけど、それが強化の場から出てきて、事務局、理事会が一体となって進めて行けた。あるいは急きょ世界リレーを日本に誘致して、そこでリレーの強化を図るというのも、あらゆる人たちの合意がなければできなかったことです。これらは、強化からの強い要望があってできたことなのです。
2017年に桐生選手(祥秀、日本生命/当時・東洋大)が男子100mで日本人初の9秒台(9秒98)を出して以降、オリンピック種目に限って言うと14種目で日本記録が誕生しています。これだけの活況は日本の陸上史を紐解いても、おそらく初めてだと思います。結果だけでなくそのプロセスに対しても、高い評価をしています。
麻場 さかのぼって考えると、今のトップ選手の強化が始まったのは、2012年のロンドン五輪後からです。一つはダイヤモンドアスリートに象徴されるように、ジュニアからの流れがきちんと構築されて、U20世界選手権などを経験した選手たちが、シニアの舞台でもきちんと結果を残し始めました。もう一つは競歩です。今村文男オリンピック強化コーチの体制ができて、「競歩チーム」として結果を出し始めて8年です。その途中からスタートしたのがMGCなのですが、そういった取り組みがある程度時間をかけて熟成されて、今に至っていると思います。何もなければ「日本新ラッシュ」と言えるような成果は現れなかったと思います。
──2019年の日本新ラッシュを、選手側はどう見ていましたか。
澤野 若い選手たちが台頭してきて、新しい名前がいろんな種目で目立った印象があります。私は今39歳ですが、10年前、20年前には考えられないようなレベルの記録をポンッと出してくる選手が増えています。日本陸上界が新たなステージに来ているんだなという思いと、自分自身そういった中で現役として戦えていることに幸せを感じますね。
──澤野選手は2016年のリオ五輪で7位タイの入賞を果たしていますし、昨シーズンのドーハ世界選手権には教え子の江島雅紀選手(日大)と一緒に出場しました。
澤野 実際、東京五輪が決まった時「2020年は40歳になる年だよな」と思って、地元のオリンピックはまったく見えていなかったんです。でも、リオ五輪に36歳で出場し、自身初めてオリンピックで入賞という結果を残すことができた。これは自分だけの力ではなく、サポートしてくださるいろいろな方の支えがあってできたことなのですが、そこで味わった幸福感は何物にも代えがたいものでした。「こんなにスポーツって素晴らしいんだ」と心の奥底から感じることができたのです。
もう一つは、純粋に棒高跳をしていることが楽しくて仕方がなかった。そこで、年齢を度外視して「競技を続けられるかどうか」と考えた時、痛いところもない、身体は動く、記録は出ている。「だったら、辞める必要もないのかな」と。そこから東京五輪を目指し始めた、というのが正直なところです。それを実現できるぐらいのレベルに今、自分がいるのはすごく幸せですね。
──2020年9月16日に40歳の誕生日を迎える澤野選手のような超ベテランもいれば、まだジュニア世代の選手もいて、年齢層としてはバランスがいいですね。
尾縣 本当にベストな状態だと思います。ここ数年、中体連や高体連とも交流を密にして、「どうあるべきか」ということを話し合う機会が多くありました。ユース世代からトップに行くまでの道筋をしっかり考えて、強化だけでなく医事や科学などすべての委員会の知恵を出し合ってやってきた成果だと思いますね。スイミングスクールが普及している競泳などと違って、陸上はほぼ学校単位でやっているわけですが、一貫した育成強化の考え方さえ浸透できれば、私は問題ないと思っています。大事なのは、それを実現するような取り組みです。

麻場 そうやってきちんとした考え方を提示することが一つと、もう一つはそれをきちんと実践してくれるアスリートが先輩たちにいるということが大切です。私はいろいろなところで言ってきたつもりなのですが、リオ五輪の澤野選手のような競技ができる人が増えてくれば、日本のレベルはもっと上がります。メダルを取るというのは簡単なことではないので、やっぱり入賞する選手をいかに増やすか。入賞の延長線上にメダルがあると思っていますので、澤野選手のような競技生活が送れるアスリートが増えることが大事だと思いながら、強化に携わってきたつもりです。
澤野 そう言っていただけるとうれしいです。今、選手寿命が延びている要因として、やはり東京五輪の存在があると思います。私自身も東京でオリンピックがなかったら競技を続けていたかどうかわからないですし、周りにも「東京五輪があるから」と言って這いつくばりながら競技を続けている選手はいます。それが東京五輪の持つ力ですよね。
──澤野選手も一時はケガに悩まされました。
澤野 そうなんですよ。今までアキレス腱を痛めたら引退に追い込まれる選手がほとんどでしたけど、私は今、アキレス腱の痛みどころか、何ともないんです。スポーツ医学の進歩が選手寿命に大きく貢献しているのでしょうね。ですから、ケガから復活したノウハウを、後輩たちにどんどん伝えていく役目もあると思っています。
尾縣 2007年の大阪世界選手権の年は、澤野さんは何歳でしたか。
澤野 27歳です。
尾縣 すごく失礼な言い方になりますが、大阪世界選手権の予選で敗退した時、内心「そろそろ(終わり)かな」と。実は「競技者育成プログラム」を新しくしたのが2008年の北京五輪後で、その時に中心だったのが澤野さんや女子走幅跳の池田(久美子、現在・井村)さんら、あの世代だったのです。私は「競技者育成プログラム」のエディターだったので、勝手に「ここからどう新しい選手に移っていくか」などと考えていました。
でも、澤野選手は今こうやってまだ第一線でやっている。これはものすごいことだと思います。そういうモデルが増えることで、1回「辞めようかな」と思っても続ける選手が増えるはずです。おそらくそういった選手の中から、さらに競技力を高める選手が必ず出て来ると思います。
『第14回 2020東京五輪イヤーを迎えて(2)』に続く…
●構成/月刊陸上競技編集部
●撮影/船越陽一郎
※「月刊陸上競技」にて毎月掲載されています。
.jpg)
出席者(左から)
尾縣貢:専務理事
澤野大地:富士通
麻場一徳:強化委員長
2020年のスタートに寄せて
──新年が明けて、東京五輪開幕まであと半年になりました。2020年を迎えた心境はいかがでしょうか。
尾縣 2013年9月に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定してから、さまざまな取り組みをしてきました。例えば、外部の助成を活用した安藤財団グローバルチャレンジプロジェクトや、東京マラソン財団のスポーツレガシー事業の寄付をもとに構築したダイヤモンドアスリートの強化・育成システム、また方法を見直して種目別の強化など。東京五輪は、それらの集大成だと思っています。蒔いた種が実り、収穫の時期ですね。ここまでやってきた強化の成果が問われることはもちろんですが、本当に楽しみです。
麻場 いよいよ〝その時〟が来たな、と。そういう思いです。幸いなことに選手たちが本当にがんばってくれて、良い流れができています。あと数ヵ月ですけど、最後にどれだけ後押しできるか。そこに全力を傾注したいと思います。
澤野 私は「いよいよ来たな」という思いと、「もう来たか」という思いが交錯していますね。やっぱり2013年に東京五輪が決まった時に、ほとんどの選手は「出たい」と思ったはずで、それに向かって選手たちは今、がんばっています。代表選手の選考方法が変わったりしていますので、みんな試行錯誤しながら、日本記録を出したり、世界選手権でメダルを取ったり、選手たちはすごく盛り上がっているところです。楽しみな1年がスタートしましたね。
──東京五輪が決まってから、ここまでの強化の道のりはどう評価されますか。
尾縣 素晴らしいと思います。強化委員会のほうから、いろいろな戦略が、これまで以上に出てきました。例えば、MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)というマラソン代表の選考システム。普通に考えると「一発選考」という発想は今までタブーでしたけど、それが強化の場から出てきて、事務局、理事会が一体となって進めて行けた。あるいは急きょ世界リレーを日本に誘致して、そこでリレーの強化を図るというのも、あらゆる人たちの合意がなければできなかったことです。これらは、強化からの強い要望があってできたことなのです。
2017年に桐生選手(祥秀、日本生命/当時・東洋大)が男子100mで日本人初の9秒台(9秒98)を出して以降、オリンピック種目に限って言うと14種目で日本記録が誕生しています。これだけの活況は日本の陸上史を紐解いても、おそらく初めてだと思います。結果だけでなくそのプロセスに対しても、高い評価をしています。
麻場 さかのぼって考えると、今のトップ選手の強化が始まったのは、2012年のロンドン五輪後からです。一つはダイヤモンドアスリートに象徴されるように、ジュニアからの流れがきちんと構築されて、U20世界選手権などを経験した選手たちが、シニアの舞台でもきちんと結果を残し始めました。もう一つは競歩です。今村文男オリンピック強化コーチの体制ができて、「競歩チーム」として結果を出し始めて8年です。その途中からスタートしたのがMGCなのですが、そういった取り組みがある程度時間をかけて熟成されて、今に至っていると思います。何もなければ「日本新ラッシュ」と言えるような成果は現れなかったと思います。
──2019年の日本新ラッシュを、選手側はどう見ていましたか。
澤野 若い選手たちが台頭してきて、新しい名前がいろんな種目で目立った印象があります。私は今39歳ですが、10年前、20年前には考えられないようなレベルの記録をポンッと出してくる選手が増えています。日本陸上界が新たなステージに来ているんだなという思いと、自分自身そういった中で現役として戦えていることに幸せを感じますね。
──澤野選手は2016年のリオ五輪で7位タイの入賞を果たしていますし、昨シーズンのドーハ世界選手権には教え子の江島雅紀選手(日大)と一緒に出場しました。
澤野 実際、東京五輪が決まった時「2020年は40歳になる年だよな」と思って、地元のオリンピックはまったく見えていなかったんです。でも、リオ五輪に36歳で出場し、自身初めてオリンピックで入賞という結果を残すことができた。これは自分だけの力ではなく、サポートしてくださるいろいろな方の支えがあってできたことなのですが、そこで味わった幸福感は何物にも代えがたいものでした。「こんなにスポーツって素晴らしいんだ」と心の奥底から感じることができたのです。
もう一つは、純粋に棒高跳をしていることが楽しくて仕方がなかった。そこで、年齢を度外視して「競技を続けられるかどうか」と考えた時、痛いところもない、身体は動く、記録は出ている。「だったら、辞める必要もないのかな」と。そこから東京五輪を目指し始めた、というのが正直なところです。それを実現できるぐらいのレベルに今、自分がいるのはすごく幸せですね。
40歳目前で地元五輪に挑戦できる意義
──2020年9月16日に40歳の誕生日を迎える澤野選手のような超ベテランもいれば、まだジュニア世代の選手もいて、年齢層としてはバランスがいいですね。
尾縣 本当にベストな状態だと思います。ここ数年、中体連や高体連とも交流を密にして、「どうあるべきか」ということを話し合う機会が多くありました。ユース世代からトップに行くまでの道筋をしっかり考えて、強化だけでなく医事や科学などすべての委員会の知恵を出し合ってやってきた成果だと思いますね。スイミングスクールが普及している競泳などと違って、陸上はほぼ学校単位でやっているわけですが、一貫した育成強化の考え方さえ浸透できれば、私は問題ないと思っています。大事なのは、それを実現するような取り組みです。

麻場 そうやってきちんとした考え方を提示することが一つと、もう一つはそれをきちんと実践してくれるアスリートが先輩たちにいるということが大切です。私はいろいろなところで言ってきたつもりなのですが、リオ五輪の澤野選手のような競技ができる人が増えてくれば、日本のレベルはもっと上がります。メダルを取るというのは簡単なことではないので、やっぱり入賞する選手をいかに増やすか。入賞の延長線上にメダルがあると思っていますので、澤野選手のような競技生活が送れるアスリートが増えることが大事だと思いながら、強化に携わってきたつもりです。
澤野 そう言っていただけるとうれしいです。今、選手寿命が延びている要因として、やはり東京五輪の存在があると思います。私自身も東京でオリンピックがなかったら競技を続けていたかどうかわからないですし、周りにも「東京五輪があるから」と言って這いつくばりながら競技を続けている選手はいます。それが東京五輪の持つ力ですよね。
──澤野選手も一時はケガに悩まされました。
澤野 そうなんですよ。今までアキレス腱を痛めたら引退に追い込まれる選手がほとんどでしたけど、私は今、アキレス腱の痛みどころか、何ともないんです。スポーツ医学の進歩が選手寿命に大きく貢献しているのでしょうね。ですから、ケガから復活したノウハウを、後輩たちにどんどん伝えていく役目もあると思っています。
尾縣 2007年の大阪世界選手権の年は、澤野さんは何歳でしたか。
澤野 27歳です。
尾縣 すごく失礼な言い方になりますが、大阪世界選手権の予選で敗退した時、内心「そろそろ(終わり)かな」と。実は「競技者育成プログラム」を新しくしたのが2008年の北京五輪後で、その時に中心だったのが澤野さんや女子走幅跳の池田(久美子、現在・井村)さんら、あの世代だったのです。私は「競技者育成プログラム」のエディターだったので、勝手に「ここからどう新しい選手に移っていくか」などと考えていました。
でも、澤野選手は今こうやってまだ第一線でやっている。これはものすごいことだと思います。そういうモデルが増えることで、1回「辞めようかな」と思っても続ける選手が増えるはずです。おそらくそういった選手の中から、さらに競技力を高める選手が必ず出て来ると思います。
『第14回 2020東京五輪イヤーを迎えて(2)』に続く…
- 普及・育成・強化
- 【延期】第32回オリンピック競技大会(2020/東京)
- 澤野大地
- チームJAPAN
- 東京五輪
- 東京オリンピック
- TOKYO2020
- Challenge to TOKYO 2020
- 強化
- 尾縣貢
- 麻場一徳