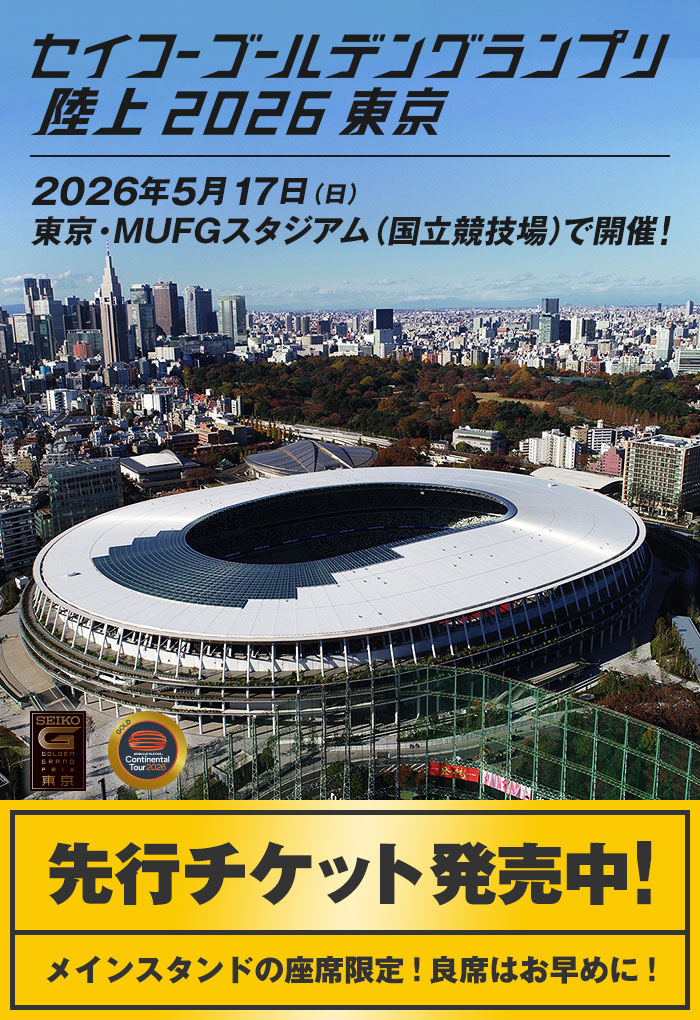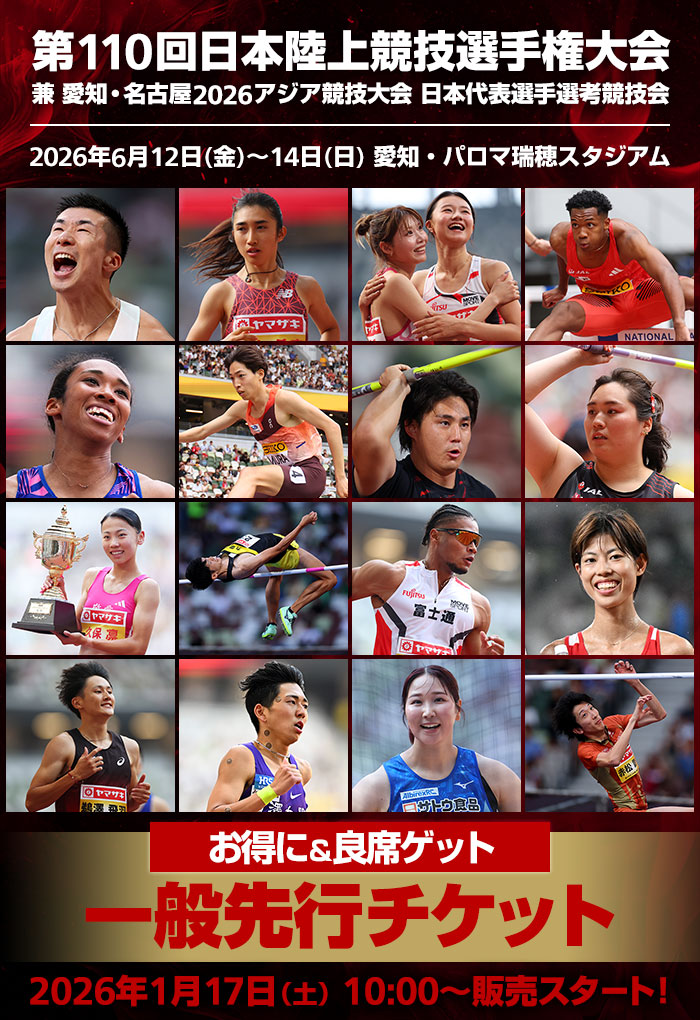日本陸連は、8月22日、東京都内において、育成年代の競技会ガイドラインに関するメディアブリーフィングを行いました。育成年代の競技会ガイドラインについては、すでに本年3月の段階で、2025年度の策定を目指して進めていくことが示されています。田﨑博道専務理事と山崎一彦強化委員長が登壇して、記者会見方式で実施した今回のブリーフィングは、ここまで行ってきた各対応の経過と現在の状況を伝える、いわば「中間報告」に加えて、ガイドラインの柱である競技会スケジュールと仕組み(競技会の仕様、運営方法、種目配置等)の根本改善について、具体的な改革案も示しながら、その重要性・方向性を改めて説明する場として設けられました。
>>「育成年代の競技会ガイドライン」に関するメディアブリーフィングレポート➁
日本陸連は、2025年度の事業計画において、「主催・主要競技会における暑熱対策」とともに、「育成年代(アンダーカテゴリー)の競技会」について、①競技会の仕組みの見直し、②年間スケジュールの調整の2つを示しています。また、それぞれの活動において、以下の目標と今年度末に目指すべき姿を掲げました。
【主催・主要競技会における暑熱対策】
<目標>主催・主要競技会での暑熱への具体的な対策(クーリングスペースやアイスステーション設置など)を、各団体と連携し着手する。
<目指すべき姿>
外部からの規制を待つことなく、暑熱対策の議論を踏まえながら、競技会を持続可能な形に自主的に再構築し、継続していく。
【アンダーカテゴリーの競技会】
<目標>①競技会の仕組みの見直し:アンダーカテゴリーの早期専門化を防ぐため、2027年度からの改変を目指し、協力団体と検討し、方向性を定める。
②年間スケジュールの調整:競技会の開催時期を見直し、選手だけではなく、競技会に関わる人の負担を軽減するスケジュールと競技会の編成案を、第1案として策定する。
<目指すべき姿>
2年間の取り組みを通じて、アンダーカテゴリーの競技会を持続可能な形に進化させ、発育発達段階に適した競技会の枠組や種目設定について科学的な根拠をもとに、最適化が実現している。
・アンダーカテゴリー競技会の最適化:中学生・高校生・大学生の競技継続率が向上し、競技者層の拡大につながっている。
・選手の身体的・心理的負担の軽減:競技会過多などにならないよう年間の競技会スケジュールが適正化され、選手の故障リスクが低減、また、指導者・選手・審判員の負担が軽減されている。
(※「公益財団法人日本陸上競技連盟第15期事業計画」の該当箇所を抜粋し、一部体裁を変更)
具体的な議論は、2025年度からスタートしています。その方向性については、陸連の委員会の枠を越えたワーキングチームが1年以上をかけて検討を重ねてきました。都道府県陸協強化責任者および各協力団体の強化責任者が集まって行われる全国強化責任者会議(昨年12月に実施)において、議論が行われるなど(https://www.jaaf.or.jp/news/article/21282/)、多くの関係者の意見も集約しながら進められてきています。
待ったなしの対応が求められていた暑熱下の競技会是正とあわせて、特に育成年代の競技会システムを改善していけるよう、その骨子となる「育成年代における競技会開催ガイドライン」の策定を本年度中に行うことを4月上旬の段階で公表。
陸上の全国大会として参加人数が最も多く、7月(または8月)の酷暑下で行われているインターハイから、見直しに取り組んでいくと、メディアを含めて(https://www.jaaf.or.jp/news/article/21609/?category=99)、さまざまな場面で説明、周知してきました。
今回のメディアブリーフィングは、今年度実施した「主催競技会における暑熱対策」(https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202506/19_102652.pdf)に則った対応により、実際にインターハイで日程や競技実施方法に大幅な変更が生じた直後だったこともあり、そこで浮き彫りになった事柄も踏まえながらの説明となりました。
冒頭で、田﨑専務理事が、年頭から進めてきたインターハイの日程見直しについて、その経過と進捗状況を報告。そのうえで、山崎強化委員長が、暑熱対策も含めて根本的な見直しを進めていこうとしている育成年代の競技会システムについて、改めて、その課題や目指すべき方向を説明し、議論を進めるための「叩き台」として新たな競技会スケジュール案を提示しました。
以下、それぞれの要旨をご報告します。
育成年代の競技会ガイドライン策定に向けた経過と現状(要旨)
◎田﨑博道専務理事

「待ったなし」といわれている酷暑下における競技会やスポーツのあり方については、日本陸連としても、今年3月の理事会で協議し、今後の検討を対応や方向感について、メディアの皆さんにも説明した。
その方針に沿って、すでに開催が確定していた今年7~8月の主催大会については、WBGT(暑さ指数)31℃を超えた場合は、原則、競技を中断・中止することをメルクマールとして、酷暑下を避けるさまざまな努力を行ってきた。日程や競技方式(トラック種目でのタイムレース決勝、フィールド種目で試技回数を減らす等)の変更、メイン会場やウォーミングアップ場、待機場所などに野外テントや冷風機、ミストファンなどを設置するなど、あらゆる機器を駆使し、WBGT31℃を超えない場所の確保すること、アイスステーションの設置や熱中症対策アイテム(塩分補給タブレット等)の配布などを行い、その対策に努めてきた。
選手をはじめとして、関係するすべての方々のご理解やご尽力により、大会を無事に終えることができたが、その一方で、WBGTが31℃を超えることが想定される時間帯を避けて、朝夕の2部制にする競技会スケジュールでの実施は、選手・関係者にとっても運営側にとっても心身への負担、さらには宿泊や移動を含めたコスト面でも大きな負担になることが明白となった。また、全国大会は、要員面でもインフラ・コスト面でも多くのサポートを得られるが、むしろサポートを十分に整えることができない地区予選等が、今後、酷暑の中で実施されていくことになる可能性を考えると、WBGTが31℃を超えることが想定される7月・8月に屋外スポーツを行うことについて、根本的に見直す必要があると強く感じた。
酷暑下のスポーツのあり方への社会の関心は、加速度的に高まっている。インターハイとともに育成年代の大きな全国大会である全日本中学校選手権が終わったあと、改めて陸連のなかで総括を行い、皆さまにご報告したいと思っている。
◎インターハイ日程見直しに関する経過
インターハイの競技日程見直しについては、日本陸連としては2026年滋賀インターハイからの施行を目指して進めてきた。実際に私自身も、3月に実施した陸連の理事会において、「2026年滋賀インターハイに間に合わせるためには、高体連陸上競技専門部と検討を積極的に進め、8月を目処に答申的な提言を行うことができれば…」と説明した。その方向感で、ここまで働きかけをしてきたが、目処に掲げていた8月を迎えたため、現段階で状況を、これまでの経過を含めて、ご報告したい。<インターハイ日程変更に関する経過>
・1月22日:高体連本部に訪問して、会期の変更について、正式な検討をお願いした。
・3月26日:日本陸連理事会において、2026年滋賀インターハイからの施行を目指して進めていうことを協議・承認。
・8月6日:日本陸連との窓口となる高体連陸上競技専門部(以下、高体連陸上専門部)から、2026年度以降のインターハイ実施案について3つの提示を受ける。
・8月19日:高体連陸上専門部の部長・副部長が陸連に来訪。8月6日に示された案について、対面にて説明を受けた。この提案内容については、具体的な検討・議論に入るために、改めて書面でいただくことになった。一方で、この面談の場で、本件に関して、高体連本部と高体連陸上専門部との打合せにおいて示された高体連本部としての正式な回答を、専門部長より受けた。その内容は以下の通り。
1)2026年の滋賀、2027年の神奈川、2028年の愛知については、すでに開催通知を出していることから、開催時期の変更は極めて困難である。
2)高体連の中には、陸上を含む全専門部が入る「インターハイの在り方プロジェクトチーム」というものがある。そのプロジェクトチームが8月末に各専門部の意見の集約をし、2026年3月末までに、ワーキンググループで何を検討するかを検討することになっている。当初の検討項目に、開催時期の見直しが含まれていないため、それを新たな検討項目に加えるかどうか検討することを検討する。
高体連本部からは、高体連陸上専門部長に対して、「高体連本部としては、インターハイ全体として時期の見直すかの検討ができていないなかで、陸上だけの時期をずらすことの検討はできない」との説明もあったそうである。
この高体連本部の回答では、来年の滋賀インターハイでの対応はもとより、3年先まで現行のスケジュールで開催することが前提となってしまう。陸連としては、暑熱対策の緊急性・重要性に鑑み、3月の理事会で決めた方針をもとに、今後の進め方も含めて関係各所と意見交換を行いながら、引き続き、働きかけを進めていく考えである。
◎「叩き台=叩かれ台」の提示で、具体的に動かしていく
こうした経緯もあり、これから山崎強化委員長が説明する「育成年代における競技会開催のあり方、年間競技会スケジュール案」は、3月の段階で目指していた答申的な位置づけには至っていない。ついては、高体連をはじめとする関係部署との今後の議論において、陸連が用意した叩き台(我々の間では「叩かれ台」と言っているが)の位置づけであることを大前提に聞いていただきたい。また、育成年代の競技会のあり方は、当然のことながら、日本陸連が掲げている「国際競技力の向上」「ウェルネス陸上の実現」という2つのミッション実現に向けた、目指すべき競技会システムの議論の上に成り立つものである。従って、まずは、陸連が現在、議論している「目指すべき競技会システムのあり方」(今後、理事会や関係各所において叩いていく必要があるため、こちらも「叩かれ台」の位置づけにあるが)を説明したうえで、「育成年代における競技会開催のあり方、年間競技会スケジュール案」を説明する。
競技会システムについては、今までも課題として何度も指摘されてきた問題。「具体的な一歩」が踏みだせていないまま、今の状況があることに、関係する誰もが危機意識を持っていると思う。既存の枠組みや考え方、ルール、方法を、社会や環境の変化や状況に応じて柔軟に見直し、最適化させていくことは、スポーツ基本法にあるナショナルフェデレーションの役割である。私たちは、これを果たしていくために、勇気を持って、まずは議論の「叩かれ台」を提示していく。
また、ここで説明する具体的な内容は、「陸連内での叩き台、関係する皆さまからの叩かれ台」として、8月20日の理事会で協議した内容でもある。本件については、競技運営、施設用器具、強化、指導者養成、さらには医事、科学、法制、財務、そして何よりもアスリートと、陸連内のすべての専門委員会が一体となって取り組んでいく。検討過程の段階にあるこうした内容を、メディアの皆さんにブリーフィングすること自体がよいのかどうかは私自身も悩んだ。しかし、空中戦ではなく、具体的な行動に移す議論を進めていくためには、「叩かれ台」が必要だと考えている。大切なステイクホルダーであるメディアの皆さんにも、このプロセスを開示し、皆さんからもアドバイスやご支援をいただきたい。
>>「育成年代の競技会ガイドライン」に関するメディアブリーフィングレポート➁
文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)