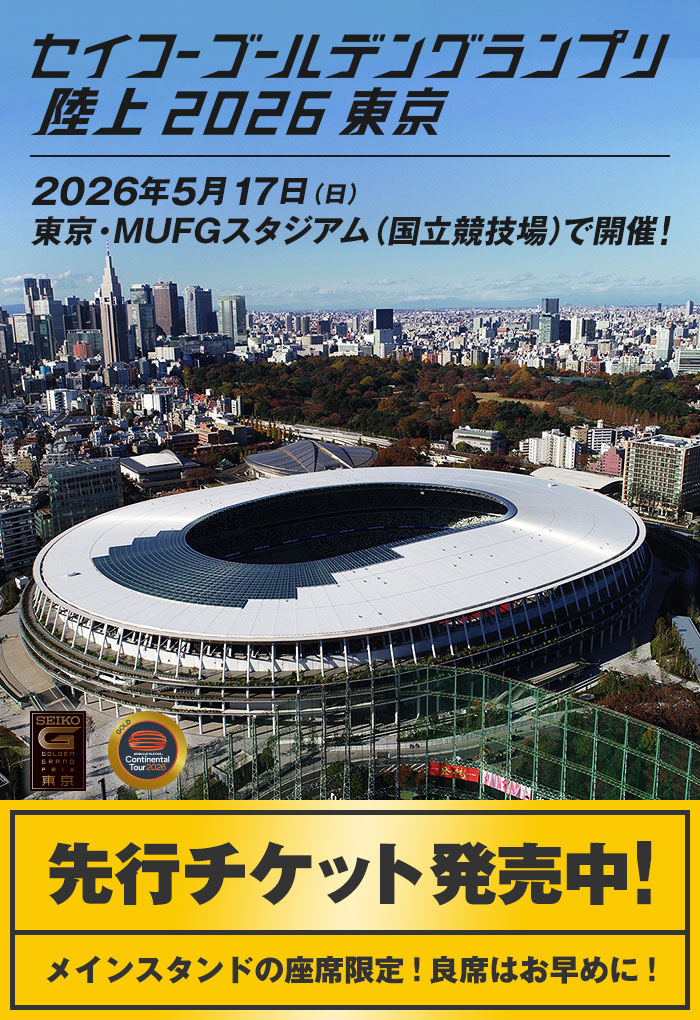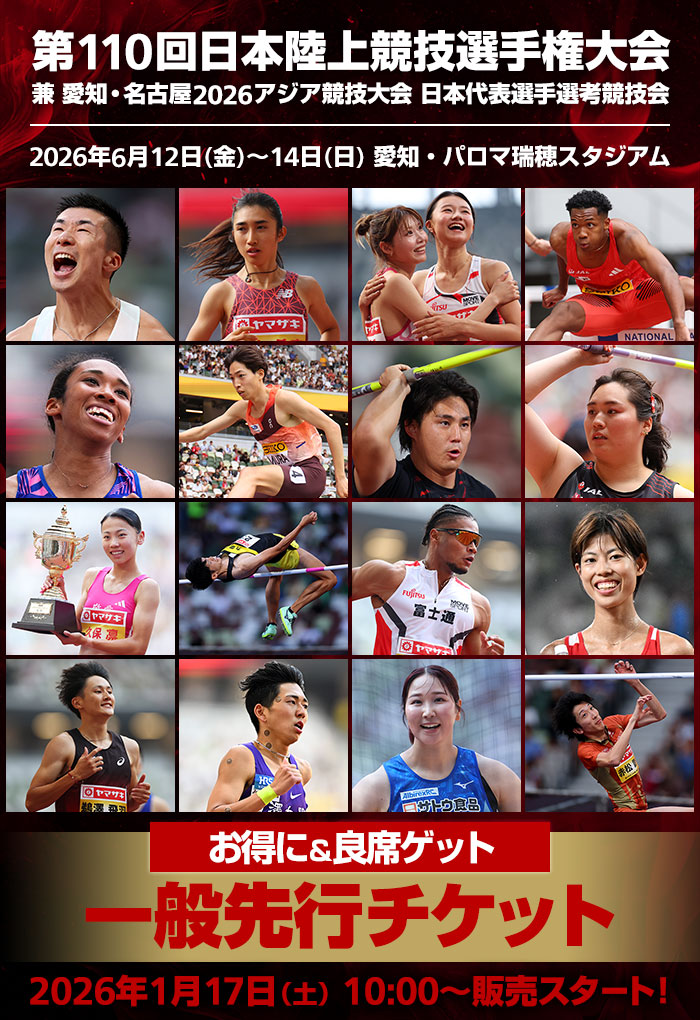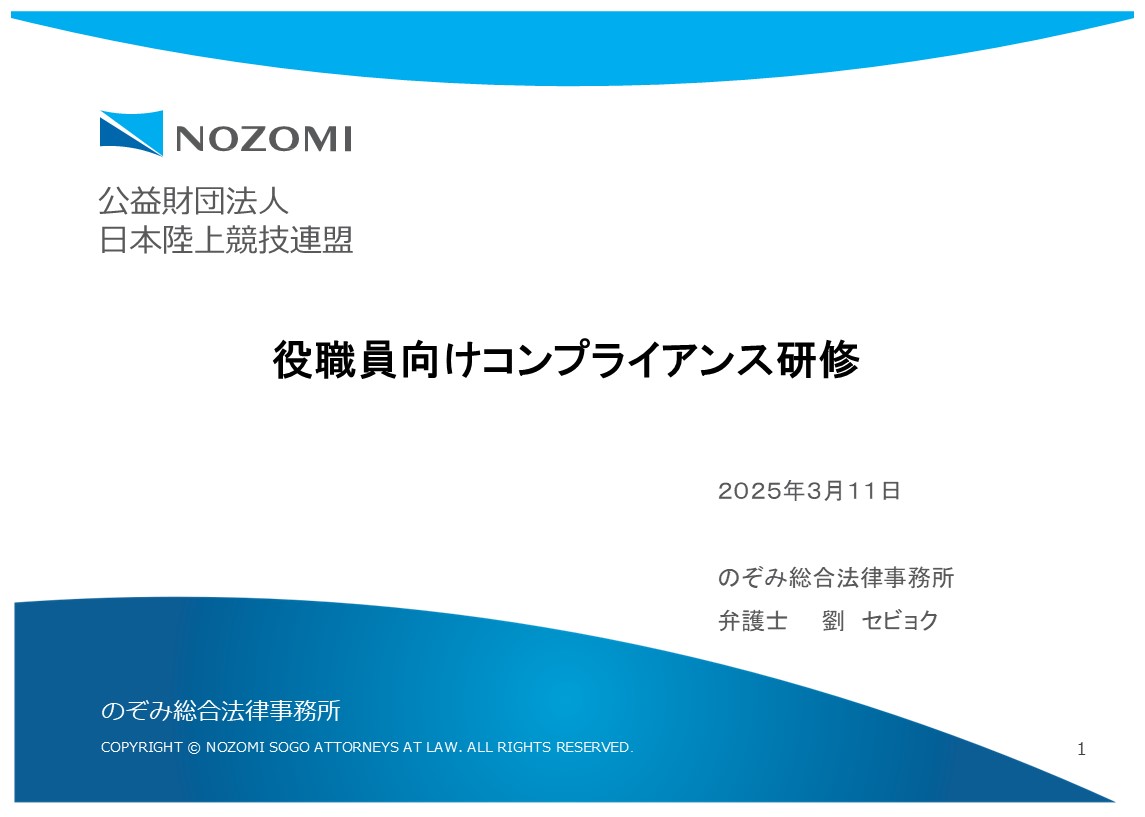
「人の多様性を認め、受け入れて活かすこと」を意味するダイバーシティ&インクルージョンを重視する日本陸連では、競技団体としてのダイバーシティ&インクルージョン実現を目指し、関係者の認識や理解を深める研修活動を展開しています。3月11日には、連盟理事・監事等役職者と事務局職員を対象に、3回目の研修が、オンライン形式で行われました。
今年度最後の研修として実施されたのは、「コンプライアンス研修」です。コンプライアンスは、「法令遵守」という本来の概念から、近年では組織内の規定や倫理、さらには社会的な規範まで、遵守の対象が広がっていて、社会全般で組織運営における重要な命題に位置づけられています。その流れはスポーツ界においてもスタンダードなものとなり、どの競技団体においてもスポーツ団体が適切な組織運営を行ううえでの原則・規範を示した「スポーツ団体ガバナンスコード」に則った取り組みを進めています。
日本陸連でも、すでに2020年度から年に1回のコンプライアンス研修を実施してきましたが、昨年度からはダイバーシティ&インクルージョン研修に組み込む形で展開していくことに。今年度も、初回から講師を務めている弁護士の劉セビョク氏(ゆ・せびょく;のぞみ総合法律事務所)による研修が行われました。
劉弁護士は、日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁人・調停人候補者や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会プロボノサービス(※アスリート等に無償で法的アドバイスを行うサービス)の手続代理人候補者の実績を持つなど、スポーツ法務分野においても幅広い活躍で知られている人物。今回の研修では、導入としてコンプライアンスの総論やスポーツ界での状況等を共有したうえで、コンプライアンス違反の事例としてスポーツ界で取り沙汰されることの多いハラスメント、特にパワーハラスメントに焦点を当てたレクチャー&ディスカッションが行われました。
スポーツ界にコンプライアンス強化が必要な理由
「すでに何度か研修を受けている方には、おさらいということになるが…」と断った上で、最初に劉弁護士が説明したのは、「コンプライアンスとは何か」。日本語では「法令遵守」と訳されるこの言葉が、「実際に我々がカタカナで用いるコンプライアンスという言葉は、もう少し広い意味を持っている」として、①一般的な法令の遵守、
②組織や業界が定める内部規範の遵守、
③社会規範の遵守、
の3つを挙げました。そして、「公共性、あるいは公益性の強い組織であればあるほど、①だけにとどまらず、②、③と深いところまで遵守していくことが求められる」と、公益財団法人として存在している日本陸連が置かれている立場を示しました。
続いて、「スポーツ界におけるコンプライアンス強化の目的」について、劉弁護士は、「まず、“スポーツにおいてはインテグリティ(高潔性)自体が価値”だからという考えが第一にあり、その発想のもとスポーツ団体が自律していくことで、競技が普及され、経済的にも発展し、最終的には競技力も向上する。コンプライアンスの強化は、こういった良い循環を生みだしていくために必要」と説明。また、競技団体がコンプライアンスを強化することによって、
・一般企業等に比べると非常に多いステークホルダー(直接的・間接的に影響を受ける利害関係者)への配慮になる、
・そのスポーツに “する・みる・ささえる”の3側面で関わっている人々すべての心理的安全性の確保につながる、
・ルールの明確化により競争が活発化し、競技力が向上する、
として、それらがスポーツの恒常的な発展に結びつくことを示唆しました。
スポーツ界の不祥事から見える特徴
増える通報窓口への相談
スポーツ界が、コンプライアンスの強化に目を向けるようになった背景には、スポーツ界での暴力や暴言などのハラスメントが発覚し、事件・不祥事として社会的な問題として大きく取り沙汰されたことが契機になっています。劉弁護士は、2013年に日本体育協会(現日本スポーツ協会)、日本オリンピック委員会など統括5団体が共同で「スポーツ界における暴力根絶宣言」を採択するに至ったその経緯に触れるとともに、これが「各団体が通報窓口を設置する大きなきっかけになった」と述べました。また、スポーツ界における不祥事の特徴として、「客観的証拠が残っておらず、アンダーグラウンド化しやすい」「未成年がヒアリング対象者になる場合がある」「被害者が自らを責めたり被害意識を有していなかったりする場合がある」の3つを挙げ、この特徴ゆえに顕在化しづらいという特殊性も解説。併せて、日本スポーツ協会の通報窓口に寄せられた相談件数(コロナ禍後、2022・2023年度と連続して過去最多となっている)や内容・相談者の情報も共有されたことで、受講者たちは、通報窓口を存在させることの重要性や現在の状況を認識するとともに、スポーツ界ならではの特殊性を踏まえて不祥事を減らしていく対策をとる必要があることを理解しました。
「パワハラ」を理解する
続いて研修は、今回のメインとなる「ハラスメント」の話題に入っていきました。ハラスメントは、相手に不快感を与える嫌がらせやいじめ全般を指す言葉で、代表的なものとして「パワーハラスメント(パラハラ)」「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」「マタニティハラスメント(マタハラ)」の3つが挙げられますが、このほかにも、「アカデミックハラスメント」「モラルハラスメント」「アルコールハラスメント」「カスタマーハラスメント」など、さまざまなハラスメントが言葉として用いられるようになっています。劉弁護士は、「パラハラ、セクハラ、マタハラは、法律上も存在する概念だが、そのほかについては、一つの見方として、いろいろな局面における“形を変えたパワハラの一種”と捉えることができる」と説明。ハラスメントの存在が、組織に及ぼす影響を示したうえで、「先ほど挙げた“心理的安全性”を守っていくためにも、ハラスメントの防止は非常に大切」と強調しました。ここで紹介されたハラスメントのなかでも「パワハラ」は、スポーツ界で最も起こりやすい、また実際に起きているハラスメントといえるでしょう。劉弁護士は、「ハラスメントという概念は、もともとは職場内や同一組織内においてのみ問われていた概念だったが、近年ではいろいろな局面、つまり違う組織の人との間やスポーツにおいても問題視されるようになった」と述べ、日本においては「厚生労働省のワーキンググループが挙げていた概念が、数年前に法律上の規定として明文化されるに至った」ことを説明したうえで、具体的なパワハラの構成要素として、
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、
③雇用する労働者の就業環境が害されること、
の3つを挙げ、「この3つが揃って初めてパワーハラスメントに当たる」とコメント。これら1つ1つについて、スポーツ現場で起こり得るケースに置き換え、何が問題であるのかを、以下のように解説していきました。
① 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
「職場」を「スポーツの現場」に置き換えて考えるとよい。指導者から選手に対する場合だけでなく、選手同士など形式的には同じ立場にあっても、実質的に優越的な関係が認められるケースもある。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
「明らかに必要ないものはダメ」というだけでなく、「指導上、必要であったとしても、やり過ぎてはいけない」ということ。例えば、指導に当たって不適切な言葉や表現を使う指導者は、令和の時代にも存在する。また、指導の目的から逸脱した行為に及ぶケースもこれに当たる。
③ 雇用する労働者の就業環境が害されること
スポーツの現場でいえば、「スポーツをする人たちやスポーツに関わる人たちの、スポーツに関わる環境が害されること」と言い換えることができる。平均的な人物における感じ方を基準とするとされているものの、何をもって“害された”かは、具体的な事実関係を踏まえて判断する必要があることから、非常に線引きが難しい。
セーフとNGの線引きは困難
「ハラスメントに見えない、思われない言動」を
パワハラの構成要素を説明した劉弁護士が、ここで指摘したのが、「パワハラか否かの線引きの難しさ」です。「よく、ハラスメント研修の講師依頼を受ける際に、“裁判例などを通じて、セーフとNGの境目を教えてほしいと言われるが、そのような線引きは非常に難しい」と話し、その理由を、「判例に残るようなセクハラやパワハラの事案の多くは、“誰が見てもダメ”というものばかりで、微妙なラインの事案は判例に残らないケースが多いし、事案ごとの個別具体的な事情を踏まえて検討する必要があることから、一般化して線引きすることができない」と説明。「だからこそ、“ハラスメントにならない言動をすること”だけでなく、“ハラスメントに見えない、思われない言動をとること”も同様に重要だと私は思っている」と、きっぱり言いきりました。そして、「もちろん、心の持ち方が第一にあるべきだが」と前提を述べたうえで、「ハラスメントにあたるかどうかは、ちょっとした表現の仕方や伝え方の工夫次第で、結論が変わり得る。それは、伝え方に関する技術的な工夫の問題でもある」とコメント。厚生労働省が6類型に分類しているパワハラの具体例と違法性を解説したのちに、いくつかのケーススタディを示し、受講者と意見交換しながら考えていく時間へと移っていきました。
ケーススタディを挙げての議論では、劉弁護士が3つのケースを提示。そこで示された指導者の言動がパワハラに該当するか否か、該当する場合はどの言動に問題があるのかを、手を挙げた受講者が回答し、どこを変えればパワハラに該当する可能性を低減できるだろうかという視点から、ディスカッションされました。さらに、劉弁護士からは、「では、こういう背景があったうえでの言動だった場合は?」と検討の幅を広げる問いかけも。受講者たちは、追加された情報を踏まえながら、「それでも、この発言には配慮が必要」「自分だったら、こう話す」「こういう形で声を掛けるべき」と対話を深めていきました。
競技団体の運営に携わっていたり、スポーツ現場で指導に当たったり、教壇に立ったりと、さまざまな背景を持つ受講者が、自身の経験も踏まえて発言したことで、意見交換で出てきた内容は、非常にリアルかつ実践的なものになりました。劉弁護士が最後にまとめた事柄も含めて、今回の研修において示された、ハラスメントを避ける向き合い方や留意点は、下記のとおりです。
◎ハラスメントを避ける向き合い方と留意点
・ハラスメントの問題においては、「伝え方」が非常に重要。暴力については正当化の余地が全くないが、いわゆる「暴言」によるハラスメント行為については、正当な指導目的に基づくもののアプローチの仕方が適切でなかったために結果的にハラスメントに及んでしまっているケースが多い。
・ちょっとした工夫と我慢で回避できるトラブルは少なくない(役員に向けて、アンガーマネジメント、伝え方の工夫を研修する企業もあるほど)。
・一方的に話す、不必要に疑問文の形で話すことは、相手が答えられない状況をつくるとともに、傍からは正常なコミュニケーションと思われにくくなる。パワハラ事案が発生すれば、例えば、録音されたデータが文字起こしされたものが裁判やスポーツ仲裁の証拠として持ち込まれる。簡単ではないが、普段から「録音されている」と思って言葉を選ぶことを心掛ける。
・同じ言葉でも、口頭で伝えた状態より、テキスト(文字)になったときのほうが、冷たい印象を残す。とりわけ大人が子どもに使う言葉遣いは、使っている側の感覚以上に、活字化すると冷たい印象を受けることを念頭に置き、配慮することが必要。
・不用意に人と比べない。「誰々に比べて」「誰々だったら」「○年生でもできる」といった他者と比べる言い方は、相手の自尊心を刺すので、できるだけ避ける。
・LINEやメールなどのテキストでのやりとりは、倒置法や体言止めをなるべく使わない。同じことを伝えても倒置法や体言止めを用いると威圧感や雑にあしらわれているイメージを与えてしまう。これは、指導者と選手の関係性においてだけでなく、例えば陸連内部の仲間同士のコミュニケーションにおいても留意したい。
・「ハラスメントにあたる行為をしないこと」だけでなく、「ハラスメントを疑われる行為をしないこと」も重要。最近では、選手同士あるいは指導者同士のハラスメント事案も増えてきている。自由闊達で多方向のコミュニケーションが許されている組織では、職務上の立場が対等であるからこそ、声の大きな人の影響力が強くなり、そうでない人が却ってハラスメントを受けているように感じてしまう、ということもある。
・「望ましい」「望ましくない」とされる言動は、時代や状況によって変わり続けている。特に差別的とされる言動は、今、問題なく使えている言動でも、5年後、10年度に望ましくないものになる可能性もある。互いにコミュニケーションをとりながらアップデートしていくことが大事。
文:児玉育美(JAAFメディアチーム)
関連ニュース
-
2025.10.29(水)
日本陸連が目指す「ダイバーシティ&インクルージョン」の推進「JAAF人権ポリシー」「JAAFインテグリティ行動指針」公表に際して――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより
その他 -
2025.09.10(水)
【レポート】8月8日開催「ダイバーシティ&インクルージョン 高校生ワークショップ」テーマ:インクルーシブな競技の在り方を考える
その他 -
2025.09.09(火)
WAが新たに設けた「女子カテゴリー」参加資格に関する規則への日本陸連の対応 ――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより
その他 -
2025.08.26(火)
ダイバーシティ&インクルージョンの推進「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」の制定について
その他 -
2025.04.14(月)
2月18日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」研修。テーマ:女子競技の参加資格に関するWA規定を考える
その他