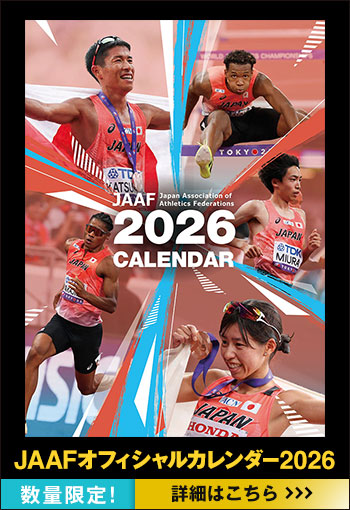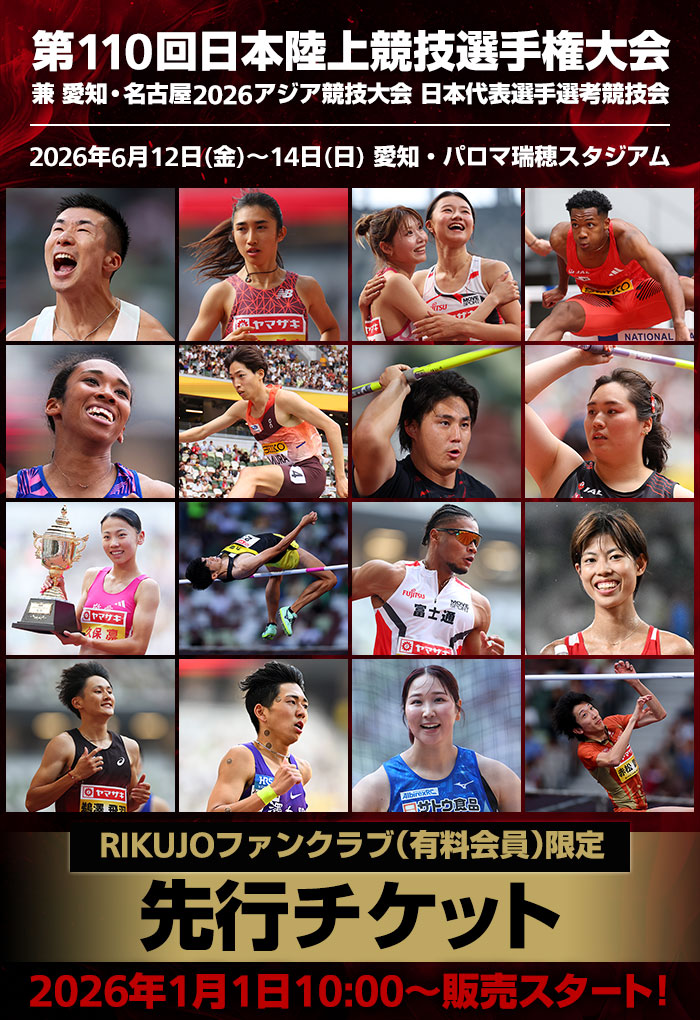日本陸連では、「人の多様性を認め、受け入れて活かすこと」を意味するダイバーシティ&インクルージョンを重視し、競技団体としてのダイバーシティ&インクルージョンを実現すべく、昨年度から関係者の認識や理解を深める研修を行っています。今年度も全3回での開催を予定しており、その1回目となる研修が、1月31日に実施されました。
>>日本陸連 ダイバーシティ&インクルージョンに関するページ
https://www.jaaf.or.jp/diversity-equality-inclusion/
今回の研修からは、参加の対象を、昨年度までの日本陸連役員(理事・監事)および事務局職員から広げて、加盟団体(各都道府県陸上競技協会)や協力団体(日本実業団陸上競技連合、日本学生陸上競技連合、全国高等学校体育連盟陸上競技専門部、日本中学校体育連盟陸上競技部、日本マスターズ陸上競技連合)関係者にも声をかけての開催に。当日は、日本陸連内に研修会場を設けるとともに、オンラインでも配信するハイブリッド形式で実施され、全国各地から84名の関係者が参加しました。
開会に際して、挨拶に立った田﨑博道日本陸連専務理事は、日本陸連が「ダイバーシティ&インクルージョンの精神を、すべての活動・施策において不可欠なものと捉え、2023年度に改めて推進の中期計画というものを策定し、進めている」こと、そのためにまず「自らの意識、組織自体の多様性を高めるステップを踏んでいく」機会とすべく本研修を企画したことを説明し、昨年度の実施内容を挙げ、ここまでの流れを振り返りました。そのうえで、今回、講師として招いた株式会社リクルートホールディングス兼株式会社リクルートの柏村美生さんの経歴を紹介。「今回、柏村さんに企業経営の立場から、またグローバルの視点から、D&I推進のポイントやリアルな実例などを聞かせていただくことで、我々が多くの気づきを得られればと思っている」と述べ、柏村さんにマイクを渡しました。
DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)とは?
今回の研修は、「企業におけるDEIの取り組みと課題」がテーマです。「DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン:ディー・イー・アイ)」は、Diversity(ダイバーシティ:多様性)、Equity(エクイティ:公平性)、Inclusion(インクルージョン:包括性)の頭文字をとった言葉で、「人の多様性を認めて尊重し、受け入れて活かす」というダイバーシティ&インクルージョンの概念に、「公平であること」を加味した考え方。「人はそれぞれに背景やスタート地点が異なる」という前提のもと、そこに起因する不均衡をなくす土台や施策を設けることで、関わる人々が公平に機会や情報を得て自身の能力を発揮していけるようにしようとするアプローチです。社会が「ダイバーシティ&インクルージョン」に取り組んでいくなかで、その概念がさらに進化・発展したということができるでしょう。近年ではDEIを経営の重要テーマに位置づけ、推進する企業が増えています。講師を務めた柏村さんは、1998年にリクルート(現リクルートホールディングス)に入社。20代の頃から、様々な事業でリーダーを担ってきました。上海に赴任して、2004年に社内の新規事業提案制度を活用し、結婚情報誌『ゼクシィ』を中国で事業化、帰国後は美容情報事業『ホットペッパービューティー』事業責任者等を経て、2015年にリクルートホールディングス執行役員に就任。その後、リクルートスタッフィング代表取締役社長、リクルートマーケティングパートナーズ(現リクルート)代表取締役社長などを経て、2021年4月から現職*1。並行して、東大PHED専門部会委員(障害と高等教育に関するプラットフォーム)や経済産業省人的資本経営コンソーシアム企画委員など、社外でもさまざまな要職を務めています。
*1 ・株式会社リクルートホールディングス執行役員 経営企画本部PR
・株式会社リクルート執行役員 人事、広報・渉外、サステナビリティ
(2025年1月31日講演時点)
1960年に大学新聞専門の広告代理店として創業したリクルートは、大学生への求人情報を集めた就職情報誌を発行することからスタートし、その後、さまざまな切り口の情報誌を世に送り出して、企業と個人をマッチングさせるビジネスモデルを確立。その事業領域を拡大させていきました。いち早く情報のデジタル化にも取り組み、1990年代に紙メディア(情報誌)をインターネットへ、そしてアプリケーションへと転換するなど、時代を先取る取り組みで大きく成長。2000年代からはグローバル市場にも進出。現在では、国内外を含めたグループ従業員数は5.1万人を超え、サービス展開は世界60カ国以上にのぼっています。
今回の研修では、株式会社リクルートのDEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)をリードする執行役員柏村さんが、同社で行っているDEIへの取り組みを、具体的な事例を交えながら紹介。参加者たちは、推進にあたってのポイントや課題のほか、実践によって期待できる変化や未来への展望など、さまざまな視点からDEIを学んでいきました。
創業当初からの価値観「個の尊重」
まず、柏村さんが紹介したのが「個の尊重」という言葉です。これは、リクルートが掲げるバリューズ(大切にする価値観)の1つで、「従業員一人ひとりを尊重し、いかに活かすか、ということを真ん中に置き、その結果、社会に新しい価値を創造し、さらにその結果として社会に貢献していこう」(柏村さん)というもの。柏村さんは、「個の尊重」が、創業時からリクルートがずっと大事にしてきた考え方で、ミッションやビジョンとともに日常的な従業員間の対話でも出てくる言葉であると述べたうえで、そうした企業文化が醸成されている同社の特徴を、・特許や工場など物質的な資産がなかったため、創業当初から「人」が最大の資産だった、
・企業として生き残るために、多様な「個」が自らの能力を最大限発揮することにフォーカスした経営が行われてきた、
・当初は応募を増やすことが目的だった、当時では珍しい「学籍、性別、国籍を問わない」求人が、結果として多様な人材を集めることになった、
・性別を問わず等しく働く環境が早い段階からできていた。このため、女性が活躍し、マネジメントラインに上がっていくケースも自然なことだった、
と、歴史的な背景を踏まえながら紹介していきました。
DEIは、世間では近年になってようやく注目されるようになってきた概念ですが、リクルートにおいては、DEIに通じる概念が創業当初から土壌にあり、スタートの段階こそ存続をかけての選択だったこれらの方向性が、結果として、同社の強力な武器となって発展につながっていったことが示されました。
DEI実現の加速に向け、2021年に方針を明文化
ダイバーシティ&インクルージョンに向けた取り組み自体は、2006年の段階から専任組織を設けて進めてきたなか、時代の変化や5万人規模のグローバル企業に成長したことに伴い、2021年、DEI実現に向けた取り組みを改めて明文化して発表しています。「価値の源泉は“人”であることをベースにしながら、従業員一人一人に期待すること、会社が約束することを改めて再定義し、この中にDEIを改めて織り込むということをした」と柏村さん。担当役員として指揮を執るこの取り組みについて、「2030年度までにリクルートグループの上級管理職・管理職・従業員の女性比率を約50%にする」と公言して進めている「ジェンダー平等」をはじめ、「働きがい」と「働きやすさ」の実現に向けて取り組んでいるさまざまな施策を、データなどを盛り込みながら解説していきました。
また、それら取り組みが3年、4年と積み重なっていくなかで同社に生じた変化についても具体例を示しつつ紹介。貴重な事例を目の当たりにする形となった受講者たちは、組織がDEIを推進していくなかで得られること、ポイントとなること、留意すべきこととして、次のような事柄があることを理解しました。
・すべての「個」を活かせるような制度や施策、カルチャーを、手に入れるには時間がかかる。長期的な視点での取り組みが必要。
・DEI実現を目指す取り組みは、組織全体や個人が自らのアンコンシャスバイアス(無意識の思い込みや偏見)に気づく機会となる。
・ありとあらゆるテーマが世界中で目まぐるしく変化する現代では、誰かひとりだけで正解を見出すことが非常に難しくなっている。いろいろな背景を持つ人が属することは、組織としての変化対応能力を高める。
・従業員が多様になることで、いなければ気づけなかった点に気づくことができる。その結果、より社会で求められているサービスに対応できるようになる。
・ジェンダーテーマから始まった施策も、取り組みが進んでいくと、性別に関係なく有益性の高いものへとアップデートされていく。ダイバーシティは属性でなく個体差。女性が対象であっても、女性のテーマに閉じないという意識が大切。
・組織にも個人にもアンコンシャスバイアスがあるのは当然ことで、それは悪いことではない。ただ、「自身にアンコンシャスバイアスがあるということを自覚できるか」が大切で、また、組織においては「必要のないアンコンシャスバイアスをいかに取り除ける仕組みがつくれるか」が求められる。
Q&Aセッション
日本陸連がDEIを推進するために
柏村さんの講演に続いて行われたのは、しっかりと時間をとってのQ&Aセッションです。ここでは、スポーツにおけるジェンダー問題の第一人者で、日本陸連のダイバーシティ&インクルージョン推進を担当する來田享子常務理事がファシリテート。講演に対して、「“自分自身を出していく”というのは、そのこと自体がなかなか難しく、柏村さんは、その仕組みをすごくたくさんつくってこられたのだなということを実感した」と感想を述べた來田常務理事は、「陸連で、それができるようになっていくためには、みんながいろいろな形で“これ、どうしてだろうな”と思い、それを自分が変えていくこと、(変わる)きっかけをつくっていくことが大事なのかなと思う」とコメント。事前に参加者から集めていた質問や、その場で出た参加者の声に対する見解を、柏村さんから聞いていくなかで、DEIに対する認識を深めていく形がとられました。以下、その一部をご紹介しましょう。來田:リクルート社での取り組みで、やって一番良かったこと、大切と思ったことは?
柏村:一番大事なのは「アンコンシャスバイアスの自覚とそれを取り除く制度や仕組み」。ただ、働き方を自律的に選べる環境でないと、どんなに良い制度があってもチャレンジできない。ベースとしての働き方に柔軟性があったうえでのアンコンシャスバイアスの自覚と排除が大切と考える。
來田:「その人が、その人らしく生きていないと、いろいろなことも思いつけない」ということ。陸連における働き方改革についても、こういう視点を持って取り組んでいけたらと思う。では、逆に、「やめたほうがいい」ということは?
柏村:数字だけを追いかけること。振り子が逆に振れてしまう恐れがある。本質的なところをきちんと進化させること。その結果として数字が上がることが大事だと思う。
來田:上げる数字も、意味のあるものでないといけない?
柏村:その通り。理念をあとづける数字でないといけない。
参加者A:陸連では、「数字に換算できないものが多すぎる」ことが悩み。数値化しづらいために、評価をどう測るかが課題になっている。例えば、フロントオフィスの業務も、バックオフィスの業務も、どちらもなければならない仕事だが、それぞれの働き方をどう評価するか。あるいは、日本選手権の開催は、盛大にできるほうがよいかもしれないが、やればやるほど費用や手間もかかることを考えると、何をもって成功をはかればよいのか。そういった判断が非常に難しい。また、日本選手権を含めた事業は、その年に無事に終えても、1年経つとまた同じ事業が来るので、ときに回し車のなかを走り続けているリスのような感覚に陥ることがある。その事業が、何を持って「ちゃんとなされた」と判断できるのかの判断がすごく難しいという実感がある。
柏村:働き方の評価については、会社組織でも実は同じかと思う。私たちの場合は、それぞれのミッションごとに対する成果で評価をしている。その時に大事なのは、「期初のタイミングで、このミッション(仕事)は、どのような成果が出たらどのような評価になるか、ということを本人とすり合わせて決めている」こと。途中で仕事が変わって、(評価の基準が)ずれたりすることもあるが、その都度、修正しながら進めている。そうしたことを何年も繰り返していくと、組織の中で、きちんと仕事のゴールを決めて、評価をして、フィードバックするという循環が回るようになり、それができると、それぞれの仕事をリスペクトし合えるようになっていく。時間はかかるが、実はとても大事なことといえる。
また、毎年実施するイベントや大きな大会は、ビジネスでいうプロジェクトみたいな話かと思う。確かにプロジェクトの評価は難しいが、話を聞いていて、「プロジェクト単位で評価指標を決めてやっていくことを回していく」というのを苦労しながらやっていくしかないのかなと感じた。
参加者A:今まで、仕事に就く前の段階で、「あなたにこれをやってほしい」ということをしっかり伝えきれておらず、マッチングが足りなかったのではないかという反省から、今後は、「この組織として、このポジションで、これをやってほしい」ということを伝えたうえで、当事者のやりたいことを含めて対話していこうとしている。それによって、肉付けができ、成長していけるのではないかと考えている。
柏村:すごく素敵なチャレンジだと思う。
参加者B:陸連では2017年にJAAFビジョンを作成し、そのときに、アスレティックファミリーの数の目標値を設定した。ただ、最近懸念しているのは、重要なのは「それを成し遂げたときの世界観がどうなっているか」なのに、実際には「これとこれを足したら、その(目標の)数字になる」という議論になってしまうのではないかということ。先ほどの「理念をあとづける数字でないといけない」という話を、まさにそうだなと思いながら伺った。
質問したいのは、男女の比率の関する事柄。ここ数年、スポーツ団体ガバナンスコードのなかでもずっと言われてきていて、我々の間でも取り組んできていることでもある。一方で、日本陸連の登録者で見ていくと、中学生は男女半々の比率が、高校で2対1、大学生では4対1となり、一般になると女性の比率が非常に少なくなるという現実がある。そのなかで、女性を登用していこうとするのは、審判も、コーチも、役員も含めて非常に難しいというところが課題になっている。今日の話でいうと、「それを女性の問題として捉えるのではなく、入ってこられない人がいる原因がどこにあるかを考え、どうすれば参加できるか、参加できるような環境をつくれるかという点からスタートしていくのがよいのだろうか?
柏村:これは、ビジネスの世界でもエンジニアやデーターサイエンティスト等の職種でも同じ課題に直面している。そもそも日本ではSTEM(科学・技術・工学・数学)分野に占める女性の比率が非常に低いという状況があり、その背景には、「女性は文系でいい」という社会のアンコンシャスバイアスが大きく影響しているといわれている。つまり、陸上だけの問題でなく、社会構造のなかで起きているということ。それを変えていくことは、一団体では難しいが、「現状に違和感がある」ということに対して課題設定し、団体として活動することは大事。働き方ということでは、これだけ人口が減少しているなかで、「昔からの働き方に合う人、出来る人だけでやる」こと自体が、男女関係なく難しくなっている。まずそれを認識したうえで、どうしていくかを考えなければならない。
來田:スポーツ界のDEIについて、どういうイメージをお持ちか。
柏村:本当に無知な中で、イメージで言うと、勝ち負けが明確で、基本的にデータ数字に基づいて、科学して進化に挑んでいる。さまざまなスポーツで海外交流も進むなか、スポーツ業界のほうがDEIについてはある種、進んでいるだろうなと考えている。かたや個別で見ていくと、属した時代や環境によって監督やコーチ、組織のケイパビリティ(能力や強み、特性)には差があるのではないかと思っている。画一的な教育方針やルールの中で強くなってきた場合、その再生産をしてしまうケースもあると思う。そういう観点では、集合知として進化できるポイントがありそうだなとみている。
参加者C:審判の養成で、世界大会の審判員に女性を登用したいと考えていても、蓋を開けてみると人数自体が少ない現実がある。解消するためには、もっとルーツの部分…競技者の普及レベルまで掘り下げて考えないと、引退後に指導者、審判になっていくところまで辿り着かないのではないかと感じている。例えば、企業では、若い年代や女性が入りやすくするようなことは何かやっているのか?
柏村:DEIの問題だけでなく、未来をつくる子どもたちをどう育てるかというテーマにつながることが共通項と感じた。我々も、大人だけにフォーカスしても社会は変わらないと考え、アンコンシャスバイアスにさらされている中高生をサポートすることなどを始めている。
審判員になるプロセスは、おそらく今までの当たり前や継続性を重視して構築されているのではないかと思う。そのために、「そのプロセスが本当に必要か」という問いが立てにくい状況が起きているのではないかと感じた。審判業務を全く知らない人が見ると、全く違うアプローチの提案が出てくる可能性があるかもしれない。「女性が」というよりは、審判を育成・任用するプロセス自体を、より良い形に変革させることにチャレンジしてみるのもよいかもしれないと感じた。
参加者C:確かに、「全体の公正性を考えて、朝早くから全員集合して、担当部署の役割が終わっても全体の競技が終わるまで帰れない」というような、従来からの「競技運営のカルチャー」を変えていくことも考えないと…。
柏村:「これ、いらないかも」と声を出す人がいるのは、ほかにも同じ思いの人がいることの表れであるような気がする。まさに変化させるいいタイミングといえる。賛否両論はあるかもしれないが、未来に向けたポジティブな挑戦は、団体にとってよいことだと思う。
來田:最後の質問を。DEIを進める際、管理職レベル、その少し下にいるレベルの人々、年齢層の高い人々などは意識を変えるのが難しいと言われている。そうした特定の集団にどうアプローチすればよいか?
柏村:最も苦労するのは「自分はDEIをパーフェクトにできている」と思っている人がアンコンシャツバイアスを自覚することかもしれない。まずは変わることに前向きな人たちと一緒にどんどん変えていく。変わる人が増えれば自然に全体も変わっていく。一気には無理だが、少しずつ変化させて、それを広げていくというイメージ。
◇◇◇
來田常務理事からの質問に加えて、途中には、日本陸連としての“現場のリアル”が伺えるような意見交換もあり、予定していた時間はあっという間に過ぎていきました。柏村さんは最後に「皆さんの日々の仕事や規範がわからないなかで話をさせていただいたが、皆さんは、きっとチームとして、団体として成し遂げたい世界をお持ちだと思う。そこに向けて個が生かされるのは、今の自分にとっても、未来の自分にとっても、これからこの団体にジョインする方にとってもすごくハッピーなことだと思う」と呼びかけたうえで、「もし皆さんが“もうちょっと、こうだったらいいのに”と思うことがあるのなら変えていったほうがいいし、逆に、“この団体はこのことだけは絶対に変えない”というのを決めることも、個を活かす上ではすごく大事。すべてを変えなくてはと思う必要はない」とアドバイス。「ぜひぜひ、頑張ってください」というエールの言葉で研修を締めくくりました。
文:児玉育美(JAAFメディアチーム)
関連ニュース
-
2025.10.29(水)
日本陸連が目指す「ダイバーシティ&インクルージョン」の推進「JAAF人権ポリシー」「JAAFインテグリティ行動指針」公表に際して――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより
その他 -
2025.09.10(水)
【レポート】8月8日開催「ダイバーシティ&インクルージョン 高校生ワークショップ」テーマ:インクルーシブな競技の在り方を考える
その他 -
2025.09.09(火)
WAが新たに設けた「女子カテゴリー」参加資格に関する規則への日本陸連の対応 ――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより
その他 -
2025.08.26(火)
ダイバーシティ&インクルージョンの推進「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」の制定について
その他 -
2025.05.27(火)
【レポート】3月11日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」コンプライアンス研修
その他