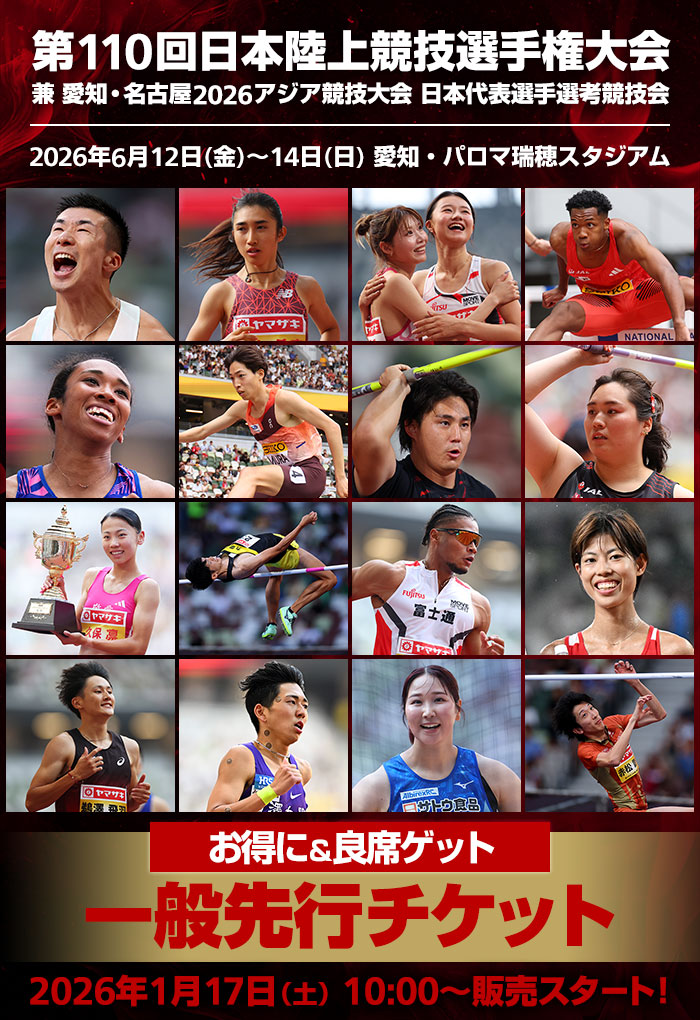活動のミッションに「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」を掲げる日本陸連では、これらを遂行していくうえで、陸上競技に関わるすべての人が、スポーツを通じて心も身体も満たされたウェルビーイング(Well-being)な状態であることを重要と捉えています。そして、この実現に向けて、リーフレットを作成・配布するなど( https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088/ )、アスリートはもちろん、アスリートを支えるすべての人が、正しく競技と向き合い、アスリートの健康を守るための知識や学びを深めていけるきっかけつくりに取り組んできました。今年は、その活動の幅を、さまざまな形でさらに広げていくことを計画しています。
1月11日には、翌日に開催される全国都道府県対抗女子駅伝に併せて、一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業協力のもと、『プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」』と題したセミナーを、京都市内で開催しました。
本セミナーの内容について、全五回に分けてお届けします。
今回は、その第一回目となります。
今回のセミナーは、全国都道府県女子駅伝に参加するチーム関係者(指導者)や保護者に加えて、陸上競技の指導者や京都近隣の方々を対象に開かれました。女性アスリートがウェルビーイングな状態でスポーツ活動に取り組み続けていくための基盤となる「発育発達期にあるアスリートの健康を守るために必要な事柄」を、パネラーとして迎えたプロフェッショナルたちと一緒に考えていこうというものです。パネラーには、日本陸連副会長の有森裕子氏、スターツ陸上競技部監督の弘山勉氏、元陸上競技選手でスポーツコメンテーターの小林祐梨子氏、日本体育大学児童スポーツ教育学部の須永美歌子氏の4名が参加。各界で活躍する豪華な顔ぶれが揃っての開催が実現しました。
当日は、まず、主催者を代表して、日本陸連においてウェルビーイングに向けた取り組みの推進役を務めている有森副会長が挨拶に立ちました。ウェルビーイングという切り口でのセミナー開催について、有森副会長は「日本陸連としては、これが初めての試み。この時間を通して皆さんと考えていく話題は、これからの若いアスリート、その指導者に対して、とても大事な内容であると私たちは考えている。このへんをどんどん意識として根づかせていかなければ、本当の意味で、世界で継続して戦えるアスリートを健康に育てていくことができない。今日は、全部を知っていただくには非常に短い時間ではあるが、皆さんと一緒に考えていけるような、そんな前向きな時間にしていきたい」と述べ、セミナーをスタートさせました。

【第1部:講義】
アスリートの健康を守ろう! ~ウェルビーイングのためにできること~
セミナーは、講義とディスカッションの2部構成で進められました。最初に行われたのが、須永氏による「アスリートの健康を守ろう! ~ウェルビーイングのためにできること~」と題した講義です。須永氏は、運動生理学やトレーニング科学研究の第一人者。運動時生理反応の男女差や、月経周期の影響について検討し、女性のための効率的なコンディショニング法やトレーニングプログラムの開発を目指す研究が専門です。日本体育大学では、大学・大学院で教鞭を執るとともに、同学が展開する女性アスリート競技力向上プロジェクト『N-FADP』のプロジェクトリーダーとして、女性アスリート特有の課題解決に向けた調査研究の成果や教育資料を発信するほか、教育プログラム( https://www.nittai.ac.jp/female_project/program )の開発や普及に取り組み、女性アスリートの育成・支援を推進。また、学外でも、日本陸連科学委員、日本体力医学会理事、日本トレーニング科学会会長を務めるなど、各方面で幅広く活躍している人物です。
「ウェルビーイングとは何か」に触れるところからスタートした今回の講義では、参加対象に併せて女性アスリートのウェルビーイングが焦点に。女性アスリートが心も身体も健康な状態で長く競技活動に取り組んでいくうえで特に大きな鍵となってくる「スポーツにおける相対的エネルギー不足(REDs)」「月経周期とコンディション」「鉄不足と貧血」について、昨年、日本陸連で製作したリーフレット( https://www.jaaf.or.jp/news/article/20088 )に記載されている基本的な知識を解説したうえで、留意すべき点や対処の方法などを、一つ一つ紹介していきました。
◎ウェルビーイングとは
・ウェルビーイングの状態を簡単に言うと、「心も身体も健康で、さらに社会的な結びつきが良好である」こと。日本陸連としては、選手たちのウェルビーイングを生涯にわたって整えていきたいと考えている。しかし、現在、スポーツ界においては、その実現を阻む健康障害が問題になっている。◎スポーツにおける相対的エネルギー不足(REDs)
・いろいろな健康問題のベースとなってくるといえるのが「スポーツにおける相対的エネルギー不足(REDs=レッズ)」。エネルギー不足による問題は、以前は女性アスリートの三主徴(エネルギー不足、無月経、骨粗しょう症)など女性特有の側面ばかりがクローズアップされていたが、研究が進んだ今では、男女に関係なく、身体全体の機能に障害を招き、発育発達や認知機能、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼす重大な要因でなることがわかっている。当然、その状態で競技活動を続けていると、筋力や持久力も低下し、ケガのリスクも高まる。同じトレーニングをしても食事で十分なエネルギーを取れている選手と、そうでない選手とでは、パフォーマンスに大きな差が出てくる。・REDsに陥っているかどうかを正しく判断するためには、エネルギーの摂取量と消費量をすべて調べて算出する必要があるが、①疲れがなかなかとれない、②筋力トレーニングをしても筋肉量が増えない、③疲労骨折や貧血と診断されたことがある、④月経が来ない(15歳になっても初経を迎えていない、月経が3カ月以上止まっている)などの自覚症状は、エネルギー不足のチェック項目と考えることができる。
・エネルギー不足を防ぐために、最も強く勧めたいのは糖質の摂取。一般的には低糖質や糖質を抜くダイエットも流行っているが、エネルギーとして糖質を使うアスリートの場合は、糖質を抜くことはありえない。肥満予防のアプローチとアスリートの身体つくりのためのアプローチは別と考えるべき。アスリートにおいては、大まかな目安にはなるが、1日1~3時間練習を行う場合、体重1kgあたり6~10g(体重50kgなら300~500g)は摂ることを心掛けたい。
・IOC(国際オリンピック委員会)は、選手のエネルギー不足による健康障害や摂取障害、さらにドーピングに繋がる行動に結びつく恐れがあるとして、特に18歳未満のアスリートには医学的目的以外は体組成の評価は行うべきでないという指針を出している。個人的には全く測定しなくてよいのかという疑問もあるが、IOCは、そのくらい体重や体脂肪率の数値のとらえ方、管理の仕方に、十分な注意が必要であると訴えていることを指導者は知っておいてほしい。
・中高校生アスリートがスポーツに取り組むうえでは、「Health first, Performance second(健康第一、パフォーマンスは第二)」。なんとしても子どもたちの健康を守りながら、パフォーマンスの向上を目指していかなければならない。
◎月経周期とコンディション
・月経については、まず、選手の月経が正常であるのかどうかを見極めることが難しい。特に指導者が男性の場合は、選手側は言えない(言いづらい)、指導者は聞けない(聞きづらい)という問題も起こりがち。しかし、指導者が医学的な知識として、正常な月経周期、周期の数え方、月経の期間や経血量の捉え方、不正出血など、チェック項目となる事柄を知っておくことは非常に大切。・女性アスリートは月経周期に伴う女性ホルモンの増減によって、心身のコンディションに変化が生じる。私が実施した調査では、月経中と月経前にコンディションが悪くなる選手が多かったが、全く関係ないという選手も一定数存在し、個人差が大きいことがわかる。それだけに、本当に月経周期がコンディションに影響しているのかどうかは、選手当人や指導者が見極めなければならない。
・月経中や月経前に調子が悪くなる原因としては、まずは月経困難症を挙げることができる。これには、病気が原因である場合とそうでない場合(プロスタグランジンの分泌量が増え、子宮が過剰に収縮することが強い痛みとなる)がある。日常生活に支障が生じる症状が出る場合は、婦人科に行くことを勧めたいが、もし、痛み止めの市販薬を服用する場合は、ドーピングにひっかからないものであるかを調べて利用する。この場合、プロスタグランジンの分泌を抑えられるよう、痛みが弱いうちに飲むのがポイントであることを、知っておいてほしい。
・月経前症候群(PMS)は、周期的に症状が出ることが特徴。婦人科の診察でも使われるチェック項目があり、そこに挙がっている症状が、過去3サイクルにわたって月経前に認められた場合は、PMSとして認められる。
・実際の指導場面において、PMSのなかでアスリートが非常に気にするのは体重の増加といえるだろう。また、ネガティブな精神的症状が出るために、選手が普段とは異なる受け止め方をするケースがあることも知っておきたい。月経周期に向き合って、選手の体重変化や、そのときの精神状態などを観察・記録するなどして把握していくことは、コンディショニングにおいて非常に大切になってくる。
・月経前の体重が増加することが多いが、その正体は水分。増加する女性ホルモンが水分を溜め込んでしまうことによって生じる。体重増加やむくみが気になる場合は、ナトリウム(塩分)の多い食品を避ける、調理などでナトリウムを減らす工夫をするとよい。
・月経の問題は、なかなか口にしにくい問題でもあるが、まずは、中・高校生が、周りの大人に相談できるような環境をつくっていくことが重要。男性が指導者の場合、月経について発言するのはセクシャルハラスメントになるのではと心配する人もいるが、学校の教育やスポーツチームにおいて、健康やトレーニングに関する専門的な話題であれば、適切かつ必要なコミュニケーション。もちろん言い方や、女性アスリートに対する教育は重要だが、ぜひ、一緒に考えていけるようになってほしい。また、自分の身体に不調があるときに、それを言葉で指導者に伝えられることは、アスリートとして非常に重要な能力。もし、女性アスリートのほうが「恥ずかしい、言いたくない」というのであれば、それは教育によって変えるべき。そういった時に、なぜ、月経周期と向き合わなければいけないのかを、指導者としてきちんと伝えていきたい。
◎鉄不足と貧血
・貧血になると、立ちくらみや息切れ、疲れやすさなどの自覚症状が出る。しかし、自覚症状だけで判断してよいものではない。貧血を疑う症状があった場合は、病院に行って、まずは血液検査をすることが必須。ヘモグロビンやフェリチンの数値を測定し、そのうえで診断へと進む。治療に向けて、この正しい手続きを必ず踏んでほしい。・貧血に関しては、日本陸連の医事委員会で、アスリートの貧血対処7か条( https://www.jaaf.or.jp/medical/anemia7.html )や、不適切な鉄剤注射の根絶を目指して公表したガイドラインに関するパンフレットやリーフレット( https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/ )を制作している。基本的な知識や治療のための必要な情報が盛り込まれているので、参考にしてほしい。
・貧血の診断が出たとき、あるいは貧血を防ぐために、まず取り組まなければならないのは食事の改善。鉄を含む食品(ヘム鉄、非ヘム鉄)をバランスよくしっかり摂ること、1日3回の食事でこまめに摂る(鉄は1回で吸収される量が決まっているので、余分なものは排泄されてしまう)ことを心掛ける。また、鉄は吸収率が本当に悪いことが特徴。このため鉄の吸収を高めるタンパク質やビタミンCなどを多く含むものとの食べ合わせによって吸収率をアップさせるよう工夫したい。逆に、お茶やコーヒーなど食べ合わせると鉄の吸収を妨げるものもある。治療中の場合は避けたほうが望ましい。
・忘れてはならないのが、鉄は、「取りすぎると毒になる」ということ。体内の鉄分が過剰になりやすい鉄剤注射は、治療として医師がどうしても必要と判断した場合にのみ用いられる手段。競技パフォーマンス向上も含めて、それ以外の目的で用いることはすべて不適切であり、急性・慢性ともに重篤な症状や疾患を招く危険があることを正しく知り、食事で鉄を補給することを大前提としてほしい。
文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)
今後の掲載予定
#2 パネルディスカッション
アスリートの健康管理とパフォーマンス「相対的エネルギー不足(REDs)のリスクと予防」
#3 パネルディスカッション
女性アスリート特有の課題「月経周期とコンディション」
#4 パネルディスカッション
鉄不足と貧血「鉄不足がパフォーマンスと健康に与える影響」
#5 パネルディスカッション
精神的健康とモチベーションの維持「長距離選手におけるメンタルヘルスと社会的サポートの重要性」
準備でき次第、順次掲載をしていきます!
関連ニュース
-
2025.07.01(火)
【アスリート委員会】が迷惑撮影に対する声明を発表しました!
委員会 -
2025.05.28(水)
指導者セミナー ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」
その他 -
2025.03.07(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#5
その他 -
2025.02.28(金)
【JAAFウェルビーイングセミナー】プロフェッショナルとともに考える「女性アスリート×ウェルビーイング」#4
その他 -
2025.02.21(金)
【Well-being指導者向けセミナー 受講者募集】『ウェルビーイングとは?「指導者と考えるこころとからだの健康」』
その他