 バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちら
バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちらTALK × TALK

第二回RIKUJOJAPANスペシャル対談陸上でスポーツ界、ニッポンを変えていく。
陸上の可能性と未来を考える『RIKUJO JAPAN』プロジェクト。今回のスペシャル対談は、「陸上現場をつくっていく人」「陸上現場を支えていく人」に登場いただいた。オリンピックメダリストで、日本陸連副会長をはじめ数々の場面で要職を務める有森裕子氏、日本陸連オフィシャルスポンサーとして日本の陸上界をがっちりとサポートする株式会社アシックスの常務執行役員でスポーツマーケティングのスペシャリストである甲田知子氏、そして、トップスプリンターから引退したのちビジネスパーソンとして活躍し、昨年度から日本陸連専務理事に就任して日本陸上界の舵を取る田﨑博道氏の3人だ。
田﨑専務理事のナビゲートで進んだ対談では、豊富な人生経験を背景とする3人ならではの忌憚のない貴重な意見が続出! 『RIKUJO JAPAN』が目指す「2040年の世界」実現に向けて、今、日本の陸上界がやるべきことが、くっきりと浮かび上がってきた――。

有森裕子Yuko ARIMORI日本陸上競技連盟副会長。日本体育大学を経て、リクルート入社後にマラソンで頭角を現し、1992年(銀)、1996年(銅)と、2大会連続で五輪メダルを獲得。日本陸上界で初めて名実ともに「プロ」として活動した選手でもある。引退後は、NPO法人「ハート・オブ・ゴールド」、マネジメント会社設立をはじめ、スポーツ界と社会を繋ぐ様々な場面で活躍。現在も、日本陸連副会長のほか、国際オリンピック委員会Olympism365委員会委員、ワールドアスレティックスカウンシルメンバー、大学スポーツ協会副会長等、各方面で要職を担う。

甲田知子Tomoko KODA株式会社アシックス常務執行役員。高校・大学とバスケットボールの強豪チームで活動。大学卒業後、日本生命、IBMにて業務推進を担当。1997年ナイキジャパンに入社し、14年間マーケティング部にてブランド戦略、広告宣伝のディレクターとしてマーケティングをリード、その後3年間同社にてカテゴリービジネスのGMとしてトレーニング、野球のビジネスの成長に取り組む。2016年アシックスにマーケティング統括部長として入社。2019年執行役員に就くと、2022年からは常務執行役員に就任。同社のマーケティング、スポーツマーケティング、広報部門を率いて現在に至る。

田﨑博道Hiromichi TASAKI日本陸上競技連盟専務理事。中学・高校時代からスプリンターとして活躍。慶應義塾大2年時の1976年日本選手権で男子100mを制している。大学卒業とともに競技から退き、東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)に入社。同社常務執行役員(2012年~)、同社代表取締役専務執行役員(2016年~)を歴任。株式会社東京海上日動キャリアサービス代表取締役社長(2018~2022年)、一般社団法人日本人材派遣協会会長(2020~2022年)の要職を経て、2023年6月より現職を務める。
「こうなりたい」2040年の姿
 田﨑:日本陸上競技連盟専務理事の田﨑博道です。
田﨑:日本陸上競技連盟専務理事の田﨑博道です。
私は、大学までは陸上競技を一所懸命にやり、それ以降は陸上の世界から離れて生活を送ってきました。4年前に、アスリートの人材育成という側面に関わったことがきっかけで連盟とのご縁ができまして、現在に至っています。
今日は貴重な時間をいただきましたので、ぜひ、いろいろなお話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 甲田:甲田知子と申します。株式会社アシックスでマーケティング、スポーツマーケティング、広報、あとパラスポーツ企画部の管掌をしています。
甲田:甲田知子と申します。株式会社アシックスでマーケティング、スポーツマーケティング、広報、あとパラスポーツ企画部の管掌をしています。
私、学生時代まではバスケットボールをやっていて、ずっとアシックスのシューズを履いていたんですね。最終的に、やっぱり日本のスポーツブランドを元気に、グローバルに、ということで、今のお仕事をさせてもらっています。今日は、ご一緒できることを本当に光栄に思っています。ありがとうございます。
 有森:有森裕子です。中学はバスケットボール部で、高校から陸上部。鳴かず飛ばずで大学を卒業して、実業団に入って、やっと芽が出て、たくさんの皆さんに支えられてオリンピックまで行きました。今現在、日本陸上競技連盟の副会長を…役立っているかどうかわかりませんが…笑、やらせていただいています。よろしくお願いします。
有森:有森裕子です。中学はバスケットボール部で、高校から陸上部。鳴かず飛ばずで大学を卒業して、実業団に入って、やっと芽が出て、たくさんの皆さんに支えられてオリンピックまで行きました。今現在、日本陸上競技連盟の副会長を…役立っているかどうかわかりませんが…笑、やらせていただいています。よろしくお願いします。

 田﨑:では、始めましょうか。まずは、お話を伺う前段として、今、日本陸上競技連盟が何に取り組んでいこうとしているのかを、少し整理してご説明しますね。
田﨑:では、始めましょうか。まずは、お話を伺う前段として、今、日本陸上競技連盟が何に取り組んでいこうとしているのかを、少し整理してご説明しますね。
日本陸連では、中長期計画として「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」の2つを、ミッションとして掲げています。2040年に国際競技力でアジアNo.1、そして世界トップ3になることを、そして「ウェルネス陸上の実現」として、陸上を楽しんでいる人口を2000万人に増やすことを、それぞれ目標に掲げて達成しようとしているんです。
2040年というと、今5歳の子が20歳になっているころです。スポーツでいうなら、20歳はオリンピックで戦う日本代表選手の主力層かもしれないわけです。そうすると、そうした人たちが元気に活躍できるような「何か」を、今、私たちがしていかなければならないということになります。
そういう意味で、より具体的に2040年の日本が“こんな状態になっていたらいいよね”という世界観みたいなものをつくって、それを発信していったらどうだろう?という話になったわけです。そして、「たくさんの人に共感してもらえるような、そんな動きが起きてほしいな」という願いを込めて、みんなで検討してきました。
ここで、私たちが描いた「こうなりたい2040年の日本」をご紹介したいと思います。
2040年、日本の陸上競技界は躍動していた。オリンピック100m決勝進出8名のうち2人の日本人選手が出場。一人が日本人初の金メダルを獲得した。様々な種目において力を発揮し始めた日本選手たちは世界中から注目を集め、アジアNo.1の地位を不動のものとしていた。
この壮大な進化の背景には、街角のあらゆる場所に設置された特別な設備があった。全国の公園、運動場、さらにはゲームセンターには、市民誰もが自由に使用できる30m走のタイム測定器が設置されていた。100分の1秒まで測れるこれらの設備は、老若男女を問わず、誰もが短距離走の楽しさに親しむことを可能にしていた。
ある日のこと、東京の小さな公園にて、年配の夫婦が微笑みながら30m走の挑戦を楽しんでいた。隣では、若いカップルが互いのタイムを競い合い、高揚した笑い声が響いていた。子供たちは、プロアスリートのような真剣さでタイムを測り、その結果に歓声を上げていた。この熱狂は、まるで国民全体が一つの大きな競技会に参加しているかのようだった。
毎週末、家族連れや友達同士が集まり、お互いの記録を更新し合っていた。学校では、子供たちが陸上の授業で新たな記録を目指し、教師たちは彼らの熱意を全力でサポートしていた。クリスマスや誕生日のプレゼントには、少しでも速く走れるランニングシューズが次々と購入されていた。
この運動熱は、社会全体にも良い影響を与えていた。市民の健康意識が高まり、公共施設への投資が増え、さらには地域コミュニティの絆が深まっていた。スポーツビジネスは社会に出る若者たちの一番就きたい仕事になっていた。多くの子供たちが世界で活躍するアスリートを目指し、陸上で鍛えられたアスリートがサッカーや野球など、陸上以外のスポーツでもかつてない活躍をし始めた。
日本中の人々が、それぞれの場所で汗を流し、笑顔を分かち合うことで、国はただ強いだけでなく、一体感のある温かい社会へと変貌を遂げていた。2040年の日本は、陸上競技を通じて、まさに新たな黄金時代を迎えていたのだ。
工夫次第で、2040年を待たずに実現できる!?
 田﨑:これが我々の目指す世界観です。いかがでしょうか。
田﨑:これが我々の目指す世界観です。いかがでしょうか。
 有森:2040年の前にできちゃいそうな気がします。そうなるためのイメージも浮かんできました(笑)。
有森:2040年の前にできちゃいそうな気がします。そうなるためのイメージも浮かんできました(笑)。
 田﨑:そういうことが、すでに起きているということですか?
田﨑:そういうことが、すでに起きているということですか?
 有森:例えば、バスケットボールは街とか公園とかに行くと、ちょっとしたスペースにバスケットゴールが設置されていることもあるんじゃないかと…。競技を見に行かなくても日常的に目のつくところにある、その身近さも、バスケットボール熱が高まった背景の一つにあるんじゃないかと思うんですよね。
有森:例えば、バスケットボールは街とか公園とかに行くと、ちょっとしたスペースにバスケットゴールが設置されていることもあるんじゃないかと…。競技を見に行かなくても日常的に目のつくところにある、その身近さも、バスケットボール熱が高まった背景の一つにあるんじゃないかと思うんですよね。
陸上って、「マザー・オブ・スポーツ」と言われています。それはなぜかというと、人間が生きていくうえでベースとなるもの…基本的な体力とか、必要な全ての動きとかが、全部混ざっているからなんです。そう考えると、ちょっと工夫すれば、もっと日常生活のなかに簡単に取り入れていけると思うんですよ。例えば、公園の中に目安にできるようなラインを入れてみるとか、散歩道のコースに距離表示を入れたりトラックのレーンのようなラインを引いてみたり。砂場とか、高さのある壁とかがあるのなら、そこに世界記録や日本記録を実際に示して見せたり、そういう見せ方はいくらでもあって。もし、そういうことが、今年からできていくようであれば、2040年まで待たなくても、もっと早く、そういう世界が実現するんじゃないかなと思ったんです。

 田﨑:すごく具体的な話ですね。そう考えると、掲げた世界観が、はるか先にあるような夢ではなく、近い将来に実現できる、そういう期待感が出てきますね。
田﨑:すごく具体的な話ですね。そう考えると、掲げた世界観が、はるか先にあるような夢ではなく、近い将来に実現できる、そういう期待感が出てきますね。
 甲田:アシックスでは、「VISION2030」という将来ありたい姿を設定していて、「誰もが一生涯、運動・スポーツに関わり心と身体が健康で居続けられる世界の実現」というのを目指しています。たぶん、同じ世界を描いている人たちがたくさんいると思うんですよ。今、田﨑さんがおっしゃったのは、陸上競技としてのお話でしたが、そこにいろいろなスポーツが入ってきて、それをみんなで一緒にやると、実現するタイムラインはもうちょっと前倒しができるのかなと、聞いていて思いました。
甲田:アシックスでは、「VISION2030」という将来ありたい姿を設定していて、「誰もが一生涯、運動・スポーツに関わり心と身体が健康で居続けられる世界の実現」というのを目指しています。たぶん、同じ世界を描いている人たちがたくさんいると思うんですよ。今、田﨑さんがおっしゃったのは、陸上競技としてのお話でしたが、そこにいろいろなスポーツが入ってきて、それをみんなで一緒にやると、実現するタイムラインはもうちょっと前倒しができるのかなと、聞いていて思いました。
実現の鍵となるのは…?
 田﨑:「もう少しやったらできるよね、実現するよね」ということだとすると、その「もう少し」というのは、どんなところだと思いますか?
田﨑:「もう少しやったらできるよね、実現するよね」ということだとすると、その「もう少し」というのは、どんなところだと思いますか?
 有森:公共施設に対する入り込みじゃないですかね。陸上って、さっきも言ったように「マザー・オブ・スポーツ」で、人間に一番近い、親しみやすい競技であるのだけれど、競技会になると、めちゃくちゃ遠いんですよ。あの大きなスタジアムで、1周400mもあるトラックで囲まれているわけで、そのなかで競技をやっている選手たち、めちゃくちゃ小さいじゃないですか。特に、フィールド競技は遠いんですよ。遠くから見るので、そのすごさが実感しづらい状態が起きているんですね。
有森:公共施設に対する入り込みじゃないですかね。陸上って、さっきも言ったように「マザー・オブ・スポーツ」で、人間に一番近い、親しみやすい競技であるのだけれど、競技会になると、めちゃくちゃ遠いんですよ。あの大きなスタジアムで、1周400mもあるトラックで囲まれているわけで、そのなかで競技をやっている選手たち、めちゃくちゃ小さいじゃないですか。特に、フィールド競技は遠いんですよ。遠くから見るので、そのすごさが実感しづらい状態が起きているんですね。
だから、なるべく日常的にそのすごさが感覚的にわかるような場面を、どれだけつくっていけるか。そこで感じたすごさを、「本物を見に行きたい!」という気持ちにさせて、足を運ばせる…。
 田﨑:それが競技場?
田﨑:それが競技場?
 有森:はい、競技場です。そうであれば、もうすごさは日常でわかっているから、遠くに見ることになっても、具体的な実感をもって見ることができる。そういう人の寄せ方が足りていないと思いますね。だから子どもからお年寄りまでが日常的に接する場に、どれだけ落とし込んだ工夫ができるか。高さ、幅、速さ、重さ…そういったものを感じられるような、「へえーっ!!」って思うような場所を増やしていくと楽しいし、みんなのアイデアでつくっていくことができるんじゃないかと思うんですよね。
有森:はい、競技場です。そうであれば、もうすごさは日常でわかっているから、遠くに見ることになっても、具体的な実感をもって見ることができる。そういう人の寄せ方が足りていないと思いますね。だから子どもからお年寄りまでが日常的に接する場に、どれだけ落とし込んだ工夫ができるか。高さ、幅、速さ、重さ…そういったものを感じられるような、「へえーっ!!」って思うような場所を増やしていくと楽しいし、みんなのアイデアでつくっていくことができるんじゃないかと思うんですよね。
 田﨑:日本陸連には、キッズ向けプログラム『キッズデカスロンチャレンジ』というキッズ向けのプログラム(通称:デカチャレ)があるんですね。これは、「キング・オブ・アスレティックス」と呼ばれる十種競技(デカスロン)にちなんで、多種目の基本運動(走・跳・投)に子どもたちがチャレンジできるようアレンジしたものです。有森さんもおっしゃっていた運動の基本を、子どもたちが遊び感覚で、楽しみながらできるようにして伝えていこうということで始めて、主催大会のときなどに、スタジアムの内外で実施していく取り組みを広げています。今、有森さんが言われたことは、そういう「伝わらないものを伝えていく努力を、もう少ししようよ」ということなのかなと感じました。
田﨑:日本陸連には、キッズ向けプログラム『キッズデカスロンチャレンジ』というキッズ向けのプログラム(通称:デカチャレ)があるんですね。これは、「キング・オブ・アスレティックス」と呼ばれる十種競技(デカスロン)にちなんで、多種目の基本運動(走・跳・投)に子どもたちがチャレンジできるようアレンジしたものです。有森さんもおっしゃっていた運動の基本を、子どもたちが遊び感覚で、楽しみながらできるようにして伝えていこうということで始めて、主催大会のときなどに、スタジアムの内外で実施していく取り組みを広げています。今、有森さんが言われたことは、そういう「伝わらないものを伝えていく努力を、もう少ししようよ」ということなのかなと感じました。
 甲田:「マザー・オブ・スポーツ」ということで考えると、幼稚園とか保育園とかの段階で、一番最初にやるのは「かけっこ」なんですよね。そういう意味で、陸上 って、誰もが一番最初に関わるスポーツで、その年齢から入っていくことができるわけです。ただ、これは、うちの近所の話だけかもしれないけれど、陸上教室みたいなものを小学校でやっていると、低学年のころは参加する子どもがすごく多いのに、高学年になると減っていくんですね。サッカーに行き、どこどこに行き…と、ほかのスポーツに行く子どもが増えてくるから。もしかしたら、「なんで、そこで陸上から離れていってしまうのか」というところに、何か気づきのようなものがあるかもしれませんね。
甲田:「マザー・オブ・スポーツ」ということで考えると、幼稚園とか保育園とかの段階で、一番最初にやるのは「かけっこ」なんですよね。そういう意味で、陸上 って、誰もが一番最初に関わるスポーツで、その年齢から入っていくことができるわけです。ただ、これは、うちの近所の話だけかもしれないけれど、陸上教室みたいなものを小学校でやっていると、低学年のころは参加する子どもがすごく多いのに、高学年になると減っていくんですね。サッカーに行き、どこどこに行き…と、ほかのスポーツに行く子どもが増えてくるから。もしかしたら、「なんで、そこで陸上から離れていってしまうのか」というところに、何か気づきのようなものがあるかもしれませんね。

 田﨑:楽しさが続いていかないのかな?
田﨑:楽しさが続いていかないのかな?
 有森:楽しさというより、やっぱり陸上でやれていることは、「何かに生かす」ことがベースなんですよ。だから、陸上をずっと続けてエキサイトするというイメージよりは、それを使ってサッカーボールを追いかけるとか、「それを使って」ということに、小学校くらいだとなってしまいやすいのかなと思いますね。だから、そこで、「陸上を追求していくと、こうなんだよ」ということを見せられるかどうかなのかなと思います。
有森:楽しさというより、やっぱり陸上でやれていることは、「何かに生かす」ことがベースなんですよ。だから、陸上をずっと続けてエキサイトするというイメージよりは、それを使ってサッカーボールを追いかけるとか、「それを使って」ということに、小学校くらいだとなってしまいやすいのかなと思いますね。だから、そこで、「陸上を追求していくと、こうなんだよ」ということを見せられるかどうかなのかなと思います。
世界室内で実感した
「ショートトラック」の面白さを子どもたちに
 有森:今、ちょうど運動会の話が出ましたけれど、今年、室内の世界選手権(世界室内)を見に行く機会があったんですね。陸上の室内大会って、ショートトラックといって、1周200mのトラックで行われるのですが、そこでのレースが、めちゃくちゃ面白かったんですよ。小学校の運動会って、1周200mくらいのトラックをつくってやりますよね。子どもたちが見たら、きっと「自分が運動会で走ったのと同じ200mのトラックを、あんなに速く走るんだ!」と驚くと思うし、「こんなに投げているんだ」「こんなに跳ぶんだ」と実感できるはず。そういうのを知ると、「自分もやってみたい」という気持ちになるんじゃないかと思ったんですね。
有森:今、ちょうど運動会の話が出ましたけれど、今年、室内の世界選手権(世界室内)を見に行く機会があったんですね。陸上の室内大会って、ショートトラックといって、1周200mのトラックで行われるのですが、そこでのレースが、めちゃくちゃ面白かったんですよ。小学校の運動会って、1周200mくらいのトラックをつくってやりますよね。子どもたちが見たら、きっと「自分が運動会で走ったのと同じ200mのトラックを、あんなに速く走るんだ!」と驚くと思うし、「こんなに投げているんだ」「こんなに跳ぶんだ」と実感できるはず。そういうのを知ると、「自分もやってみたい」という気持ちになるんじゃないかと思ったんですね。
そういう形で、子どもたちに「最高の、最速の、最強のもの」を見せて、陸上というものの意味に落とし込むということが、できなくはないなって…。「すごい!これ、運動会の最高バージョンじゃん!」みたいな感じで(笑)。きっと、子どもたちが見ても、めちゃくちゃ面白いと感じるんじゃないかと思いました。
 田﨑:さっきちょっと触れたデカスロン(デカチャレ)は、とにかく「走る」「投げる」「跳ぶ」というシンプルな行動を体験してみるというところで、子どもには入りやすいんですよね。そして、我々がその様子を見ていて、すごく思うのは、「親も興奮する」ということ。一緒になってやり始めちゃうような親も出るほどなんです。そういう意味では、「身体を動かすことの嬉しさ、楽しさ」みたいなものが、どこかにちゃんと残っているような形で、「次のステージ」「次のステージ」と見せていけるようにすることが大事だなというのを、今の話からも感じますね。
田﨑:さっきちょっと触れたデカスロン(デカチャレ)は、とにかく「走る」「投げる」「跳ぶ」というシンプルな行動を体験してみるというところで、子どもには入りやすいんですよね。そして、我々がその様子を見ていて、すごく思うのは、「親も興奮する」ということ。一緒になってやり始めちゃうような親も出るほどなんです。そういう意味では、「身体を動かすことの嬉しさ、楽しさ」みたいなものが、どこかにちゃんと残っているような形で、「次のステージ」「次のステージ」と見せていけるようにすることが大事だなというのを、今の話からも感じますね。
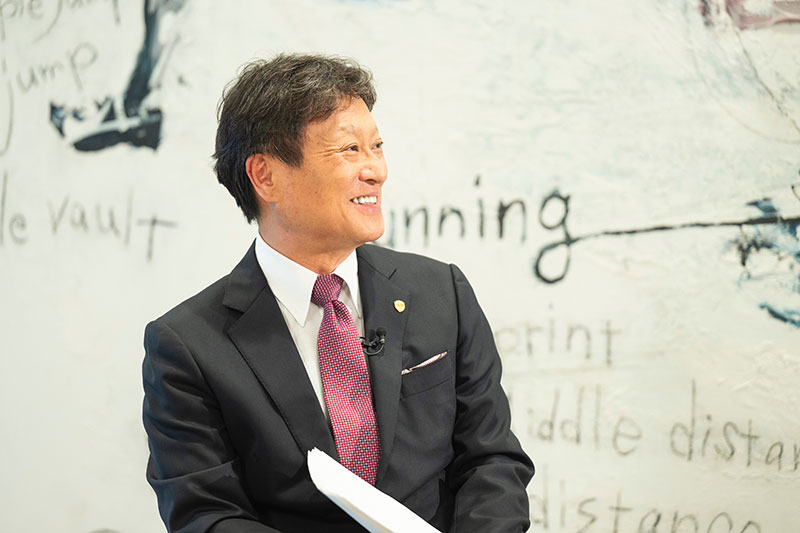
「場をつくっていく」ために必要な視点
 田﨑:「場をたくさんつくっていく」「いろいろなステージをつくっていく」という意味では、行政を含めて地域社会や企業に対して我々が働きかけていくことが大事だなと思いますね。
田﨑:「場をたくさんつくっていく」「いろいろなステージをつくっていく」という意味では、行政を含めて地域社会や企業に対して我々が働きかけていくことが大事だなと思いますね。
 甲田:そうですね。そうなると、露出が重要になりますね。テレビとかの電波じゃなくても、今は、SNSもありますし。チラシとかでも効果はある。実は、小学校って、毎週すごい数のチラシが回ってくるんですけど、競技間の競争なんですよ、もう。で、そのなかで圧倒的に頑張ってるのはサッカーなんです。
甲田:そうですね。そうなると、露出が重要になりますね。テレビとかの電波じゃなくても、今は、SNSもありますし。チラシとかでも効果はある。実は、小学校って、毎週すごい数のチラシが回ってくるんですけど、競技間の競争なんですよ、もう。で、そのなかで圧倒的に頑張ってるのはサッカーなんです。
 田﨑:子どもの取り合いってことですか?
田﨑:子どもの取り合いってことですか?
 甲田:取り合いですね。そういう意味では本当にいろいろな媒体があるなかで、どうやって陸上の魅力を伝えていけるか、なんですよね。スポンサーもいろいろな媒体を持っていることを考えると、やっぱりみんなで発信していくのが大切なのかなとも思いますね。
甲田:取り合いですね。そういう意味では本当にいろいろな媒体があるなかで、どうやって陸上の魅力を伝えていけるか、なんですよね。スポンサーもいろいろな媒体を持っていることを考えると、やっぱりみんなで発信していくのが大切なのかなとも思いますね。
さっき、イベント(デカチャレ)の話をしてくださいましたが、私たちもイベントをよくやっているんですね。子どもが走るとか、大人も走ろうとか、いろいろあるわけですが、その1回は走るけれど、走り続けるとか、やり続けるとかいう場所が、もしかしたら、先ほど挙がった自治体とか、公共の場とかに、うまく流してあげる、そういう仕組みをつくってあげるといいかなと思います。
 有森:それはすごくありますね。土・日は圧倒的にイベントとかで、(そのスポーツを)知ってもらえるけれど…。
有森:それはすごくありますね。土・日は圧倒的にイベントとかで、(そのスポーツを)知ってもらえるけれど…。
これ、トレーニングと一緒だと思うんですよ。よくマラソンを走りたい人は、練習する時間のことを気にするのですが、練習って、別に時間のある土日だけじゃないんですよね。日常も、朝起きて自分が寝るまで動いているし、仕事場までの往復もあるし、一つ手前の駅で降りて歩けば、それが練習の距離になるわけです。それと同じで、イベントをした時だけのものではなくて、それが終わったあとの次の月曜日にもつながってほしいですね。例えば、ホテルなどでは、最近よく、散歩マップやランニングマップが置かれていますよね。ああいったものが地域でつくられていたら…。
 甲田:いいですね。
甲田:いいですね。
 有森:そういう案を、公共の場をつくる自治体に出して、街全体の健康増進につなげるのに、陸上というものが何かしら見え隠れしていたらいいんじゃないかな、と思うんです。もしかしたら、すぐに「陸上」という意識に結びつかないかもしれないけれど、そうしたことを通じて、陸上を忘れないでいくという流れがつくっていけるような気がします。
有森:そういう案を、公共の場をつくる自治体に出して、街全体の健康増進につなげるのに、陸上というものが何かしら見え隠れしていたらいいんじゃないかな、と思うんです。もしかしたら、すぐに「陸上」という意識に結びつかないかもしれないけれど、そうしたことを通じて、陸上を忘れないでいくという流れがつくっていけるような気がします。
私は、スポーツもあくまで人間社会のなかの一つのものだと思っているので、「陸上」だけに特化した説明や見せ方ではダメだと考えているんです。この点は、オリンピックも含めてスポーツすべてにいえることで、「競技、スポーツ=特別」ではダメ。「すべては人間社会の日常という土台があっての存在ですよ」と。だから、そこを無視した、そことは関係ないという考えを一つでも持ってしまったら意味をなさないし、継続もしないというくらいの意識を、もうそろそろ持つべきです。そうしないと、陸上も含めてスポーツ界が、本当の意味で社会に浸透して、すべての人を巻き込んだものにしていくことはできないんじゃないか。そういうことを、ここ数年で随分感じています。

超高齢化社会の2040年
陸上は、地域社会の元気の源になる!
 田﨑:冒頭では、2040年について、「描いた世界観になるには、そこまでかからないよ」という話も出ましたが、一方で、2040年の日本は、本当に超高齢社会になっているんですよね。日本が元気でいるために、陸上はどういう存在になれるか。ここまでの話を聞いていて、自治体など地域社会が鍵になるのなら、地域行政とか地域に関わる人々に、陸上の持つ本質的価値を具体的に伝えていかなきゃいけないな、と思いました。また、そのためには、先ほども少し出ていた「運動会」という場が一つのカギになるようにも思うんです。「陸上って、運動会みたいだよね」ということになると、陸上はまさに地域社会にとっての運動会のような存在に、これからの日本の元気の源になるんじゃないかと感じました。
田﨑:冒頭では、2040年について、「描いた世界観になるには、そこまでかからないよ」という話も出ましたが、一方で、2040年の日本は、本当に超高齢社会になっているんですよね。日本が元気でいるために、陸上はどういう存在になれるか。ここまでの話を聞いていて、自治体など地域社会が鍵になるのなら、地域行政とか地域に関わる人々に、陸上の持つ本質的価値を具体的に伝えていかなきゃいけないな、と思いました。また、そのためには、先ほども少し出ていた「運動会」という場が一つのカギになるようにも思うんです。「陸上って、運動会みたいだよね」ということになると、陸上はまさに地域社会にとっての運動会のような存在に、これからの日本の元気の源になるんじゃないかと感じました。

 甲田:そうですね。運動会は、子供たちだけでなく家族みんなが行く…。
甲田:そうですね。運動会は、子供たちだけでなく家族みんなが行く…。
 有森:会社でも運動会、しますものね。
有森:会社でも運動会、しますものね。
 田﨑:ところが最近では、地域も、会社も運動会しないんですよ。
田﨑:ところが最近では、地域も、会社も運動会しないんですよ。
 有森:運動会は、やっていないけれど、マラソン大会にはいっぱい来ていますよ、企業から。マラソン大会…、運動会にしちゃえばどうなんでしょう。マラソン大会って、今、全国津々浦々にあるわけですよ。ここに、陸上の内容を絡めたらどうですか?陸上全体の楽しさを見せるコーナーをつくるとか、マラソンをやっている42kmって、ずいぶん時間がかかりますから、その間にトラックの中でデカスロン(デカチャレ)をやるとか…。
有森:運動会は、やっていないけれど、マラソン大会にはいっぱい来ていますよ、企業から。マラソン大会…、運動会にしちゃえばどうなんでしょう。マラソン大会って、今、全国津々浦々にあるわけですよ。ここに、陸上の内容を絡めたらどうですか?陸上全体の楽しさを見せるコーナーをつくるとか、マラソンをやっている42kmって、ずいぶん時間がかかりますから、その間にトラックの中でデカスロン(デカチャレ)をやるとか…。
 田﨑:やってはいます。ただ、それをすごく前面に押し出しているというわけじゃなくて…。ちょっとまあ遠慮気味にやっているのかな。だから、もうちょっと、胸を張っていけばいいって話ですかね?
田﨑:やってはいます。ただ、それをすごく前面に押し出しているというわけじゃなくて…。ちょっとまあ遠慮気味にやっているのかな。だから、もうちょっと、胸を張っていけばいいって話ですかね?
 甲田・
甲田・ 有森:(声を揃えて)そうですね。
有森:(声を揃えて)そうですね。

 有森:確かに、私も行ってる都内で実施しているマラソン大会は、走りに行ってる間に、いろいろなコーナーがあって。そういうのをつくると何がいいかというと、ものすごく小さいお子さんとかも、親子で参加できる内容が増えるわけですよ。そういう「当たり前のコラボ」をお願いできる大会が全国にあればいいなと思いますね。今、考えているだけでも、めちゃくちゃ楽しいですもん。それ、私だけ?(笑)。
有森:確かに、私も行ってる都内で実施しているマラソン大会は、走りに行ってる間に、いろいろなコーナーがあって。そういうのをつくると何がいいかというと、ものすごく小さいお子さんとかも、親子で参加できる内容が増えるわけですよ。そういう「当たり前のコラボ」をお願いできる大会が全国にあればいいなと思いますね。今、考えているだけでも、めちゃくちゃ楽しいですもん。それ、私だけ?(笑)。
 田﨑:なんか「全部しゃべりたいけど、しゃべらないようにしている」という感じが、ヒシヒシと伝わってきますよ(笑)。
田﨑:なんか「全部しゃべりたいけど、しゃべらないようにしている」という感じが、ヒシヒシと伝わってきますよ(笑)。
「競い合うこと」を求める者、「やる楽しさ」を目的とする者
両方を満足させることの難しさ
 甲田:この前、自分で体験したことを一つだけ。私たちは、『子どもランニングフェスティバル』というイベントを、「ちょっとでも走ってみたい」という子どもたちに来てもらいたいという意図で、小学生は、3kmと5kmに設定してやっています。でも、普通の小学生で3kmとか5kmって、けっこうきついじゃないですか。そうすると、野球部とかサッカー部の子とかが、コーチに「行け」と言われて参加するケースもけっこういるわけです。
甲田:この前、自分で体験したことを一つだけ。私たちは、『子どもランニングフェスティバル』というイベントを、「ちょっとでも走ってみたい」という子どもたちに来てもらいたいという意図で、小学生は、3kmと5kmに設定してやっています。でも、普通の小学生で3kmとか5kmって、けっこうきついじゃないですか。そうすると、野球部とかサッカー部の子とかが、コーチに「行け」と言われて参加するケースもけっこういるわけです。
実は、そこですごくショックだったのが、ゴール前のところで、野球部の子の親御さんが「サッカー部に負けるな!」、サッカー部の子の親御さんが「野球部に負けるな!」とヤジる場面があったこと。「今日は友達と一緒に、1日楽しく走ろう!」という思いで来ていた子たちが、その親のヤジにみんな驚いちゃったんですね。
みんながみんな勝つためとか、速く走りたくて来ているわけではなく、楽しみたい子も来ていたのに、空気がすごく「競技」になってしまったんです。楽しむために来た女の子たちの集団が、「いやもうちょっと来年は来ません」みたいな感じになってしまって、ちょっともったいないなと思いましたね。
 田﨑:それって、ものすごく大事な話ですよね。
田﨑:それって、ものすごく大事な話ですよね。
 甲田:ありがちですよね。やはり、いかにそういう大会で、インクルーシブというか、みんなが来ていい大会という空気をつくるかは、とても大事だな、と実感しました。「あ、この女の子たち、せっかく走りに来たのに、来年はもう来ないだろうな」というのをその場で感じて、もったいないなと思いました。
甲田:ありがちですよね。やはり、いかにそういう大会で、インクルーシブというか、みんなが来ていい大会という空気をつくるかは、とても大事だな、と実感しました。「あ、この女の子たち、せっかく走りに来たのに、来年はもう来ないだろうな」というのをその場で感じて、もったいないなと思いました。

 田﨑:競い合うことは悪いことではないと思うんですが、それが負担になってしまったり、つらい思いに直結してしまったりすると、元々の楽しさを失わせてしまいますよね。
田﨑:競い合うことは悪いことではないと思うんですが、それが負担になってしまったり、つらい思いに直結してしまったりすると、元々の楽しさを失わせてしまいますよね。
 有森:「競い」じゃなくて、「争い」にしてるんですよね。
有森:「競い」じゃなくて、「争い」にしてるんですよね。
 甲田:そうなんですよね。頂上を目指したい子も、ただ、本当に楽しみたい子もいるわけです。両方の子が楽しめるイベントつくりって難しいですね。
甲田:そうなんですよね。頂上を目指したい子も、ただ、本当に楽しみたい子もいるわけです。両方の子が楽しめるイベントつくりって難しいですね。
 田﨑:大事ですね。それは、やっぱり我々大人への「もう少し考え直しなさいよ」というメッセージでしょうね。
田﨑:大事ですね。それは、やっぱり我々大人への「もう少し考え直しなさいよ」というメッセージでしょうね。
 有森:「勝つ楽しさ」を教えること、「競うことの楽しさ」を教えること、「やることの楽しさ」を教えることという全部を一緒に、同じ子たちにやるのは、なかなか難しいと思いますが、何か必要ですね。カテゴリー分けするとか。
有森:「勝つ楽しさ」を教えること、「競うことの楽しさ」を教えること、「やることの楽しさ」を教えることという全部を一緒に、同じ子たちにやるのは、なかなか難しいと思いますが、何か必要ですね。カテゴリー分けするとか。
でも、子どもたちって、そうは言っても勝つことがとても好きで、本気で競うこと、ガチで競うのも大好きなんですよ。そして、それを応援する親の気持ちもわかる。親には「応援する」というヒマな状態(笑)にせず、親自身も頑張らなきゃいけないというところに身を置くカテゴリーをつくるとか…(笑)。
 田﨑・
田﨑・ 甲田:笑。
甲田:笑。
 有森:子どもたちが、スポーツの場面で、一番喜ぶのって、どういう場面か知っていますか? いつもうるさく言っている自分の親が、必死になって、ヒーヒー言いながら走っている姿を見るときなんです。めちゃくちゃ喜んでいるけれど、めちゃくちゃ応援するんですね。
有森:子どもたちが、スポーツの場面で、一番喜ぶのって、どういう場面か知っていますか? いつもうるさく言っている自分の親が、必死になって、ヒーヒー言いながら走っている姿を見るときなんです。めちゃくちゃ喜んでいるけれど、めちゃくちゃ応援するんですね。
 田﨑:それ、運動会じゃないかですか(笑)。
田﨑:それ、運動会じゃないかですか(笑)。
 有森:ほんと運動会ですよね。それこそ自分の親が日常では見られないような真剣な顔をして走っている、一所懸命頑張っている姿を、子どもたちは、めちゃくちゃ喜んで応援しているんですよ。
有森:ほんと運動会ですよね。それこそ自分の親が日常では見られないような真剣な顔をして走っている、一所懸命頑張っている姿を、子どもたちは、めちゃくちゃ喜んで応援しているんですよ。
子どもたちのそういう姿、きっと大人は見過ごしていると思います。「何が楽しい」「何が嬉しい」というのが、「やらなきゃ」じゃなくて、「やっている個々が一所懸命なことの楽しさ」だったり、「そのなかで競う嬉しさ」だったりするとわかれば、もっと大人も考えるだろうし、そういうことによって私たちの現場つくりも変えていけるんじゃないかと思いますね。
『RIKUJO JAPAN』は
関わる人全員でやっていくこと
 田﨑:日本陸連は、2025年には創立100年を迎えるのですが、新しい時代の陸連として今回いろいろ出てきた話なども、いい形で感じ取って自由に思いきってやっていける組織になっていけばと思いますが、社会全体が進化する中で、スポーツする人=アスリートに求めることが変わってきていると感じることはありませんか?
田﨑:日本陸連は、2025年には創立100年を迎えるのですが、新しい時代の陸連として今回いろいろ出てきた話なども、いい形で感じ取って自由に思いきってやっていける組織になっていけばと思いますが、社会全体が進化する中で、スポーツする人=アスリートに求めることが変わってきていると感じることはありませんか?
 有森:変わってきていますねぇ。
有森:変わってきていますねぇ。
 田﨑:それに応えようとしているアスリートがものすごく発信をしているように思うし、自分の言葉を使うようになってきているよなと思うんですよね。
田﨑:それに応えようとしているアスリートがものすごく発信をしているように思うし、自分の言葉を使うようになってきているよなと思うんですよね。
 有森:そうですね。
有森:そうですね。
 甲田:アスリートがSNSなどで競技以外の自分を見せてくれるとやっぱり興味持ってくれるし、もう少し広がるんですけど、そこで発信することで受けるものもあるじゃないですか。そこもすごく難しいと思うんですよね。
甲田:アスリートがSNSなどで競技以外の自分を見せてくれるとやっぱり興味持ってくれるし、もう少し広がるんですけど、そこで発信することで受けるものもあるじゃないですか。そこもすごく難しいと思うんですよね。
 田﨑:競技力が強いだけでなくて、競技力が強くなっていくと同時に、発信していくものに返ってくるものがあって、それが相まって競技力そのものも強くなっていくような逞しさに繋がっている選手も出てきているんじゃないかなと。
田﨑:競技力が強いだけでなくて、競技力が強くなっていくと同時に、発信していくものに返ってくるものがあって、それが相まって競技力そのものも強くなっていくような逞しさに繋がっている選手も出てきているんじゃないかなと。
 有森:発信することで降りかかってくるものもある。それさえも味方にして、いきいきとしてやっている陸上というものを恐れなく広めてほしいと思うし、楽しんでいく姿を自分自身に持ってほしいなと思っていますね。
有森:発信することで降りかかってくるものもある。それさえも味方にして、いきいきとしてやっている陸上というものを恐れなく広めてほしいと思うし、楽しんでいく姿を自分自身に持ってほしいなと思っていますね。
 田﨑:今回のこの『RIKUJO JAPAN』は漢字は使わずに、中期計画(JAAFリフォーム)をもっとリアルに感じてもらえるように、そして、それを打ち出すことによって、それを担っていくみんなが、「自分の役割は何かな」ということを具体的にイメージできるようにするために、 2040年に「こうなっていたい」という世界観を描いて、これを命名して『RIKUJO JAPAN』としたわけです。
田﨑:今回のこの『RIKUJO JAPAN』は漢字は使わずに、中期計画(JAAFリフォーム)をもっとリアルに感じてもらえるように、そして、それを打ち出すことによって、それを担っていくみんなが、「自分の役割は何かな」ということを具体的にイメージできるようにするために、 2040年に「こうなっていたい」という世界観を描いて、これを命名して『RIKUJO JAPAN』としたわけです。
これは1人で出来るものではなく、関わる人全員でやっていくことなので、今日お話を伺ったこの瞬間からですね、もうお二人は『RIKUJO JAPAN』を実現していくメンバーだと思っていいですか?

 甲田:ぜひぜひ。実現したいさっきの世界は、一緒だったので。
甲田:ぜひぜひ。実現したいさっきの世界は、一緒だったので。
 田﨑:何かそこでは、「じゃあ、私こういうことをしたい」というのがあれば…。「この役割をやります」とか。
田﨑:何かそこでは、「じゃあ、私こういうことをしたい」というのがあれば…。「この役割をやります」とか。
 甲田:私たちはトップの選手にシューズを提供する…まあ、有森さんもそうでしたが…、ということを長くやってきましたが、同時に「運動、スポーツに関わって、心と身体の健康を」という人へのアプローチもしっかりやっていきたいことなんですね。「上だけじゃなくて、下だけじゃなくて、両方」というところをスタンスとして持っておきたいので。
甲田:私たちはトップの選手にシューズを提供する…まあ、有森さんもそうでしたが…、ということを長くやってきましたが、同時に「運動、スポーツに関わって、心と身体の健康を」という人へのアプローチもしっかりやっていきたいことなんですね。「上だけじゃなくて、下だけじゃなくて、両方」というところをスタンスとして持っておきたいので。
あとは陸上だけじゃなくて、いろいろな、いわゆる多様性とかについて、私たちは「日本陸上界をひとつに」という思いで、日本陸連と日本パラ陸上競技連盟と、日本デフ陸上競技協会の3団体と一緒にやらせてもらってるところもあるので、「そういう世界がなんか描けてるといいな」というところを、アシックスとしてご協力できたらなというのがありますね。
 田﨑:陸上も一つのスポーツですが、アシックスさんの場合は、他のスポーツのこと全部を考えていらっしゃるから、そういう意味では陸上だけの議論ではないと思います。先ほど、シューズの話を例に挙げていましたが、陸上というとシューズは我々の象徴ですよね。その一つの象徴のもとに、我々も一緒にやっていけるといいなと思います。
田﨑:陸上も一つのスポーツですが、アシックスさんの場合は、他のスポーツのこと全部を考えていらっしゃるから、そういう意味では陸上だけの議論ではないと思います。先ほど、シューズの話を例に挙げていましたが、陸上というとシューズは我々の象徴ですよね。その一つの象徴のもとに、我々も一緒にやっていけるといいなと思います。
 甲田:もちろんです。私たちはやはり、「選手が最高のパフォーマンスをするシューズを」というところを…、もちろん、ユニフォームもそうですけど大事にしています。安心安全、ケガを防いでというところは設計方針として、絶対にブラさない部分。「アスリートのために」というところで、引き続き進めていきます。
甲田:もちろんです。私たちはやはり、「選手が最高のパフォーマンスをするシューズを」というところを…、もちろん、ユニフォームもそうですけど大事にしています。安心安全、ケガを防いでというところは設計方針として、絶対にブラさない部分。「アスリートのために」というところで、引き続き進めていきます。
 田﨑:今後も、お世話になっていきます(笑)。
田﨑:今後も、お世話になっていきます(笑)。
 甲田:いつもありがとうございます(笑)。
甲田:いつもありがとうございます(笑)。
オールインクルージョンの世界を
陸上競技場のなかにつくっていく
 田﨑:副会長は、どうでしょう?
田﨑:副会長は、どうでしょう?
 有森:とりあえず肩書きのほうは、ちょっと置いておいて…(笑)。私自身は、陸上というかマラソンというものを通して、スポーツを通して、今の自分の人生を育んでくることができたので、そこで自分自身が感動したり、いろいろな学びがあったりしたことを、最大化して伝えていきたいです。
有森:とりあえず肩書きのほうは、ちょっと置いておいて…(笑)。私自身は、陸上というかマラソンというものを通して、スポーツを通して、今の自分の人生を育んでくることができたので、そこで自分自身が感動したり、いろいろな学びがあったりしたことを、最大化して伝えていきたいです。
もちろん、時代も変わって世代も変わって、もちろん環境も変わって…、いろいろなものが変わってきてはいるのでしょうが、「なにか心するもの」は、そんなに変わっていないと思うんですね。その真髄というか、陸上、スポーツというものが、人の生きる力になることを、どうすれば伝えていけるのか。それを常に探しながら考えながら、場づくりや、もちろん伝え方やコミュニケーション、見せ方を突き詰めていきたいなという思いはすごく持っています。
 田﨑:具体的には、何かあるのですか?
田﨑:具体的には、何かあるのですか?
 有森:マラソンと比較するとわかりやすいと思うのですが、沿道に応援に来る人は、走っている人が健常であっても、応援に来る人は全ての人で、そこには、車椅子の人もいれば、たぶん目が見えない人もいれば耳が聞こえない人もいる。全ての人たちがいるわけです。
有森:マラソンと比較するとわかりやすいと思うのですが、沿道に応援に来る人は、走っている人が健常であっても、応援に来る人は全ての人で、そこには、車椅子の人もいれば、たぶん目が見えない人もいれば耳が聞こえない人もいる。全ての人たちがいるわけです。
でも、もし、そのことに気づいて、それを踏まえた現場づくりを競技場の中でできたら、来る人の数は圧倒的に増えるわけですよ。今は、ソーシャルインクルージョンな社会の実現を声高らかに言う世の中になっています。企業も非常に関心を持っている共生社会というものに対して、陸上競技場の中に、それを実現できる可能性がつくれるんじゃないかと思っていて、そこは、私自身が今、興味の高いところでもあるんですね。これから先の数年も含めて、そういったものをどんどん取り組んでいく、なにかこうオールインクルージョンの『RIKUJO JAPAN』になればいいなと、役職を使って(笑)、思っております。
 甲田:ぜひぜひ!(笑)
甲田:ぜひぜひ!(笑)
 田﨑:まとめていただきましたね(笑)。私はこの立場になって1年なのですが、ここまでにたくさんの陸上競技関係者の方とお会いしてきたんですね。で、どの方にもそれぞれに夢があって、「こうあるべきだよ」とおしゃっていただきましたし、その話を聞くたびに、「そうだな」と本当に思うんですよ。ということは、自らの役割は、そういう夢を持っている方々を、なんとかお繋ぎすること。これを我がミッションとして、皆さんの描いている夢を少しでもあと押しできるような、そういう組織運営なり、立場・役回りというものを自覚してやっていく。それが「RIKUJO JAPAN」に繋がってくれたら、もう最高だなと思っています。そういう意味でも、今日は、すごくいい時間でした。
田﨑:まとめていただきましたね(笑)。私はこの立場になって1年なのですが、ここまでにたくさんの陸上競技関係者の方とお会いしてきたんですね。で、どの方にもそれぞれに夢があって、「こうあるべきだよ」とおしゃっていただきましたし、その話を聞くたびに、「そうだな」と本当に思うんですよ。ということは、自らの役割は、そういう夢を持っている方々を、なんとかお繋ぎすること。これを我がミッションとして、皆さんの描いている夢を少しでもあと押しできるような、そういう組織運営なり、立場・役回りというものを自覚してやっていく。それが「RIKUJO JAPAN」に繋がってくれたら、もう最高だなと思っています。そういう意味でも、今日は、すごくいい時間でした。
 甲田:ありがとうございます。新しい何かを取り組みを、ぜひ期待しております。
甲田:ありがとうございます。新しい何かを取り組みを、ぜひ期待しております。
 田﨑:最後に、何かこれを、と思うことがありましたら、何か。
田﨑:最後に、何かこれを、と思うことがありましたら、何か。
 甲田:そうですね。この『RIKUJO JAPAN』というプロジェクトができたことで、各スポンサーさんをみんな集めて、何か一つをやりきることができたらいいなと思いますね。それはもしかしたら、今までにいろいろな会話のなかで出てきてはいたのだけど、実際にはできていなかったというものだったりするかもしれないと思うんですよ。そこはぜひ、実現できればと思います。
甲田:そうですね。この『RIKUJO JAPAN』というプロジェクトができたことで、各スポンサーさんをみんな集めて、何か一つをやりきることができたらいいなと思いますね。それはもしかしたら、今までにいろいろな会話のなかで出てきてはいたのだけど、実際にはできていなかったというものだったりするかもしれないと思うんですよ。そこはぜひ、実現できればと思います。
 田﨑:ありがとうございます。ぜひ、一緒に進めさせていただきたいと思います。
田﨑:ありがとうございます。ぜひ、一緒に進めさせていただきたいと思います。
 甲田:(有森氏に向かって)トリ、どうぞ。
甲田:(有森氏に向かって)トリ、どうぞ。
 有森:もう言い尽くしちゃいました(笑)。
有森:もう言い尽くしちゃいました(笑)。


 一堂:爆笑。
一堂:爆笑。
 田﨑:ありがとうございました。
田﨑:ありがとうございました。
(2024年7月17日収録)
インタビュアー:紫垣樹郎
文:児玉育美(JAAFメディアチーム)
写真:平岩亨






















